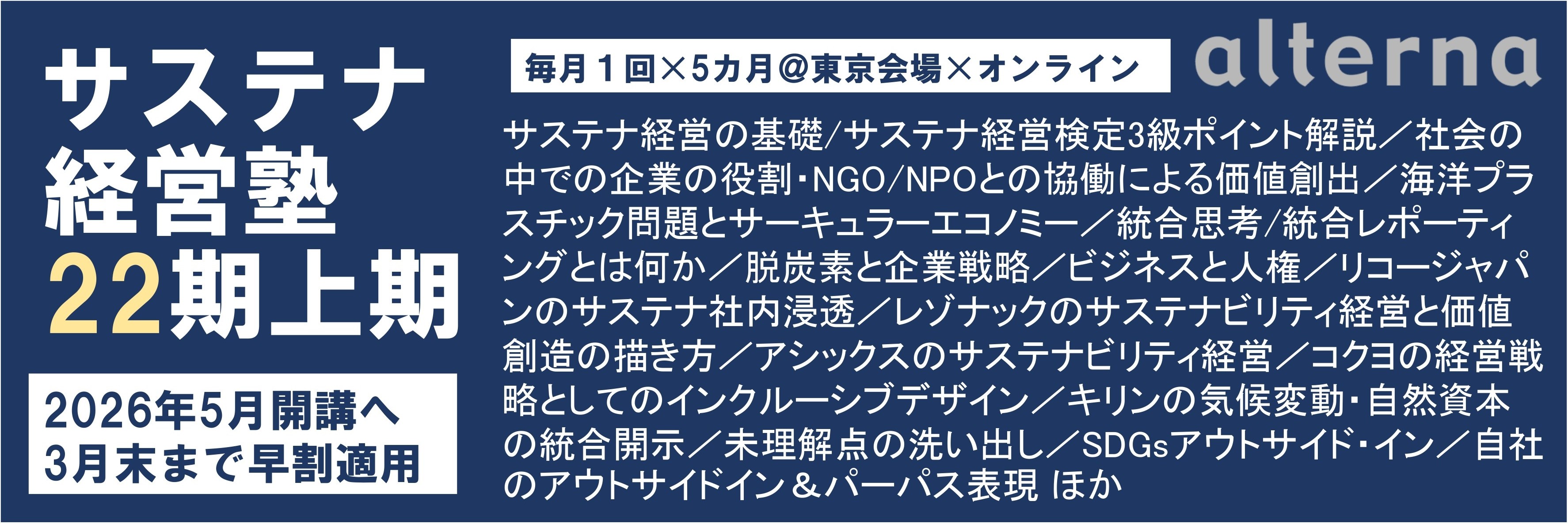記事のポイント
- LINEヤフーやNEC、サイボウズなどが遠隔で行う能登支援活動を本格化した
- 被災団体のニーズを可視化し、社員のITスキルを活用した支援活動を行う
- 遠隔から行う能登支援活動を「プロボ能登」と名付けた
LINEヤフーはこのほど、能登支援に特化したプラットフォーム「プロボ能登」の活動を本格化すると発表した。同活動では、能登地域で被災した団体のニーズとプロボノとして技術支援を希望する企業をマッチングする。LINEヤフーが立ち上げた「プロボ能登」には、NECやサイボウズなど7社が加盟する。(オルタナ輪番編集長=池田真隆)

能登地域は、能登半島豪雨災害(2024年9月)や能登半島地震(2024年1月)によって、甚大な被害を受けた。被災した地域は「復旧」から「復興」へと歩みを進めているが、依然として人材不足やノウハウ不足が課題だ。
LINEヤフーでは2024年2月から、社員の専門知識やスキルを活用したボランティア活動「LINEヤフープロボノ」を展開しており、能登支援を行ってきた。プロボノとは、仕事で培ったスキルや経験を活かした社会貢献活動を指す。
能登に訪れて行う活動に限定することなく、ITスキルを活かした支援活動を社内に呼び掛けた。具体的には、能登地域の宿泊施設の予約サイト制作や輪島の伝統工芸の情報発信支援などだ。地域固有のニーズに対応した支援を遠隔で実施してきた。
この活動をさらに発展させるため、2025年4月には、「プロボ能登」を立ち上げた。能登で被災した団体のニーズを可視化し、プロボノとして支援を希望する企業をマッチングするプラットフォームだ。
■地域資源の「循環」をITで加速へ
プロボ能登には、LINEヤフーを含めて7社が参画する。国内企業としてはプロボノの草分けであるNEC、青野慶久社長が選択的夫婦別姓の導入を訴えるサイボウズなどだ。社会問題への感度が高い企業が名を連ねる。
プロボ能登として、今年10月から、地域団体「のと復耕ラボ」が推進する「のと古材レスキュープロジェクト」と連携し、古材の在庫管理システムの構築を支援する。
のと古材レスキュープロジェクトとは、能登半島地震で被災し、解体される古民家などから、歴史や思い入れのある木材を回収し、アップサイクルして新たにテーブルやベンチなどの木材として活用する取り組みだ。
これまでは、回収した古材については能登地域のレスキュー団体などの管理に留まり、全体で在庫状況を一元的に把握することが困難だった。プロボ能登では、古材管理における業務設計からツール導入、マニュアル作成までを包括的に支援し、地域の人々が持続的に運用できる仕組み化を行う。地域資源の循環を促し、復興を後押しする。
今後も能登地域の企業のサイト運営や情報発信を支援する。能登の現状を知ってもらうため、来年の1月には活動報告会を開く予定だ。
■「プロボ能登の輪を広げたい」
LINEヤフーにはプロボノを希望する社員が約80人いる。主に40~50代の社員だが、若い世代も増えているという。プロボノ活動は通常3人1組でチームを作り、業務時間外に実施する。稼働時間は週2~3時間で、定例ミーティングは週1回30分程度で行うことが多いという。
プロボ能登を担当する、LINEヤフーのサステナビリティ推進統括本部CSR本部CSR推進部に所属する田村夏子・CSO リレーションマネージャーは、「プロボ能登の輪を広げていきたい。様々な業界から参画して頂きたい」と話した。
プロボ能登では、能登地域の復興を支えるパートナー企業の募集を随時行っている。