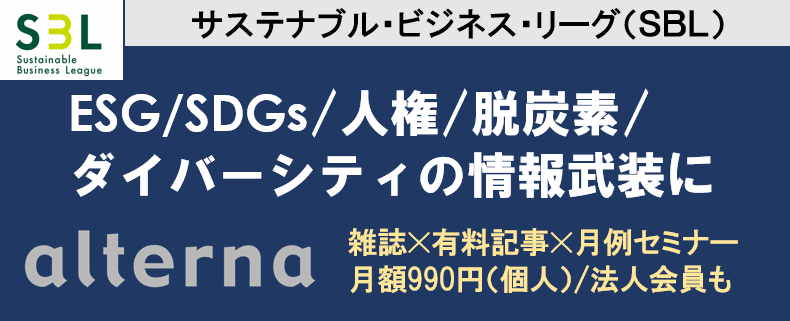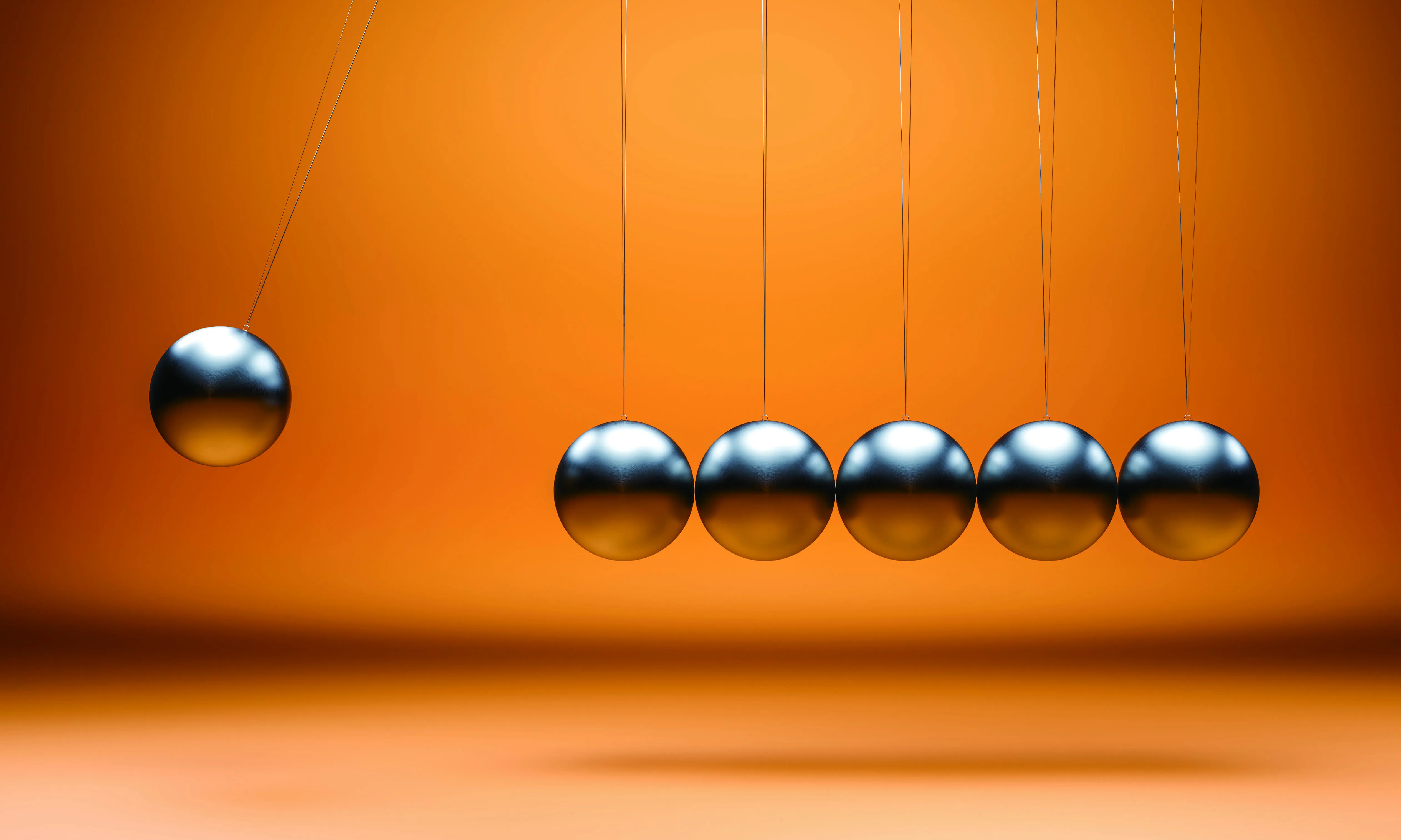■フラッシュフィクション「こころざしの譜」
鬱々とした気分のまま路地裏をさまよっている。小説家を自称し着流しで恰好をつけているが、その実私が出した本はといえば短編集が一冊だけ、それもまったく売れなかった。一向に筆が進まず呻吟する毎日で机の前で船を漕ぐのも日常茶飯事。情けないことだが昼過ぎには散歩にかこつけて街なかで時間をつぶすことにしているのである。
特にこれといった行先はなく、自然に足が向くのは馴染みの骨董屋ということになる。あこぎな店主の口車に乗せられて李朝青磁の茶碗や伊万里の大皿を買わされている。
「李朝か。五万円とは安い。まがい物じゃないのか」。小ぶりの茶碗がぐい飲みにぴった
りだと勧めた主にちょっとからんだのが運の尽きだった。
「とんでもない。間違いなく本物です。ここを見てください。ほんの少しですが欠けているのがわかりますか。実は失敗作だというので他のわれ茶碗と一緒に一旦はゴミ捨て場に放られていたもので、それが後で掘り起こした時に大したキズではないと運よく拾われたのです」
「数奇な運命だな」
「ええ、李朝の作風はなんともおおらかなのです。隙のない完璧さは求めない、釉はげや歪み、キズなどの欠陥を自然な味わいとして受け入れ評価する文化があります。まあ、キズはキズですから特別な値付けにしております。本来ならウン十万はくだらない品物ですよ」
相変わらず口が達者だ。大皿も細かいヒビが入っているのを見つけて文句を言ったら、江戸時代は技術が未熟でこうしたヒビが入る。これこそ本物の証、ときた。主の言葉を信じたわけではないが、私はどうもキズものに弱い。なぜか親近感を抱いてしまうのだ。
店内をぶらぶらしていると年代物の万年筆が目にとまった。かなり高価な本鼈甲の万年筆である。沖縄やフィリピンあたりのきれいな海を泳いでいたタイマイの甲羅からとった天然の鼈甲だろう。黄色と茶色の独特な色柄がなんとも美しい。黒い樹脂の上に鼈甲を熱で曲げて何枚も巻き付けている。今では輸入が禁止されているはずだから貴重なものだが、無傷で新しいようにも見える。最新式のボールペン類と並べられている。
そこへ店の主が揉み手で近づいてきた。
「気に入りましたか、その万年筆」
「形は古いけど、最近のものなの?」
「いい物は心を込めて磨くとピカピカに光ってくるのですよ」
「日々の努力が大切ということだな」
怠惰な己を反省する気持ちがちらっと沸き起こる。
「いいペンはいい作家をつくると申します。この万年筆ならアイデアが泉の如く湧いてきてベストセラーがどんどん書けますよ。買ってみたら。騙されたと思って」

ベストセラーという言葉に幻惑され気が付いた時にはもう万年筆を手に取っていた。使ってみると確かに筆が進む。こちらが考えた瞬間に万年筆が勝手に動くのだ。不思議な感覚だったが、とにかく筆任せで書き続けることができた。頼まれたインタビュー原稿も、ペンは相手の話した内容をすっかり記憶しているかのようにうまくまとめてくれた。
小説はどうか。まずはラブストーリー。担当の編集者が「えっ、先生、万年筆の手書き原稿ですか。いつもパソコンに打ち込んでくれるのに。会社の女の子にパソコンで打ってもらうの、結構大変なのですよ。まいったなあ」と不満たらたらだった。しかし、原稿を読んだ途端、目の色が変わった。
「一体どうしたのですか。いい出来じゃないですか。先生が恋愛の大家とは知らなかった。失礼ながら、女嫌いかと誤解していました。これならいける。すぐパソコンで打たせます」
この恋愛小説は、私のアイデアでは最後に男が女を殺すという単純なプロットだったが、ペンはこれを書き直し、男が脅すつもりで構えた刃物に女が体当たりして相手を殺人犯に仕立てあげ復讐を果たすという手の込んだ恋愛ミステリーになった。この本は私の実質的なデビュー作になり、気鋭のミステリー作家現る、と時の人として注目されることになったのである。
本格的なミステリーを書く時が来た。ある芸術家が殺される。犯人はわからない。傲慢で敵が多く人の恨みを買うこともあった。しかし、捜査は意外な展開を見せ、母親の遺産をめぐる相続争いから弟の犯行と判明する。私はほとんど何もしなかった。万年筆が猛烈な勢いで動いて書き上げたのである。ミステリーとしては史上最高の売り上げを記録、ミステリー部門の大きな賞を受賞した。新聞では「意外性の中に妙なリアリティがある」と評されたが、私はうれしくなかった。自分の作品とは思えなかったからである。
そんなある日、一通の手紙が届いた。知らない人からである。小説を読んで興味を持った、ぜひお会いしたいとある。
品のいい若い女性だった。
「私の父は三年前何者かに殺されました。犯人は捕まっていないけど、風呂場に倒れてい
たことや鉈のようなもので撲殺されたことなど犯行の状況があなたの小説にそっくりなの」
私は恐ろしくなって体が震えた。女性はさらに続けた。
「犯人は不明ですが、小説と同じく被害者の弟が怪しいとにらんでいます。彼は温厚で、殺人を犯すような人には見えないわ。だから誰も疑っていないの。でも、実はお金には非常に執着心が強い男なのです」
ふと思いついて例の万年筆を持ってきて見せた。女性は驚き、叫んだ。「まあ、父が使っ
ていた物よ。どうしてここにあるの」。
すぐに骨董屋を訪ね、店主を問い詰めた。
「試作段階なので黙っていましたが、実はあの万年筆はAI搭載型で書き手の意向を汲んで自動的にペンを走らせる能力があるのです。デザインは知り合いの科学者がたまたま手に入れた古い万年筆をコピーしたと聞きました」
不思議なことだ。殺された元々の万年筆の持ち主の怨念までもAIは取り込んだのだろうか。まもなく弟は兄殺しの容疑で逮捕された。私にとって残念なのは、それから万年筆がまるで憑き物が落ちたかのように何も書かなくなってしまったことである。(完)