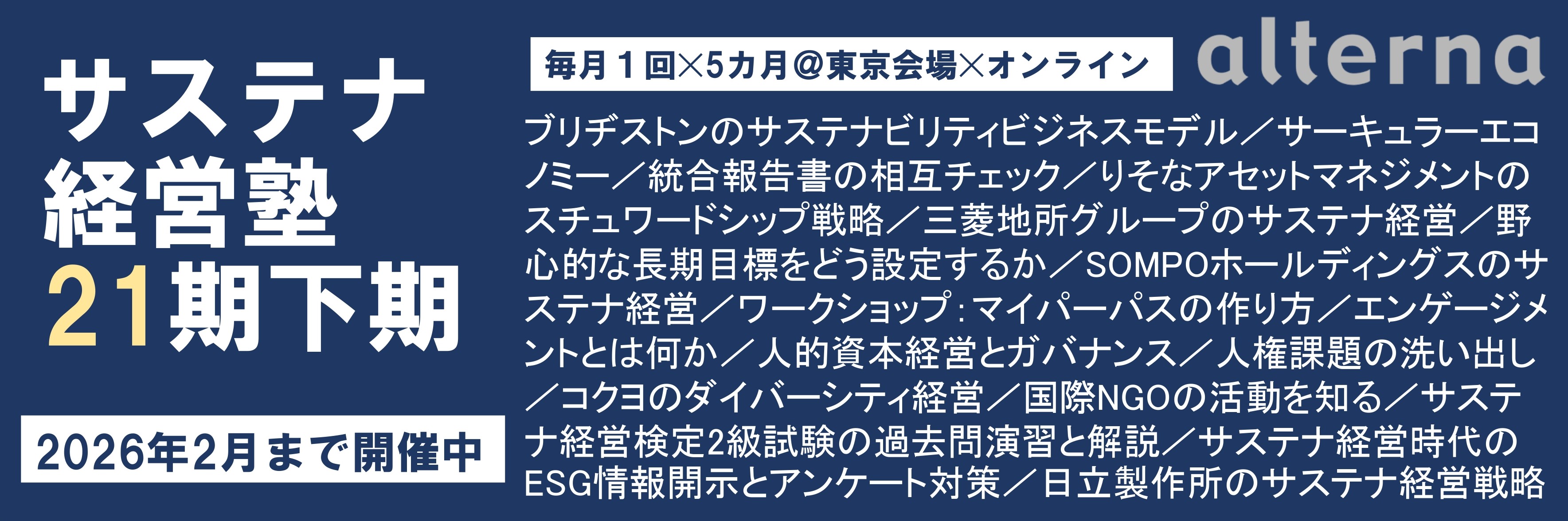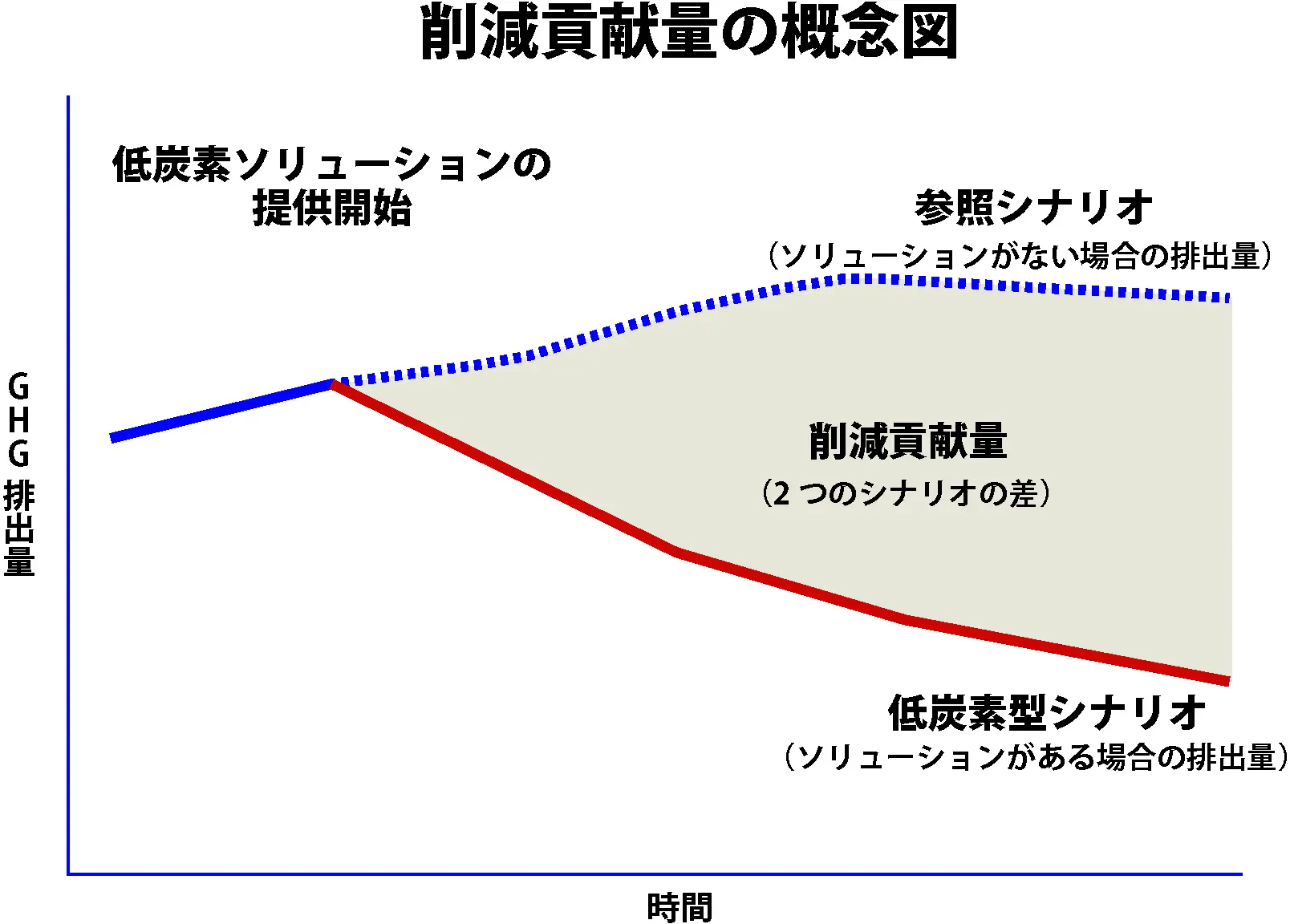記事のポイント
- 朝日新聞社は「V500コミットメント」に参画し、3つの具体的な約束を掲げた
- 「やさしい日本語」「デフリンピック協賛」「ウェブアクセシビリティ」の全社的推進だ
- 障がいのある社員の活躍と勉強会の開催で、組織文化を変革しつつある
朝日新聞社(東京・中央)が「V500コミットメント」への参画を発表したのは、2024年のことだった。V500とは「Valuable 500」の略称で、障がい者が働きやすい社会の実現を目指す国際的なイニシアティブの日本版である。500社が具体的なコミットメント(約束)を掲げ、障がいインクルージョンの推進に取り組む。デフリンピックへの関与、やさしい日本語による報道、デジタル領域でのアクセシビリティ改善──。朝日新聞社が掲げたV500コミットメントは、理念にとどまらず、現場の実践として積み上げられてきた。報道・デザイン・デジタル・人事を横断する取り組みを通じて、「誰も取り残さない報道」を形にしてきた過程を追った。(聞き手=NPO法人インフォメーションギャップバスター理事長・伊藤芳浩)

■「V500コミットメント」で3つの約束
朝日新聞社がV500として掲げた3つのコミットメントは、以下の通りだ。
(1) やさしい日本語でニュースを届ける
グループ会社のアルファサードと連携し、「やさしい朝日新聞」を公開。外国人、高齢者、子ども、障がい者など、より多くの読者にニュースを届ける。
(2)デフリンピックを支援する
東京での聴覚障がい者の国際スポーツ大会に、トータルサポートメンバーとして協賛。報道を通じて認知度向上に貢献する。
(3)アクセシビリティを全社で推進する
ウェブサイトのユニバーサルデザイン、社内勉強会の実施、障がいのある社員の活躍を紙面やデジタルで紹介する。
障がいの有無に限らず、誰もがお互いの人格を認めて支え合い、すべての人の個性や多様性を尊重できる社会を実現する。その思いから、同社はV500への参画を決めた。
■専用メディア「やさしい朝日新聞」の挑戦
では、3つのコミットメントは具体的にどのように実践されているのだろうか。
まず、V500の最初のコミットメントである「やさしい日本語でニュースを届ける」取り組みから見ていこう。朝日新聞社は「やさしい朝日新聞」という専用メディアを立ち上げた。これは、朝日新聞デジタルの記事を、やさしい日本語に言い換えて配信する独立したウェブサイトだ。
「やさしい朝日新聞」の最大の特徴は、ニュースを「やさしい日本語」に言い換える作業を、すべて人の手で行っている点だ。アルファサードの日本語教師や国語教師の出身者などが、一つひとつの記事を丁寧に書き直す。その原稿を朝日新聞社側でチェックし、内容の正確性を担保する。
一方で、ふりがなを振ったり、分かち書きにしたり、音声ファイルを生成したりする作業は機械が担う。「言い換えは人、サポート機能は機械」──。この役割分担により、温かみのある自然な日本語を、デジタルの利便性とともに届けることができている。
そもそも、やさしい日本語とは何か。短い文章で書く(一文を短く区切る)、難しい漢字や専門用語を避ける、ふりがなをつける、受動態ではなく能動態で書く、抽象的な表現ではなく具体的に書く、といった特徴がある。
たとえば、「政府は経済対策を講じる方針を固めた」という文章を、やさしい日本語に言い換えると、「政府(せいふ)は、経済(けいざい)を良(よ)くするための対策(たいさく)を決(き)めました」となる。
これは、単なる「簡略化」ではない。情報の本質を損なわずに、より多くの人に伝わる形に「翻訳」する技術だ。
では、誰がこのメディアを必要としているのか。日本語を学んでいる外国人、日本語が母語でない在留外国人、知的障がいのある人、認知症の高齢者、小学生・中学生、聴覚障がい者(日本語の習得が困難な場合がある)──。つまり、「日本語のハードルが高い」すべての人だ。
朝日新聞社がこのメディアを始めたことは、報道機関として大きな決断だった。記事を「やさしく」することは、ジャーナリズムの専門性や深みを損なうリスクもあるからだ。しかし、ウェブ開発などを手掛けるアルファサード(大阪市)創業者の野田純生さんは言う。
「『伝わらない情報』は、存在しないのと同じです。より多くの人に届けることが、私たちの使命だと考えました」
■デフリンピックに本格関与、一人ひとりの物語を伝える
2つ目のコミットメントは、デフリンピックの支援だ。これは前編で紹介したデザイン部の野口哲平さんの存在と深く関わっている。
朝日新聞社は2025年東京デフリンピックを「トータルサポートメンバー」として協賛している。野口さんの存在が、この決断の大きな原動力となった。だが、その取り組みは単なる協賛にとどまるものではない。
朝日新聞社は、自社が主催する国際的なイベントでも、デフリンピックを取り上げている。2025年10月、朝日新聞社が主催する国際フォーラム「朝日地球会議2025」で、デフリンピックをテーマにしたセッションが開催された。タイトルは、「音のない世界、音のないスポーツとは──デフリンピックで考える社会」。
登壇したのは、デフリンピック日本代表選手、選手の声を届ける手話通訳士、朝日新聞社の記者。このセッションでは、競技の魅力だけでなく、「誰でも何でも挑戦できる社会」というテーマが深く議論された。
さらに、報道の現場でも大きな変化が起きている。前編で紹介したように、社会部の斉藤寛子記者(現:ブランド企画部)は、トルコで開催された前回のデフリンピックに単独で取材に赴き、手話を一生懸命覚えて選手たちと交流した。
そして2025年11月、東京でデフリンピックが開催された。朝日新聞社は「どうすれば公平に取材できるか」を真剣に考えながら、この大会の報道に臨んだ。
朝日新聞社が組織した取材体制は、部署の垣根を超えたものだった。スポーツ部記者3人、社会部記者1人、映像報道部2人が大会を通じて取材に携わり、デスクは各部1人が担当した。
さらに単発でスポーツ部の記者がサポートに加わったり、関心の高いネットワーク報道本部の記者が記事を出したりした。競技取材は主にスポーツ部と映像報道部で担ったが、縦割りにならないように意識し、大会前から情報共有などを積極的に行った。取材班は編成しなかったが、打ち合わせなどは合同で行った。
野口さんが前編で語っていた課題「手話ができない記者が、口話ができる選手だけに取材してしまうと、公平性に欠ける」という問題に対しても、朝日新聞社は真摯に向き合った。
手話通訳者の有無や、取材対象者のコミュニケーション手段などを事前に確認したうえで取材に臨んだのだ。それでも、コミュニケーションの面で苦労する点は多かったと現場の記者からは聞いている。
報道の方針も明確だった。デフリンピックという大会をフックに、聞こえない人・聞こえにくい人をとりまく環境や課題について伝えることを意識した。また、メダルの色に左右されず、記者が事前の取材やリサーチで面白い、伝えるべきだと思ったテーマを取り上げることを大切にした。
一方で、デフリンピックやデフスポーツ、デフアスリートに関する報道がこれまで少なかったこともあり、基本的なことを丁寧に書くことを意識した。担当者は「良い悪いではありませんが、初期のパラリンピック報道に近いものがあると感じました」と振り返る。
さらに朝日新聞社は、デフスポーツへの理解を促進し、本大会を盛り上げるため、「デフリンピック特別紙面」を発行した。11月15日に東京体育館で行われた開会式では「朝日新聞社」ブースで配布したほか、デフリンピックの大会期間中は競技会場内に設置配布した。
特別紙面では、デフリンピックの概要や歴史をイラスト入りで解説。大会の競技日程の一覧や、開催地の地図のほか、自転車競技に4大会連続で出場する早瀬久美選手と手話通訳士の保科隼希さんのインタビューなどを掲載した。
報道だけでなく、大会の運営支援にも力を入れた。大会期間中は朝日新聞社員20人をサポートスタッフとして派遣し、大会の運営に協力した。
野口さんが大会前に語っていた期待「オリンピックのとき、一面に『金メダル何個、銀メダル何個』という表が載りますよね。デフリンピックでも、同じようなことができたらいいですよね」という言葉。朝日新聞社の実際の報道は、メダルの数だけを追うのではなく、一人ひとりの選手の物語や、デフスポーツが抱える課題を丁寧に伝えることを選んだ。
これは、野口さんの期待に応える別の形だったと言えるかもしれない。「当たり前の報道」が、デフリンピックにも向けられることで、聴覚障がい者のスポーツが「特別なもの」ではなく、「通常のスポーツと同じ」ものとして認知される。朝日新聞社は、メダルの数ではなく、選手一人ひとりの物語を通じて、その「当たり前」を実現しようとしたのだ。
■全社でアクセシビリティ推進、継続的に改善進める
3つ目のコミットメントは、最も広範囲に及ぶ取り組みだ。ウェブサイトやアプリのユニバーサルデザイン、社内勉強会の開催、障がいのある社員の活躍支援──。これらすべてが、このコミットメントに含まれる。
まず、デジタルメディアにおけるユニバーサルデザインの実践について見ていこう。朝日新聞社のウェブサイトやアプリには、一見しただけではわからない、細かな工夫が積み重ねられている。
例えば、色覚特性への配慮だ。色覚に特性のある人にとって、色だけで情報を伝えるデザインは読みとることができない。
そこで、朝日新聞社は、赤と緑、青と紫のような見分けにくい配色を避ける、明度差をつけて色が見分けられなくても区別できるようにする、斜線やドットなどのパターンを併用する、といったルールを徹底している。たとえば、グラフでは色だけでなく、線の太さや破線、パターンを組み合わせて見分けやすくしている。
文字の読みやすさにも細心の注意を払っている。ロービジョン(弱視)やディスレクシア(読み書き障がい)の人にとっては、文字の大きさや書体を工夫することも読みやすさにつながる。小さすぎる文字を使わない、UDフォント(ユニバーサルデザインフォント)を使用する、グラフには必ず項目名と数値を直接表示する、といった配慮をしている。
視覚障がい者への対応も進めている。視覚障がい者が使う「スクリーンリーダー」(画面読み上げソフト)に対応するため、画像に代替テキスト(alt属性)を付ける、見出しタグ(h1, h2など)を正しく使う、リンクのテキストを明確にする(「こちら」ではなく、「記事の詳細を見る」など)といった工夫をしている。
デジタル化の進展に伴い、音声読み上げへの対応は不可欠になってきている。現時点ではすべてのコンテンツで徹底できているわけではないが、改善に向けて運用体制や制作フローを見直している。
さらに、自社サイトだけでなく、外部サービスとの連携も視野に入れている。アクセシビリティは、自社サイトだけで完結するものではない。「読者がブラウザ上で文字サイズを自由に調整できること、他のサービスと併用する際に支障が出ないようにすること──これも重要な視点です」。つまり、ブラウザや外部サービスとの連携を意識しながら、より多くの人にとって使いやすい環境を実現しようとしている。
こうしたユニバーサルデザインの考え方を、大規模に実装したのが2025年1月のアプリリニューアルだった。朝日新聞公式アプリの全面リニューアルの核心は、「アクセシビリティ」にあった。UXデザインの刷新、機能の大幅強化、そして特に注目すべきは「毎週アップデート」という開発サイクルだ。
新聞各社の公式アプリは、数年に一度の大がかりなアップデートを行うのが一般的だ。しかし、朝日新聞アプリは毎週改善を重ね、ユーザーの声に即座に応える体制を確立した。このアプローチは、メディア業界では画期的だった。
朝日新聞社のウェブサイトやアプリには、一見しただけではわからない、細かな工夫が積み重ねられている。
技術的な工夫だけでは、アクセシビリティは実現しない。組織全体の意識を変え、日々の業務の中でアクセシビリティを実践する文化が必要だ。
その実践例が、デザイン部での取り組みだ。前編で紹介した野口さんが所属するデザイン部では、日々の業務の中でユニバーサルデザインが実践されている。デザイナー、デスク、出稿部が協力して検討し、色覚シミュレーションツールを使って識別性を確認し、フォーマットで基礎的なルールを定め、統一的に運用している。
野口さんは「図解やグラフなど、ニュースを視覚的に伝えるニュースグラフィックは、伝える内容によって表現が大きく異なります。見やすく、伝わりやすい表現を目指して、日々協力しながら検討を重ねています」と話す。
「アクセシビリティは、一度対応すれば終わりではありません。ユーザーの声を聞き、継続的に改善していくことが大切です」(野田さん)
■一律のマニュアルではなく、一人ひとりに向き合う
そして、V500のコミットメント(3)を支える最も重要な柱が、社内勉強会だ。前編と中編で紹介したように、朝日新聞社では複数の社内勉強会が開催されている。
聴覚障がい者にとっての情報体験をテーマにしたものや、アクセシビリティ全般(聴覚障がい・視覚障がい)をテーマにしたものなどで、多いときには会議室とオンラインで200人を超える人が参加した。当日、参加できない人のためにイントラに動画が共有されるなどしており、勉強会に参加した当事者の声が組織を動かすきっかけとなった。
注目すべきは、これらの勉強会が、「上からの指示」ではなく、現場の社員たちが自発的に開催したものだという点だ。
野田さんは語る。
「真面目な人が多いので、アクセシビリティの問題を知ると、自ら勉強し始めるんです。ただ、どこから取り組めばいいかわからないという声もあります。そこを、私たちが一緒にサポートしていきたいと考えています」
V500のコミットメント(3)には、もう一つ重要な柱がある。「障がいのある社員の活躍を紙面やデジタルで紹介する」という約束だ。その象徴的な存在が、パラノルディックスキー・クロスカントリー競技の選手として活躍する社員である森宏明さんだ。
2026年3月に開幕する「ミラノ・コルティナ パラリンピック冬季競技大会」に出場予定の森さんは、ブランド企画部でプロモーション活動に取り組んでいる。朝日新聞は、森さんの挑戦を企画記事として随時紹介している。トレーニングの様子、大会への意気込み、競技の魅力──読者に向けて、リアルな声を届けている。
社内でも応援イベントが企画され、多くの社員から応援メッセージが寄せられた。
「同僚がパラリンピックに出場するということが、社員一人ひとりにとって、障がい者スポーツを身近に感じるきっかけになりました」(担当者)
森さんの存在は、野口さんと同じように、社内のアクセシビリティ意識を高める大きな力になっている。
こうした取り組みを支えるため、朝日新聞社は障がい者雇用においても具体的な施策を進めている。V500のコミットメントを実現するには、障がいのある社員が実際に働きやすい環境を整えることが不可欠だからだ。
採用の段階から、丁寧な配慮が行われている。人事部は、採用イベントや面接の際に、事前に配慮が必要なことを本人に確認している。聴覚障がいのある人の場合は、イベント時の資料投影を字幕つきで行う、口元が見えるようにマスクを外して対応する、グループワークは別室で行い会話が聞き取りやすいようにする、といった配慮をしている。
入社後の支援も手厚い。電話対応の免除、チャットやメールでの情報共有の徹底、情報支援アプリ「UDトーク」の法人契約、Teamsのライブキャプション機能の活用、入社3年は3か月に1回の定期面談など、様々な合理的配慮を提供している。
そして朝日新聞社が最も重視しているのは、一人ひとりに合わせた配慮だ。人事部の担当者は強調する。
「同じ聴覚障がいと言っても、求めている配慮の程度や内容は人によって異なります。ひとりずつの意見や困りごとを丁寧に吸い上げ、解消していくことを目指しています」
これは、「合理的配慮」の本質を示している。一律のマニュアルではなく、一人ひとりに向き合うこと。
これらは、朝日新聞社がV500コミットメントのもとで積み上げてきた「実践」の全体像である。次回では、こうした取り組みが朝日新聞社という組織にもたらした変化に焦点を当てる。社員の意識や業務フローはどう変わったのか。そして、その変化が社内のみならず、業界や社会にどのような影響を及ぼし始めているのか。成果とともに、なお残されている課題や、次に向かうべき方向を追っていく。