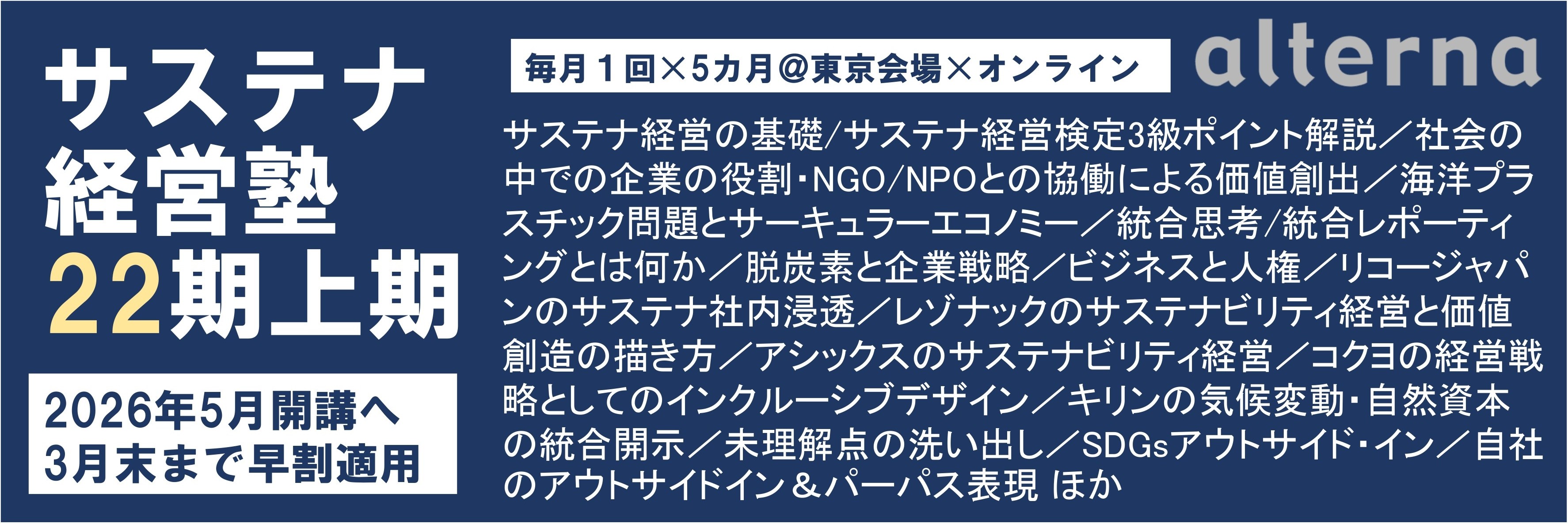オルタナ82 号をお届けします。今号の第一特集は「自国第一主義の相克: 軋きしむグローバリゼーション」です。米国のトランプ大統領だけでなく、欧州各国でも、日本でも「自国ファースト」の声が高まるばかりです。
今から10 年前の2015 年9 月25 日、国連サミットで、「SDGs(持続可能な開発目標)」が当時の国連加盟全193 カ国によって採択されました。その3 カ月後には、国連気候変動枠組条約締約国会議(COP21)が、21 世紀後半に向けた気候変動に関する国際的な枠組み「パリ協定」を採択しました。
その当時は、気候変動だけでなく、人権、ダイバーシティ、教育、貧困など全世界的な課題に向けて、各国が協調し、取り組むという機運を大いに感じたものです。それから10 年が経ち、その勢いに陰りが出ることを危惧します。
自国ファースト主義は、さまざまな国際課題から目を逸そ らせます。その筆頭格はトランプ政権で、「パリ協定」から脱退を表明しただけでなく、7 月下旬には、現在の気候変動の現状に疑問を呈した報告書がエネルギー省によって公表されました。
その影響は日本にも影を落としています。たとえばIHI は米国のバイオマス事業から撤退することが明らかになりました。その背景にはトランプ政権による脱炭素政策の見直しがあります。国内の金融機関も相次ぎ、環境や人権の世界的枠組みである「赤道原則」やNZBA(ネットゼロ・バンキング・アライアンス)からの脱退を決めました。
7 月の参院選でも、「温室効果ガスの排出削減を積極的に進める必要はない」と主張した政党が躍進しました。人権問題も同様で、移民や外国人を巡る人権侵害に対して、無関心や否定的な人たちが増えました。地球市民である私たちは、こうした社会課題に対してますます無関心になっていくのでしょうか。
「自国ファースト」がここまで広がった理由の一つとして、経済のグローバル化が先進国でも途上国でも富の偏在を進め、貧富格差が広がったことが挙げられます。グローバリゼーションは結局、人々から幸福感や利他主義を奪ったのでしょうか。
◆
アダム・スミスは「国富論」(1776 年)において、「市場が機能すれば、土地や労働や資本に対するフェアな見返りが期待でき、買い手と売り手の双方に満足のいく結果がもたらされ、社会全体にもっと望ましい形で資源を配分する価格が形成される」と説きました。これが「神の見えざる手」です。
しかし、米国の経済学者であるデビッド・コーテン博士は「スミスは、大きな皮肉を込めた。こういった結果がもたらされるのは、市場価格を操作できるほど巨大な売り手や買い手が存在しない場合のみだと強調した」(『グローバル経済という怪物』)と書きました。
いまのグローバル経済は、多かれ少なかれ、コーテン博士が指摘した『怪物』によって軋んでいるようです。その軋みが、民心をゆがめ、自己中心主義を蔓延させているように感じます。
結局、気候変動問題にしろ、人権問題にしろ、先進国でも途上国でも市民が余裕のある生活を実現し、他人を慮おもんぱかる「利他的な」気持ちが醸成されないと、その解決は難しいものです。
SDGsのゴールまであと5年。パリ協定でも2030 年における目標達成を各国に求めています。
現在の混迷から一歩抜け出して、社会課題の解決に向けて突き進めるのか。いま、私たちはその岐路に立っています。本号10 ページで取り上げた、英国「ブレグリット」やEUとの連携は、その兆候なのかもしれません。