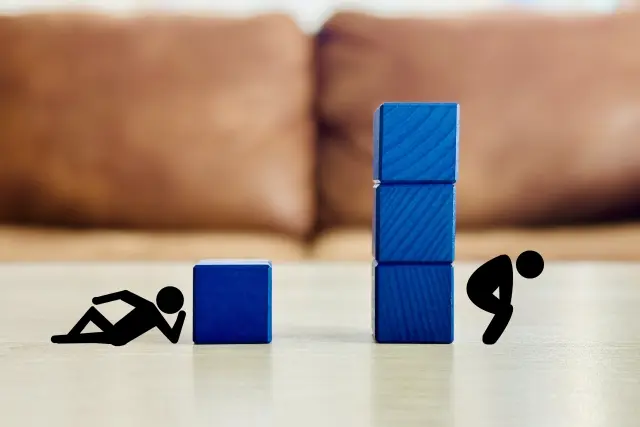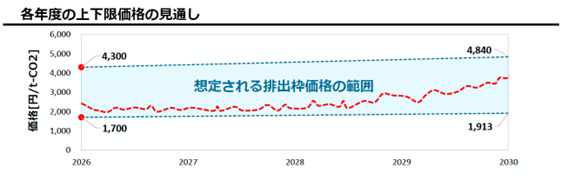記事のポイント
- サステナビリティを競争力に転換するにはR&Dの根本的な見直しが欠かせない
- R&Dを情報の非対称性を生み出し、戦略を高度化する取り組みと捉えるべき
- 日立や味の素は、R&Dで蓄積した独自の知によって競争優位性を持つ
多くの日本企業がサステナビリティに取り組みながら、それを持続的な競争力や企業価値の向上に結びつけられていません。この閉塞感を打破するヒントは、R&Dの見直しにあります。R&Dは単なる技術開発や新製品創出のためのコストではなく、戦略の質を決定づける経営の中核機能なのです。(オルタナ編集委員/サステナビリティ経営研究家=遠藤直見)
サステナビリティに取り組んでも企業価値の向上につながらない背景には、サステナビリティを外部から与えられた制約条件として扱い、経営戦略の中心に据えきれていない構造的な問題があります。
この問題を解決するには、R&Dの捉え方を根本から見直す必要があります。R&Dは単なる技術開発や新製品創出のためのコストではありません。
「情報の非対称性*」により、自社だけが持つ最先端の知を生み出し、戦略の質を決定づける経営の中核機能なのです。
*市場や競合がまだ十分に把握していない技術や将来の変化について、自社だけが高い解像度の知を持っている状態。
■R&Dは「情報の非対称性」をつくり、戦略を高度化する
2026年1月7日付の日本経済新聞「経済教室」に掲載された、清水洋・早稲田大学教授の論考「企業は『最先端の知』で経営戦略の決定を」は、この点を鋭く突いています。
主な論点は次の通りです。
・ビジネス機会の源泉は「情報の非対称性」にあるが、外部情報だけでは持続的な競争優位は築けない。
・R&Dは、自ら情報の非対称性と新規性を生み出す営みであり、新しいビジネス機会の源泉をつくりだす。
・R&Dの最も重要な成果は新製品・サービスの開発にあるのではなく、効果的な経営戦略の構築に現れる。
・経営戦略がR&Dを規定するトップダウン型から、R&Dが戦略を主導する相互作用型への転換が必要。
・日本企業の課題はR&Dの量(投資額など)ではなく質。
最先端の知へのアクセスと高度研究人材の活用がR&Dの質と競争力を左右する。
清水教授は、R&Dを「情報の非対称性と新規性を自ら創出し、より効果的な経営戦略を構築するための営み」と再定義しています。この視点は、サステナビリティ経営を考える上でも極めて示唆的です。
■経営戦略の起点はサステナビリティに
本稿の冒頭で述べたように、多くの日本企業がサステナビリティに取り組んでいるにもかかわらず、それを持続的な競争力や企業価値の向上に転換できていない背景には、サステナビリティを外部から与えられた制約条件として捉えていることがあります。サステナビリティを規制対応や情報開示の文脈で扱ってしまう構造があるのではないでしょうか。
ESG評価や国際ルール、各種ガイドラインへの対応は重要です。しかし、それらはすでに市場全体で共有された「共通知」であり、それ自体が競争優位の源泉になることはありません。こうした外部情報を前提に策定された戦略は同質化しやすいという限界があります。
この点について、清水教授は、企業の競争優位の源泉は「情報の非対称性」にあると指摘します。誰もがアクセスできる外部情報だけでは持続的な競争優位は築けない。自らが最先端の知を生み出し、他社にはない判断材料を持つことが戦略の質を決定づけるという問題提起です。
社会課題が企業価値や事業構造そのものを規定する前提条件となりつつある現在、サステナビリティを単なる制約条件ではなく、「戦略を生み出す起点」として捉え直すことが求められています。
そのためには、R&Dをサステナビリティ経営の中核に位置づける必要があります。R&Dは、社会課題や技術潮流を先読みし、将来の制約条件や機会を「知」として内製化する機能です。
サステナビリティに関する将来情報を、他社に先駆けて自社の中に蓄積していくことで、より効果的で差別化された経営戦略を構築することが可能になります。
その結果、サステナビリティ経営は「横並びの対応」から脱却し、「機会創出と競争力強化を実現する営み」へと進化していきます。
■探索そのもので得られる知が経営方針に
サステナビリティ経営におけるR&Dとは単なる技術開発ではありません。自社の価値観(パーパス、企業理念)と長期ビジョンを起点に、社会や技術の構造変化を先読みし、「まだ他社が気付いていない未来への選択肢」を探索・蓄積する営みです。この探索の過程で得られる知こそが、経営戦略の方向性そのものを形づくっていきます。
その本質は、社会課題が市場化する前、規制・ルールが変わる前、技術が汎用化する前の段階で、社会課題の構造的理解につながる知を探索し、仮説を積み上げていくプロセスにあります。
こうして蓄積された知は必ずしも短期的に製品・サービスに結実するわけではありません。しかし、それこそがR&Dの最も重要な成果です。
なぜなら、それは「なぜこの社会課題の解決に取り組むのか」「なぜその事業領域なのか」「どのような社会価値と経済価値の両立につながるのか」という問いに対し、自社ならではの価値創造ストーリーを、説得力を持って語るための根拠となるからです。このストーリー自体が競争力なのです。
■日立や味の素、R&Dを基盤に課題解決目指す
この点で示唆に富むのが日立製作所です。同社は社会インフラ、エネルギー、デジタルを横断するR&Dを基盤に、社会課題を事業機会へと転換する戦略を展開してきました。
研究開発で蓄積された知が、事業部門や顧客との協創を通じてLumada(ルマーダ)として体系化され、事業ポートフォリオ改革や経営の方向性に大きな影響を与えています。
味の素も同様です。同社は長年にわたり磨き上げてきたアミノサイエンスという独自のR&D基盤を起点に、健康・栄養・環境といった社会課題を、自社ならではの価値創造ストーリーへと発展させてきました。
これは単なる製品開発ではなく、R&Dが経営戦略の方向性を規定し、経営と一体となって価値創造の軸足を形作ってきた例といえるでしょう。
両社は、R&Dを短期的な市場ニーズへの対応ではなく、社会課題の構造を深く理解するための長期的な知の蓄積として位置付けています。ここに、他社が容易に模倣できない情報の非対称性が生まれ、持続的な競争優位を確立し、自社ならではの価値創造ストーリーを創出できる要因があります。
■R&Dの「質」と「位置付け」を問い直そう
■サステナを持続的な競争力に転換する3視点
■R&Dの再定義がサステナ経営の成否を分ける