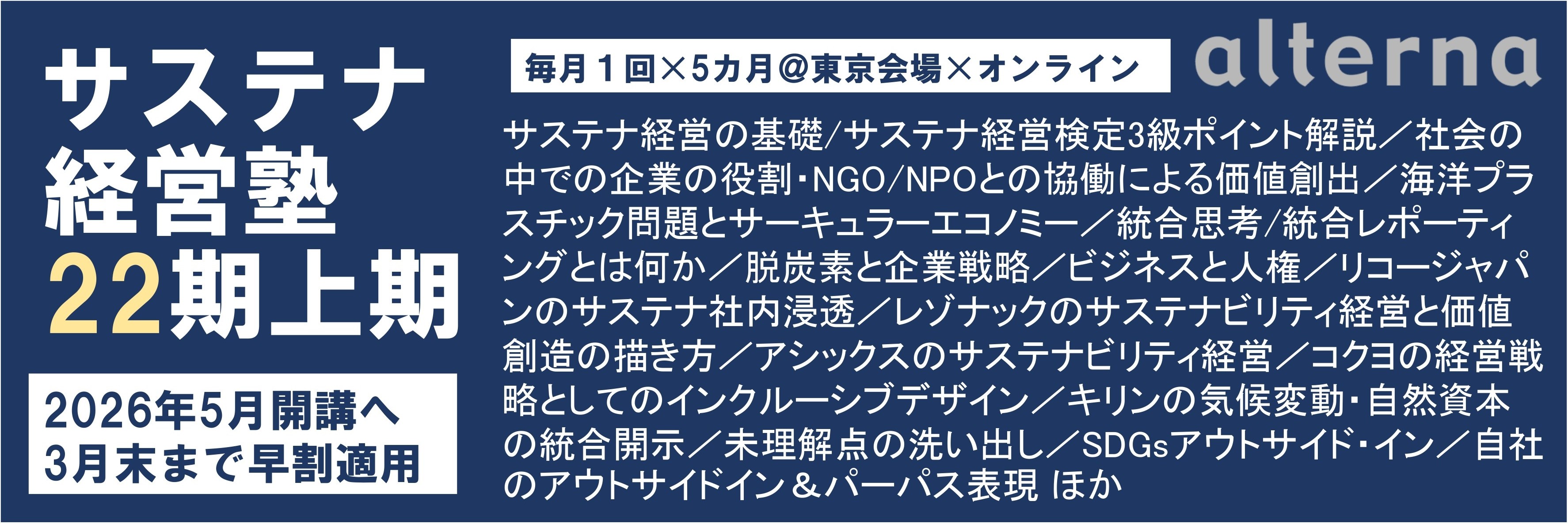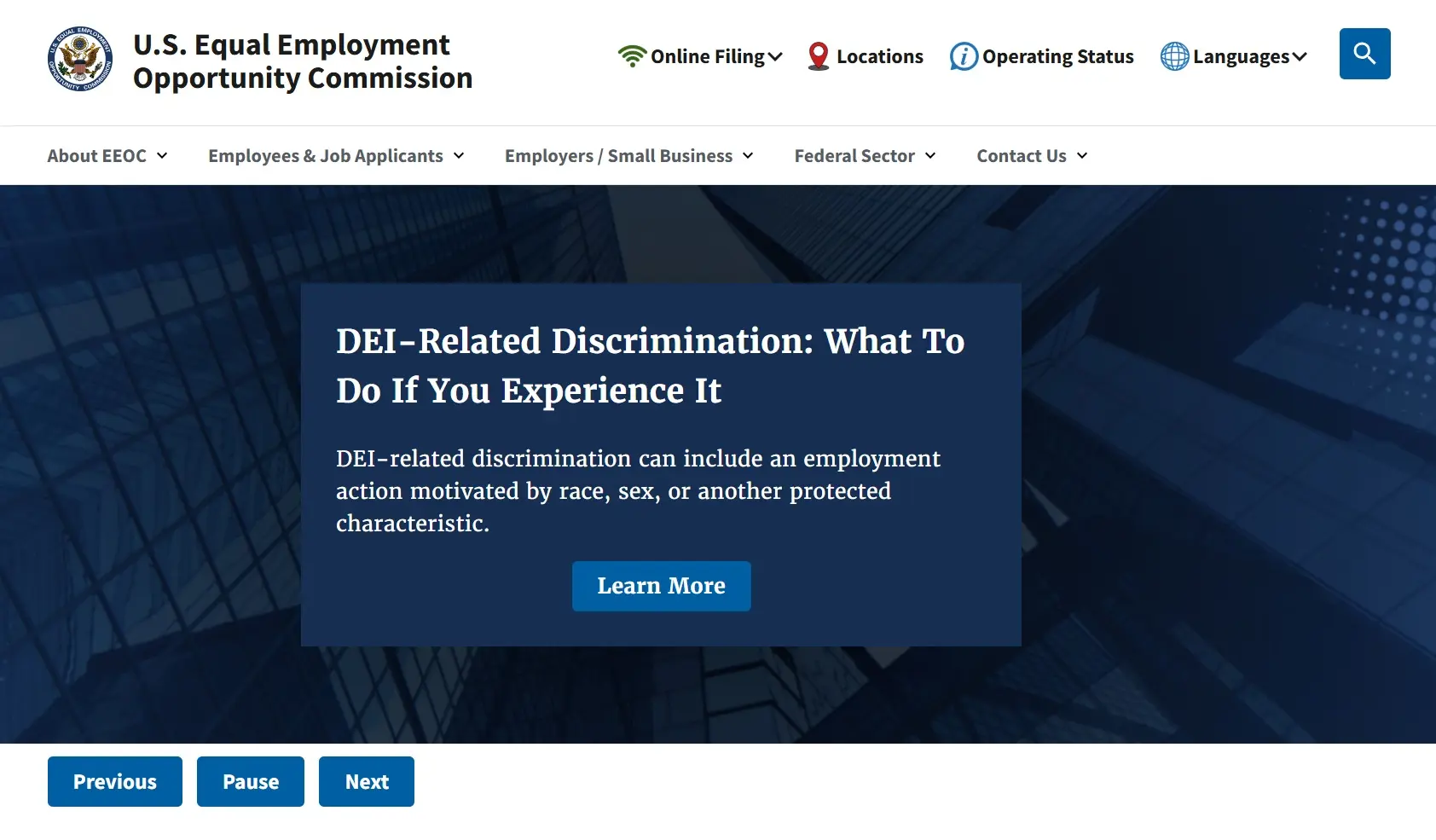■フラッシュフィクション「こころざしの譜」
山科重雄が住む郊外の古いマンションはちょっとした森の中にある。気に入って若い時に無理をして購入したものだ。バブルの絶頂期でこの辺りでは初の億ションと騒がれた。3LDKだが百平方以上あり角部屋で風が通り抜ける。天気のいい日には五階のベランダから遠くに富士山が見えた。
今日も夕陽を受けて赤く輝いている。落日の彼岸に本当に浄土があるのだろうか。以前の山科ならすぐ絵筆をとるところだが、その荘厳さと裏に潜む寂寥を過剰に感ずるこのごろはとてもそんな気になれない。部屋には自作の絵が掛かっており二科展に入選したものもあるが、傍らに張ってある新聞記事はすっかり黄ばんでいる。
下の通路から子どものぐずる声が聞こえてきた。母親に何かをねだったのに聞き入れられず駄々をこねているのだろう。ほほえましい風景のはずだが、ささいなことをうるさく感じる自分を発見してうろたえる。
老いが静かに、しかし着実に迫るなかで、 先日ショッキングな出来事があった。同じフロアの夫婦が自殺したのだ。詳しい事情はわからない。朝方、パトカーと救急車が玄関に横付けにされ、廊下を人があわただしく行き来するので玄関の扉をそっと開けてみたら女性が廊下に座り込んで泣いていた。
「何で自殺したの。一体どうしちゃったのよ」
連絡が取れなくて心配で訪ねてきた娘さんだと後で知った。亡くなったのは山科と同年代の老夫婦で、時々見かけたことがある。仲睦まじそうだったのに自殺とは。このマンションも高齢化が進んでいるはずだが実態は見えにくい。建物の方はあちこちが傷んでおり、隠しようがない。それでも、エレベーターを取り換える大工事が始まると聞いた時には驚いた。
山科は狭心症だが、何年か前に暗闇で杭に躓き膝に大けがを負った。以来杖が手放せなくなっている。妻の蓉子は精神を病んでおり週二回のデイサービスに山科の付き添いが欠かせない。蓉子はデイのレクリエーションの時間を楽しみにしている。山科は妻が終わるまで暇つぶしに別室で膝の機能訓練に励んでいる。
エレベーター工事は二カ月かかるという。その間、ごみも出しに行けない。外出も買い物もどうしたらよいのか。デイサービスも諦めるしかないか。そんな心配をしていたら、管理組合の理事会が階段昇降サービスの会社と契約し足腰の悪い居住者をリフトで運んでくれるという。駅で飲料を運んでいるところを見かけるが、アレだ。操作係は付くが、座席に座るだけでロボットの様に自動で階段を一段ずつ昇降してくれる。
山科はその便利さに感謝したが、一方で昇降機に頼らないと外出もできない自身を情けなく感じるようになった。
そんな時、起きたのが漏水事故だった。買い物から帰ってドアをあけた途端、水がドアの下からあふれ出てきた。ザーザーと音がしているのに、リビングの蓉子はソファーに座りぼんやり外を見ている。
「ごめんね。許してね。どうしてわかってくれないの」
調子の悪い時の常で、小声で見えない息子に謝り続けている。テーブルの上にはウイスキーの瓶があった。蓉子はアルコール依存症で、精神崩壊はそれが原因だった。元をたどれば、山科と蓉子の恋愛問題にたどり着く。
「漏水は排水管の劣化が原因らしい。このマンションももう終わりだなあ」
山科はそう言いながら心の奥で何かが壊れるのを感じた。デスクの引き出しをそっと開けてみる。伝手を頼って入手した青酸カリが隠してある。自分が心臓発作に襲われる前にこれを蓉子に飲ませ、その後に自分も自殺するしかない。妻が生き残ったらひとりで生きるのは困難だから。
二人は「不倫愛」だったが何の後悔もない。愛する者同士が結ばれるのは当然のことだし、ふたりは真剣に愛を育んできた。結婚して子宝にも恵まれた。なぜかは不明だが、 そのひとり息子が長じて親をなじるようになった。「自分勝手だ」と。息子は高校生の時、 家を出、今も音信不通だ。蓉子はその苦しさをアルコールで紛らわせようとしたのだ。
建物に寿命があるように人にも、もういいという限界がある。そんなある朝、杖を頼りに階段を下りてみた。やはり膝が痛い。ふと見ると思いがけなく下から幼い女の子が階段を昇ってきた。手に本のようなものを抱えて、 イチ、ニ、イチ、ニと声をかけながら調子をとって昇ってくる。生命力にあふれている。
「おはよう。わたし六階だから」
笑顔がはじけた。いいものに出合えた日だった。
自殺した後、他人に迷惑をかけたくないと思い、毛布や古い服をゴミ捨て場に持って行った。掃除のおばちゃんが怪訝そうな様子で、大掃除ですかと首をひねった。黙っていると、「今度の日曜、うちでジャガイモ掘りをするのですが、もし、よければ来ませんか」。 部屋に戻って蓉子に話すと表情が緩んだ。
おばちゃんの家は大きな農家で野菜畑や果樹に囲まれた昔ながらの暮らしだ。顔は知っているが普段、言葉を交わしたことはないが自然の中で生き生きして見える。近くの親戚もやってきてバーべキューが始まった。 そのおいしいこと。人生も悪くない。蓉子の目がそう言っていた。
ドアチャイムが鳴った。扉を開けると管理組合の理事が立っていた。
「山科さん、絵をお描きになるそうですが、 よかったら、マンションの子どもたちのためにお絵描き教室を開いていただけませんか」
思いがけない提案だった。
コミュニティ再生のためボランティアネットワークをつくった。子どもの駆けっこ大会やクリスマス会、高齢者の茶話会を企画している、地震など災害が起きたらマンションの居住者の手伝いをするのだという。
いや折角だが、と断ろうと思った瞬間、理事の後ろからあの女の子が笑顔をのぞかせた。あれはスケッチブックだったのか。
「おじいちゃん、お絵描き教えてください」
山科は言葉を飲み込んだ。そして、いつの間にか、絵の具はそろっていたかな? 絵筆とパレットはどうだったかな? そんなことを考え始めていた。(完)