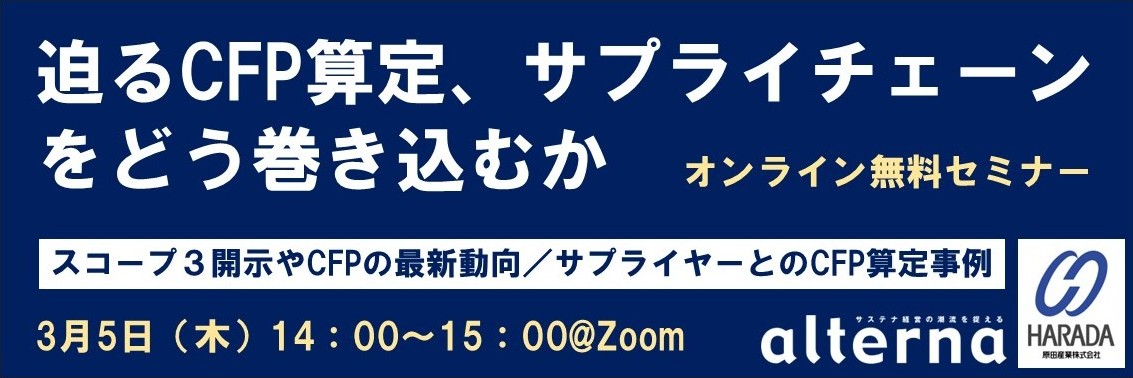記事のポイント
- 国際自然保護連合が世界自然保護会議で新たな枠組み「RHINO」を発表した
- 生物多様性保全に向けて、どこで何をすればどれだけの保全効果が得られるかを示す
- 科学的根拠をもとに、生物多様性をどこで再生すればよいのかの行動指針となる
国際自然保護連合が世界自然保護会議で、ネイチャーポジティブを高い信頼性で加速させる新たな枠組み「RHINO」を発表した。生物多様性に向けて、どこで何をすれば、どれだけの保全効果が得られるのかを、科学的根拠をベースに示すものだ。ネイチャーポジティブに向けて「どう行動し、どう測るのか」、世界共通の物差しとして、RHINOの活用促進を期待する。(サステナブル経営アドバイザー・足立直樹)

ネイチャーポジティブの加速につながる
TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)の開示を終えた企業が今、共通して直面している問いがあります。
「では、実際にどこで何をすればいいのか」
目標は立てた。開示もした。しかし株主総会で「具体的な成果は」と問われたとき、あるいは経営会議で「投資対効果は」と詰められたとき、多くの担当者が言葉に詰まっているのではないでしょうか。
この「理念」と「実行」の間にある空白—いわばミッシング・リンク(Missing Link)を埋めるツールが、2025年10月アブダビ(アラブ首長国連邦)で発表されました。
私は10月9日から12日まで、JBIB(企業と生物多様性イニシアティブ)※1の事務局長として、アブダビで開催されたIUCN(国際自然保護連合)世界自然保護会議(WCC)に参加してきました。
4年に1度開かれるこの会議は、「自然保護界のオリンピック」とも呼ばれ、世界中から数千人が集まり、NGO、政府、企業が同じテーブルで自然の未来を議論する一大イベントです。前半のフォーラム(10月9日~12日)では、様々な組織が進捗や新しい計画、イニシアティブなどを発表します。
今回の会議では、IUCNが絶滅危惧種の評価であるレッドリストの最新版や、企業の間でも関心が高まっている「NbS(自然に基づいた問題解決方法)ガイダンス第2版」など、多数の発表がありました。
その中で私が最も注目したのは、今回初めて発表された「RHINO(ライノ、Rapid High-Integrity Nature-positive Outcomes)」という、高い信頼性で自然回復を加速する新しい枠組みです。
今回はその特徴と、これが企業にとってどういう意味を持つかを解説します。なるべくわかりやすく説明しますが、どうしても専門的な内容になることはお許しください。
■なぜRHINOが必要なのか
2022年の生物多様性条約COP15(第15回締約国会議)で、生物多様性世界枠組(GBF)が採択され、「ネイチャーポジティブ」という世界目標が合意されました。
それに貢献すべく、企業はTNFDのガイドラインにしたがって情報開示を行い、さらにはSBTN(科学に基づく自然に関する目標)のガイダンスにしたがって、自然についても科学的な目標設定を進めています。
しかし、現実はどうでしょうか。
多くの企業がTNFDのレポートを発行し、SBTNで目標を宣言しても、実際の生態系は何も変わっていない。むしろ劣化と破壊は続いている。ESGファンドが「自然関連」銘柄をうたっても、投資先の現場に自然回復の証拠がない。残念ながら、それが現状なのです。
これはある程度いたしかたないことでした。なぜなら、これまではどれほどネイチャーポジティブに貢献しようという意思があっても、「実際にどう行動し、どう測るのか」という最も重要な部分が明確ではなかったからです。
RHINOは、その空白を埋めるために登場しました。 理念を実践に変えるための科学的かつ信頼性の高いツールとして、IUCNが企業に示した明確な指針と言えます。
■地球上の生物多様性「ヒートマップ」
RHINOの中心にあるのが、2020年に開発されたSTARメトリクス(Species Threat Abatement and Restoration Metrics)という、種の絶滅リスクを定量的に評価する科学的な成果指標です。
IUCNが国際的な専門機関と開発したこの数理モデルを使って、絶滅に関する状態が評価されている13万種類以上を対象に、「どこで、どんな行動を取れば、どの種の絶滅リスクをどれだけ下げられるか」を1平方キロメートル単位で数値化したデータベース、いわば地球上の生物多様性の「ヒートマップ」が作られようとしているのです。
これがどれほど革新的か、具体例で考えてみましょう。
例えば、あなたの会社の工場がある地域で植林を行うとします。従来であれば、「何本植えた」「何ヘクタール回復した」という活動量で報告するしかありませんでした。しかしRHINOを使えば、「この場所でこの樹種を植えれば、○種の絶滅リスクを△%下げられる」と事前に推定できるのです。
つまり、企業や自治体が自らの活動領域をこの地図に重ね合わせることで、「どこで何をすれば、どの程度の保全効果が得られるか」を科学的に判断できるようになります。
複数の選択肢の中から、効果的で費用対効果の高い保全行動を選び、さらに実施後にはモニタリングを行い、予測値と比較してモデルをキャリブレート(校正)する。この「計画→実施→検証」のサイクルを科学的に支えるのがRHINOなのです。
■テクノロジーが支える信頼性
RHINOの「High-Integrity(高い整合性と信頼性)」とは、単なる正確さではありません。誰がどこで計算しても同じ結果が得られる再現性と透明性を意味します。
計算式、データ構造、入力形式がすべて標準化されているため、グリーンウォッシュや恣意的な評価を防ぎ、世界共通の「ネイチャーポジティブの物差し」を提供してくれます。
さらに、理論モデル(STAR)と実測データを組み合わせることで、モデルの現実適合性を高めています。AIや衛星、リモートセンシングを駆使したキャリブレーション(校正)によって、少数の実測値から全体を高精度に推定する。この「科学的整合性 × テクノロジーによる補正」こそが、RHINOを「High-Integrity」たらしめる理由です。
RHINOは、企業に「何を守るか」ではなく、「どれだけ回復させられるか」を問うツールです。GBF、TNFD、SBTNをつなぐミッシング・リンクとして、行動と成果を一貫して可視化する。これにより、企業の活動は、理念から実装へ、宣言から検証へと進化します。
今回の会議では、6社のパイロット企業がRHINOを試用し、その有効性を報告しました。彼らの発言を額面通りに受け取るなら、RHINOはまさにネイチャーポジティブの実行プラットフォームになり得ます。
IUCNがこのタイミングでこのツールを発表したことに、私は「もう時間がない」という危機感と、「企業を本物のパートナーに」という強い意志を感じました。
■サイが示すこと
英語に強い方であれば、RHINOと聞いた瞬間にrhinoceros(サイ)を思い浮かべたのではないでしょうか。rhinoはサイの略称だからです。
サイは、絶滅が危惧されている大型哺乳類の代表であり、人間の欲望と自然破壊の象徴と言えます。しかし同時に、厚い皮膚と力強い脚で大地を踏みしめるその姿には、粘り強さ、誠実さ、そして生き残る意志も感じられます。
IUCNがこの新しいフレームにRHINOという名を与えたのは、単なるゴロの良い略称だからではないでしょう。今まさに迅速な行動(Rapid)、科学的整合性(High-Integrity)、確かな成果(Outcomes)が必要だという強いメッセージです。
そしてそれは、力強く、誠実で、自然を守るためにまっすぐ進む——私たちが今求められている姿勢も象徴しているように思います。
日本には古来、自然と共に生き、自然の一部として暮らす知恵がありました。その精神を現代の科学技術と結びつけ、次の世代に引き継いでいく。RHINOは、そのための新しい仲間になるはずです。私はこの新しい仲間の登場を心から歓迎し、みなさんに紹介したいと思います。
※1 JBIB(一般社団法人 企業と生物多様性イニシアティブ):JBIBは、生物多様性の保全と再生に真剣に取り組む70社近い企業のイニシアティブです。こうした活動に興味のある企業の方はぜひご参加ください。今回の記事のような情報をより詳しく紹介し、また一緒に研究・実践しています。
※この記事は、株式会社レスポンスアビリティのメールマガジン「サステナブル経営通信」(サス経)526(2025年10月22日発行)をオルタナ編集部にて一部編集したものです。過去の「サス経」はこちらから、執筆者の思いをまとめたnote「最初のひとしずく」はこちらからお読みいただけます。