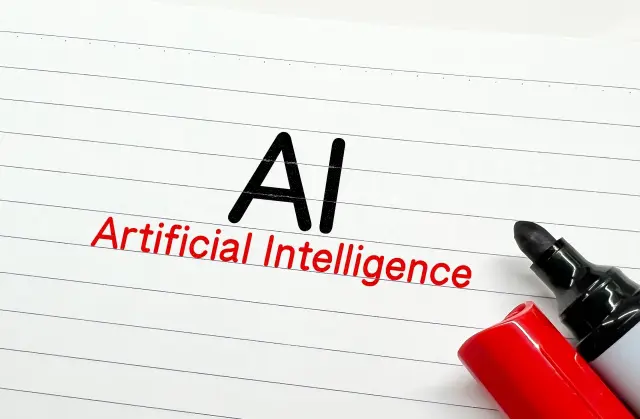「ショート・ショート」(掌小説)こころざしの譜(15)
瀬戸内海にこんな島があることは誰も知らないだろう。忘れられたような閉じた島。春は島影がおぼろに揺れ、夏には光の束がきらきらと海の面で踊る。秋ともなるとの夕焼けを背に鳥たちが仲良く巣に帰っていく。今頃の冬の季節はハンセン病療養所に流れる「赤とんぼ」や「七つの子」といった童謡の重いメロディーが胸に迫ってくる。
私は90歳を超え先は長くない。自然に還るための準備を始める齢になった。幼いころ療養所に入ったから、外の社会というものをほとんど知らない。ここには今150人が住んでいる。多くの友が既に旅立ったが寂しくはない。皆、私の周りにいる。ほら、そこのウグイスは源さん、季節はずれのセミは富やんの生まれ変わり。蝶も虫も昔の仲間だ。
療養所といっても実は本当の病人はひとりもいない。かつては不治の病と恐れられたが、特効薬の開発で全員が治っている。治癒したのなら家へ帰ればよさそうなものだが、それが難しい。病気で手足が変形したり、欠損したりしている。目をやられた人も多い。
大きな声では言えないが、われわれは実家ではとっくにあの世の住人ということになっていて戸籍がないとか、家族から「親兄弟のことを思ってくれるなら、絶対に帰ってこないでくれ」ときつくいわれていたりするのである。
本来なら頼りになるはずの子供もいない。ほとんどの人が療養所では本名を名乗らず偽名なのも納得がいく。今でもここは「囚われの島」であり、迷宮なのである。
島の西側がいい釣り場になっていて魚がいくらでも釣れる。すぐ向こう側に本土が見える。手を伸ばせばすぐに届きそうな距離だ。本土と島を隔てる海の幅はたったの22㍍しかない。この水路はその狭さにもかかわらず流れが急で渡るのは容易ではない。脱走を図った何人もが波に飲まれて死んでいる。なかなか越せない永遠の瀬なのである。
ここに収容される患者はまず待っているお金をすべて没収される。引き換えに療養所でしか使えない特殊通貨が渡される。だから無事に海を泳ぎ切っても普通のお金を持っていないので、すぐ連れ戻されてしまうのがオチであった。
療養所に戻れば、掟破りということで制裁が待っている。監房と称する牢屋があり、ここに入れられてしまうのである。反省しないと出してくれないから、冬の寒さなどでいつの間にか死んでいたなんてこともあったらしい。
療養所は病院ではなく、ひとつの「村」だったから、自分たちでなんでもしなくてはならなかった。道路工事、花壇つくりから仲間の理髪、ガーゼ再製、病人の看護まで忙しかった。死者が出たら葬式、火葬まで自ら行った。火事が起きても消防車が来るわけではないし、誰かが木で首をくくっても警察は来ない。
時々、学生さんが、ワーキングキャンプといって力仕事の手伝いに来てくれたのはうれしかった。きれいな女の子もいた。そんな学生も出入りの時は消毒の洗礼を受ける。予防着にマスクをさせられ、どんな気持ちだったろうか。
同情されるのは御免だとばかりに、学生さんに辛く当たる患者仲間もいたけど、若い人は純粋だ。最後には皆、仲良くなった。後に難病になったある学生から手紙をもらった。筋ジストロフィーを病み、絶望して自殺しようと考えた時、われわれのことが頭に浮かんだそうだ。
あれほどの苦しみの中でしっかり生き、希望を見つけようとしていた姿を思い出し、自分も強く生きようという気になったという。買いかぶりだけど、ちょっとうれしかった。
こんな信じがたい話もある。患者同士の結婚は許されていた。しかし、結婚する男はワゼトクミーという断種手術を強いられた。大変な人権問題だ。日本独自の制度で世界に例がない。私は結婚しなかったから知らないが、結婚しても暮らすのは個室じゃなかった。オッと、キジになった芳子さんが何か言いたそうだ。
「この話をちゃんと伝えるまでは、あの世にいっても落ち着きませんよ」と芳子さんの霊。若いころは端正な美人だった面影がある。
「妻となった女性が暮らす相部屋に夫が通うの。12畳に4人の女性。一応ついたてを立てるのだけれど、夫婦生活のプライバシーもなにもあったものじゃないわ。必死でこらえても、あの時の声が周囲に聞かれてしまう。同室の独身の女性なんてたまったものじゃないですよ。犬猫じゃあるまいし」
男性は断種を義務づけられていたものの、間違って妊娠してしまった例もある。今日は経験者のリスの梅さんをお招きしてある。
「身ごもっていることが分かった時、夫とふたりで療養所から逃げ出そう、赤ちゃんを産んで外の誰かに預けようと話し合った。ところが、夫の留守を狙って、医者から呼び出されたんです」と梅さんの霊は真っ青な顔で語り始めた。
「診察台の上に乗せられて足を縛られた。激痛で気を失い、しばらくして意識が戻ったら、目の前に女の赤ちゃんが。7か月だった。医者の目を盗んで赤ちゃんを見せてくれたの。かわいい子だった。そのあと、決められた通り、看護婦がガーゼを赤ちゃんの鼻に当てると、窒息した赤ん坊の足がブルブルと震えて。絶対に忘れることができない」。梅さんはこらえきれずに嗚咽を漏らした。
本当にいろんなことがあった。しかし、語るというのは難しい。自分の思いというものが変化するから。療養所の生活は辛くて、悲しくて、苦しいことばかりだった。しかし、今、思い出すのは不思議と楽しいことばかりだ。多くの出会いがあり、ここへ入ってよかったとさえ思えるくらいだ。もちろん、私を差別し、無理矢理、療養所という収容施設へ押し込めた人たちへの憎しみは消えない。しかし、縁を切られた家族や親せきには恨みはない。だって亡くなった親や兄弟たちは心の宝物だ。政府にも怒りは感じるが、今ここでの福祉的な生活を提供してくれるのは政府なんだ。あれこれ考えると何も言えなくなってしまう。
最近、療養所で1千万円、2千万円といった多額の貯金を残して亡くなる人もいる。相続人がいないということで、そのお金を国に持っていかれるケースもある。せっかく国から勝ち取った賠償金を没収されるみたいでやりきれない。
皆、貧しかったから一生懸命に貯めたお金もあるだろうに、残すべき兄弟も子供もいない、その孤独はつらい。
ああ、雪が降ってきた。冷えるわけだ。本当に静かな夜だ。もう眠らなくてはな。ああ、寒い。おやすみ。
(完)








-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)