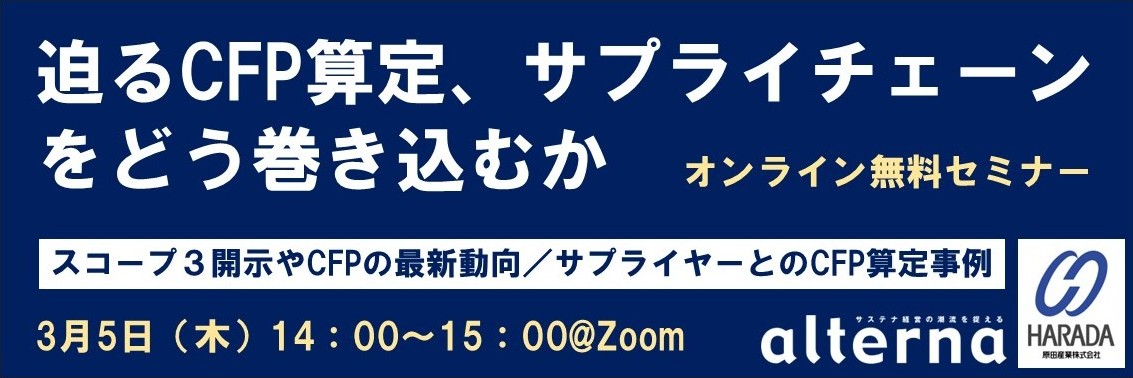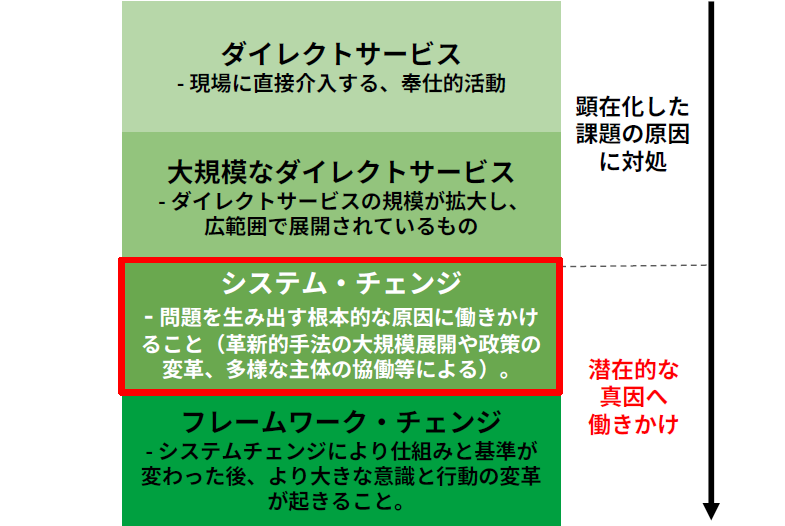企業理念を継承する重要性
『サピエンス全史』では集団は150人を超えると、その集団を維持するのが困難になるため、架空の物語を創出することで、多数の人間を同じ目的に向かって糾合できると述べられています。そうした集団を長きにわたって結束させる「妄想」が、企業理念やパーパスなど企業活動を行う目的であり、それは専ら社会的な価値と深く結びつくものであります。企業理念に「わが社の売上・利益の最大化が、わが社の第一の目的である」といったようなものを掲げても誰も心を動かされないでしょう。
社史を編纂する過程では、企業理念や社是といった企業の存在意義を規定する概念や、企業のDNAとも言える経営判断や企業文化、すなわちその企業の価値創造にまつわるストーリーを知ることができます(全ての社史でということはありませんが)。そして、社史にそれを刻むことで、後世の従業員などのステークホルダーに伝えていくのです。従業員にとっては、多くの時間と労働力を割く自分の企業の歴史や、何を大切にしてきたのか、どんな変節があったのかを知ることは、自らの使う時間に意味を付加することでもあり、より社会に開かれた意義を見出すことにもつながることでしょう。
それを裏付けるように、『創業三〇〇年の長寿企業はなぜ栄え続けるのか』では、長年生き残っている企業、創業300年以上で年商50億円以上のいわゆる「日本型サスティナブル企業」が分析されており、その経営を支える要素として「価値観をつなぐ」ことにあり、それに沿ったコア能力を発揮し、身の丈経営に徹することが重要と述べられています。この「価値観をつなぐ」ために最も適したものが「社史」、もっと言えば、「社史を制作する」という営みだと考えます。自らの企業の重要視するものは何か、それはなぜか、生々しく、深く、長期的視野による思索・議論・決定が社史編纂の過程で織りなされ、それは企業の存続理由とステークホルダーとの関係性に関わる極めて重要な活動です(制作する企業自身の制作スタンスにもよりますが)。
ぜひとも貴方と深く関わる企業の社史をご一読ください。それはその企業が情熱をもって歩んできた道のりと、それを編纂した人々の汗と涙の結晶です。社史は企業が発行するどの媒体よりも多様で、書き直しが重ねられ、想いが込められたものであり、長く遺っていく、実に興味深いものです。
一方で社史を発行する企業は、歴史に残る事業として、改めて自社の価値観を整理し、議論を重ね、屋台骨となる方針を共有したうえで、社史編纂に注力し、その社史に恥じない経営を心掛けることで、長期的な観点で、あるいは広い視野で、より社会に寄り添った意思決定をし、従業員やステークホルダーとそれを分かち合ってゆけるのではないでしょうか。
※1 『成果を生み出す社史の作り方』 浅田厚史著 SMBC経営懇話会
※2 『全国「老舗企業」調査』 東京商工リサーチhttp://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20161202_01.html
※3 『創業300年の長寿企業はなぜ栄え続けるのか』グロービス経営大学院著 東洋経済新報社
※4 『企業を活性化できる社史の作り方』出版文化社