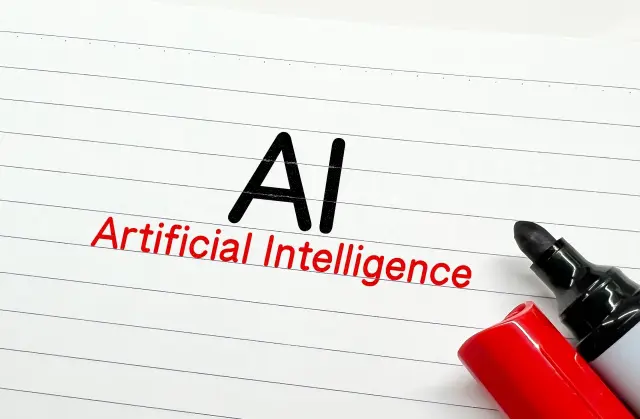霧子の墓は山の麓の寺の一画にあった。日が陰り始めた墓地を案内しながら住職は愛想がよかった。
「それはそれは、東京からわざわざ。森達哉さんとおっしゃるんですか。仏さまは高校生のころからかわいいと評判の子でしてな。気の毒なことでした」
住職が去って間もなくだった。花を供え線香をあげていると、自転車の急ブレーキの音とともに誰かが走り込んでくる気配があった。
「達哉さん、やっぱり来てくださったんですね」
振り返ると、息せき切った夕子がそこにいた。Tシャツにカーディガンを羽織っているが、ジーンズの足元はサンダル履きだった。よほど慌ててきたのであろう。
「遠くからわざわざ来ていただいて、姉も喜ぶと思います」
「夕子さん、久しぶりだね。この度は大変だったね、何と言ったらいいのか」
何年か前、霧子が東京の女子大に通っていた妹の夕子を連れてきて3人で会ったことがあった。確か、原宿でおでんを食べたのではなかったか。霧子に比べると明るい性格で、その時もよく笑った。故郷へ帰り、高校の英語の先生をしているはずだ。
「雑誌社、退社したそうですね」
「ああ、去年の暮れにね」
「やはり、姉とのことがあって?」
思いがけない質問にいくらかたじろいだ。
「ごめんなさい。でも知っています、達哉さんが姉に結婚の申し込みをして、それを姉がお断りしたことも」
何か言おうとしたが、言葉にならなかった。
「達哉さんの家族に迷惑はかけられないと言っていました。それじゃあ、結ばれないのに。馬鹿ですよ、姉は」
夕子は感情を抑えていたが、細い肩が小刻みに揺れていた。よく似た顔立ちだけに、まるで、霧子がそこに立っているかのような錯覚を覚えた。
「何を言っても言い訳になるような気がする」そう言葉を絞り出すのが精いっぱいだった。
「もう、済んだことだと、そうおっしゃるんですか」夕子の口調は容赦なかった。
霧子とは長い間、近くにいたのに、最後は気持ちがすれ違ったままだったと思い込んでいたが、自分の勝手な思い込みだったのか。
「田舎に帰って姉妹でシードルでも作ろうかなって言ってたけど、姉は東京から離れる気はなかったんだわ。どんな形であっても、あなたには一緒にいてほしかったんだと思います、きっと」
心の中を乾いた風が吹き過ぎていく。夕子はさりげなく涙をぬぐい、姉が遺したものですと、一通の封書を差し出した。
もがり笛
リンゴの夢を
絶たんとも
ついにぞ添わぬ
八重の遠の君
「単なる短歌ということで警察は気づかなかったみたいです。でも、これを受け取った時、すぐわかりました。姉のモ、リ、タ、ツ、ヤに向けた遺書だと」
私は思い出していた。二人ともまだ若かった。夕子は安いカメラしか買えなかったし、私は記事がうまく書けなくて悩んでいた。それでも幸せだった。いつも一緒だった。ずっとそのはずだった。一陣の湿った風と雨粒が落ちてきた。霧子のことは思い出としてひっそりポケットに詰め込んで生きていこうと決意していたが、今はそれもむなしい。むしろ背負うべき罪が覆い難くそこにあるような気がした。 (完)








-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)