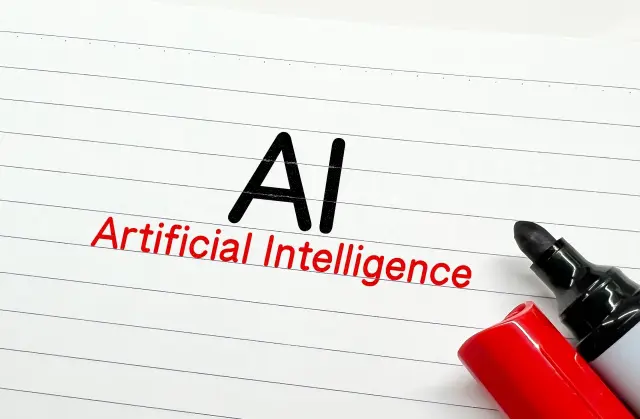◆「ショート・ショート」(掌小説)こころざしの譜(40)
子供たちを連れて丘に登る。秋の澄んだ夕陽を受けて青磁色の海が白いレースをひらめかせている。真砂卓也は埠頭に係留してあるヨットを見下ろす。五隻ほどが白い船腹を見せて踊っているようにしなやかに浮き沈みしている。
「卓先生、きょうもガマ号いるね」髪を三つ編みにした佐奈が隣に腰を下ろす。卓也が連れているのは様々な問題を抱える子どもたちだ。佐奈は特に気難しい子だった。NPOが不登校児を預かり、職員の卓也が妻、彩子ともどもアパートで共同生活をしている。
佐奈は全長40フィートを超す大型艇がお気に入りで、その船を勝手にバスコ・ダ・ガマと名付けていた。
「卓先生がヨットで大航海をしたのは佐奈ちゃんと同じ中学生の時なのよ」風で乱れた髪を押さえながら彩子が口をはさむ。
「知っているよ。その話を聞いたからあの船にバスコ・ダ・ガマ号って名前をつけたんだ」佐奈が口をとがらせる。
卓也の父は霞が関の中央官庁に勤めていたが過労で亡くなった。いわゆるノンキャリだった。
「お父さまは死ぬほど働いても出世できなかったのよ。やっぱり東大に入って国家公務員総合職試験に合格しなくてはね」
それが母の口癖だった。卓也は中学2年生の秋、不登校になった。朝、家を出ても途中で気分が悪くなり公園でぶらつく毎日。母親はヒステリーを起こし、ちゃんと学校へ行っているか、卓也を尾行するようになった。反抗した卓也は母に暴力を振るい心療内科に通うほど病状が悪化した。
主治医から母に思わぬ提案があったのは、そんな時だった。
「知り合いに変わり者がいましてね、ヨットで南太平洋のテスト航海をするんだが、卓也君を乗せてみませんか」。40日間かけて、グアム、トラック諸島を回りミクロネシアのポナペ島までという大航海だったが、引きこもり支援のNPOのプロジェクトだと聞いて母は首をタテに振った。わらにもすがる思いだった、と後で聞いた。
「青い海、緑の島。私も行ってみたいなあ」
給食費が払えなくて不登校になったという佐奈が羨ましそうにつぶやく。
「ところが、それがひどい船旅でね」卓也は遠くを見やる。
いつの間にか、子どもたちが周りに集まってきている。クジラや海蛍の群れに出合い頭上の流れ星を楽しんだのも束の間、ヨットを巨大な嵐が襲ってきた。大波に10メートル以上も持ち上げられたかと思うと、次の瞬間、ジェットコースターよろしく海面にたたきつけられた。ゲーゲー吐いた。死ぬかもしれないと覚悟した。怖くて辛くて声を出して泣いた。
心配そうな母の顔が思い浮かんだが、頼れるのは自分だけだった。雨と海水に濡れながらベッドで足を踏ん張り続けやがて眠りに落ちた。
父島に到着すると髭面の船長が人懐っこい笑顔を向けて来た。「卓也、よく頑張ったな」。NPOの代表だった。他のクルーもコーラで乾杯してくれた。「バスコ・ダ・ガマ号にカンパーイ」。それが船の名前だった。
「嵐の中で引きこもりを乗り越えたんだね、卓先生」と男の子が勢いよく尋ねる。
「髭の船長に言われたんだよ。悪いのは親だ。お前は何も悪くないってね。僕は母が苦しんでいる姿を見ていたから、ダメな自分を責めていた。でも、その一言でスーッと楽になった。初めて自分を認めてもらえた気がしたのさ」
ポナペ島までヨットで行き、そこから飛行機で帰国した。自宅に戻って母と暮らすとまた不登校がぶり返した。環境が変わっていないのだから再発するのは当たり前だった。
鬱々とした日々が続く中、翌年の夏、突然、ポナペ島から電話が入った。髭の船長からだった。
「ことしは引きこもりや不登校児をたくさん連れてポナペ島にいる。スタッフが足りない。卓也、こっちへ来ないか」
飛行機でポナペに飛び近くの無人島での共同生活が始まった。豚の丸焼きとサカオという赤い飲み物で歓迎してくれた。気になる日本人の女の子がいた。日本が恋しいのか泣いてばかりいた。波うち際で星を見ながら話し合った。
「その女の子が、実は、この私」と彩子が照れながら自分を指さす。
「えーっ、無人島で知り合ったのか、スゲー」
皆が歓声を上げる。
一度壊れた親子関係を元に戻すのは至難の業だった。卓也も定時制高校を卒業するのに8年もかかった。卒業する時、何をしたらいいのかわからず、思いあまって髭船長に連絡した。
「ちょうどいい。職員として雇うから手伝ってくれ」。
NPOは、苦しむ子どもたちを明るく開放的な現地校で学ばせたり、日本食堂を開いて働いてもらったり、皆を元気にする事業を拡大していた。その最前線に放り込まれた卓也は夢中で働いた。貧困や差別、いじめ、病気など社会の病巣が子どもたちの背景に存在することもわかった。働くことで自分を取り戻し、はじめて母と対等になれた気がした。ようやく母と和解した。
「船長の息子が小さい時、海外事務所に来てね。そこで働いていた僕と一緒に暮らしたことがある。そのあと彼はそこで働き始め、いま僕の子供を預かってくれている」
「そういうのって、pay it forwardって言うのね」佐奈が言った。「何かをもらっても、それに対してお返しをするのではなくて、次の誰かのために力を貸すの」
彩子がうなずく。
「そう、日本語では『恩送り』というの」
ヨットの大航海は何回も続き、多くの悩める若者が参加した。同じ船の中で他人同士が暮らし、自分をさらけ出す。ギリギリの関係の中でケンカをし、和解し、そして相談しながら生きていく。教えるのでも教わるのでもない。他人を家族のようい受け入れていく。ともに生きるということを学んでいくのである。
「私たちが、アパートの共同生活で実践しているのは船の生活の再現なのね。でも、ガマ号の大航海はどうして中止になってしまったの?」
佐奈の質問に卓也はしばらく無言だった。
「子ども同士のケンカがあってね、ひとりが転んだ拍子に打ち所が悪くて死んだ。不吉だと言って現地の人がガマ号を焼いてしまったんだよ」
眼下の白いヨットを見ながら、卓也は、年老いてすっかりしぼんでしまった母に電話を入れてみよう、そう思った。 (完)








-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)