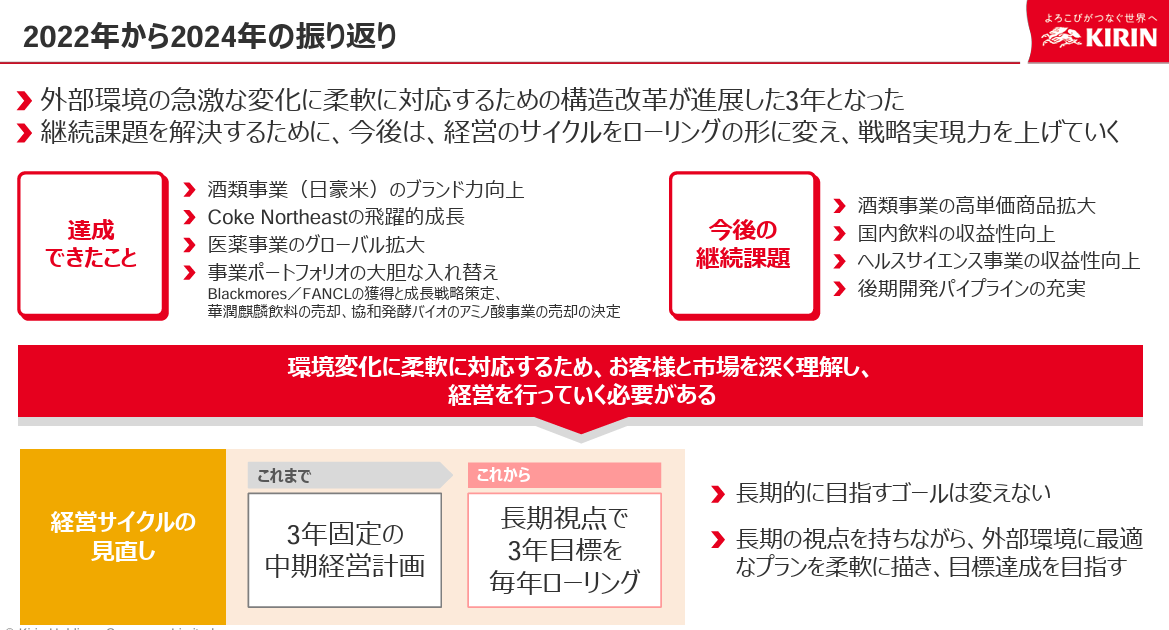■「エコ」視点の再解釈は広がるか
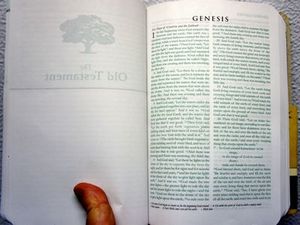
この本は内容だけではなく外装も「グリーン」だ。再生紙を使い、大豆原料のインクで印刷しており、表紙カバーは天然綿だ。また聖書の本文で、自然に関する教えが書かれた場所は文字の色が緑色になっている。
巻末には自然や環境のキーワードの索引集が付いている。大地、山、月、草などの約1千の言葉で、聖書に出てくる場所が示されている。
この本は大手出版社ハーパーの系列会社が発行した。同社サイトによれば、多くの人が環境に関心を向けているのに、その視点から編集した聖書がこれまでなかったことから企画したという。
反響はおおむね好評だ。リベラル色が強く、環境への感度が高い『ニューヨーク・タイムズ』『ワシントンポスト』など、米東部地域のメディアが好意的な書評を掲載した。
自然保護団体「シエラクラブ」、動物愛護団体の「ヒューマン・ソサエティ」なども、この聖書の販売を支援している。
ただし懐疑的な意見もある。一部報道によれば、ある宗教指導者は、「隣人を愛せ」などの言葉で知られるイエスの重要な教え『山上の垂訓』を引用しながら、「この時に主は他の生物のことを語らなかった。主は人間と他の生物を対等に扱っているのだろうか」と疑問を示していた。
環境倫理では、米国の歴史学者リン・ホワイト(1907―1987)の説をめぐる論争がある。ホワイトは、キリスト教を貫く人間至上主義の考えが、西欧の思想に影響を与え、環境を考えない科学技術や資本主義の暴走を生んで、現代の「生態学的危機」の一因になったと主張した。
ホワイトは自説の論拠に創世記中の「支配権」の問題を取り上げた。この論争は今でも繰り返され、決着はついていない。
過去にキリスト教は環境と対立する面があったかもしれない。しかし現代では、時代の流れに合わせ、その教義を見つめ直す新しい動きが始まった。
米国や世界の人々の心にどのような影響を与えるかはまだ不透明だが、社会を環境保護に動かす可能性があることは確かだ。(オルタナ編集部=石井孝明)