記事のポイント
- パルシステムは畜産加工品に「お米マーク」の表示を始めた
- 畜産動物の飼料に穀類ではなく米の使用を促し、米農家の経営を支える
- 畜産農家には、円安による輸入穀物の高騰リスクを回避できるメリットもある
パルシステム(東京・新宿)は2022年から、畜産加工品に「お米マーク」の表示を始めた。畜産動物の飼料に米の使用を促し、米農家の経営を支える。畜産農家にとっては、円安による輸入穀物の高騰リスクを回避できるメリットもある。(オルタナ編集部・下村つぐみ)

日本のコメの消費量の減少に歯止めが掛からない。農水省によると、主食用米の需要量は毎年、10万トン程度の減少が続く。日本の人口減少に加え、最近では、低糖質ダイエットが普及し、世代を問わず、コメを食べる人が少なくなっているという。
そうしたなか、パルシステムは、国内のコメ消費量を向上させるため、畜産動物の飼料としての活用に乗り出した。
お米を飼料として与えた畜産動物の加工品には、「米マーク」を付与する。マークには、「10」、「40」など数字が記載されており、飼料用米の活用が全飼料の何%に当たるかを示す。
パルシステムの畜産物仕入れ価格は、畜産家との話し合いによって決まる。飼料用米を使用していれば、「資源循環型」として仕入れ価格加算の根拠になり、生産者にとってもメリットになる。
農水省は2008年から、飼料用米の作付けに対する助成を始めた。2022年の飼料用米の作付面積は14.2万ヘクタールと、2014年の3,4万ヘクタールから8年で約4倍に増えた。飼料用米への転作は、棚田など地域の田園風景を守る意味合いもある。
2022年時点は、輸入トウモロコシと国内の飼料用米の価格はほぼ同じであったという。今後、さらに円安が進むと、輸入飼料はさらに値上がりが予想される。畜産農家にとって国産米の使用は、価格リスクのヘッジにもなる。



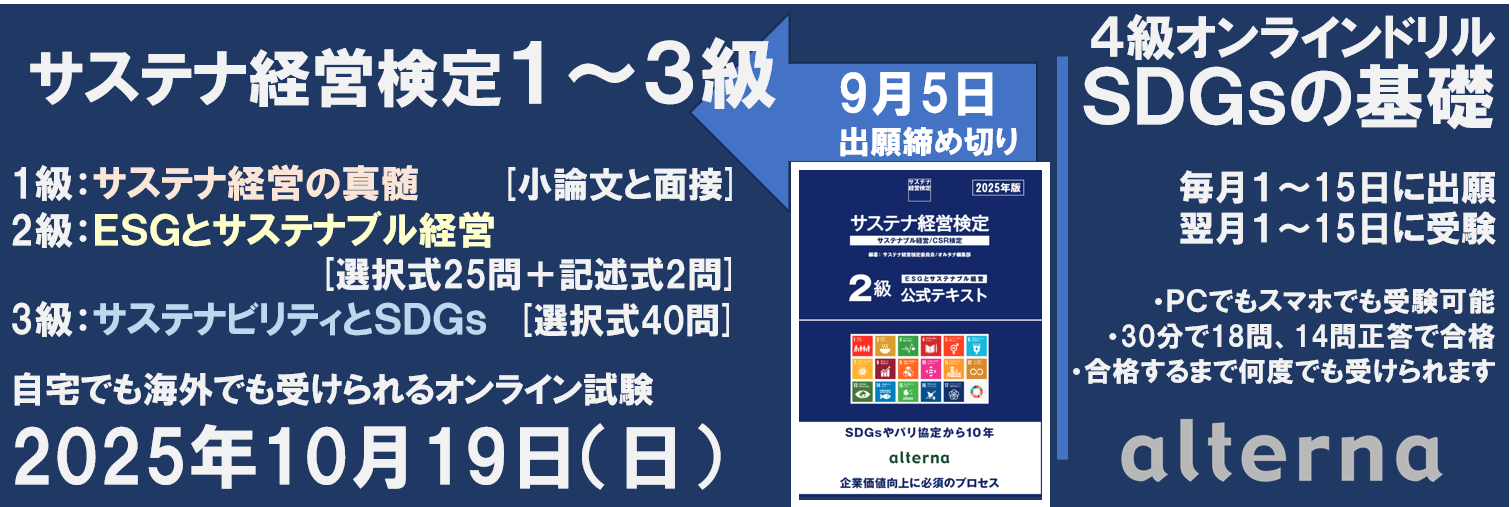






-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)






















