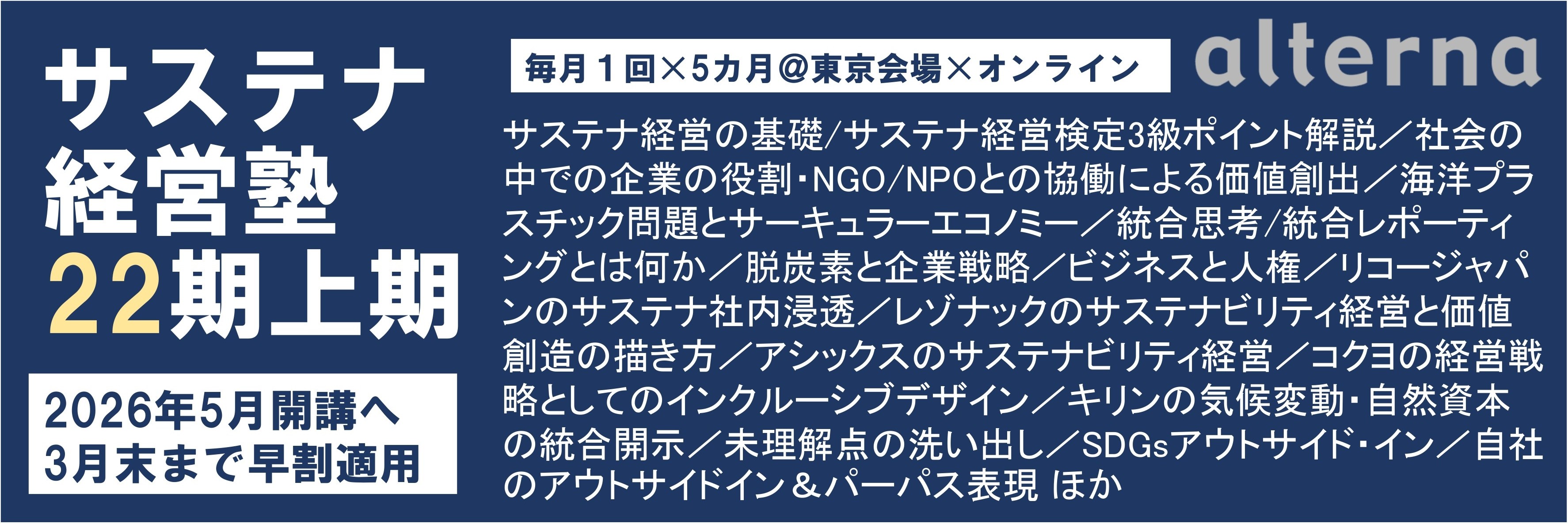宮城県石巻市で子どもの遊び場(プレーパーク)を運営する「こども∞(むげん)感ぱにー」が大事にするのは、やりたい遊びを自ら考える子どもの思いとそれを地域で見守り育てる居場所づくりだ。東日本大震災の復興支援のなかで生まれた。他団体との連携を通じ「プレーパークを石巻から全国へ」発信し続ける活動とそれを支える組織運営について、田中雅子代表に聞いた。(聞き手・村上佳央=非営利組織評価センター、堀理雄)

――活動のきっかけを教えてください。
私は東日本大震災直後の2011年3月20日に、宮城県石巻にボランティアに入りました。緊急支援を続ける中で気づいたのは、まちに子どもの姿が見えないこと。公園も被災して、子どもの遊び場や人の集まる場自体がなくなっていました。

地域の人たちと一緒に行政と掛け合いながら、被災した公園を更地に。そこでどんな遊びをし、どんな遊具を置きたいのか、子どもたちや地域の方と話し合いながら手づくりで遊び場をつくっていこうと決めました。何もない更地からのスタートでした。
緊急支援後も、子どもや地域の人が集まる大切な場を継続したいと、2013年に団体を立ち上げました。
子どもを信じる
――遊び場で大事にしていることは何ですか。
子どもが自分で考えてつくりだし、「やってみたい」を実現できる場をひらくことです。大人が何かを提供してあげる必要はありません。
例えばケンカが起きたとき、大人が止めて事情を聴いて「両方悪いね、お互い謝ろう」なんて、子どもにとっては大きなお世話なのです。ケンカのあと口を利かなくなるにせよ、仲直りするにせよ、自分たちが決めたこと。大切なのは子どもが自分で考えることです。私たち大人の役割は、子どもを信じて見守り、大きなけがなどにつながる予期せぬ危険(ハザード)を取り除く環境づくりです。

――地域の交流の場にもなっています。
私たちの活動の軸は、「遊び」と「居場所」の2つを地域のなかでつくっていくこと。遊び場の運営のほか、フリースクール事業や保護者向けの子育てサポート事業など、居場所づくりを大事にしています。

近所のおばあちゃんが「つけ物漬けたから」と持ってきたり、未就学児を抱えたお母さんがお茶を飲みながら旦那の愚痴をこぼせたり。震災で一度コミュニティーが崩壊した地域にとって、人びとが気軽に集まれる居場所は大切です。
また子どもは悩みがあっても、信頼できる関係がなければ話しません。いつでも行ける遊び場やフリースクールなどの居場所のなかで、ふとしたときにつらい思いがぽろっと出てくる。
そうした場を運営するスタッフにも、「失敗してもいいから自分で考えてやってみて」と伝えています。現場で生の声を実感して、それぞれが当事者として活動を進めていくことが、私たちの団体にとっても大事なことだと感じています。