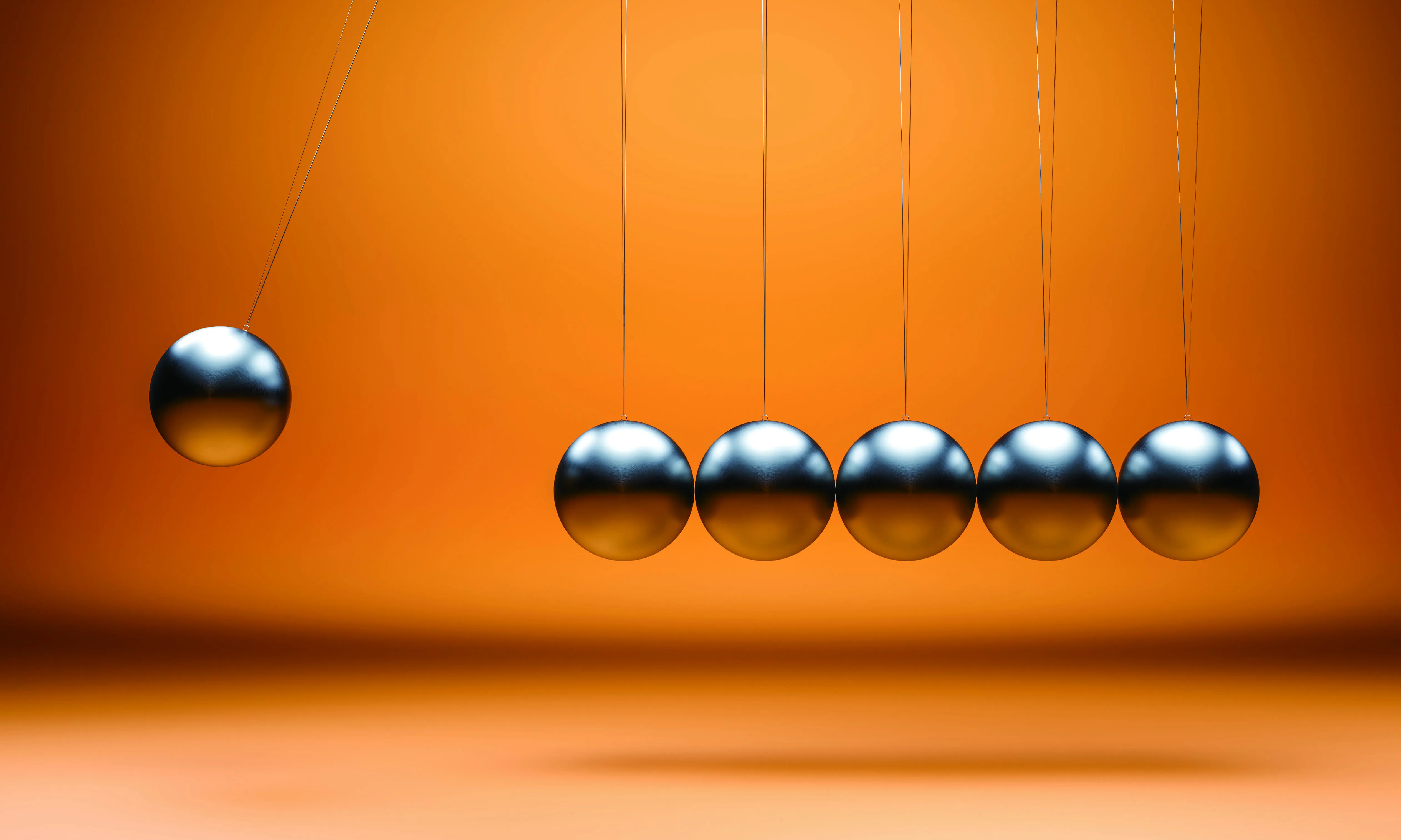モリンガをアフリカの女たちが植える日――「ショート・ショート」(掌小説)こころざしの譜(4)
まもなく着陸するという雑音交じりの機内アナウンスに日菜は窓の外に目をやった。一面に茶褐色の乾いた大地が広がり、ところどころ、枯れかけたブッシュが申し訳ない程度に顔をのぞかせている。
とうとうやって来たという熱い思いと、苦い不安が胸の中で交錯する。大学在学中にワシントンにある国際機関でインターンをし、途上国の貧困問題に取り組もうと勇んだが、職場の雰囲気になじめなかった。
職員のほとんどは途上国に行ったことのない高給官僚で、貧しい人たちのことを何も知らなかった。いや関心すらない。あるのは、同情と憐憫であり、慈善意識だった。
怒りにも似た焦燥感に駆られて深夜、静まり返ったオフィスのパソコンで、「アフリカ」「最貧国」とキーワードを打ち込んだ。画面に現れたのが、いま訪れようとしているこの国の名前だった。
日菜の農場めぐりが始まった。沖縄から持ってきた種をこの国の人たちに植えてもらおうというのだ。知り合いのNGOのツテで首都近郊の村を紹介してもらい、村長が村の男たちを集会場に集めてくれた。
日菜は、生活向上には農業収入を増やす必要があること、そのために、持参したモリンガの種を植えることを提案した。
「モリンガを乾燥させてお茶にすれば日本に輸出できます。見本の種を回しますから見てください」と語りかけたが、農民からはほとんど反応がなかった。
みな、眠そうな顔で下を向いているばかりである。座が白けたのを気にしたのか、最初に村長が口を開いた。
「ところで、そのモリンガという樹木の葉を食べると、あんたみたいに白い肌になるのかね」
男たちが一斉に卑猥な笑い声をあげた。「まずくても精力がつけばええがな」。あとはヤジの応酬と馬鹿笑いで集会は終わった。回覧した種は戻ってこなかった。遠くから女たちが冷ややかな視線を送っていた。日菜はへこたれなかった。農家の個別訪問を開始したのだ。
「モリンガはインドの原産だけど、現地でもあまり知られていません。温かい地域でないと育たないので熱帯の国にはぴったりよ」
「どんな植物なんだね?」
「とにかく栄養価が高いの。ビタミンでいうと、Aがニンジンの4倍、B2が真イワシの50倍、Cがオレンジの7倍といった具合。それだけじゃない。カルシウムが牛乳の20倍」
「ちょっと待ってくれ。国連やNGOに勧められていろんな換金作物を手掛けたがね、みな失敗だったよ」
どこの農家の主人も相手にしてくれなかった。3カ月たっても何の成果もなかった。それどころか、先日は何者かが大きな石を投げ込み、窓ガラスが割られた。
今日は、朝から大雨が降っている。村長が紹介してくれた民家の離れで大粒の雨滴が屋根から流れ落ちるのを眺めていた。やっぱり突然、アフリカに乗りこむというのは無謀だったか。日菜は後悔し始めていた。
考えてみれば、自分のような人間が、貧しい人を助けたいなどと思うこと自体が不遜なのではないか。中学時代、日菜は荒れていた。浮気性の父と嫉妬深い母は諍いが絶えなかった。それが嫌さに、日菜は暴走族の仲間に入り、騒ぎまくった。
ある日、敵対関係にある隣町の暴走族グループの襲撃を受けリンチされた。日菜は復讐を誓った。親は反対したが、強くなりたい一心で、空手の強豪校である商業高校に進んだ。ひたすら練習に没頭し、気がついたら全国でも有数の実力の選手になっていた。
怨念の対象だった暴走族のリーダーが、親の経営する零細企業の倒産で一家心中したという記事を目にしたのもそのころだ。
人生というのは不思議なものだ。空手の実力が評価され、日菜はAO入試で難関私大に合格したのだ。大学は個性的な学生が多く、日菜の中に潜んでいた何かが刺激された。
外資系の金融機関に就職したゼミの先輩、祐太から「もっと世界に目を向けろ」と言われ、日菜が関心を持ったのが途上国の貧困だった。ソーシャル・アントレプレナー、社会起業家という生き方があるのを知り、自分がしたいのはこれだと意を決して今日がある。
翌日はカラリと晴れ上がった。重い足をひきずって農家めぐりを再開したが、農家のまなざしは一層冷たくなったように感じる。夕方、成果のないまま村の道をとぼとぼ歩いていると、突然、女たちの集団に取り囲まれた。日菜は身の危険を感じた。
どうやら、どこかに連れていくつもりらしい。抵抗しても仕方ないので、日菜は女たちに取り囲まれながら、ついて行った。家々を抜け、ブッシュを通り過ぎる。小一時間も歩いただろうか、山の麓の寂しい一画に出た。ここだよ、という風に先頭を歩いていた年配の女が前方を指さした。
あっ、と日菜は思わず声をあげた。小さな木にふさふさとした葉が目を出し、一部では白い花のつぼみが咲こうとしている。
「何、これ、一体どうしたっていうの?」
女たちはにやにやしている。日菜のあまりの驚きぶりがおかしいのか、次第に笑い声が大きくなった。
「サンキュー、ありがとう。本当にありがとう。みんなで種を植えてくれたんだね。うれしいわ」
キャアー。その時、後ろの方で悲鳴があがった。若い女が夫からたたかれ、強引に連れ去られるところだった。
日菜は女たちを抱きしめた。女たちも緊張で青くなっている。
「いい野菜をつくれるのは私ら女だ。男たちは保守的で頭が固い。このままじゃ一生、貧乏暮らしさ。モリンガでおカネを稼いで、子どもたちの病気を治し、いい学校に入れてやりたいからね」
「そうそう、だから皆でモリンガを植えるの。乾燥させてお茶にする方法を教えて」
女たちがうなずく。日菜は全員と握手を繰り返しながら、涙が流れるのを止められなかった。
帰宅すると、祐太にメールを打った。「やったよ。アフリカにモリンガを植えた、農家の女性たちが自分で」。
返事はすぐ来た。
「日本でのマーケットだけど、モリンガ茶なら、ティーバッグにした方が飲みやすいと思う。30包で1500円くらいなら売れそうだ。モリンガのパウダーや錠剤もいけるんじゃないかな」
日菜はうれしさがこみ上げてきた。涙のせいで重要な最後の一文を読み落とすところだった。
「日菜、俺、会社辞めることにしたよ。金だけの世界にはもう飽きた。モリンガ、よかったら手伝わせてくれないか」
(完)




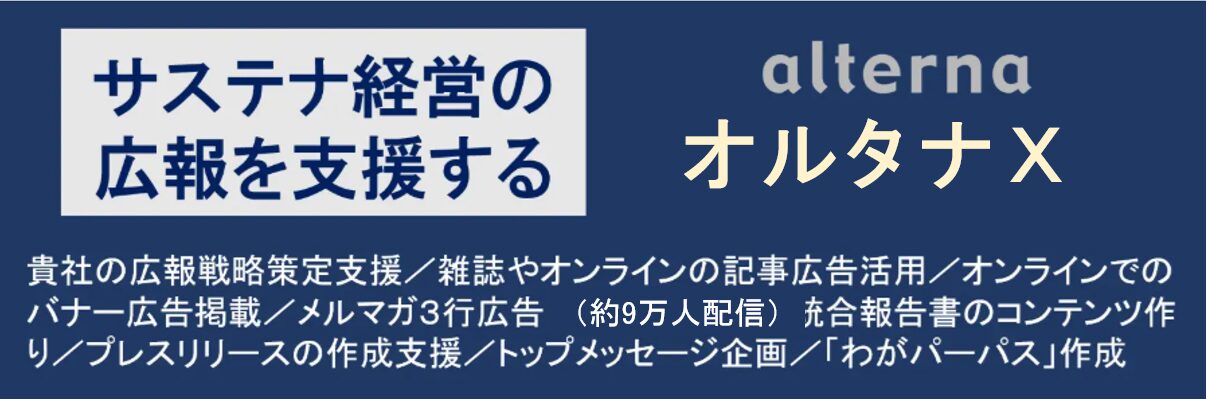
























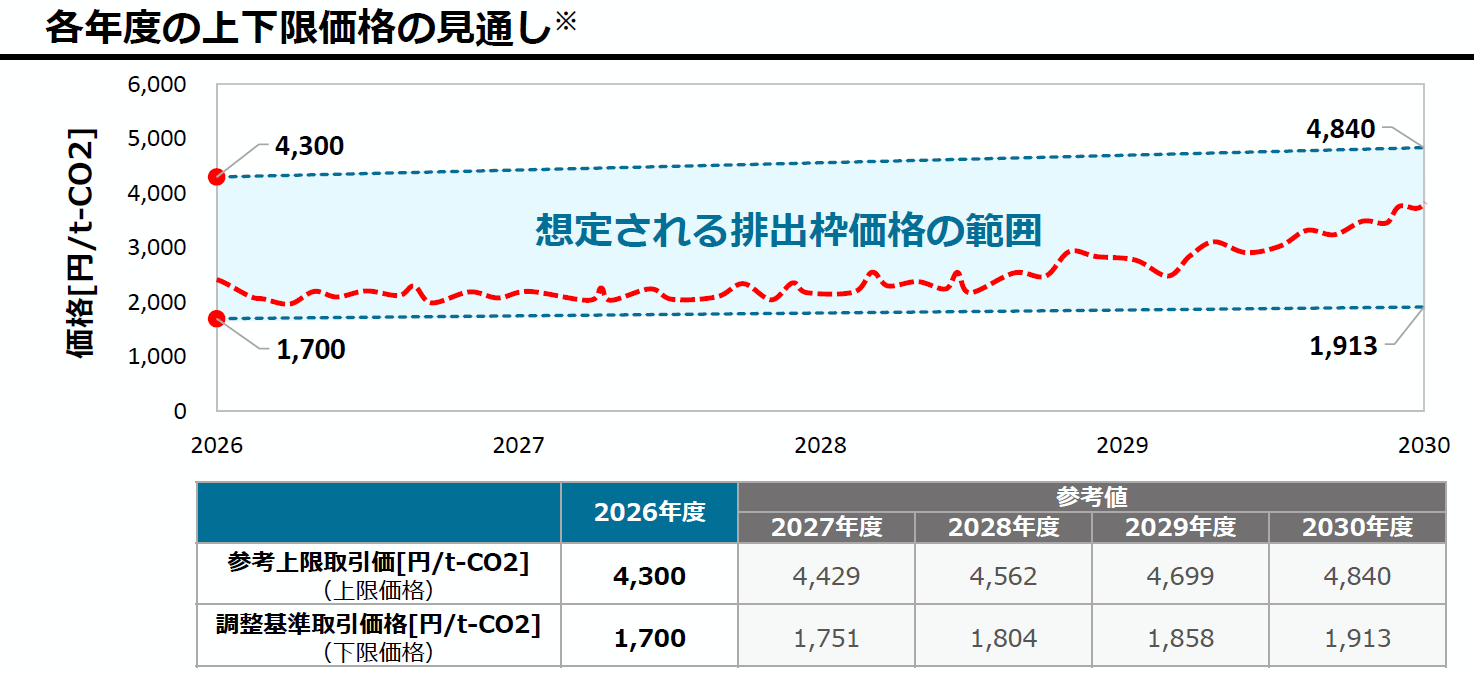
.jpg)