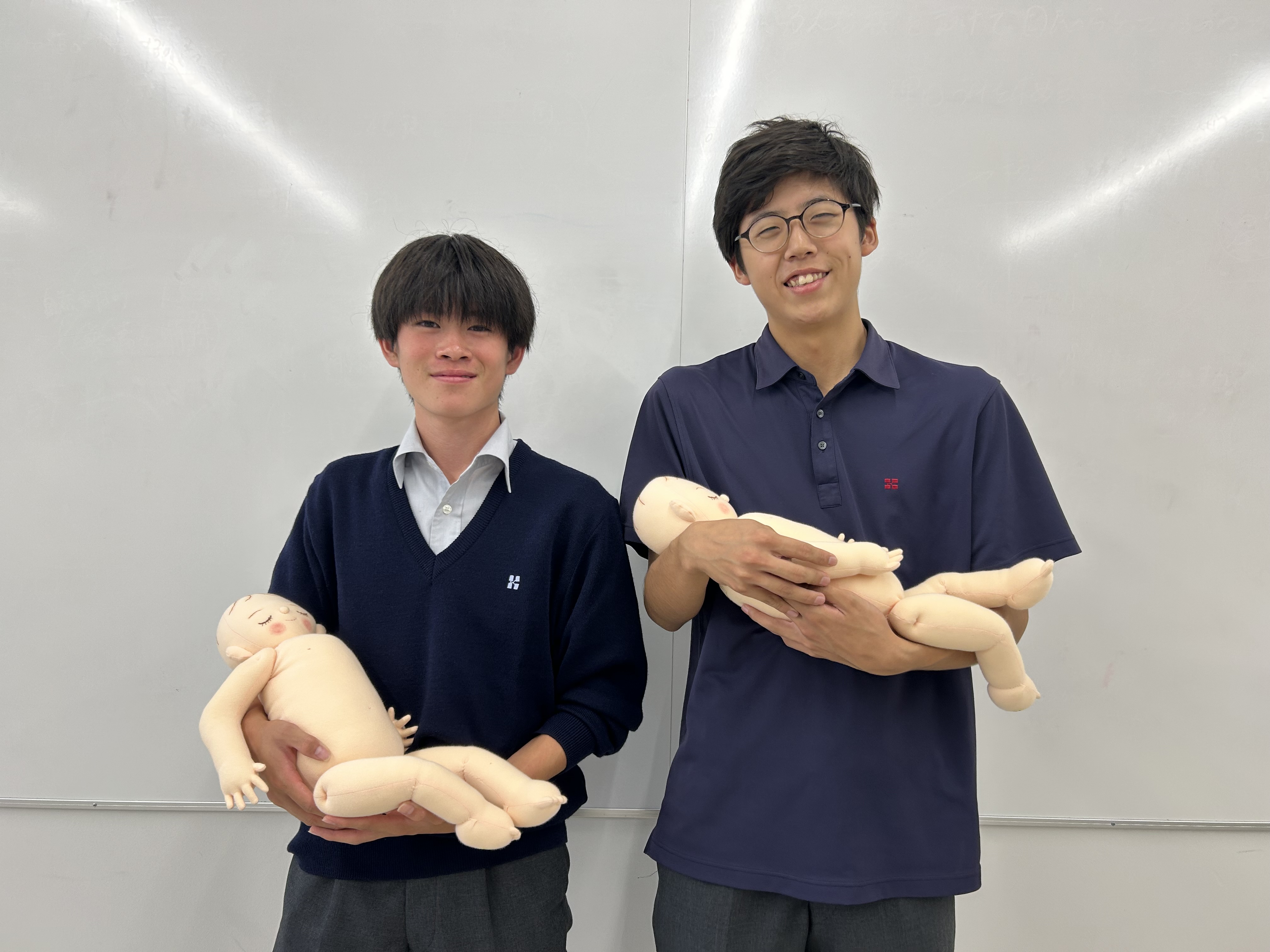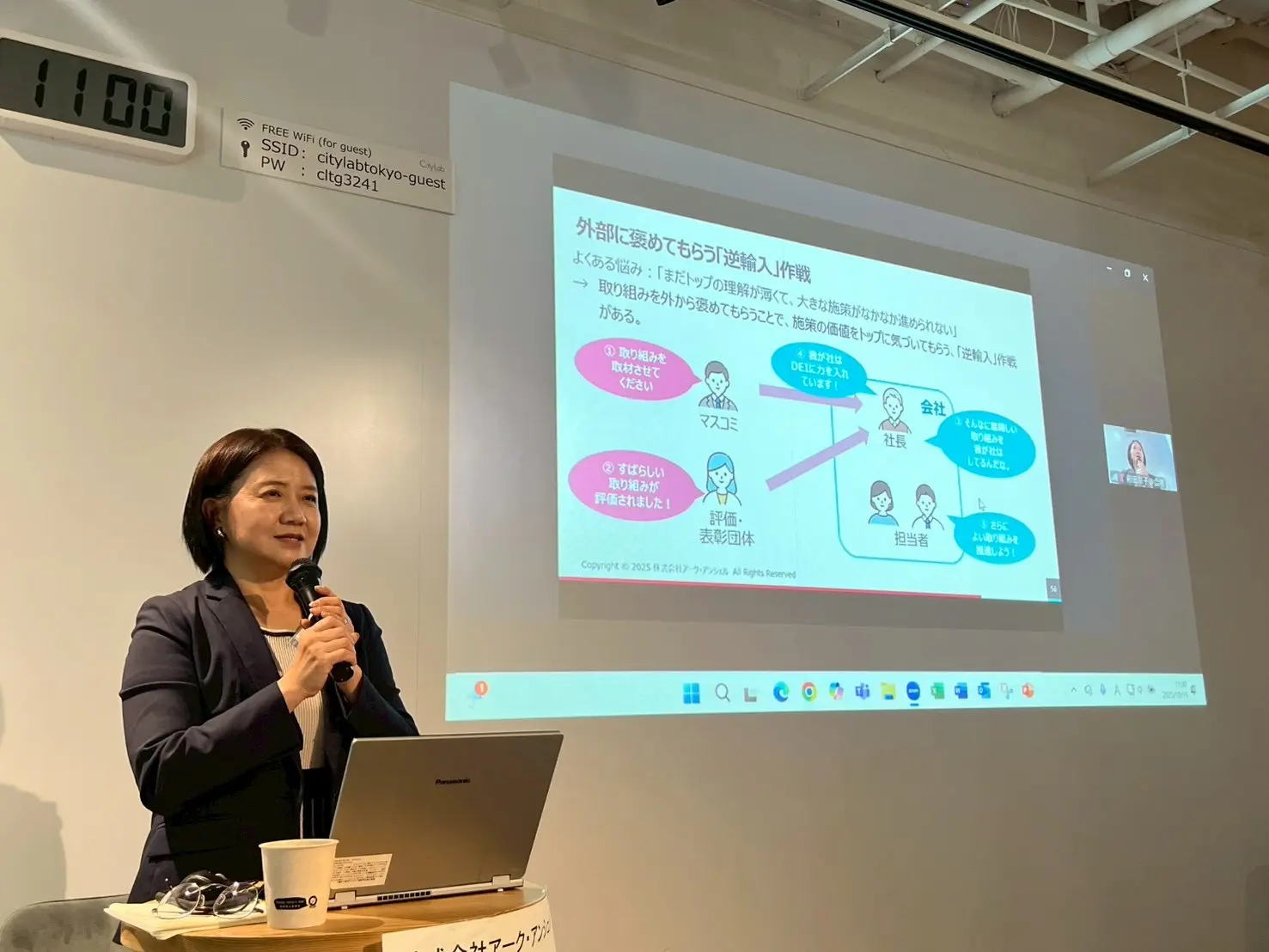「ショート・ショート」(掌小説)こころざしの譜(13)
底冷えのする暗い夜だった。周りの山には骨ばったカラスの脚のような小枝が広がっている。嫌なことが起きなければいいが、と不吉な予感を抱えながら八重は食器を洗っていた。こんな夜、夫がいてくれたらと思うが、亡くなってもう3年になる。その時、突然の電話のベルが八重を怯えさせた。
「八重さんかね」。男はぶっきらぼうにそう切り出した。無礼な電話だと感じたのもつかの間、次の言葉が八重の心を鷲づかみにした。
「あんたには、育ての親のほかに本当のお母さんがいる。俺はその弟なんだ。そのお母さんが今大変な病気なんだ。死ぬ前に一度会ってやってくれないか」。何を馬鹿なことをと笑おうとしたが、声がでなかった。
「突然の電話で驚かせてしまったようだが、名前は節子という。実はハンセン病でな。知っているかい、癩病(らいびょう)だよ。群馬県の草津温泉に近い療養所で暮らしている」
「冗談でしょう。私をからかっているんですか。私に実の母親がいるなんて聞いたこともない。それもハンセン病だなんて。ばかばかしい」。八重はそう返事をするのが精いっぱいだった。突然のことで認めたくないというよりうろたえていた。実はこここそが瀬戸内海にあるハンセン病療養所だった。八重自身がその病気だったのだ。男はそのことを知らないようだった。
男はしばらく沈黙していたが、やがて、八重の知らない話をゆっくり語り出した。
「産みの親の節子は、あんたを産んで間もなく自分がハンセン病にかかっていることを知った。当時は業病といわれ、患者は療養所に強制的に収容された時代だよ。村八分にあい、戸籍が抹消されるケースも珍しくなかった。一緒にいては子どもに感染してしまうと思い、節子は八重さんを連れての療養所行きを諦め、同じ職場の友人の養女にしてもらったんだ。それが育ての親だよ。ハンセン病の母がいては八重の将来に障りがある。自分のことは忘れ、元気に育って幸せな結婚をしてもらいたい。節子はそんな思いから、その後、あんたへの連絡をいっさい断ってきたんだよ」
弟だと名乗った男の話に、八重は引き込まれていった。
戦後、特効薬が開発されハンセン病は完治するようになった。全国に13ある療養所に今も2,000人の入所者がいるが、患者ではない。全員が治っている。ただ、失明や手足の変形といった後遺症や、いまも続く社会の根強い偏見で故郷に帰れない人たちなのである。ハンセン病は遺伝ではなく、癩菌(らいきん)によって引き起こされる感染症だ。感染力が極めて弱いが、免疫力の弱い赤ちゃんの場合はつばなどで飛沫感染をすることがある。そういう意味では、節子の判断は間違ってはいなかった。しかし、何という皮肉だろう。時すでに遅し。小学校にあがって間もなく、八重は発症してしまった。
もちろんそこからの記憶は八重にははっきり残っている。火鉢で大やけどを負っても全然痛みがなかった。痛さを感じる神経が侵されていたのだ。療養所に収容され子供舎に入った。成績のいい八重は長じて離島の別の療養所に設置されている高校へ入学した。同じ境遇の仲間だけに偏見もなく楽しい寮生活だった。多くの友人が大学へ進み社会復帰していった。
八重はいったん元の療養所に戻り、そこで知り合った男友達と結婚した。一生、療養所で暮らすのはあまりにも寂しい。思い切って夫婦で社会復帰した。しかし、夫は手足に後遺症があることから社会の偏見にさらされ、どの職場にもなじめなかった。困窮生活で無理を重ねたこともあり、夫が病気を再発し、療養所に戻った。結婚する時、断種を強要されたため、夫婦に子どもはいない。
母の弟、つまり八重にとって叔父にあたる男は、八重がハンセン病であることを知らないまま、節子への見舞いをくどいほど懇願して電話を切った。八重はしばらく放心したままだった。
今さら、という思いもあったし、気持ちの整理がつかなかった。療養所の自治会長に相談してみた。会長は後遺症で失明していたが大変な読書家だった。感覚の鈍った指の代わりに舌で点字をたどる舌読でたくさんの文学作品に親しんでいた。群馬の療養所にそれとなく探りを入れてくれたらしく、1冊の本を持って訪ねてきた。
「八重さん、叔父という人の言うことは本当らしいね。育ててくれたお母さんもいつかは真実を話すつもりだったんだろうが交通事故で急死してしまったから、その機会がなかったんだろう。群馬にいる実の母の節子さんだが、詩人らしい」
そう言いながら、会長は白川節子詩集という本を開いた。
重い病を背負い 家を後にした
幼子をひとり残し 何度も何度も振り返り
いま、やるせない気持ちで山に行く
無性に愛しい娘の名前を呼び続ける
大声で 八重、八重、八重と
八重は涙をぬぐうと矢も楯もたまらず、押し入れから旅行鞄を引っ張り出すと、療養所を飛び出した。母に会わねばならない。病気をうつしたくないと思い続けた母、そのために子どもとの縁まで切った母、辛かったに違いない。
しかし、それでも私は病に侵され、場所こそ違え療養所に暮らす。このあまりに過酷な運命を母に知らせてよいものだろうか。このまま黙っている方がいいのではないだろうか。「幸せに暮らしているから、そっとしておいてほしい」。母の待っているのは、そんな一言ではないのか。そうは思いながらも、八重の気持ちははっきりと群馬の療養所へ、母のベッドへと向かっていた。
そして、先ほどの考えにかぶりを振る。いや、そうではない。確かに病気はつらかった。嫌な思いもしたし差別も受けた。それでも病気のおかげでいろんな出会いがあった。療養所には運動会もあるしカラオケ大会も楽しい。編み物や陶芸教室の仲間もいる。社会復帰に向けて車の運転の教習を受けた思い出も懐かしい。負け惜しみでなく、この病気になってよかったと思う。そうでなければ、ぼんやり一生を送ってしまったに違いない。母から病気をもらったおかげで、苦しみながらも強く生きることを学んだ。
そのことを母にどうしても伝えたい。詩によって強く生きた母自身、同じような思いを抱いているような気がする。八重はそう感じた。私の考えを母が知ったら、なんと言うだろう。初めは泣くだろう、嘆くかもしれない。でも、そのあとで、こう言うのではないか。なんだ、同じ病気だったの、お互い大変だったねえ。でも、頑張ったんだね、と。
列車から山の間にゆっくり沈んでいく夕日が見える。車窓に、後遺症を残した顔が映っている。この顔こそが私なのだ、私の生きた証なのだと八重は自分に言い聞かせる。そして、今朝届いた離島の高校の同級生からの懐かしい便りを思い出していた。
「久しぶりに、皆で一杯やらないか」
(完)




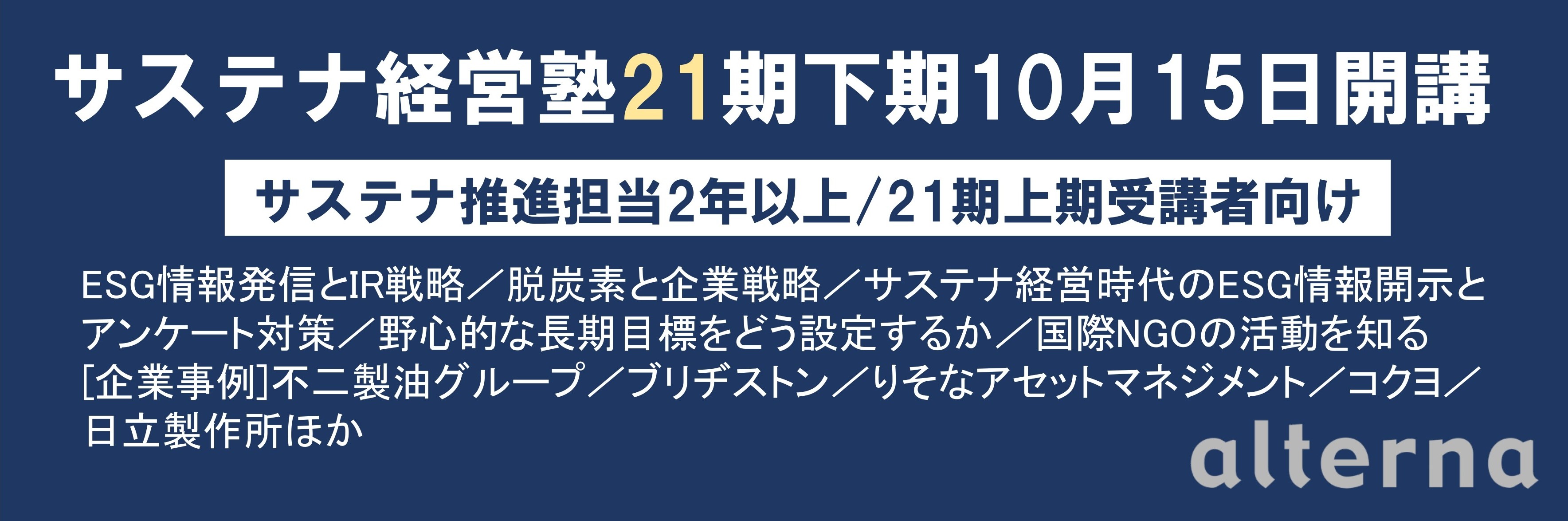








-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)