
内閣府は2月14日、日本の2010年の名目国内総生産(GDP)が5兆4742億ドルとなったと発表した。これにより、同年の名目GDPを5兆8786億ドルと発表した中国を下回ることが確定。翌日の新聞各紙は「GDP世界3位に転落」(東京新聞)「ついに米国に次ぐ世界第2位の座を明け渡した」(読売新聞)などと、慨嘆を込めて伝えた。「縮小社会」が話題に上る今、日本が目指すべき未来は。識者に聞いた。
■「フローからストックへの転換を」
「中国がGDPで世界2位になっても驚くにあたらない。人口では中国の10分の1の日本がこれまで上回ってきたことの方が不思議」。そう語るのは、NPO気候ネットワークの浅岡美恵代表だ。
中国外務省報道官は15日の会見で「中国は依然として途上国」との認識を示し、さらなる経済成長に意欲を見せた。その後をインドやブラジルなどが追う。
浅岡代表は警鐘を鳴らす。「しかし地球の資源は有限であり、今後も経済成長は可能なのか。中国はCO2排出量では既に米国を抜いて1位。エネルギーや資源の効率を高めることは必須だが、早期に排出総量をピークアウトさせ、減少に転じるべき」
日本はどうするべきか。豊かさの指標をGDPに求め、米国を追いかけた経済は疲弊し、人心さえも蝕む。「有限の地球を考えれば、もはやフローの指標であるGDPではなく、ストックを含めた新たな豊かさの指標が必要。とりわけ日本はGDP2位の時代に、それにふさわしい有形無形のストックを残せなかった。今こそ、人や将来世代に引き継げる財や文化に投資し、持続可能な低炭素の社会に転換する好機だ」と浅岡代表は説く。
■ローカル化通じ「軟着陸」を
「人間の欲望は無限だとして、それを満たすことを追求したのが経済成長を価値とするGDP神話の内実だ。それを信じていた人々が、経済の縮小に寂しさを感じるのは当然」。環境文化NGO・ナマケモノ倶楽部世話人の辻信一氏は、新聞報道に現れた慨嘆を読み解く。その上で「どうにかそれを乗り越えてほしい」と語る。
「GDP神話の前提は、ピークオイル(石油の減耗)や自然と人間の荒廃などの形をとって破綻した。GDPの増大では、もはや人も自然も持たない。そこからのダウンシフトが必要で、その受け皿になるのが地域に根ざして生きる『ローカル化』ではないか」
ローカル化のキーワードは食やエネルギー、精神性などであると辻氏はいう。そしてこう言葉を結んだ。「『成長の限界』の先にあるハードランディングを避けるなら、GDP神話の真逆に向かうべき。3位の今こそそのチャンスで、2位に返り咲こうとかバカなことは考えない方がいい」(オルタナ編集部=斉藤円華)2011年2月17日



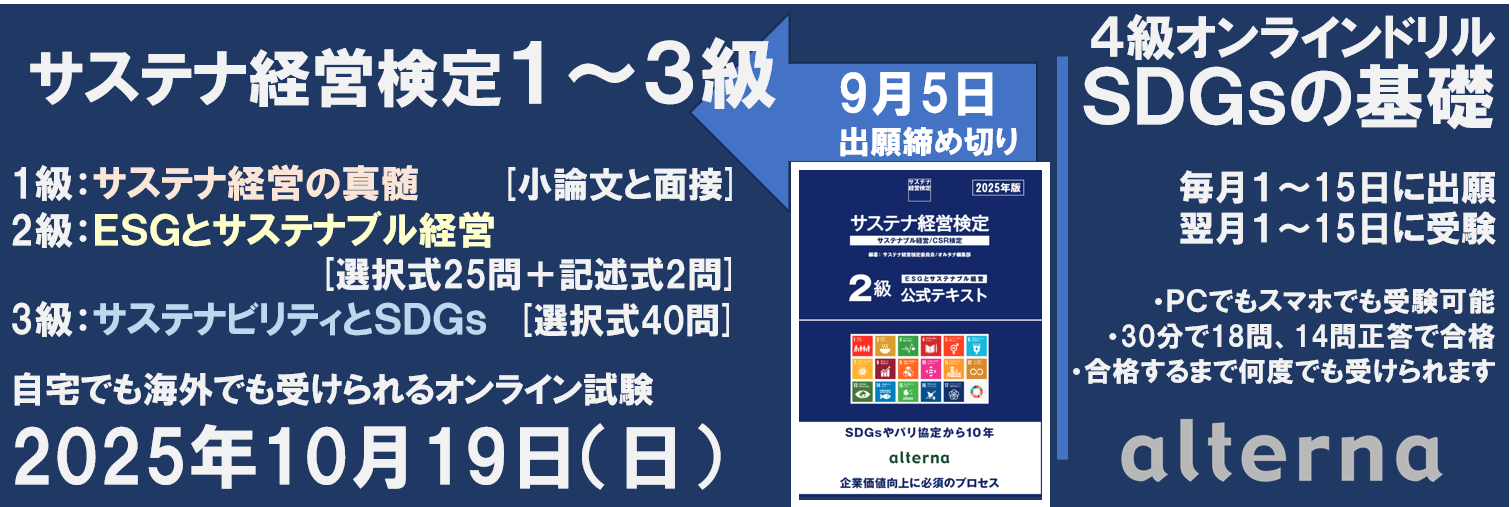






-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)




















