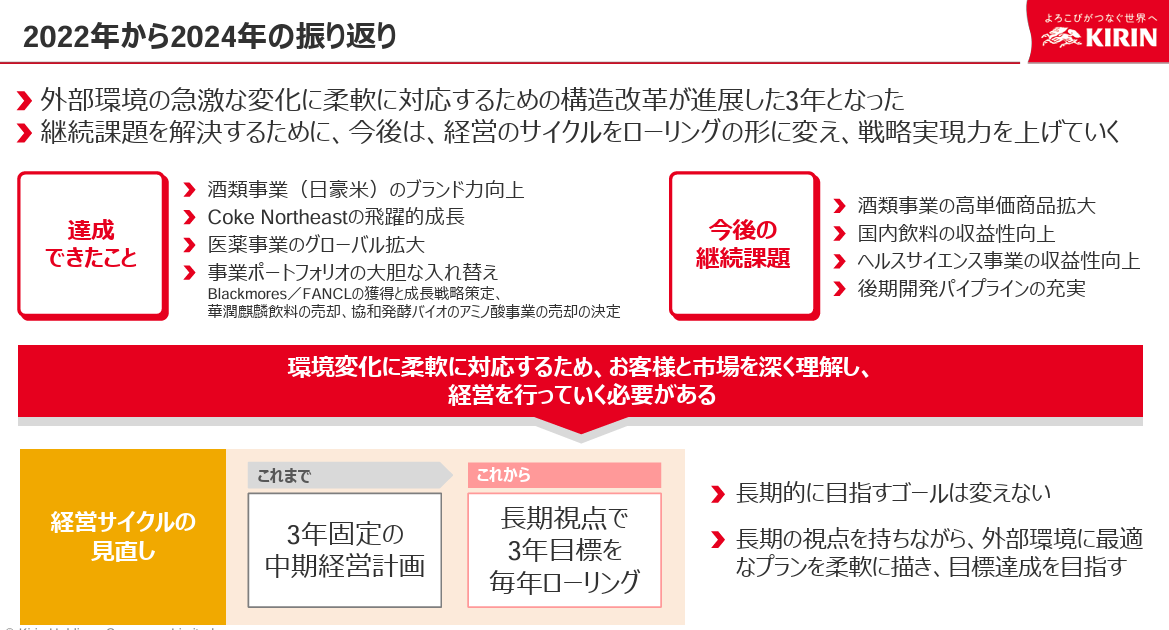IUCN(国際自然保護連合)が定義する「絶滅のおそれのある野生生物のリスト」には、2014年11月時点で約2万2千種が登録されている。生物多様性の確保は喫緊の事項だ。本コラムでは、味の素バードサンクチュアリ設立にも関わった、現カルピス 人事・総務部の坂本優氏が、身近な動物を切り口に生物多様性、広くは動物と人との関わりについて語る。(カルピス株式会社 人事・総務部=坂本 優)
気象庁は3月23日、靖国神社の標準木に基づき、東京の桜(ソメイヨシノ)の開花を宣言した。昨年より2日、平年より3日早いとのこと。満開は31日頃と予想されている。
気象庁による1953年以来の桜開花の記録からは、年によってばらつきはあるものの、過去半世紀の間に、関東以北では概ね1週間前後、開花が早まっているのではないかとの解析もある。早期化は全体として見たときには地球温暖化によるものと推定されている。
写真は、桜の花の蜜を求めてやってきたメジロを撮影したものだ。普段、何気なく目にする春の風景だが、桜も他の生物の命の糧になっているという、今更言うまでもない生物多様性と桜との関わりの一端を示している。
桜などの開花が早まるということは、それらの花や実、葉につく昆虫などを餌とする野鳥にとっては、決して小さな問題ではない。多くの野生生物は、餌が豊富になるタイミングに合わせて子育てをする。開花や満開、結実の時期がずれることは雛や子の生育にも影響する。餌が豊富な時期に繁殖のために渡ってくる渡り鳥にとっては、その時期に餌がないということは、種の存続をも左右しかねない一大事だ。
開花より影響が大きいと思われる満開の時期については、1981年以降の記録が気象庁のホームページに掲載されている。東京のデータを見ると、20世紀の期間中、満開が4月となったのは、20年のうち16年と8割を占めるが、21世紀に入ってからは、14年のうち6年で5割以下となる。