「薬用植物の甘草(カンゾウ)を見て、『これが化粧水に使われる有効成分の元だったのか』と初めて知る社員も多いんです。実際に見て触ることで販売にも説得力が増します」と案内してくれたCSR部環境企画室の小幡 観さん。同行した同室の田口邦彦さんは「先日の朝も、小幡さんが居ないなと思ったら真っ先にこの屋上へ来て手入れをしていた」と笑って教えてくれた。

全ての植物に育て方のマニュアルがある訳ではなく、一株ごとの植物の生育具合を見ながら試行錯誤しているそうだ。それぞれの植物の特徴を熱っぽく説明してくれる2人の姿に、庭づくりへの情熱を感じた。今後は近隣の小学生を招いて環境授業を実施するなど、地域の子どもたちにも来てもらえるような企画も検討しているという。

「資生の庭」には資生堂のもうひとつのシンボルマークである「椿(ツバキ)」も植えられ、赤い実をつけていた。同社は長崎県の五島列島、和歌山県白浜町、横浜市の「横浜こどもの国」などで、ツバキの保全活動を行っている。特に五島列島ではヘアケア製品の「TSUBAKI」の原材料にその実が使われるツバキを守り育てる活動を行っている。原料産地への恩返しと製品への理解を深めてもらうことが目的だ。

創立140周年を迎えた2012年には、「未来椿プロジェクト」と題して事業所ごとに、口紅の原料になるベニバナを人手不足の秋田の農園に収穫の手伝いに行くなど様々な社会貢献活動を実施した。その根本にあるのは、化粧品メーカーとしての事業と社会貢献の両方への強い意識だろう。
資生堂の創業の地である銀座に植物や鳥など多くの生き物と人々が共に憩っている。そこには社名の由来となった易経の一節「万物資生」(ばんぶつとりてしょうず:「全てのものはここから生まれる」の意)の精神を伝える姿があった。



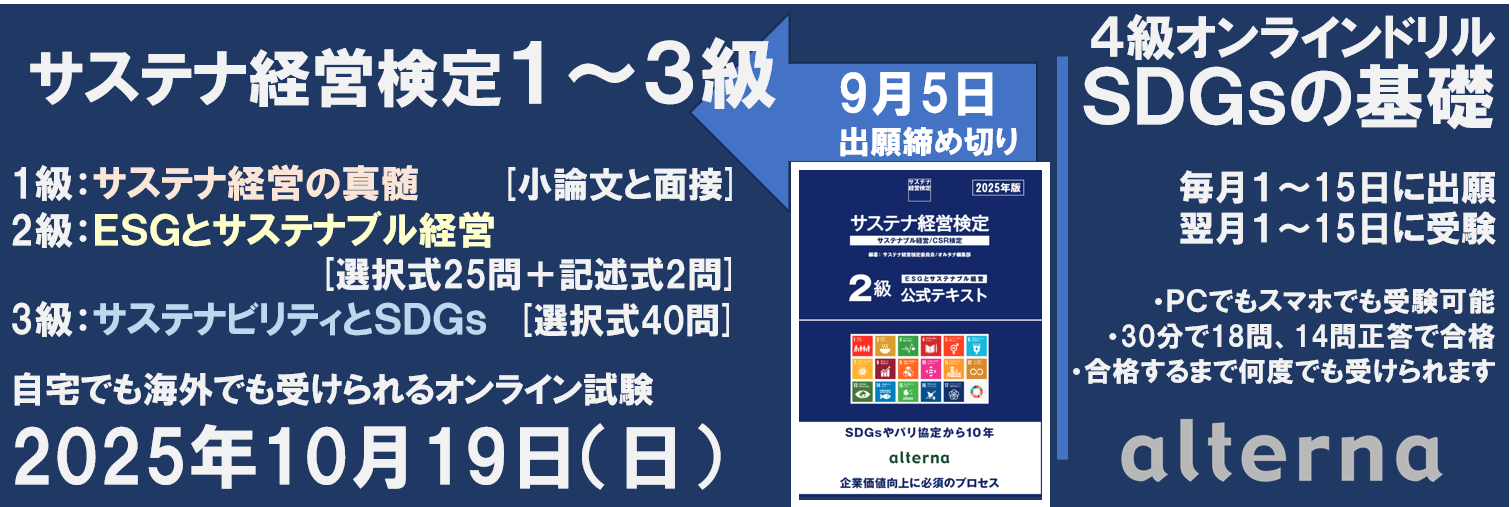






-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)




















