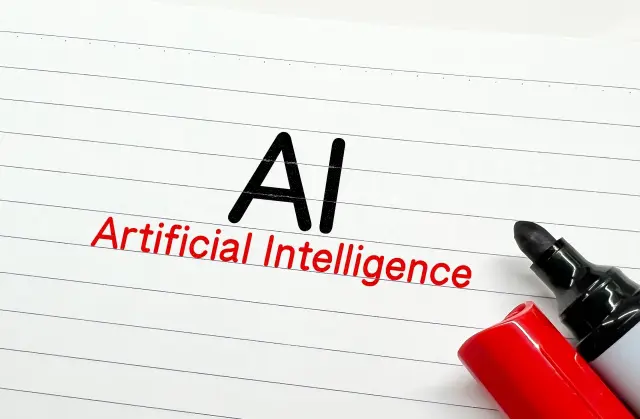「ショート・ショート」(掌小説)こころざしの譜(19)
永年勤めた新聞社を私はきょう定年退職する。事件や事故を扱う社会部が長かっただけに仕事には恵まれた。短気な性格で上司ともよくぶつかった。辞めようと思ったことも一度や二度ではない。よれよれでゴールにたどり着いた老いぼれ事件記者だ。いい記者人生だったのかもしれない。送別会であいさつしてくれと頼まれている。大きなスクープを抜いたわけでもないので自慢話はできないが、「幸福」という小さな食堂の物語だけは語り残しておきたいと思う。
あれから、もう7年か。東日本大震災の時は、それはもう大変な騒ぎで、われわれも文字通り不眠不休で働いた。
うちの新聞社の紙面でも、被災直後から「亡くなった方々」というコーナーを新設、死亡が確認された被災者の氏名を連日掲載した。その欄の担当者が私だった。被災直後は二、三ページにもわたって名前が載ったが、それも徐々に減り二か月もするとずいぶん小さなスペースになってしまった。ちょうどそんな折りに社会部の部会があった。私は、このコーナーの中止を提案した。名前だけ何人も並べても意味がないのではないか。もっと、津波の教訓とか今後の防災対策とかの記事の方が読者の関心を呼ぶと考えたのだ。ところが、部長が渋い顔をする。結果、死亡コーナーは継続された。私は不満だったが、上司に逆らうことはできなかった。
そんなある日、都内の音楽大学に通っている宮城出身の女子大生から手紙が来た。
「『亡くなった方々』コーナー御担当様 今日の貴紙朝刊に私の母の名前が掲載されました。本当にありがとうございました。母は長い間、行方不明でしたが、遺体の身元が確認されようやく私たち家族のもとへ帰ってきてくれました。こんなにうれしいことはありません」で始まる手紙に私は頭を思い切り殴られたような衝撃を受けすぐにその女性に会いに行った。
目のくりっとした色白の女子学生だった。
「早く近くの高台に逃げろ、父が母にそうどなったのに、足の悪いおばあちゃんを迎えに行って逃げ遅れたんですよ。自分のことより他人のことばっかり考えて」
麻衣と名乗ったその子は「お母さんたら、他人に気を使ってばかりで、馬鹿だあ、本当に」と言ってしゃくりあげた。母を探してあちこちの遺体安置所を訪ねたが、見つからなかったのだという。顔が膨れて人相が変わっているし、傷みの激しい遺体も多かった。首にあったイボを目印にしたが、水につかってふやけてしまっていてよくわからなかったらしい。結局、決め手になったのは「ちゃんと歯を磨かないとお母さんにみたいになっちゃうよ」というのが口癖だった母の歯の治療痕だった。
「津波に持っていかれちゃったけど、幸福という名の小さな食堂を夫婦で切り盛りしていました。母は明るくて、お客さんには好かれてました。食堂に来る子どもたちには玩具のプレゼントを欠かさなかったので、街で子供たちに会うと、あっ、玩具のおばちゃん、と呼ばれて、うれしそうでした」
小学生の時、麻衣の同級生が五人で食堂にやってきた。注文はラーメン一杯。母は笑いながら、五杯のラーメンを出してくれたのだという。
それまで、いっぱしの新聞記者を気取っていた自分が恥ずかしかった。掲載されるたった一行の名前にどれだけの人生と、人とのつながり、思いが込められているのか、そのことに思いが至らなかった自分が情けなかった。名前は記号ではなく、小さな記事だったのだ。
新聞社に帰り一本の原稿を書いた。「君は幸福食堂を覚えているか」という見出しで、皆に愛された麻衣の母親の人生を伝えた。すぐに麻衣から電話があった。あの記事、ネットでも話題になっています、と教えてくれた。
「新聞読んでビックリしたよ。津波で、あの幸福食堂がなくなっちゃったんだって。覚えている?」
「当たり前だよ。海岸に近い道路の端にあったあの店だろう。オヤジとオフクロと三人でいつも食べにいってたから」
「食堂のおばちゃん、おもしろい人だったよな。いつも大声で笑ってて」
「そうそう、おじさんは無愛想だったけど。野菜炒めとか、焼そばとか、おいしかったね。高校の帰りによく食べた。懐かしいな、あの味。もう一度食べたいなあ」
「食堂、再開しないのかな」
そんなやり取りがネット上でかわされているのだという。
「幸福食堂を覚えてくれている人が一杯いたんですよ。私の所にも友達から問い合わせが結構来ました。新聞の影響力ってすごいですね」
そういう麻衣に、私はバツが悪くて何も言えなかった。
麻衣は続けた。「一度、実家に帰ることにしました。ようやく友達にも会いたいという気持ちになれました。父もひとり残されてガックリきているみたいだし。そんなんじゃ、お母さんに怒られるわよって、しかってきます」。
「それは、いいことだね。麻衣さん、お父さんも喜ぶよ」
「私、東京の音楽関係の会社に就職しようと思っていたんですけど、本当にそれでいいのかって悩み始めています。故郷があんなになっているのに。昔、ラーメンをタダ食いした悪友たちが、幸福食堂を再開しろなんて、とんでもないこと言いだしているんですよ」
「幸福食堂を再建しようってわけか。食堂が皆をつなげていたんだね。いや、今もつなげている。うらやましいなあ」
私は引き出しを開け、麻衣の母の名前が載った「亡くなった人々」の新聞をもう一度読み直す。一行、一行、一人ひとりの名前をたどってみる。もちろん、知らない人ばかりである。ただ、それぞれの人が、何物にも代えがたい、貴重な人生を送ってきたことを今は理解できる。
一歳の男の子。生まれたばかりで、命を奪われた。何と過酷な運命だろう。お父さん、お母さんは、どうしているだろう。心の傷が癒える日は来るのだろうか。九十歳のおばあちゃん。自宅が津波に襲われたのだろうか。あるいは施設に入っていたのか。もし、施設なら、息子さんたちは、施設に預けたことを後悔しているのではいなだろか。名前の背後には膨大な物語があった。命の重さ。そんな言葉が浮かんだ。
街の復興が進む中、あれから幸福食堂はどうなったのだろう。お父さんが再開したかもしれない。ひょっとして麻衣が手伝っていたりして。現地を、ぜひ訪ねたいと思う。定年後の私の楽しみである。
(完)
※登場する人物・団体・名称等は架空であり、実在のものとは関係ありません。




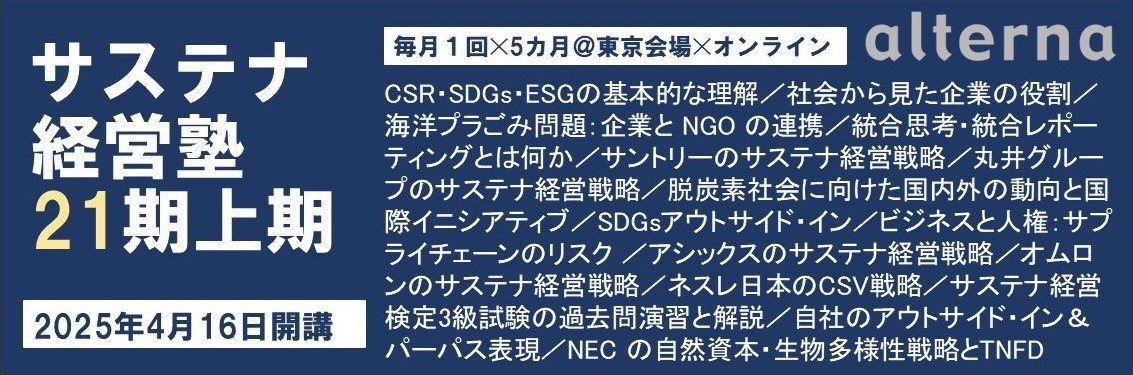




-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)