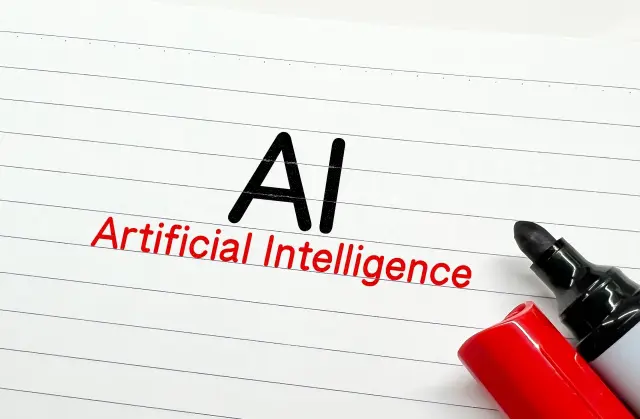「ショート・ショート」(掌小説)こころざしの譜(26)
「セニョール、若い女の子のお店行きませんか。安くはありませんが」。夕食を終えて通りへ出たところで、裕也たちはひとりの男に呼び止められた。ポンコツの白いクラシックカーを運転している。春とはいえ、まだ肌寒い。南アメリカのこんなうらぶれた街にも客引きがいることを不思議に思った。
「裕也、この車ってフォード・サンダーバードじゃない。プラモデルでしかお目にかかったことないヴィンテージ・カーだよ」。車好きの愛助がはしゃいでいる。省太はといえば、小太りの背中を丸めて財布の中の手持ちをチェックしている。
3人は学生時代の同級生だ。裕也は首尾よく外資系の証券会社に就職したものの、カネ万能の社風になじめず辞表を出した。外国へ旅に出るつもりだと打ち明けると、ブラック企業としてメディアで批判されていた居酒屋チェーンの愛助と、介護施設で激務と薄給で疲れ切っていた真面目人間の省太も会社を辞めてついてきた。
この旅行は観光が目的じゃない。起業のネタ探しの旅である。旅を終えたら、3人で会社を立ち上げよう。そう約束して日本を出発したのがことしの初め。米国からメキシコに入り、カリブ、中米からコロンビア、ベネズエラを回って、さらに南に向かうところである。
「社会に役立つソーシャル・ビジネスをと思ったけど理想が高すぎたかな」。タクシーの中で裕也がつぶやく。バーで乱闘に巻き込まれ、空港では荷物をひったくられる散々な旅になった。メキシコの民族衣装、パナマの手芸品、コロンビアのコーヒー。ビジネスのヒントになりそうなものはあったが、決め手にはならなかった。
昔から何をやっても長続きしないダメ男の愛助が声を張り上げた。「だから、社会貢献ビジネスなんて偽善だ、胡散くさいって言っているじゃないか」。
「そろそろ日本へ帰りたくなったよ。いいことは、カネと暇のあるおばちゃんに任せようよ」。省太がぼやく。
教会の横を通り過ぎる時、運転手が胸の前で十字を切ったのを裕也は見逃さなかった。
店は郊外にあった。がらんとした広くて古色蒼然とした一軒家だ。
「いらっしゃいませ」。出迎えた3人の女性は色白で美しかった。省太はラムをちびりちびりやりながら幼さの残るアドリアーナからスペイン語を習い始めた。愛助はルンバのステップを踏みながら、ブロンドのテレサの腰を抱いていた。裕也はマリアとカトリック教会の役割について語り合ったが、悪酔いをし、気が付けばベッドの中だった。朝の明るい日差しの中で、薄く擦り切れたシーツのほころびが気になった。
「朝食の用意ができました」。マリアに案内されてダイニングルームに行くと、既に愛助と省太が座ってかしこまっている。向い側に品のいい老夫婦が座っている。
「マリアの父です。昨夜はありがとうございました。満足いただけましたか。私が病気で市役所を解雇されてからは収入が途絶え、生きるために不本意な商売で糊口を凌いでおります」。涙ながらに頭を下げる。あれっ、よく見ると昨夜の運転手ではないか。
「国の経済が破たんし、男は麻薬シンジケートで働き、女は海外に出稼ぎに行く窮状です。身売りする女の子も跡を絶ちません。テレサは実は左翼ゲリラとの戦闘で亡くなった弟の娘さん。アドリアーナは貧しい親戚の子ですわ。マリアを含め3人とも大学で学んだ知識が生かせません」。夫人は固い表情を崩さない。「私たちは困った時は助け合うんです。みんな家族ですもの」。
こんな形でお礼を言われるのは初めてのことで、とまどうばかりだったが、3人の娘は屈託がない。省太は発音のことでアドリアーナから叱られている。「省太、S(エス)を食べちゃだめよ。お早うは、ブエノ・ディアじゃなくてブエノス・ディアスでしょ。キューバ人のガールフレンドでもいたの?」。
「あらあら、厳しいのね。でもアドリアーナは教え方がうまいのよ。実は私たち、夏のシーズンにはスペイン語の語学学校を開いているの。欧米の学生なんかが旅行がてら短期の語学留学で勉強しに来るわ」とマリア。講師はシングルマザーが多い。そんな語学学校がいくつもあるのだという。
マリアがサンダーバードでホテルまで送ってくれるという。車の中でも、省太がスペイン語を話している。不思議に思って助手席から振り返ると、何とスカイプである。見せてくれた画面ではアドリアーナ先生が怖い顔をしている。
愛助が省太をせっつく。「テレサと代わってくれ。俺にもスペイン語を教えてくれ。彼女が先生なら頑張って勉強するよ」。
おい、日本に帰ってもスカイプがあれば会話ができるぞ、そう裕也は言いいかけて、あっと思った。ひらめくものがあったのだ。
「おい、いいことを思いついた。スカイプで日本人にスペイン語を学んでもらうっていうアイデアはどうだ」
ふーん、と愛助と省太は真面目な顔になった。
「そうか。スカイプによるスペイン語学校か。先生はアドリアーナたちここのセニョリータというわけか」と省太。
「生徒は日本の大学生か。確かにみんなが喜ぶ社会貢献ビジネスだ」と愛助も目を輝かせている。そうだ、これだ、やっとビジネスが見つかった。3人はうなずき合った。
「マリア、悪いけど、引き返してくれ」。マリアに新しいビジネスのことを説明すると、「ディオス・ミオ(なんてこと)」。
裕也たちはマリアの案内で語学学校を回り、30人ほどの講師候補者を確保した。夏休み以外は暇で困っている人が多かったため、大歓迎してくれた。シングルマザーはこれで子どもたちに腹いっぱい食べさせ、学校や病院にも行けると喜んでくれた。
帰国すると、すぐに大学を回ったのは言うまでもない。スペイン語を教えている大学は意外に多かった。初めは南米と聞いて驚くが、本国のスペイン語に近いと説明すると、皆納得してくれた。コストも安いし、何より、1対1でいつでも会話の練習ができる点が評価された。デモテープの会話のイントロに音楽を入れたのもよかった。もちろんお気に入りのダンスミュージックだ。
「明るくて、ラテンアメリカらしいわね」と立ち上がって踊り出す教授もいた。マリアたちのうれしそうな顔が目に浮かんだ。そして、あの父親のちょっと照れたやさしい顔も。
(完)








-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)