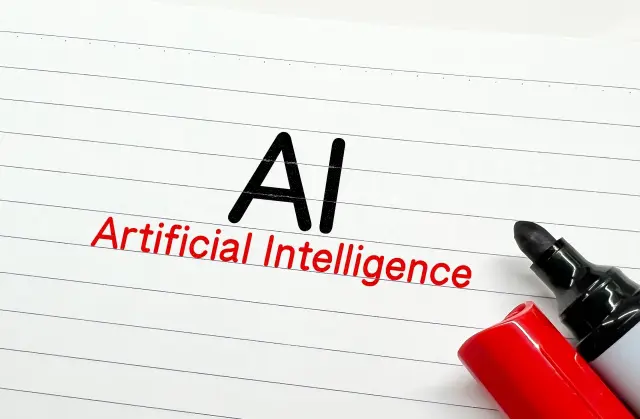令和が内緒で手話教室に通い始めたのはそれから間もなくのことである。手話は「新しい言語」だと思った。日本語を話せないマイノリティの外国人は自分の国の言葉を頼りに日本で小さく固まっている。聴覚障害者の世界はそんなコミュニティそっくりだ。手話を通じて闇の中をひと塊になって歩いている。便利な世の中になったといっても、それはあくまで健常な日本人というマジョリティにとっての話に過ぎない。携帯電話ひとつとっても、耳が聞こえない人には使えないではないか。
手話は難しく、居間で繰り返し練習した。「おはよう」は右手をグーにしてこれを耳からあごへ下げた後、両手の人差し指を立て曲げる。人と人があいさつしている姿をイメージしたものらしい。
「愛している」は左手をグーにして、このうえに右手の手のひらを乗せ2回クルクルと回す。これは恥ずかしくて使えないなあ。あれ、ニャンコがこちらをじっと見ている。紫っぽい灰色の背に白い腹。冗談半分で「おはぎ」と名付けたが案外いい名前だと思う。仕事一筋で夫とも離婚した母との葛藤から不登校になった時、癒しに買ってくれたのがこの猫だった。
美柚とのデートはもっぱら筆談だった。困った時は、例の遠隔手話通訳を依頼した。ある時、ちょっとしたことで喧嘩になった。
「将来はかわいそうな人たちの役に立つ仕事をしたい」なにげなく令和がそう言ったのを、美柚が聞きとがめた。「私ってかわいそうな人なの?」。画面の遠隔手話通訳者も困った風だった。夜になって美柚からメールが届いた。
「急に怒ってゴメンね」。それが書き出しだった。「父が自宅で心臓発作を起こした時、母は仕事で、私しかいなかったの。すぐ119番したわ。でも、消防署の人が電話に出ても、私には何も聞こえないし、何も伝えられなかった。いたずら電話かと思われて切られてしまった。もう一度電話して、叫んだの。私には言葉がないの。だって生まれてから一度も聞いたことも口にしたこともないから。だから、うなり、叫び、泣いたの。でも電話は切られた。そして父は死んだ。私は何もできなかった。耳が聞こえないって、そういうことなの。かわいそうでも、あなたに助けてもらうことなんてできないのよ。わかる?」
もう会いたくないと言う美柚を説得して駅前のカフェで待ち合わせたが、話ははずまなかった。
「何、その猫。変わった色ね」
「わが家の愛猫、おはぎっていうんだ。母が長期出張中で僕もゼミの合宿だから駅裏のキャットホテルに泊めてもらおうと思って」
「フーン。じゃあ、忙しいわね。私もう帰る。きょうをサヨナラ記念日にしましょ」
そう言って立ち上がろうとした美柚がおはぎをじっと見ている。そして、口を押えた。目が見る見るうちに潤んできた。令和に抱かれたタマは左手を前に出し、上に右手を乗せてクルクルと回し続けていた。
「おはぎ、お前いつのまに」。令和はうろたえて猫を抱き寄せた。
美柚は、右手で2を作った後、両手の人差し指を近づけた。
「えっ、また会いましょうだって?」
美柚の涙にあふれた瞳は様々な思いを投げかけていたが、扉の向こうへ跳ねるように消えていった薄いピンクのスニーカーが、夏の訪れを感じさせる陽光をはね返していた。
おまえ、ちょっとやりすぎだぞ、と令和がいたずらっぽく頭をつつくと、おはぎは椅子の上で白い腹を下にして紫に丸まり、嬉しそうにニャアと鳴いて、大きなあくびをした。
(完)
うちのニャンコは名通訳:希代準郎
1 2
キーワード:








-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)