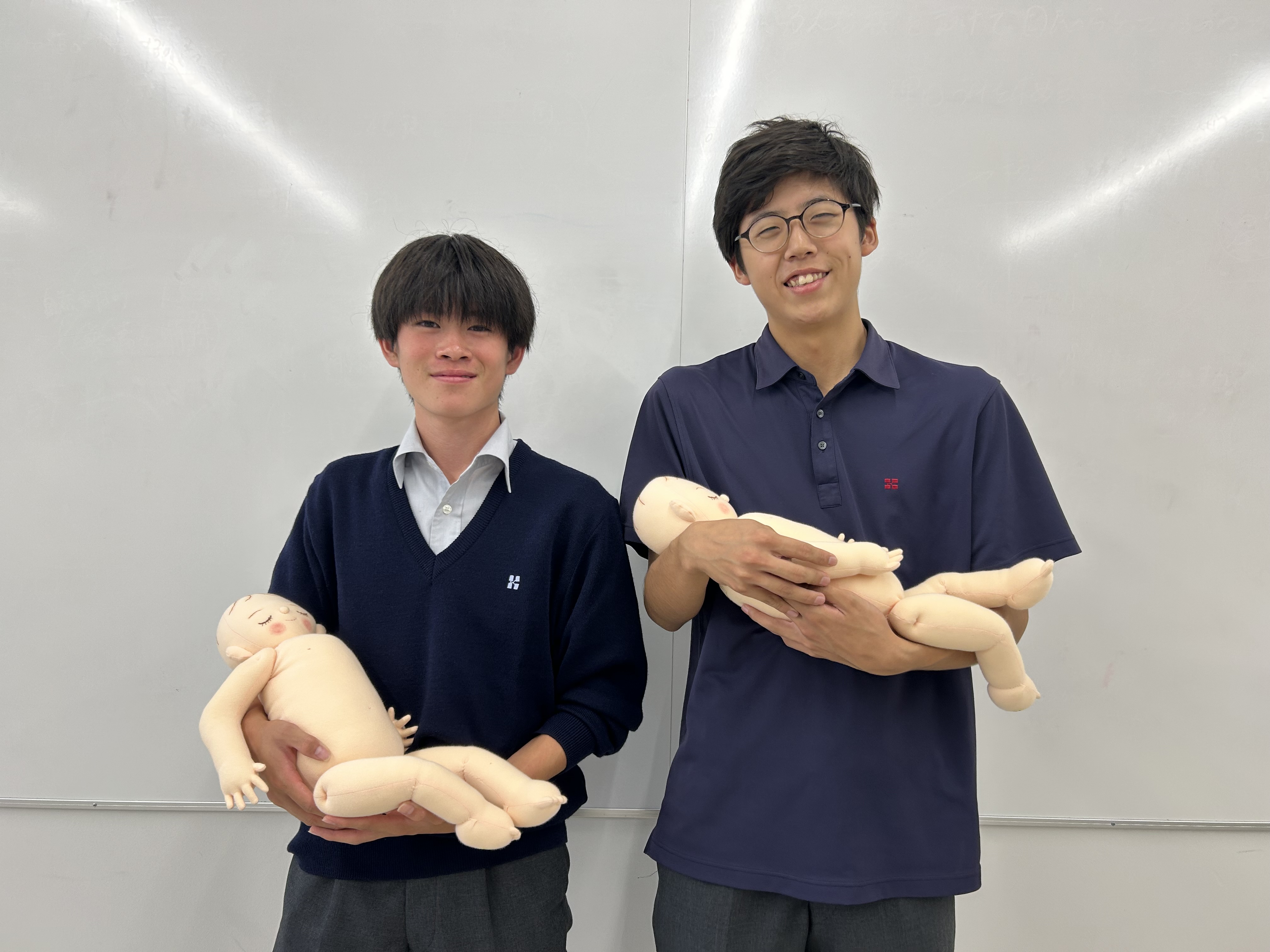経済産業省が「SDGs経営ガイド」を作成し発表した。いよいよSDGsを経営が結びつける動きが加速している。この度、おかげさまで、笹谷は公益社団法人全日本能率連盟主催、経済産業省後援の「第70回 全国能率大会懸賞論文」において最優秀賞である「経済産業大臣賞」を受賞させていただいた(2019, 5, 27授賞式)。論文題名は、「持続可能性新時代におけるグローバル競争戦略―SDGs活用による新たな価値創造―」である。この内容も踏まえ改めてSDGs経営について考えておきたい。(CSR/SDGsコンサルタント/ 社会情報大学院大学客員教授=笹谷秀光)
■「SDGs経営」時代とは何か
SDGsが「経営マター」になったと聞くが、どういう意味であろうか。
SDGs(Sustainable Development Goals/持続可能な開発目標)とは、少し硬い用語であるが、要するに、これからの未来について語る場合の世界の共通言語である。
17の目標と169のターゲットによって構成され、持続可能な社会作りに関する取り組みの集大成で、先進国も途上国も、政府も企業も関係者も、すべてで自主的に取り組む2030年への目標である。
一方、投資家を中心に、ESG、つまり環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance)への要請が世界的に強まっている。そして、ESG投資家はその判断にあたり企業のSDGsへの取り組みを一つの指標として使い、ESGとSDGsは「裏腹の関係」になってきた。
これはSDGsへの対応が株価水準に影響するようになったことを意味する。経営者が対応するIR(Investor Relationsインベスター・リレーションズ)の局面に直接関連する。これが、これまでの CSRなどと違って「経営マター」になった最大の理由であろう。非上場企業も取引先の上場企業からSDGsを求められるので例外ではない。
また、17目標のカバー範囲は極めて広い。企業統治や環境課題への対応のみならず、働き方改革、優秀な人材の確保、採用、マーケティングやブランディング、地域社会との関係など幅広いテーマをSDGsはカバーしている。
さらにSDGsは世界での共通言語であり、グローバルビジネスには必須だ。SDGsに関心の高いミレニアル世代・ポストミレニアル世代の消費者への対応や採用への対応も重要だ。
まさに、SDGsは株価水準、ブランディング、働き方、人材確保すべてに絡むので、社内全部署に関連し、経営トップも重大な関心を寄せる、経営マターになったのである。
経済産業省もSDGs経営/ESG投資研究会を行い、その取りまとめとしてSDGs経営ガイドを発信した。https://www.meti.go.jp/press/2019/05/20190531003/20190531003.html













-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)