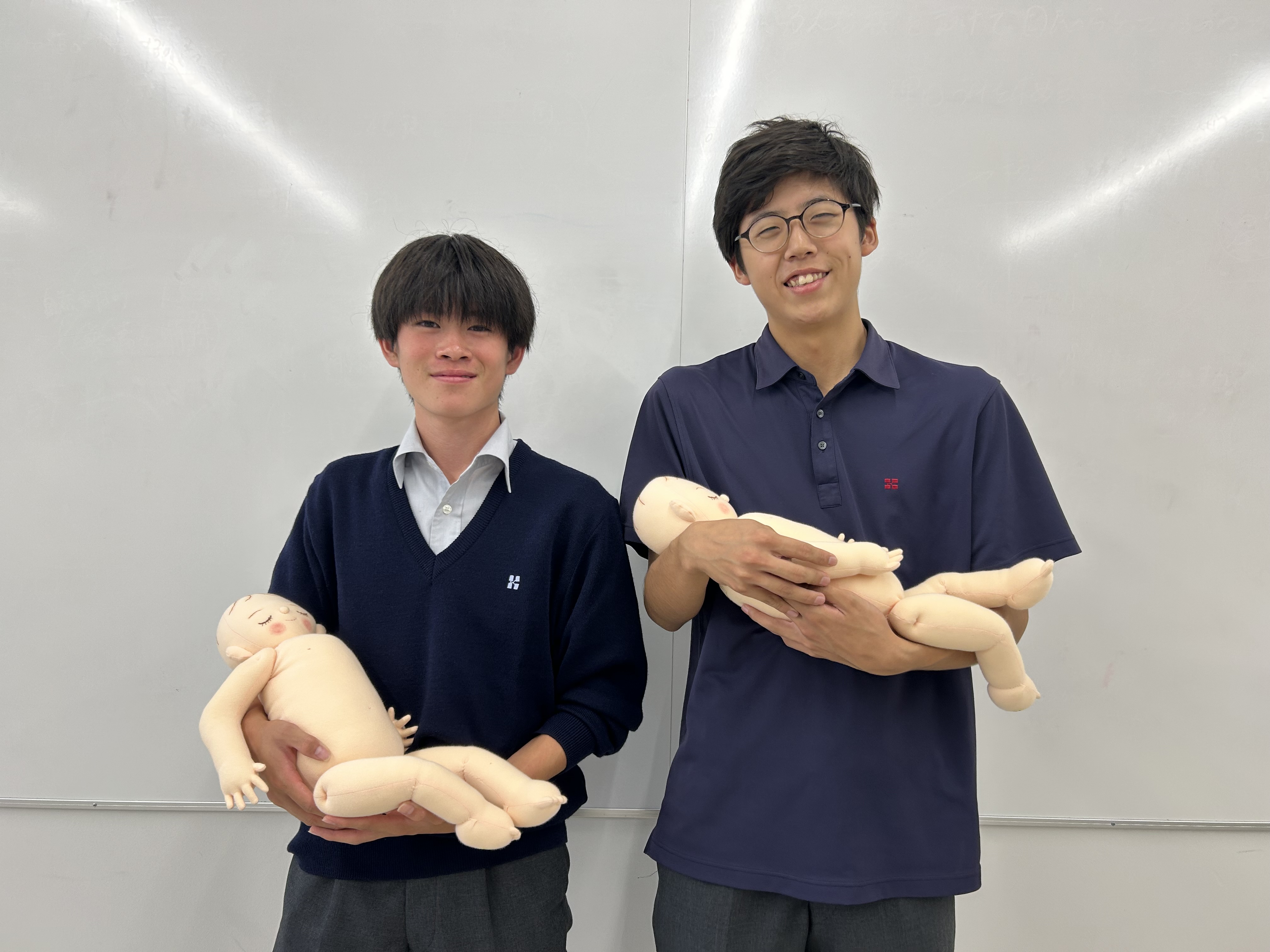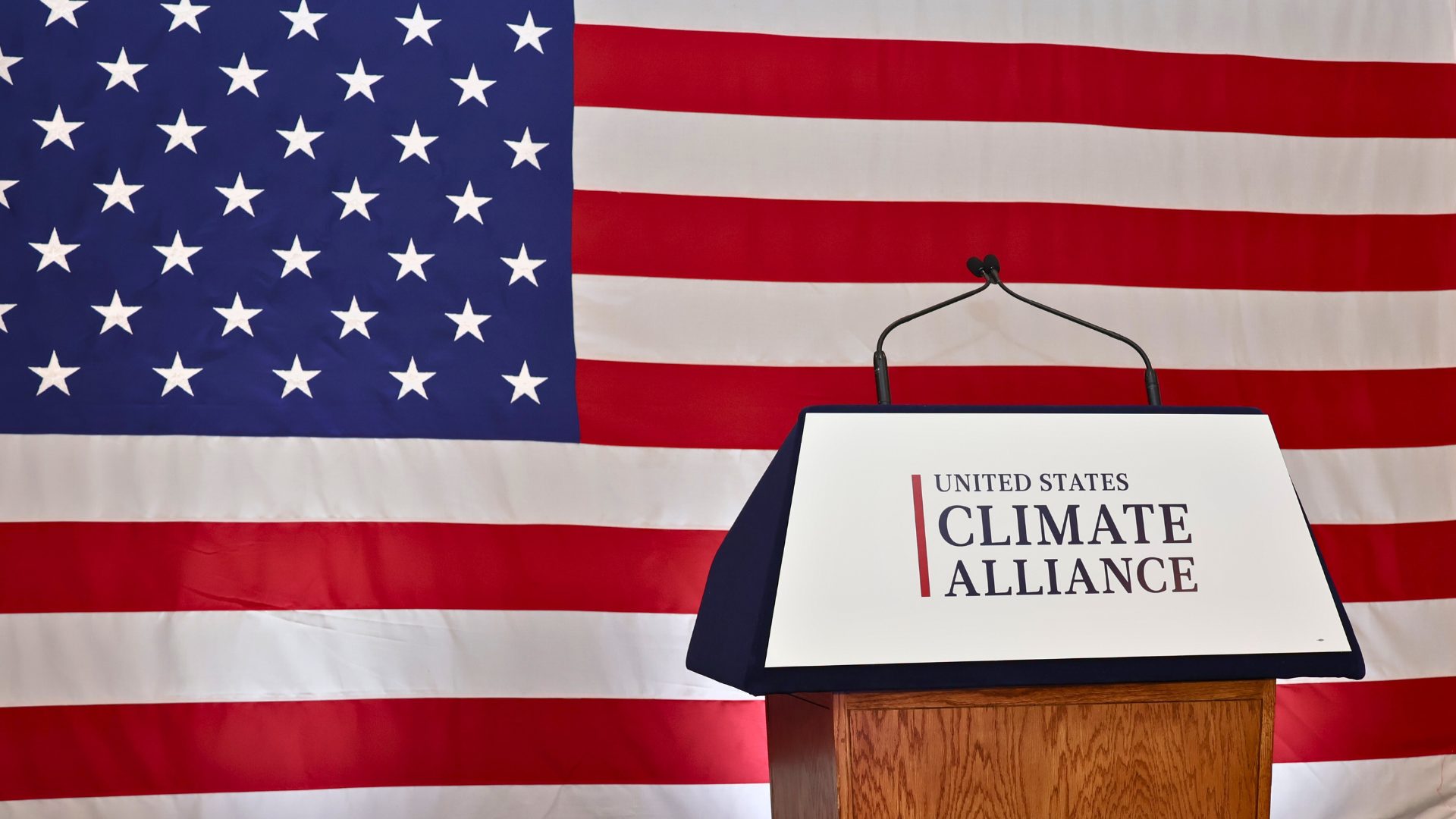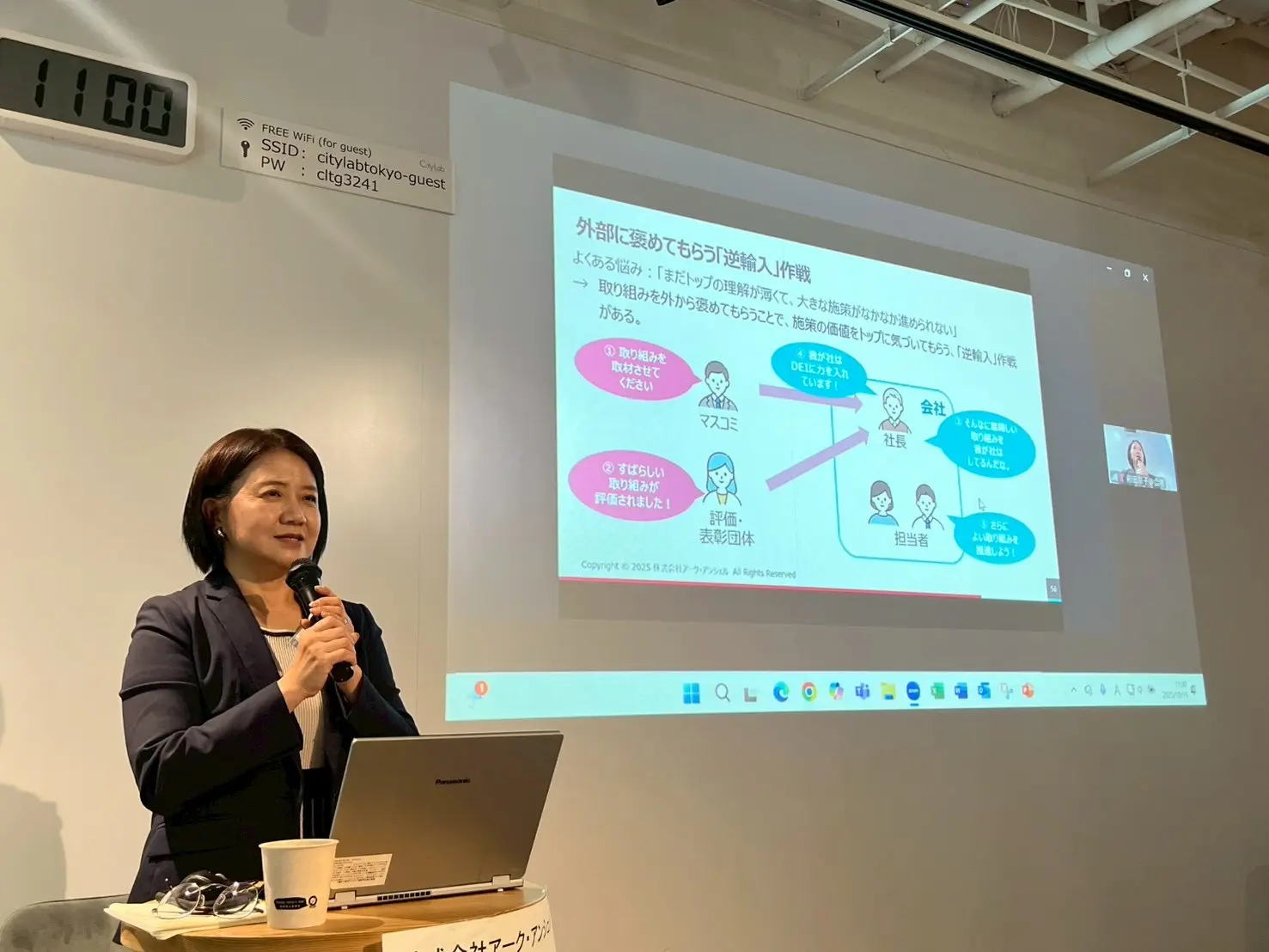目標11「住み続けられるまちづくり」は「都市SDGs」ともいわれ、SDGsの17ゴールの中で唯一、具体的な空間をイメージしたものだとされる。都市は「Systems of Systems」であり、多様なシステム(エネルギー・交通・下水道・社会・経済など)を持つため、最も連携が必要とされている分野だ。中でも交通システムが重要である。中欧で持続可能な交通を考えた。(CSR/SDGsコンサルタント/ 社会情報大学院大学客員教授=笹谷秀光)
■SDGsの国別順位:中欧は高順位
ドイツのベルテルスマン財団と国連持続可能な開発ソリューション・ネットワーク(SDSN)が「SDGsインデックス&ダッシュボード」という名でSDGsの国別達成度のランキングを発表している
https://www.sdgindex.org/reports/sustainable-development-report-2019/
2019年発表では日本は162カ国中15位(2018年も同順位、2017年は11位)。1位デンマーク、2位スウェーデン、3位フィンランド、4位フランス、5位オーストリアの順。ドイツ6位、イギリス13位、米国35位、中国39位。
5位オーストリア、7位チェコ、25位ハンガリーを、目標11「住み続けられるまちづくり」のうち交通システムを意識して回ってみた。まちづくりで主要な指標の一つが、持続可能な交通システムだからだ。上記のランキングではSDGs各目標についていくつかの指標で比較しているが、目標11では、次の3つである。
・都市部での2.5未満の粒子状物質(PM2.5)
・改善された水源、配管(アクセスできる都市人口の割合)
・公共交通機関に対する満足度(%)
このうち先進国都市では、1番目や2番目はクリア済みなので、3番目の公共交通機関に対する満足度の指標に差が出るだろう。各指標評価には経年変化も出ている。



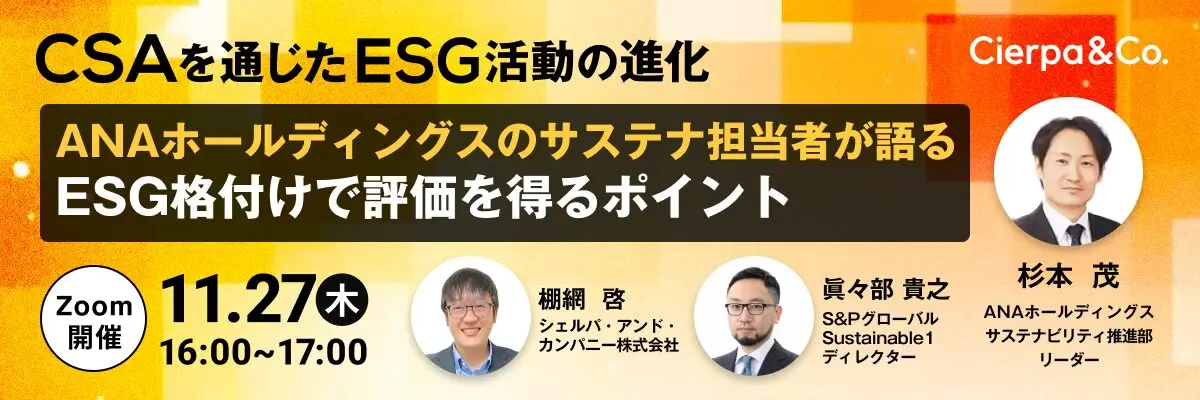









-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)