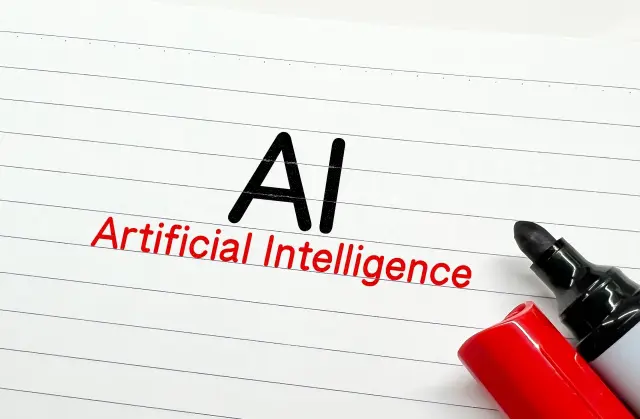◆「ショート・ショート」(掌小説)こころざしの譜(42)
先日亡くなった旧友から突然手紙が届いた。葬儀が終わったら投函するよう誰かに頼んであったのだろうか。
男の名前は加納正司。元プロ野球選手だった。故障がちで二軍暮らしが多かったから誰も名前を知らないだろう。私はその男と高校で同級生、同じ野球部だった。剛腕で注目された加納。私は地味なキャッチャーで好対照だった。私はノンプロで野球を続け今は母校の野球部のコーチをしている。
二人とも背が高く、ツインタワーというあだ名をもらったこともあり気が合ったが、いつの間にか連絡が途絶えた。加納には友達がいなかった。
「お前がこの便りを読むころには俺はこの世にいない。古い付き合いのお前に頼みがあってこの手紙を書いている」
手紙はそんな出だしで始まり、息子を頼むと書いてあった。未婚だったはずの加納に子どもがいたことに驚いたが、その頼み事というのがまた意外なものだった。
芳沢、聞いてくれ。驚くと思うが、独身の俺に男の子がいる。プロに入る前、付き合っていた女がいた。同級生の轟恵美子だ。高校3年の時、妊娠し学校を中退した。中絶したとばかり思っていたのだが一人で産んだらしい。ずいぶん後になってそのことを知った。結婚しようと思って連絡を取ろうとしたが、結局、会えず仕舞だった。
芳沢は轟という名前に記憶があった。色白の控えめな子で、確か卓球部じゃなかったか。卒業を待たずに退学したことでとかくのうわさが立ったと記憶している。
信じてくれ、芳沢。先日、偶然、病院のテレビで見たんだ。「目指せ甲子園・東北の隠れた逸材~轟駿也手」という番組でな。間違いなく息子だった。俺が元気なら自分で教えてやれるんだが、ガンで余命いくばくもない。俺の代わりに例の魔球でプロ野球選手にしてやってくれ。34歳で死んでいく友達の最後のお願いだ、頼む。
やれやれと芳沢はため息をついた。あいつらしい。ドラフト1位で舞い上がり、顰蹙を買ったんだよな、お前。
東北とはいえ夏の季節は東京と変わらない。県大会準決勝のマウンド上の長身のピッチャーの剛速球は高校生離れしていた。うちの高校とはえらい違いだ。球速は150キロを超えている。これでは打てないなと思った通りまともにバットに当たらない。9回裏、1対0で勝っているが、満塁だ。
「駿也、あと一人だ」キャッチャーが大きな声をかけた。
「オーケー、大輔」
大輔という捕手の構えは変わっている。膝を曲げずに、両膝を地面について構えるのだ。よほど肩に自信があるのだろう。外角球だ。カキーン。相手バッターが軽く出したバットが快音を発した。万事休す、サヨナラ負けだ。青い空を切り裂いてぐんぐん伸びる右中間への打球に芳沢がそう思った瞬間、俊足のライトが大地を蹴りながら風のようなスピードで打球に飛びつき、クルリと体を一回転させるとグラブを高々と掲げた。
「やったあ、ゴンちゃん。すげえ」大歓声である。
ゴンちゃんと呼ばれたちょっと太めの選手は皆とハイタッチしている。
「おじさん、野球の神様かい?」芳沢が帰りの電車の中で、おめでとうと声をかけた時、駿也から返ってきた第一声がこれだった。「おばあちゃんがいつも話しているんだ。お前のところにいつか野球の神様がやってくるよって」
間近で見る駿也は体つきも顔も父親の加納にそっくりだった。
「いや、神様じゃない。東京から来た神様の友達だ」
「えーっ、遠くから来たんだ」
「最後のボールはカーブか」駿也はうなずくときまり悪そうに下を向いた。あれだけのスピードボールが投げられるなら、あとは落ちるボールがあれば完璧だ。右手を見せてもらった。思った通り、身長の割に指が短い。加納もそうだった。
「駿也君、落ちる球を覚えないか」
「フォークは苦手で」
「その指じゃな。少し工夫しよう」








-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)