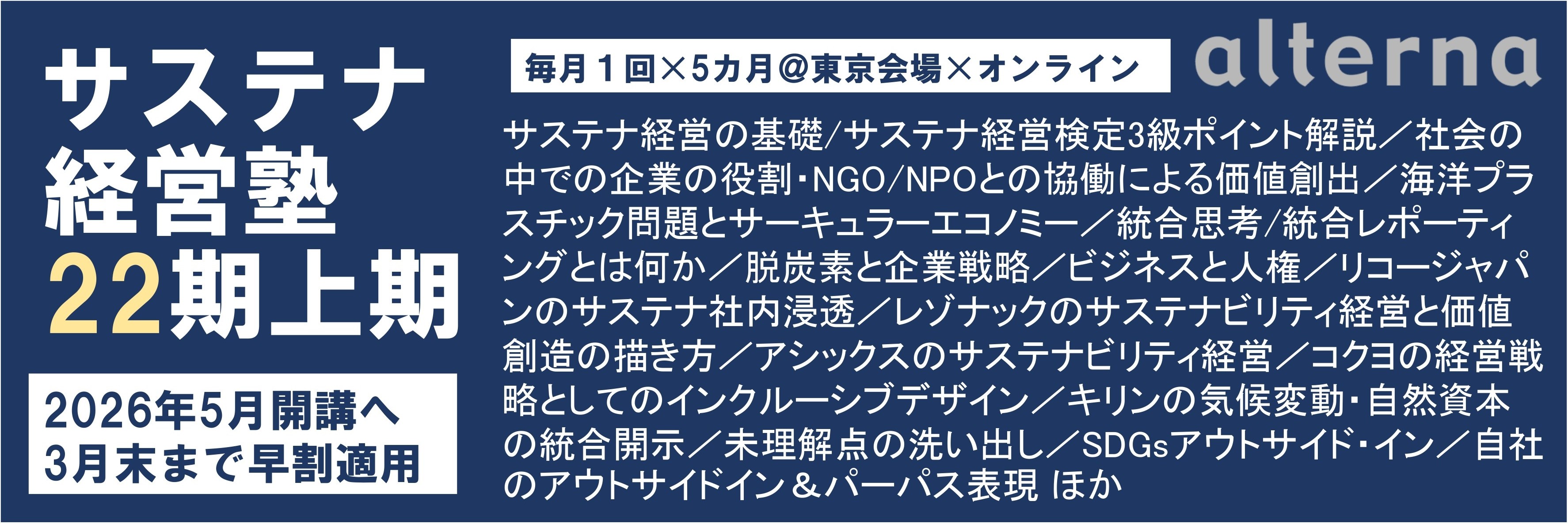WWFジャパンはこのほど、サステナブル(持続可能な)シーフードを選ぶ目安をまとめた「おさかなハンドブック」を発行した。魚介類のサステナビリティ評価一覧を全面的に刷新したのは8年ぶり。従来はパンフレットだったが、今回は買い物の際のヒントを具体的に示すため、A5判47ページの冊子とした。10月30日にはポスト・コロナの魚食を考えるオンラインイベントを開催し、参加者にはPDFを配布する。(オルタナ編集委員・瀬戸内千代)
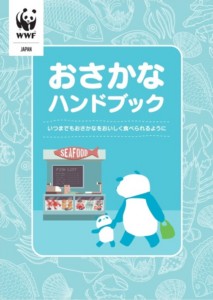
2012年発行、2014年改訂の「寿司(さかな)ガイド」は、評価一覧を切り取り名刺サイズで携帯できるパンフレットで、天然・養殖別に寿司ダネになる魚介類のサステナビリティを示していた。
今回、最新の資源状態を反映して2020年9月に発行した「おさかなハンドブック」は、対象魚種を増やし、携帯性よりも「知る」ための情報量を優先したという。魚が海で獲られて食卓に届くまでの流れや、漁法の違い、魚種ごとの資源状態などの解説を、1冊にまとめている。
「サステナビリティ評価一覧」は見開きに掲載し、36種の魚介類を漁場や漁法別に71のカテゴリに細分して持続可能性を緑色から赤色までの5段階で示した。安心して選べる上位2段階の緑色ゾーンに入ったのはアラスカのサケ類や日本の垂下養殖ホタテガイなど14カテゴリのみだ。
日本でも国産牛では「個体識別番号」の表示が義務付けられ、トレーサビリティ(追跡可能性)が実現している。しかし水産物では、原産地の代わりに水揚げ漁港の県名のみを表示することが許され、一部の刺身盛り合わせのパッケージなどでは魚の名称すら確認できない。
WWFジャパン海洋水産グループの滝本麻耶パブリックアウトリーチオフィサーは、「身近なイカやタコも減って輸入品を消費している。サステナブルな魚を選びたくても今の表示制度では情報不足で選びようがない。この冊子が、現状を知り消費者から声を上げるきっかけになれば」と語った。
WWFジャパンとタイガーモブは冊子発行を記念して、10月30日にオンラインイベント「ポスト・コロナ時代に求められる 人と自然の関わり方 おさかな編」を開催予定だ。
WWFジャパン「おさかなハンドブック」
https://www.wwf.or.jp/campaign/osakana/