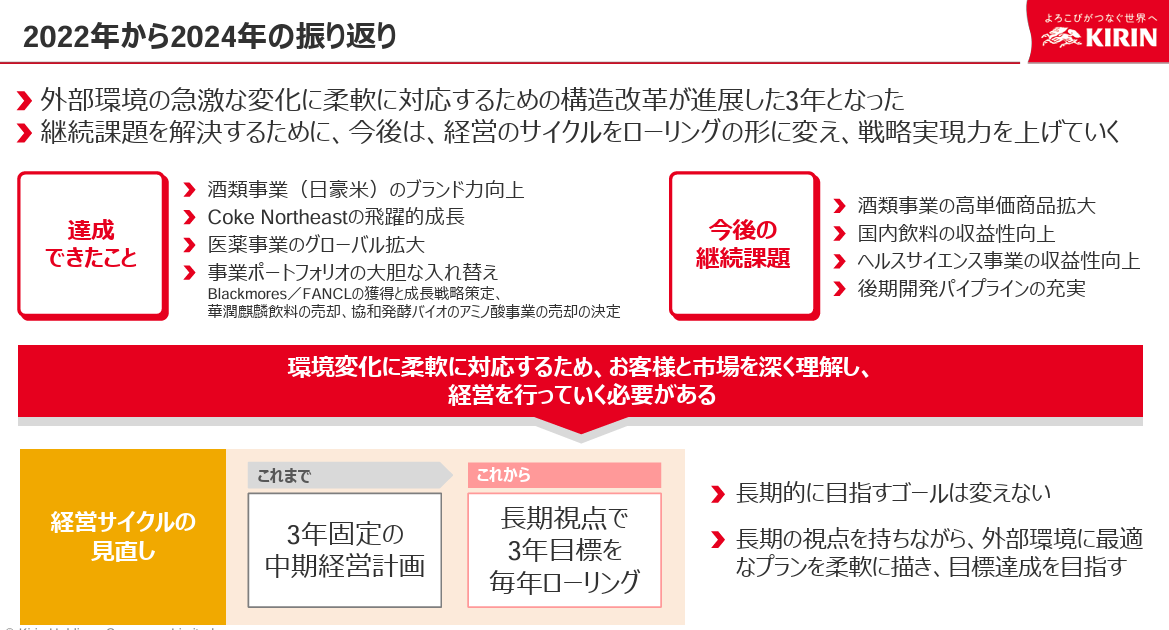■争点は「セーフガード」と「森林の定義」
こうした経緯をたどって現在へと至るREDD+だが、COP16の議論ではREDD+の実効性をどう担保するのかが焦点となる。ここで争点になるとみられているのが「セーフガード」と「森林の定義」だ。

セーフガードとは、REDD+の実施が、森林の生物多様性や、熱帯雨林などに暮らす先住民に対して悪影響を及ぼさないように講じる対策のことだ。具体的には、REDDに伴い天然林から人工林への転用が生じないことや、土地や自然資源の利用について、先住民や地域社会の権利や慣習が守られることなどを意味する。REDD+のもう一方の当事者である生物多様性や先住民、地域コミュニティを尊重するのが目的だ。
RAN(Rainforest Action Network)日本代表でJATAN(熱帯林行動ネットワーク)運営委員の川上豊幸氏は、セーフガードをめぐる議論について「コペンハーゲンの時点では、セーフガードの実施を『促進する』『支援する』というやや弱い表現が使われていた。これに対してNGOや一部の国などは『確保する』という、より強い表現での合意を求めており、今回の議論でもこの点を攻防の焦点にしたい」と語る。
また、森林の定義をめぐっては、REDD+の対象を天然林に限定できるかどうかが争点となる。もし仮に森林の定義に人工林を含めた場合、CO2の吸収を名目に天然林から人工林への転換が起こる可能性があるのだ。例えばパームヤシや紙原料のアカシアなど、単一樹種の植林への土地転換が森林減少や劣化とは認識されない事が起こりうる。こうなっては、REDDの本来の目的である森林の減少と劣化を食い止めることは難しい。
川上氏は「そもそも森林の減少、劣化の原因について先進国の責任が明確になっていないことも問題」とした上で「先進国による森林資源の消費の仕組みにメスを入れることが必要だ」と指摘する。今回のカンクンでの議論で、REDD+をめぐる合意はどこまで進展するのか。その行方は温暖化対策だけでなく、森林の未来そのものを左右する。(オルタナ編集部=斉藤円華)2010年12月6日