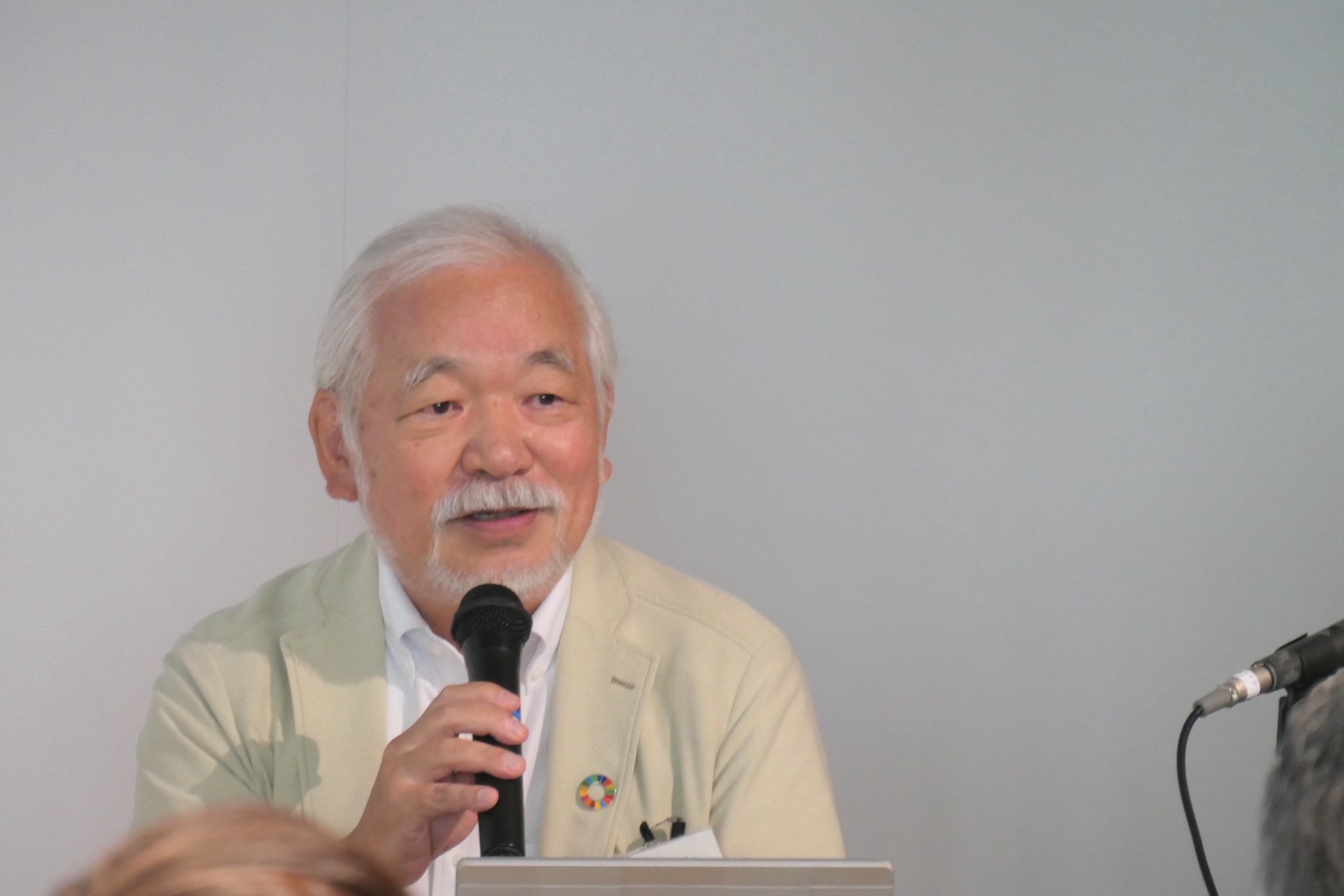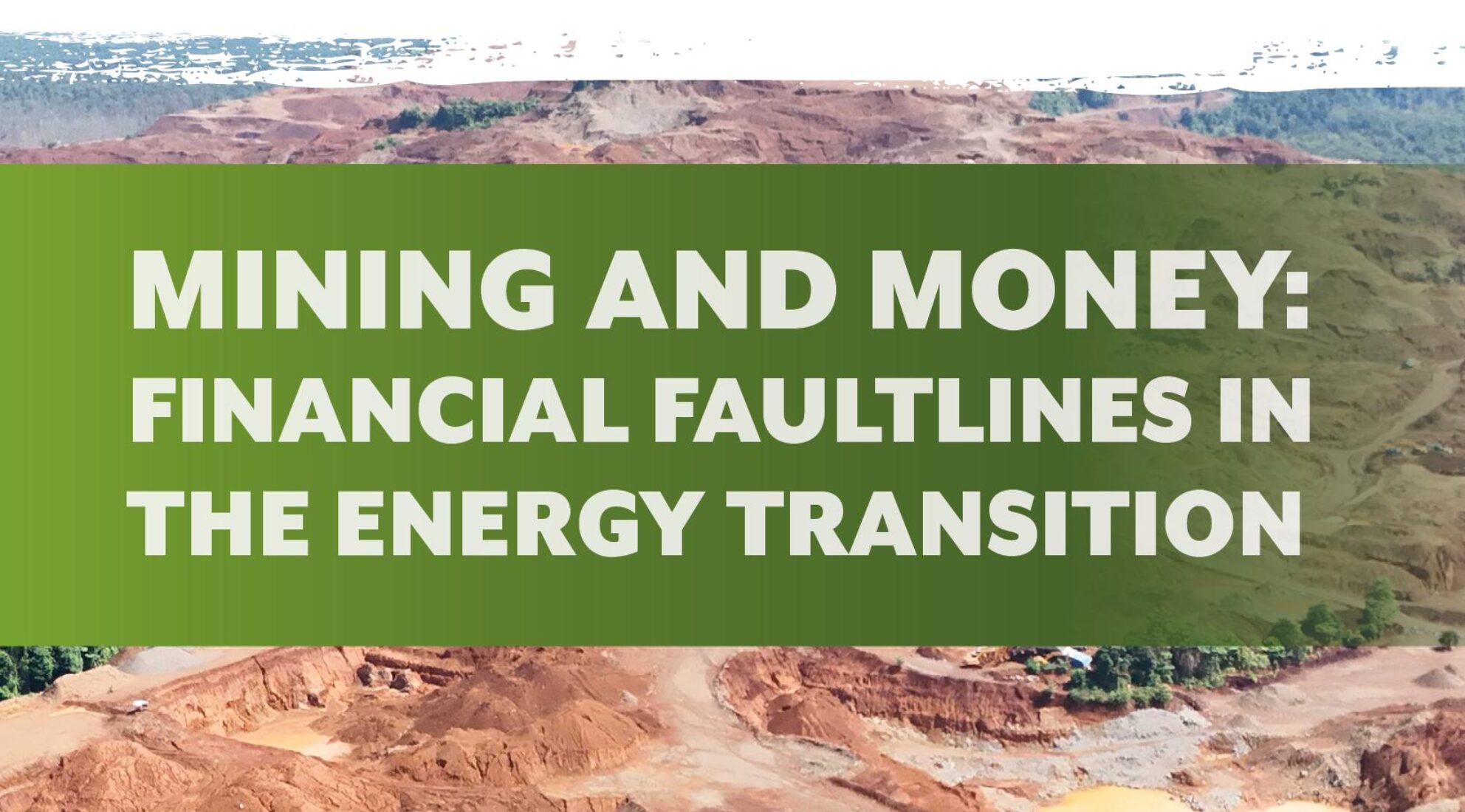【連載】ソーシャルデザイン最前線



2019月2月、細田守監督の「未来のミライ」がアニー賞で長編インディペンデント作品賞を受賞した。日本人監督初の快挙である。個人的には、細田監督の作品の中で最も共感したアニメ映画だ。
細田監督の作品には、共通してあるテーマを見つけることができる。
「サマーウォーズ」は「大家族のありがたさ」。結婚した奥様の実家が、長野県上田市にあり、大家族であったことがモチーフとなって生まれた。「おおかみこどもの雨と雪」は「シングルマザーの子育て」。監督のお母さんが亡くなったことで、母の総括をしたいという思いから生まれた。「バケモノの子」は「父親の子育て」。監督に息子が誕生し、父親となったことから生まれた。
そして「未来のミライ」は「兄妹の子育て」。監督の長男にとって妹となる長女が誕生したことで作品が生まれた。
これらの作品は監督の家族をモチーフに描かれている。家族テーマは人間の普遍的な課題で、世界でニーズがある。「子どもを育てる大切さありがたさ、そして子どもの成長はアニメの力で表現する」ことに一貫してブレがない。
監督は富山で生まれ育ち、金沢美術工芸大学の油描学科出身。私も同大学でデザイン学科を卒業しているが、絵が一番上手い学生は油絵学科に行く空気やプライドがあった。
油絵学科は自画像を含め時間をかけて1枚の絵を描くことから、必然的に自分と真剣に向き合うことになる。学生の頃から常に自分にアポをとっているので、自分の主体性を育てるのは得意中の得意である。
監督は絵コンテを描くために約8カ月間、一人部屋にこもるという。そんな長い時間一人で向き合える能力は、おそらく強い感情と学生時代からの習慣からくるものだ。
自分は何者か常に自分を掘り下げ、自分の主体性を大切にすることで、自分を信じる力になる。人は大人になっていく過程で、毎日の生活において気になることや、引っかかること、おかしいこと、つまらないことなどのさまざまな気づきや疑問などの感情に、蓋をしてしまう傾向がある。
蓋をせずに大切にしまっておいて、勇気を出してそれをもとにしたアイデアを生み出し、臆せずに人に伝えられる人が優秀なクリエイターだろう。
アニメを作ることが大好きで得意分野であって、それを仕事に生かしている。監督にとっても家族にとっても社会にとっても良くなる。こんな素敵な活動はほかにない。
ソーシャルデザインは、社会や世界を変えたいと言う思いから語られることが多いが、多くの人にとっては世界を変えるなんておおげさに思えるかもしれない。だが、自分が変われば世界が変わり、普段見ている光景が変わる。社会が悪い、会社が悪い、調子が悪い、格好が悪い、親が悪い、地元には何もないなど、そう思っていないだろうか。
それでも誰もが何かしらの強みがあり、大切な感情がある。細田監督のように自分の存在意義をつくることで、社会の優しさを残すことになるだろう。
ソーシャルデザインは宝探しであり、宝は自分の中にあるのだ。
雑誌オルタナ57号(2019年6月24日発売)から転載



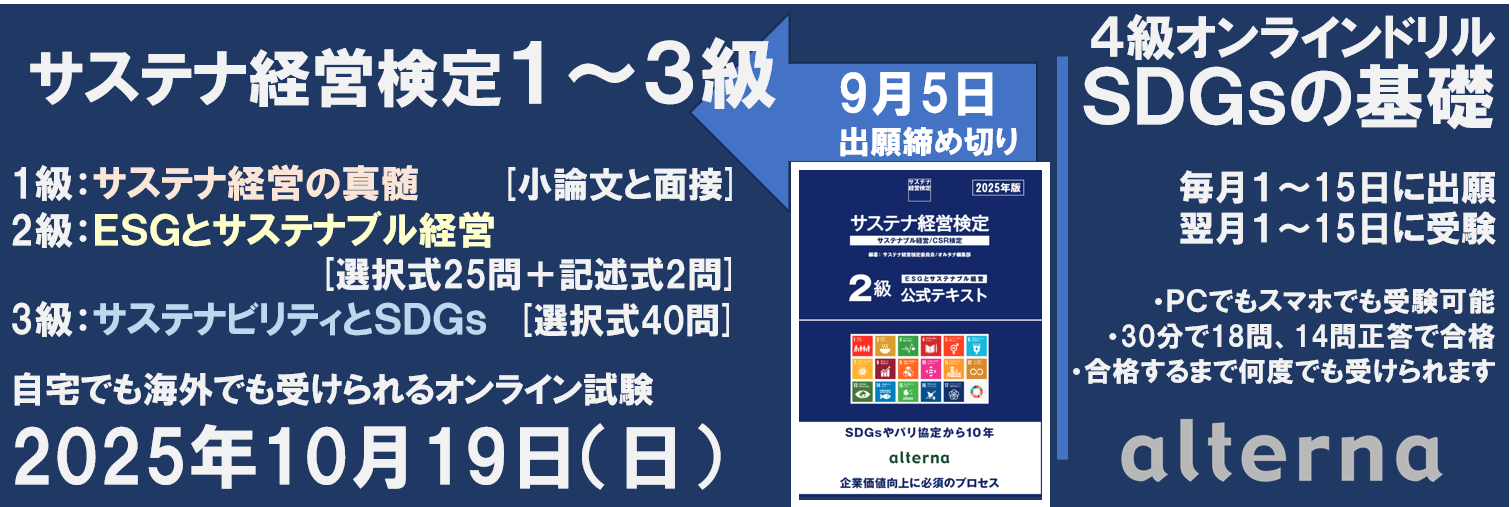






-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)