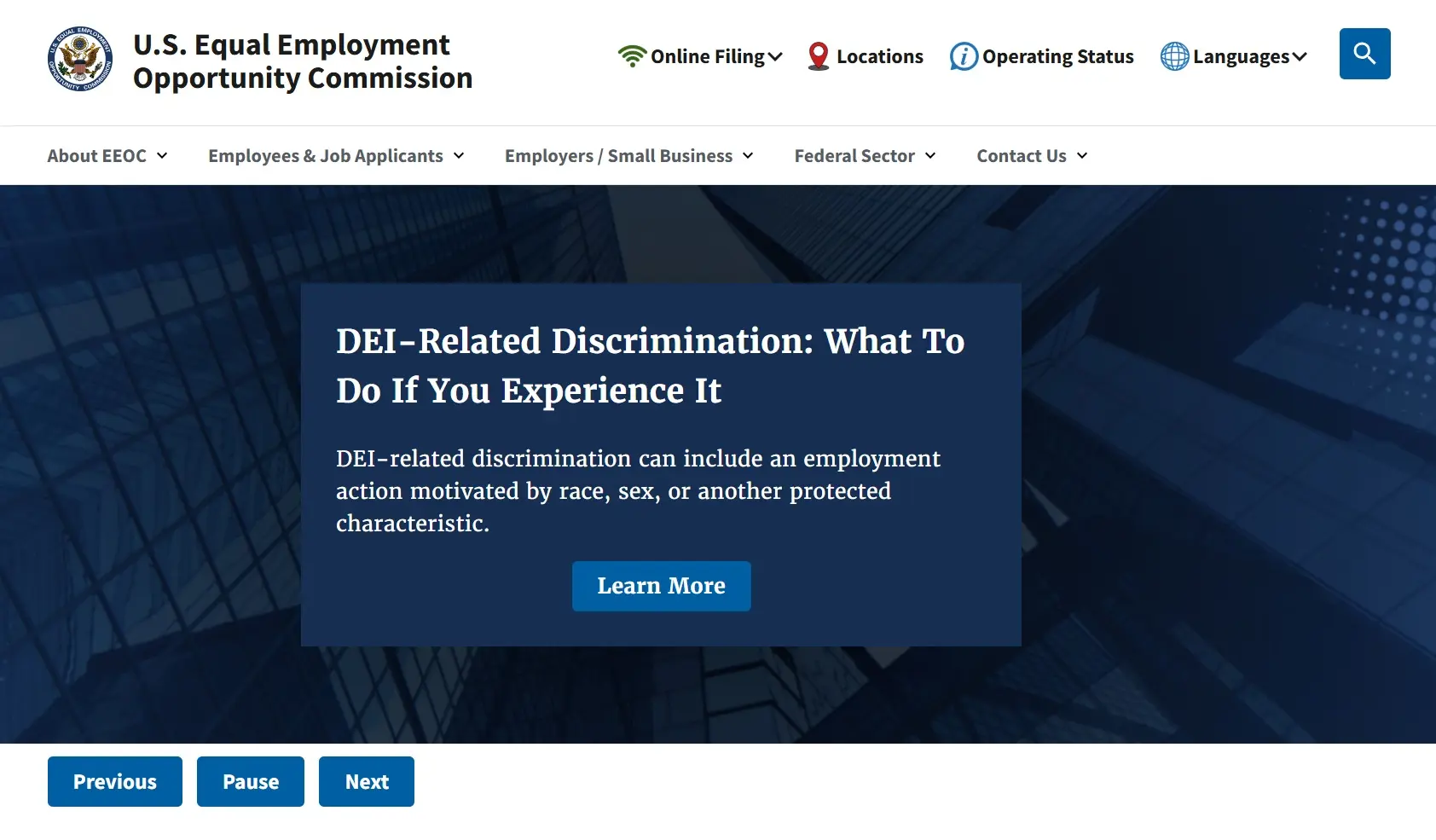記事のポイント
- 地震や火災など自然災害に備える防災拠点の重要性が増している
- ハード面の強化もさることながら防災の基本は、「自助・自立」だ
- 不測の事態に対応する「サステナブルな地域ハブ」をどうつくるか
地震や火災など自然災害に備える防災拠点の重要性が増している。施設のハード面の強化もさることながら防災の基本は、「自助・自立」があってこそだ。自然災害はこれからも増えることが予測されており、不測の事態に対応する「サステナブルな地域ハブ」をどうつくるのか。(オルタナ客員論説委員=竹村眞一)
日本三景の一つ、東北・三陸海岸の松島に「KIBOTCHA(キボッチャ)」という興味深い施設がある。東日本大震災津波で被災した廃校を再生して「スマート・エコビレッジ」を創生、非常時には1万人規模を収容できる避難所としても機能する「防災体験型」の宿泊・グランピング施設(開設から約7年で累計来場者数17万人超)だ――。
これだけでも画期的だが、そんな平板な紹介では収まらない数々の先駆的な社会実験がそこに芽吹いている。「希望+防災+未来=フューチャー」を圧縮したその施設名そのままに、日本と世界のこれから進むべき道がそこに示されている。
■「DAO」で善意の好循環を促す
防災の基本は何より「自助・自立」――。災害で電気や水道、食料供給が途絶えても、地域の人々のライフ(=生命・生活・人生)の持続可能性を担保すること。
そのために敷地内に湧水池を造り、最小限の水で水耕栽培ができる先端技術(注1)を取り入れて屋内で野菜を作り、特殊な冷凍方法で肉や魚の鮮度を何カ月も維持・保存する新技術も導入(注2)。
自家発電の電気をEVに貯めてV2H(Vehicle to Home=EVが家庭用蓄電池として機能する仕組み)で施設の電力を担保する体制も準備中だ。
こうしてハード面のインフラの災害耐性を更新するとともに、子どもが遊ぶ遊具空間にも、人間としての自助・防災能力を高めるような工夫を盛り込んでいる。
たとえば火災時など煙を避けるのに必要な「ほふく前進」を楽しく身につけられる仕掛け、傾いた家の屋根を登ったり、障害物競走のような環境から脱出スロープを滑ったりと、まるで災害時の避難に近い体験ができる環境を造作し、いわば「心とからだのOSのアップグレード」もさりげなく図るデザインがなされている。(ここは航空自衛官出身の創設者・三井紀代子さんの経験資源が生かされているように感じた。)
だが「自助」は「共助」とセットになって初めて力を発揮する。そこで共助のつながり、価値創造と善意の好循環を促す仕組みとしてDAOが導入されている。
DAOとはもともと「自律分散型組織」(Decentralized Autonomous Organization)の略で、特に近年はブロックチェーン技術の進化とも相まって、中央銀行や政府が発行する法定通貨ではない「地域で自発的・分散的に発行・流通する代替貨幣」の意味で使われることが多い。
わかりやすく言えば、誰かの働きや貢献に地域通貨=トークンが支払われ、それを別の誰かの仕事(の成果物)を買うことに使えるという仕組みだ。
たとえば、ある人がライドシェア(送り迎え)や街の美化(アートワーク)、ゴミの片付けなどを手伝ってトークンをもらう。それを使って受けられる「気功マッサージ」を両親にプレゼントする。あるいは家族でご飯を食べに行く――。
そんな価値の循環を可能にするDAOのベースには、もう一つ「ゴミから価値を生みだす」というこの組織のポリシーがある。
■「昨日3日ぶりにお金を使った」
まずKIBOTCHA(キボッチャ)は規格外の野菜や果物、あるいは営業時間が終わる夕方以降は廃棄食になってしまう食材や料理を、法定通貨「円」でなくこのトークンで支払って食べられるシステムを設計した(現在はこのシステムを採用する飲食店が「きぼっちゃ」以外にも市内にいくつも増えている)。
あるいは街のクラフトビール醸造所でタンクの下に残るビール残渣――といっても少し酵母が多めに溜まっているだけで美味しいビールなのだが――を、このトークンで飲めるようにした。
こうして自分の働きが誰かの役に立ち(トークンをもらい)、ゴミが有用な価値を持つものに再生(Re-generate)され(事業者も廃棄コストを削減でき)、ほとんどお金を使わずに美味しい暮らしが成り立つという「善意の好循環」が街の経済にビルトインされることになった(実際このトークンで食べられる「まかない」を家族3人で食べていた中心スタッフの一人は「昨日3日ぶりにお金(円)を使った」と語っていた)。
DAOとはそんな人間資本と自然資本、社会関係資本をつなぐ価値循環のループをデザインする仕組みなのだ。ともすれば頭でっかち=理論先行型になりがちなDX通貨システムDAOが、ここではしっかりと身体的なレベルのDAO(=自立分散的な物質循環のシステム)に根を下ろしていた。
これはあらゆるゴミや下肥(うんち)までアップサイクルして100万都市を支えた江戸以来の日本の文化OSの更新ともいえる。
利休の「侘び茶」では、漁夫が使う魚籠(びく)も結構な花入れ・茶道具としてリフレーミングされる。あるいは廃棄するしかないように思われる割れたお皿も、「金継ぎ」してオリジナル以上の価値(=新しい景色)をそこに現出させる。
「サーキュラーエコノミー」などという外来語を使わずとも、廃棄物や無価値なモノをアップサイクルする日本の価値創造OSはもともと半端ではない。
だが、これが東松島で行われていることには、また特別は背景もある。それは今では「東松島モデル」と呼ばれている、震災後の瓦礫処理の物語だ。
通常は国の予算で専門業者が行う瓦礫処理を、東松島では住民自らが行った。瓦礫処理を請け負った街の建設業協会会長・東松島市商工会会長の橋本孝一氏の創意で、瓦礫処理の予算は被災した人々のべ1000人の雇用に充てられた。
徹底した分別で瓦礫の山はほぼ100%近く「資源化」され、国から交付される瓦礫処理コストも結果的に当初予算の3分の1で済んだ(1千億円以上下回った)という。こうした偉業もさることながら、こうして街の再建に「参加」する回路を得た地元の人々の、心とからだの健康への寄与はいかに大きかったかは想像に難くない。
それは街の再建を通じた人の心の再建プロセスであり、その地域社会のDNAがKIBOTCHA(キボッチャ)という地域外の人々のコミットメントで創設・運営される組織にもしっかりと継承されている。
■「マルチハビテーション」が日本の未来を開く
■1万人規模の「いのちの安全保障」拠点を全国に
■教育の未来形、人間資本のアップグレードを