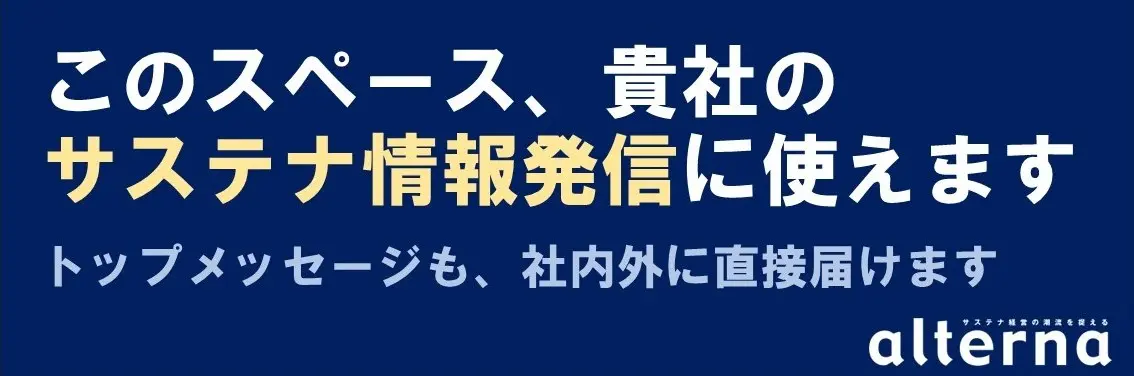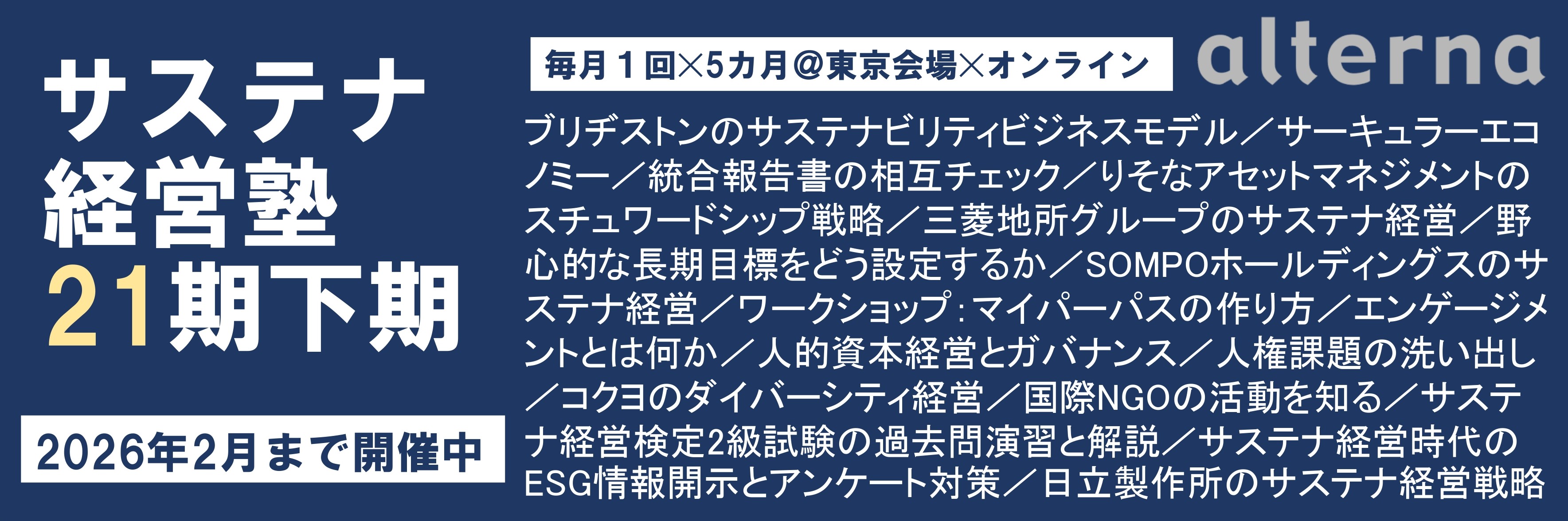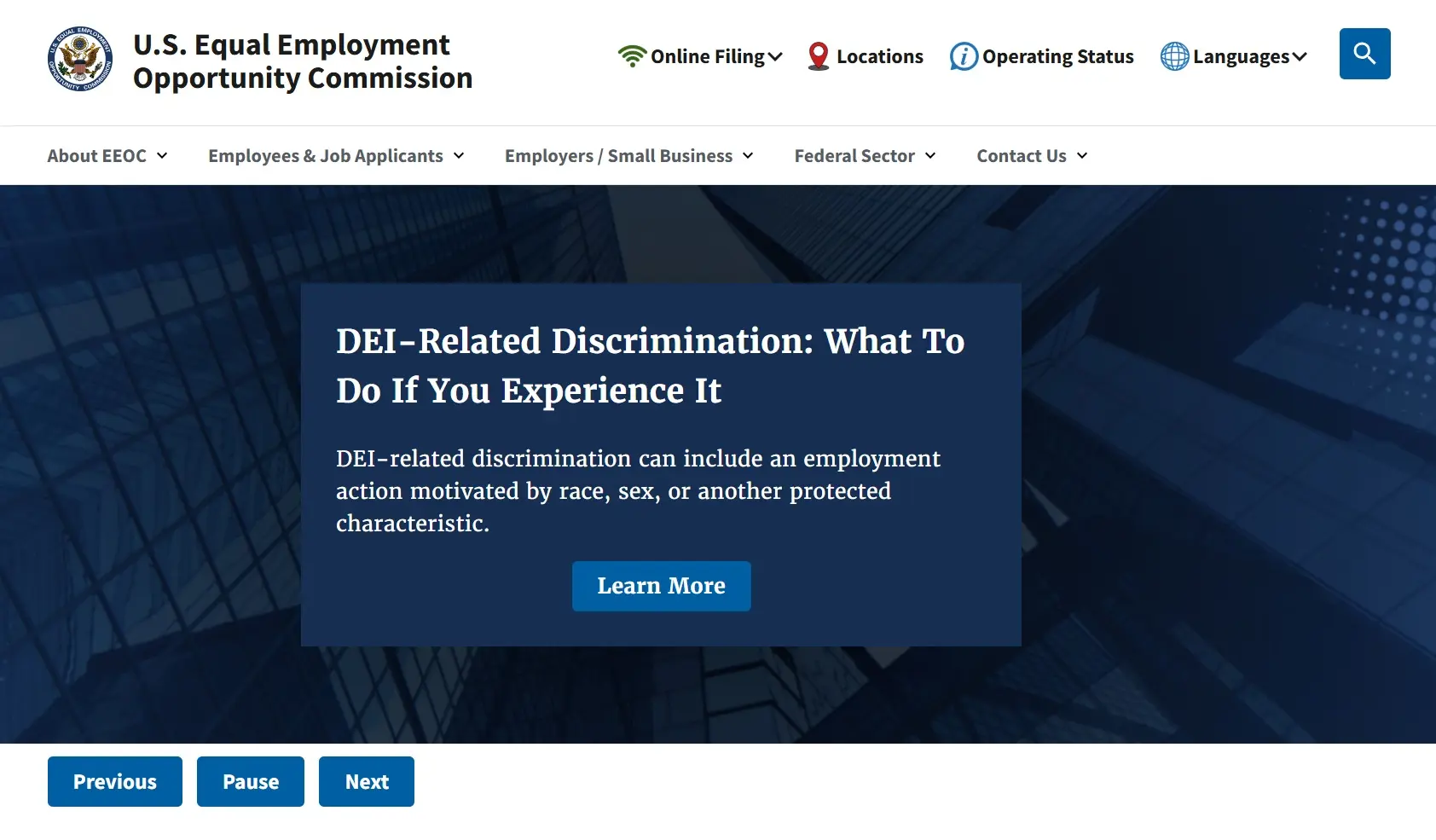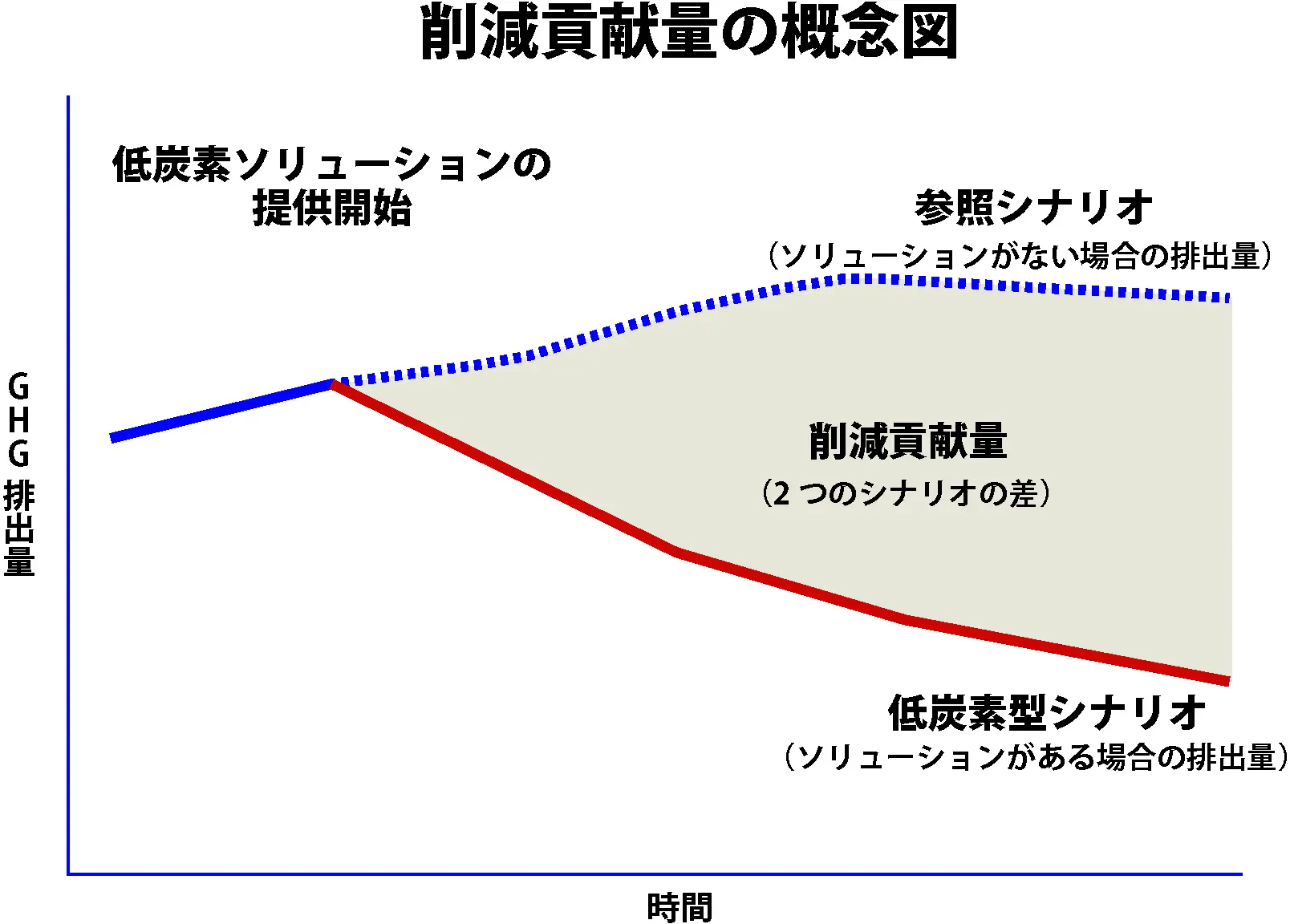記事のポイント
- アルファサードが「やさしい日本語」自動変換システム「伝えるウェブ」を開発した
- 朝日新聞グループに参画し、メディアのアクセシビリティ改善に取り組む
- 当事者と共に声を上げ、選挙公報や災害時の情報保障などの社会課題に挑む
朝日新聞グループの会社案内や採用サイトには、ページ上部に小さなボタンがある。クリックすると、難しい記事が「やさしい日本語」に変換され、ふりがなも自動で振られる。外国人、子ども、高齢者、障害者──。これまで「言葉の壁」に阻まれていた人たちに、ニュースを届けるための仕組みだ。
その技術を生み出したのが、ウェブ開発などを手掛けるアルファサード(大阪市)創業者の野田純生さんだ。20年間、ウェブの世界を走り続けてきた彼が、60歳を目前に朝日新聞グループに加わったのは、「メディアのアクセシビリティを変えたい」という強い想いからだった。(聞き手=NPO法人インフォメーションギャップバスター理事長・伊藤芳浩)
■短い文章で、誰もが理解できる形に
2018年、野田さんは学習院女子大学で開催されたあるイベントに、一人の参加者として足を運んだ。テーマは「やさしい日本語と多文化共生」だ。
「当時、やさしい日本語というものがあることは知っていましたが、主に在留外国人のための取り組みだと思っていました。でも、そのイベントで出会った『スローコミュニケーション』という団体の活動を知って、考えが変わりました」(野田さん)

一般社団法人スローコミュニケーション(千葉県浦安市)は、長年にわたり知的障害者への情報保障として、「ステージ」という新聞を発行していた。難しい言葉を避け、短い文章で、誰もが理解できる形でニュースを届ける。その実践を聞いた野田さんは、「言葉の壁」にも共通性があることに気づいた。
「外国人も、障害者も、同じように『日本語の難しさ』という壁に直面していた。やさしい日本語は、国籍や障害の有無を超えた、『誰にも伝わる言葉』だったんです」(同)
ウェブ開発の専門家として、野田さんは「『言葉の翻訳』を、機械的にできないだろうか」と考えた。
■ゼロから作った「伝えるウェブ」
野田さんは、やさしい日本語への自動変換を提供しているAPIやエンジンはないか、すぐに調べ始めた。しかし、2018年当時、そのようなサービスは存在しなかった。
「今でこそAIブームですが、当時はまだそこまで進んでいませんでした。本当に使えそうなものがなかったのです」(野田さん)
ならば、自分で作るしかない。野田さんは、アルファサードのメンバーと共に開発に着手した。「私は作るのが好きなのです。半分、趣味みたいなものもあって、すごく楽しく作っていました」(同)。
こうして誕生したのが、「伝えるウェブ」だ。難しい漢字や専門用語を自動的に検出し、より簡単な言葉に言い換える。ふりがなも自動で振られ、文章構造もシンプルにする。
しかし、開発は簡単ではなかった。言葉の「言い換え」は、単なる辞書的な置き換えではない。文脈を理解し、意味を損なわずに、より伝わる表現を選ぶ必要がある。
「最初は辞書ベースで作りましたが、すぐに限界が見えました。文脈によって、同じ言葉でも言い換え方が変わるからです。そこで、ルールエンジンを改良し、少しずつ精度を上げていきました」(野田さん)
■M&Aで朝日新聞グループに参画
2003年から20年間、野田さんはアルファサードの経営者として走り続けてきた。しかし、年齢を重ねるにつれ、「後継者」の問題が頭をよぎるようになった。
「来年、60歳になります。まだまだ働けますが、やはり一つの区切りとして、次の仕事に取り組みたいという思いがありました」(野田さん)
いくつかの企業が興味を示してくれたが、野田さんが選んだのは朝日新聞グループだった。2024年1月に朝日新聞グループ入りし、再編も経て、現在は朝日新聞社の100%子会社となっている。野田さん自身はアルファサードの取締役として開発の仕事を続けながら、朝日新聞社の技術戦略を司るCTO室の技術顧問も兼任するという形だ。
「普通、M&Aでオーナー社長が会社を売ると、『引き続き数年は会社の仕事をしてくれ』と言われます。でも私は、それだけじゃなくて、朝日新聞の仕事もさせてほしいと条件を出しました」(野田さん)
朝日新聞に決めた理由は、「メディアのアクセシビリティに、ずっと課題を感じていたから」(同)だった。
■メディアが抱えるアクセシビリティの課題
野田さんは、新聞やメディア全般のアクセシビリティについて、かねてから問題意識を持っていた。
「紙の新聞は減っていて、どのメディアもデジタルに力を入れなければいけない。それは外から見ていても明らかでした。でも、デジタルのアクセシビリティへの取り組みは、まだまだ不十分だと感じていました」(野田さん)
例えば、視覚障害者にとって、多くのニュースサイトは使いづらい。広告が突然表示されたり、画像に代替テキストがなかったり、スクリーンリーダーでの読み上げに対応していなかったりする。
「聴覚障害者も同じです。動画に字幕がなければ、何も伝わりません。メディアは『誰にでも伝える』ことが使命のはずなのに、実際には多くの人が置き去りにされています」(同)
野田さんは、この状況を変えたかった。そのためには、単にツールを提供するだけでは足りない。メディアの内側に入り、組織全体のアクセシビリティ意識を変える必要がある。
「朝日新聞なら、それができるのではないかと思いました。影響力のあるメディアがアクセシビリティに本気で取り組めば、他のメディアにも波及するはずです」(野田さん)
■ウェブの「小さなボタン」に込められた一歩
朝日新聞グループのウェブサイトに「伝えるウェブ」のボタンが実装されたのは、野田さんが参画してすぐのタイミングだった。
「会社案内や採用サイトなど、朝日新聞グループの複数のサイトに実装されました。ページ上部に言い換えボタンとひらがなをつけるボタンがあります」(野田さん)
この小さなボタンは、クリックするとふりがなが振られたり、やさしい日本語に変換されたりする。朝日新聞がアクセシビリティに本格的に取り組む象徴的な第一歩となった。
導入後、少しずつ反響が広がっている。読者からは、「記事が読みやすくなった」「ふりがながあると助かる」といった声が届いた。
しかし、野田さんは「営利企業」として、バランスも意識している。「企業なので、ビジネスとしてちゃんと回していかないといけません。でも同時に、社会的な意義も追求したい」(野田さん)。
そこで、アルファサードは毎年、無料で「伝えるウェブ」を試用できる期間を設けている。地方自治体や非営利団体は、予算化が難しい場合も多いため、約10か月間、無料で使えるようにしているのだ。
「6月から翌年3月まで、お試しで使っていただいて、翌年度の予算に組み込んでもらえたら嬉しい。もし予算化できなくても、必要な人に届けることが大事だと思っています」(野田さん)
また、災害時には無料で提供する方針も打ち出している。
「災害時は、誰もが情報を必要としています。そんなときに、言葉の壁で情報が届かないのは許されない。だから、大きな災害が起きたら無料で使えるようにしています」(同)
■当事者と一緒に声を上げる
朝日新聞社内では、9月12日のデジタル版に芥川賞作家の市川沙央さんの寄稿『奪われた「共生の」言葉 障害者なき対話に』が掲載されたことも、アクセシビリティや当事者参画について、社内で立ち止まって考えるきっかけとなっていた。
障害当事者の視点から、メディアが「共生」や「対話」を語る際に見落としがちな視点を可視化した内容だ。
「市川さんの寄稿を受けて、その直後に、社内で勉強会を開くことになりました。第一回は外部の方を招いて、第二回は私と、社員で聴覚障害者の野口哲平さん(デザイン部)、それから視覚障害者の大島康宏さん(朝デジ事業センター)という3人で」(野田さん)
朝日新聞社内で開催されたこの勉強会には、約150人が参加した。会議室とオンラインを併用し、録画も後で見られるようにした。野田さんは、アクセシビリティの技術的な側面を解説し、野口さんと大島さんは、当事者としての「困りごと」を率直に語った。
「私が言ってもダメなんですよ。やっぱり、当事者の声が一番響くのです」(野田さん)
野口さんは聴覚障害者として、大島さんは視覚障害者として、それぞれ日常の中で感じる「情報のバリア」を共有した。
「会社の中に当事者がいるという気づき。それが、一番大きな変化を生むんだと思います」(同)
この勉強会をきっかけに、社内の意識は少しずつ変わり始めたと感じている。問題を知ると、自ら学び始める人が増えた。「アクセシビリティって、何から取り組めばいいかわからないという声もあります。そういうところに対して、私たちアルファサードのメンバーも一緒に解決していきたいと思っています」(野田さん)
■選挙公報を「そっと閉じる」当事者
野田さんの活動は、社内にとどまらない。2025年、彼は選挙公報のアクセシビリティ問題に取り組んだ。
選挙の際、各候補者が発行する「選挙公報」は、多くがPDF形式で公開される。しかし、その多くがスクリーンリーダー(音声読み上げソフト)に対応していなかった。
「視覚障害者の方は、選挙公報を読むことができなかったのです。これは明らかに、情報保障の問題です」(野田さん)
野田さんは調査結果をまとめ、NHKの取材を受けた。「ニュースウォッチ9」という番組で紹介され、大きな反響を呼んだ。総務省や選挙管理委員会にもさまざまなルートを使って問い合わせや働きかけを行った。ところが、反応の多くは次のようなものだった。
「立候補者が提出したものをそのまま載せることしかできないので…」
野田さんは、反論した。「でも、視覚障害者の方が合理的配慮を求めて『読めないぞ』と言ったら、対応しないといけないはずですよね?」。
しかし、問題はそこにあった。野田さんが知り合いの視覚障害者に聞くと、こう答えが返ってきた。
「読み上げできなかったら、もうそっと閉じます」
声を上げない。諦めてしまう。それが、多くの当事者の現実だった。
「だから、私たちは一緒に声を上げないといけないんです。専門家や大学の先生が言うのも大事ですが、やっぱり当事者の人と一緒に問題提起していかないと、変わらないと思います」(野田さん)
この経験は、野田さんにとって大きな教訓となった。技術を提供するだけでは足りない。当事者と共に、社会に働きかける必要がある。
■アクセシビリティに取り組む団体を基金で支える
野田さんは、朝日新聞やアルファサードの仕事とは別に、個人としての活動も始めている。「情報アクセシビリティ推進基金」だ。
これは、野田さんが個人で立ち上げた支援の仕組みで、アクセシビリティに取り組む団体やプロジェクトに資金を提供する。
「朝日新聞やアルファサードとは関係なく、私が個人的にやっている活動です。今のところ、応募がまだあまり来ていないんですが、もっと広く知っていただいて、活用してもらえたらと思っています」(野田さん)
野田さんは、この基金を継続的に運営したいと考えている。
「今年うまく活用してもらえたら、また来年も続けていきたい。アクセシビリティを『当たり前』にするために、個人でもできることをやっていきたいんです」(同)
■音声で届けるアルキキとポッドキャスト
朝日新聞の取り組みは、「見える情報」「読める情報」だけにとどまらない。視覚障害者や、文字を読むことが難しい人のために、「聴く」という選択肢も重視している。
その代表例が、音声ニュースサービス「朝日新聞アルキキ」だ。人工合成音声によるニュースサービスで、2016年4月にiOS/Androidアプリとして事業を開始した。その後、2020年度に開始した「朝日新聞ポッドキャスト(朝ポキ)」内の一番組として移管し、現在はニュースのサマリーを深夜以外は1〜2時間おきに配信している。
ビジネスパーソンらをターゲットに、移動中や自宅での家事の隙間時間に「ながら聴き」してもらい、朝日新聞ニュース接触の習慣化や記事詳細を読むきっかけづくり、広告によるマネタイズなどを狙いとして始まった。
■音声ニュースが新たな読者層との接点に

導入後、利用者からは様々な反響が寄せられている。特に印象的なのは、高齢者の家族からの声だ。
「ご高齢の方のご家族の方から、活字が読みにくくなってきたが記事には興味があり、ポッドキャストの聞き方を教えたら喜んでいた、という声はいくつもいただいています。スマートスピーカーを使うケースも多いようです」。コンテンツ編成本部ディレクターの神田大介さんが語る。
音声ニュースは、視覚に頼らずに情報を得られる手段として、確実に必要とされている。
興味深いのは、このサービスが新しい読者の開拓につながっていることだ。
「朝ポキの特徴は、政治からスポーツまでテーマは多岐にわたる反面、どの番組もほぼ同じくらいの再生回数があるということです。リスナーにとって興味のない話題の接点として活用されているのを感じます」(神田さん)
リスナー層を見ると、その若さに驚かされる。20代以下が46%、30代以下で3分の2を占めるという。新聞の読者は高齢者に偏っているが、音声ニュースは明らかに新しい読者層への接点になっている。若いリスナーが多いユーザー特性が幸いし、学生や若手ビジネスパーソンを意識した商材の広告のお問い合わせや出稿も増加傾向にあるようだ。
では、今後の展開はどうなるのか。神田さんからは意外な答えが返ってきた。
「将来的には、むしろ機能を制限したいと考えています。シンプルに聴くことに特化させたいんです」
機能を増やすのではなく、削ぎ落とす。「聴く」という体験を、より純粋に届けたいという思いが込められている。
伝えるウェブによる「読む」アクセシビリティ、アルキキによる「聴く」アクセシビリティ──。朝日新聞では、こうした多様な取り組みが同時並行で進んでいる。野田さんが技術顧問として参画してから約1年半。これらの取り組みは、組織全体にどのような変化をもたらしているのだろうか。
■社員の意識が変わりつつある
朝日新聞の社員たちの意識は、実際に変わったのだろうか。野田さんは、確信を持って答える。
「変わってきていますね。やっぱり、市川さんの寄稿がきっかけで、今まで考えていなかった人が勉強し始めたんです。問題を知ると、すごく真剣に取り組むんですよ」(野田さん)
しかし、同時に、「どこから取り組めばいいかわからない」という声も多い。
「そういうところに対して、私たちも一緒に解決策を考えていきたいと思っています」(同)
野田さんは、技術顧問として社内のさまざまな部署から相談を受けるようになった。たとえば、朝日新聞の記事データベースのサービスを利用している海外の大学からは、アクセシビリティ対応を求められたという。
「アメリカでは、公的機関がアクセシビリティに対応していないものを購入してはいけないという法律(リハビリテーション法508条)があるんです。そういう話が来ると、私のところに相談が回ってくるようになりました」(野田さん)
これは、野田さんが朝日新聞に参画したときに予想していた未来だった。
「私自身は、まったく驚いていません。想像通りです。アクセシビリティが『求められる』時代が、確実に来ていると感じています」(同)
■読者の声が組織を動かす
野田さんは、読者からのフィードバックの重要性について、こう語った。
「意見をいただくと現場は動きやすいので、マイナスの話もポジティブな反応も、ぜひフィードバックをお願いしたいと思っています」(野田さん)
実際、カスタマーサポートに寄せられた障害者からの意見(リニューアルで使いにくくなったなど)を社内の勉強会で共有したり、SNSで寄せられた「やさしい朝日新聞」への意見や反応などには目を通したりしており、改善できる部分は改善しているという。
「『これいいじゃないか』という声があると、みんなそっちに気が向くんですよ。たとえば、『やさしい朝日新聞』を読んで『読みやすかった』と感じたら、その声を届けてほしい。『地球会議の字幕があってよかった』といった反応も、組織を動かす力になります」(同)
「良いことも悪いことも、どんどん反応をいただけると、組織を動かしていけるんです。だから、批判も応援も、よろしくお願いします」(同)
野田さんの言葉には、メディアの内側から変化を起こそうとする覚悟と、同時に、外部の声を必要としている謙虚さがあった。
■アクセシビリティで「生き残る」
野田さんの最終的な目標は、明確だ。
「アクセシビリティを頑張ったから、朝日新聞が成長して、生き残って、社会から必要とされる存在になった──そんな事例を作りたいんです」(野田さん)
新聞は、「オールドメディア」と呼ばれることもある。SNSと比較され、時代遅れだ、と。
「でも、私は信じています。アクセシビリティにしっかり取り組むことで、メディアはちゃんと成長できる。社会から必要とされて、存在意義があるから生き残れる。事業が継続していける──そういう状態を作りたいんです」(同)
アルファサードは、「お客さんと一緒に走る」企業だ。朝日新聞だけでなく、他の企業とも協力しながら、アクセシビリティを「当たり前」にしていきたい。
「60歳を前に、新しいチャレンジを始めました。でも、私一人では何もできません。当事者の人たちと一緒に、メディアの人たちと一緒に、そして読者の皆さんと一緒に、変えていきたいんです」(野田さん)
野田さんの目には、確かな未来が見えている。それは、「誰にも届く情報」が当たり前になる社会。言葉の壁も、技術の壁も、すべてを超えて、ニュースが届く世界だ。
「伝えるとは、相手の世界に近づくこと。デザイナーの野口さんも同じことを言っていました。私たちは、技術とデザインと当事者の声を組み合わせて、その未来を実現したいと思っています」(同)
次回の後編では、朝日新聞の障害者を包摂(インクルージョン)するための行動計画である「The Valuable 500」へのコミットメント、ユニバーサルデザイン・情報保障への全社的な取り組みについて掘り下げる。デフリンピックへの協賛、社内制度の変化、そして業界全体への波及──一企業の挑戦が、社会をどう変えていくのかを追う。