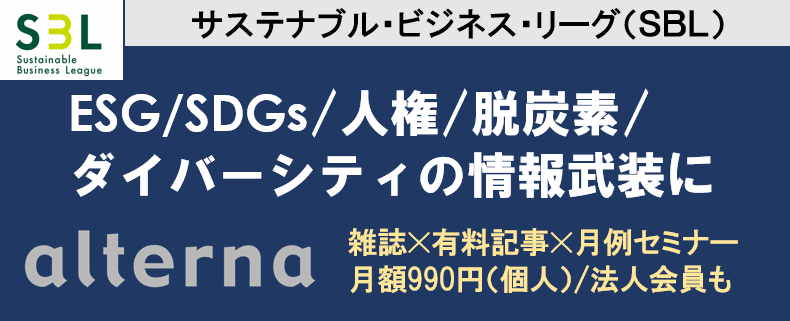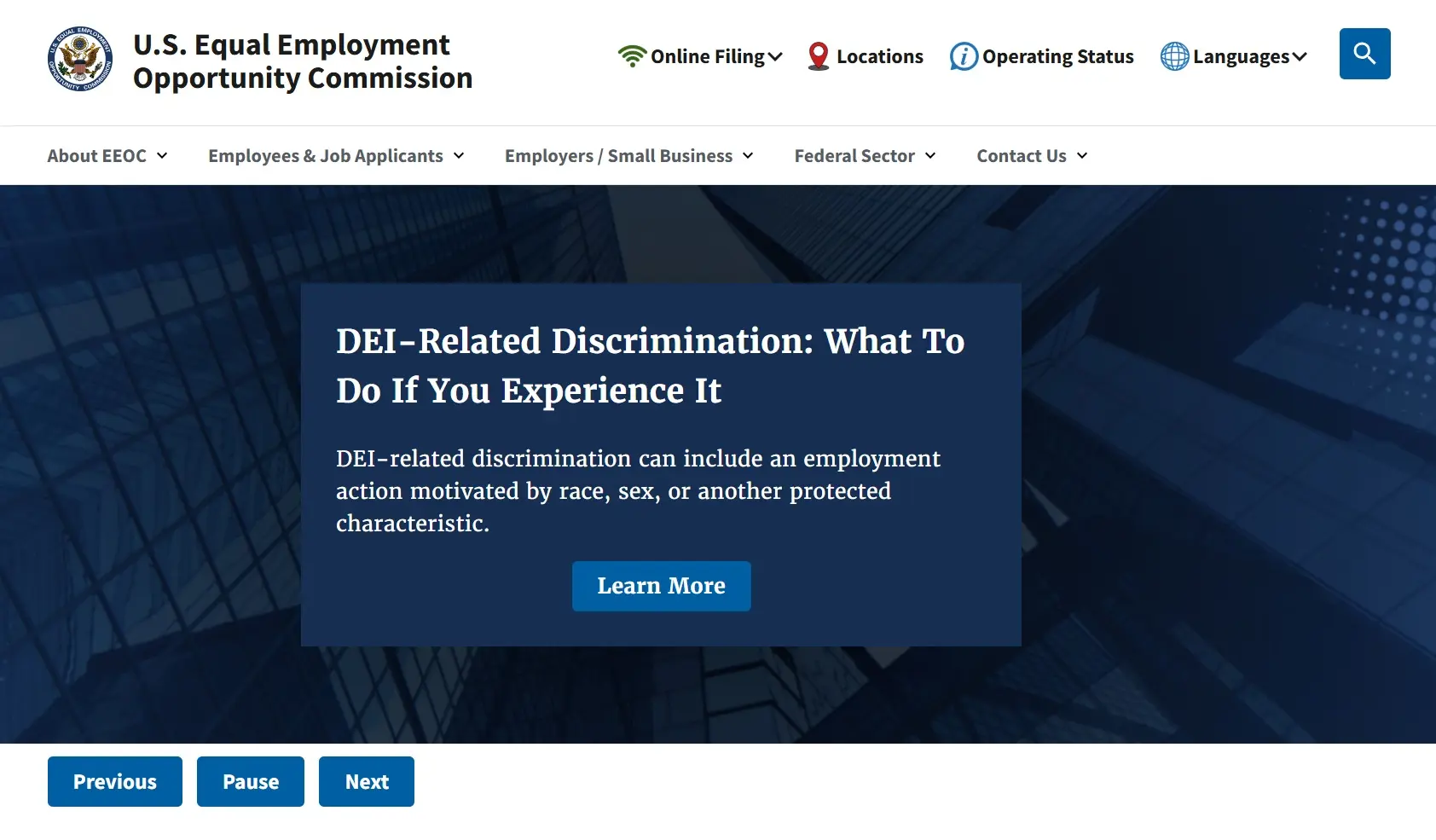記事のポイント
- 朝日新聞のアクセシビリティは「特別な配慮」から「当たり前の視点」へと変化した
- 社員の意識に変化が生まれ、外部からの要請にも応えられる体制が整いつつある
- 成果と同時に、未達成の課題や今後に向けた挑戦も明確になっている
現場でのアクセシビリティ改善の取り組みを積み重ねた結果、朝日新聞社(東京・中央)という組織には、どのような変化が生まれたのか。社員の意識、業務フロー、そしてメディアとしての責任の捉え方──。V500コミットメントは、確実に社内の風景を変えつつある。ここでは、3つのコミットメントがもたらした成果を振り返るとともに、なお残されている課題を見ていく。(聞き手=NPO法人インフォメーションギャップバスター理事長・伊藤芳浩)
■現場から見える組織の変化とは
V500コミットメントに関する取り組みは、理念や制度にとどまらず、日々の職場のあり方にも影響を及ぼし始めている。
では、実際に障がいのある社員と働く現場では、どのような変化が生まれているのだろうか。デザイン部の同僚や上司は、聴覚障がい者の野口哲平さんと一緒に働く中で多くのことを学んだという。
同僚は語る。「野口さんは、職場の雰囲気を明るくすることを心がけています。人と話すことが好きで、積極的に会話に入ってきてくれる。障がいのことをあまり気に留めたことはありません。それほど意思疎通ができているんです」。
コミュニケーションの方法については、本人の希望を確認しながら工夫している。「口話や視覚的・文字情報の併用など、本人の希望する方法を確認しながら進めています。手順が多い場合は、番号つきで箇条書きにして文書化する。チャットで共有する。視覚的に確認できる形での情報提供を心がけています」(同僚)という。
評価についても、公平性を重視した対応がなされている。上司の倉重奈苗さんは、「健常者と同様に、仕事の機会を与え、障がいの有無にかかわらず評価しています。障がいがあることを理由に、不利益となる評価基準は設けていません。その分、評価が厳しめになることもありますが、公平性という観点を大切にしています」と語る。
こうした取り組みが実現できた背景には、過去の経験の積み重ねがある。倉重さんは、「前任の聴覚障がいのあるデザイナーが、大変優秀な方でした。彼女の築き上げた信頼から、その後につながりました」と明かす。
これらの声からわかるのは、「特別扱いせず、でも必要な配慮をする」というバランスだ。
■V500への参画が社員の意識を変えた
では、V500への参画と3つのコミットメントの実践は、朝日新聞社という組織にどのような変化をもたらしたのだろうか。ここまで見てきた様々な取り組みを通じて、どのような成果が生まれているのか。
最も大きな変化は、社員の意識の変革だ。野口さんや視覚障がいがある大島康宏さん(朝デジ事業センター)といった当事者の存在、野田さんのような技術顧問の参画、そして勉強会や日々の業務を通じて、アクセシビリティは「特別な取り組み」から「当たり前の配慮」へと変わりつつある。
野田さんは語る。
「変わってきていますね。やっぱり、芥川賞作家の市川沙央さんの記事がきっかけで、今まで考えていなかった人が勉強し始めたんです」
意識の変化は、業務フローの改善にもつながっている。技術顧問として社内のさまざまな部署から相談を受ける野田さんのもとには、具体的な課題が持ち込まれるようになった。たとえば、海外の大学が朝日新聞の過去記事データベースを使いたいという要望があった際、アクセシビリティ対応を求められたという。
「アメリカでは、公的機関がアクセシビリティに対応していないものを購入してはいけないという法律(リハビリテーション法508条)があるんです。そういう話が来ると、私のところに相談が回ってくるようになりました」(野田さん)
これは、野田さんが朝日新聞社に参画したときに予想していた未来だった。
「私自身は、まったく驚いていません。想像通りです。アクセシビリティが『求められる』時代が、確実に来ていると感じています」(同)
朝日新聞社は、自社の変化だけでなく、業界全体への波及も視野に入れている。V500への参画は、朝日新聞社だけの変化にとどまらない。業界全体への波及を意識した取り組みでもある。
ウェブ全体では、ボタンのデザインなどユーザーインターフェースの基本要素が徐々に共通化されてきており、朝日新聞社もそうした業界の流れを取り込みながら対応を進めている。こうした業界全体のスタンダードに沿うことは、ユーザーの混乱を減らし、アクセシビリティの底上げにつながる。
つまり、朝日新聞社だけが「特殊な」アクセシビリティ対応をするのではなく、業界全体の標準を高めることを目指しているのだ。
この取り組みは、日本が直面する国際的な要請にも応えるものだ。野田さんが指摘したように、アメリカでは公的機関がアクセシビリティに対応していないものを購入してはいけないという法律がある。日本でも、遠くない未来にそうした要求が強まるだろう。V500への参画は、朝日新聞社がその先を見据えて動いている証だ。
■「一歩ずつ前に進んでいます」
業界に先駆けてアクセシビリティ向上を実現してきた朝日新聞社だが、現状に満足しているわけではない。V500のコミットメントを完全に実現するには、まだ課題は多いと朝日新聞自身も認めている
例えば、すべてのコンテンツに代替テキストをつけること、動画すべてに字幕をつけること、音声読み上げへの完全対応、手話通訳の費用負担など、実現できていないことは多い。今後の取り組みとしては、運用体制や制作フローの継続的な見直し、より多くの社員へのアクセシビリティ教育、読者との対話を深める仕組みづくり、他メディアとの連携・情報共有といった課題に取り組んでいく予定だ。
野田さんは率直に語る。
「完璧ではありません。でも、一歩ずつ前に進んでいます。読者の皆さんの声を聞きながら、改善を続けていきたいと思っています」
■朝日新聞の3つの物語と3つの視点
ここまで3回にわたって、朝日新聞社のアクセシビリティへの取り組みを追ってきた。そこには、3つの異なる視点からの物語があった。
野口さんは、デザインを通じて「見える伝え方」を追求した。野田さんは、技術を通じて「言葉のバリア」を壊した。そして朝日新聞社という組織は、制度と文化を通じて「誰も取り残さない報道」を目指した。
この三つの物語は、一つの場所で交わっている。それは、「伝える」という行為の本質だ。
野口さんは言った。「伝えるとは、相手の世界に近づくこと」
野田さんは言った。「当事者の人たちと一緒に、声を上げていかないと変わらない」
朝日新聞社はV500で宣言した。「誰もがお互いの人格を認めて支え合い、すべての人の個性や多様性を尊重できる社会を実現したい」
■当事者と実現するアクセシビリティ
この変革の物語は、まだ完結していない。そして、この物語の次の展開を作るのは、朝日新聞の読者である私たち一人ひとりだ。
最後に、野田さんの言葉をもう一度思い出したい。
「やっぱり、皆さんの声が力になるんです。良いことも悪いことも、どんどん反応をいただけると、組織を動かしていけるんです」(野田さん)
「やさしい朝日新聞」を読みやすいと感じたら、伝えてほしい。デフリンピックの報道が素晴らしいと思ったら、声を上げてほしい。逆に、まだ不十分だと感じたら、それも伝えてほしい。
メディアは、読者と共に作るものだ。アクセシビリティは、当事者と共に実現するものだ。
野口さん、野田さん、そして朝日新聞の取り組みは、まだ始まったばかり。2025年のデフリンピック、2026年のミラノ・コルティナ パラリンピック──これらの大きなイベントを通じて、日本のメディアは変わろうとしている。
そして、その変化を加速させるのは、読者である私たち一人ひとりの声だ。
【これまでの記事】
①朝日新聞デザイナー、聞こえないからこそ「見えるニュース」を
②朝日新聞は報道のアクセシビリティをどう改善したのか
③朝日新聞社、ウェブアクセシビリティを高める3つの取り組み
【参考情報】
●朝日新聞「やさしい朝日新聞」: https://easyjp.asahi.com/
●伝えるウェブ: https://tsutaeru.cloud/
●アルファサード(大阪市): https://alfasado.net/
●2025東京デフリンピック: https://tokyo2025deaflympics.jp/
●V500コミットメント(Valuable 500): https://www.thevaluable500.com/