菜園つき老人ホームや介護に園芸療法を用いるなど、高齢者に農ある暮らしを提供する動きが広まっている。お年寄りの生きがいを生みだしつつ都市部の農地を保全できる一挙両得の試みだ。
■農は高齢者に人気 介護予防にも
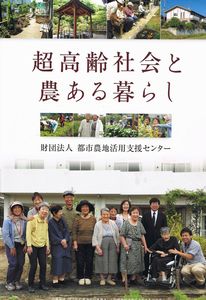
農に対する高齢者のニーズは高く、約 28%の高齢者が趣味に盆栽・園芸を挙げ(内閣府調べ)、三大都市圏のとある市民農園利用者の約70%は 60歳以上が占めるという。また、園芸や農作業は介護予防や治療効果もあるとされ、介護サービスとしても有望だ。
「ベルガーデン水曜クラブ」は、NPO日本園芸療法研修会と横浜市の地域ケアプラザが共同で行う介護予防・認知症予防の園芸療法プログラムだ。要支援の在宅高齢者の安心な外出先、交流の場として2005年に立ち上げられた。約300平方メートルの篤志家の庭を借り、四季を通じて花や野菜を栽培。園芸療法スタッフや地域ボランティアがつくる採れたて野菜の昼食を皆で囲むなど、多世代間の交流もある。
ケアマネージャーや家族とも連携をはかり、地域福祉に貢献。NPO代表の澤田みどり氏によると、園芸療法は、趣味やレクリエーションから治療やリハビリテーションまでさまざまな取り入れ方が可能だという。
■都市農地は市民に開放されるか
日本の農制度では、農家しか農地を利用できないのが原則だ。練馬区のように所有者から生産緑地を借りて区民に有料で貸す事例もあるが、都市農地の多くは所有者の高齢化や後継者不足、相続が原因で宅地化されるか、休耕地となる。レクリエーションとしての農地ニーズは高くても、一般市民に農地は供給されてこなかった。

しかし、超高齢化をきっかけに新しい農地利用法が生まれつつある。兵庫県伊丹市の介護付有料老人ホーム「ライフェール」は隣接する1千坪の生産緑地を入居者や周辺住民の農体験の場として活用している。有機農業を行い、今後は市内の市場への出荷も検討中だという。
京都府亀岡市の「青空ふれあい農園・ハーブ倶楽部」では、農園デイサービス事業、高齢者の働く場づくり「ハーブ栽培・加工・販売」事業を展開。東京都国立市には、社会福祉協議会による青空デイサービス「やすらぎ農園」がある。
財団法人都市農地活用支援センターは、そうした各地の先進的とりくみをまとめた「超高齢社会と農ある暮らし」を編纂した。収録事例をみると、個人やNPO、URなど事業主体も仕組みも多様でユニークだ。
生産からレジャーや介護サービスまで「農」の可能性が広がる一方で、農地の所有と活用に関する仕組みはまだ発達段階といえよう。市民の手で農地を保全しながら共用できるような制度改革が待たれる。(オルタナ編集部=有岡三恵)2011年2月23日






























.jpg)



