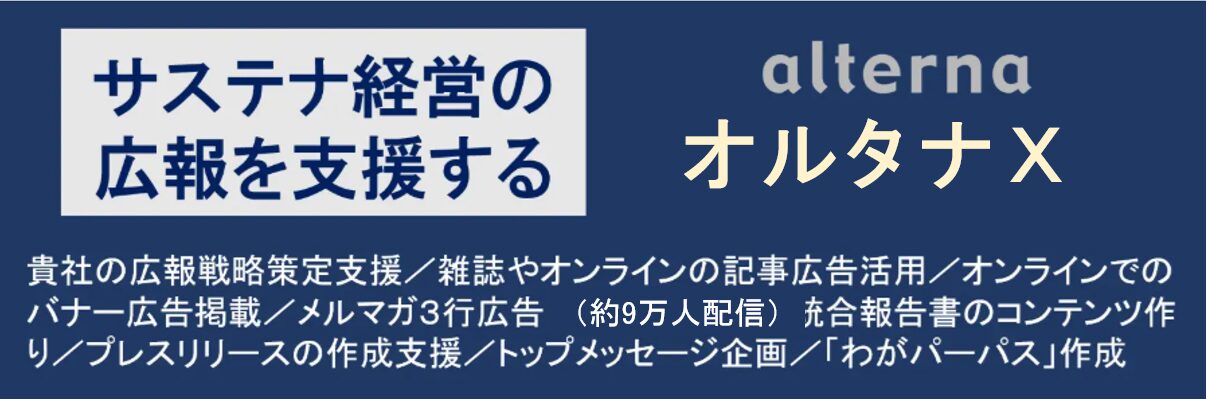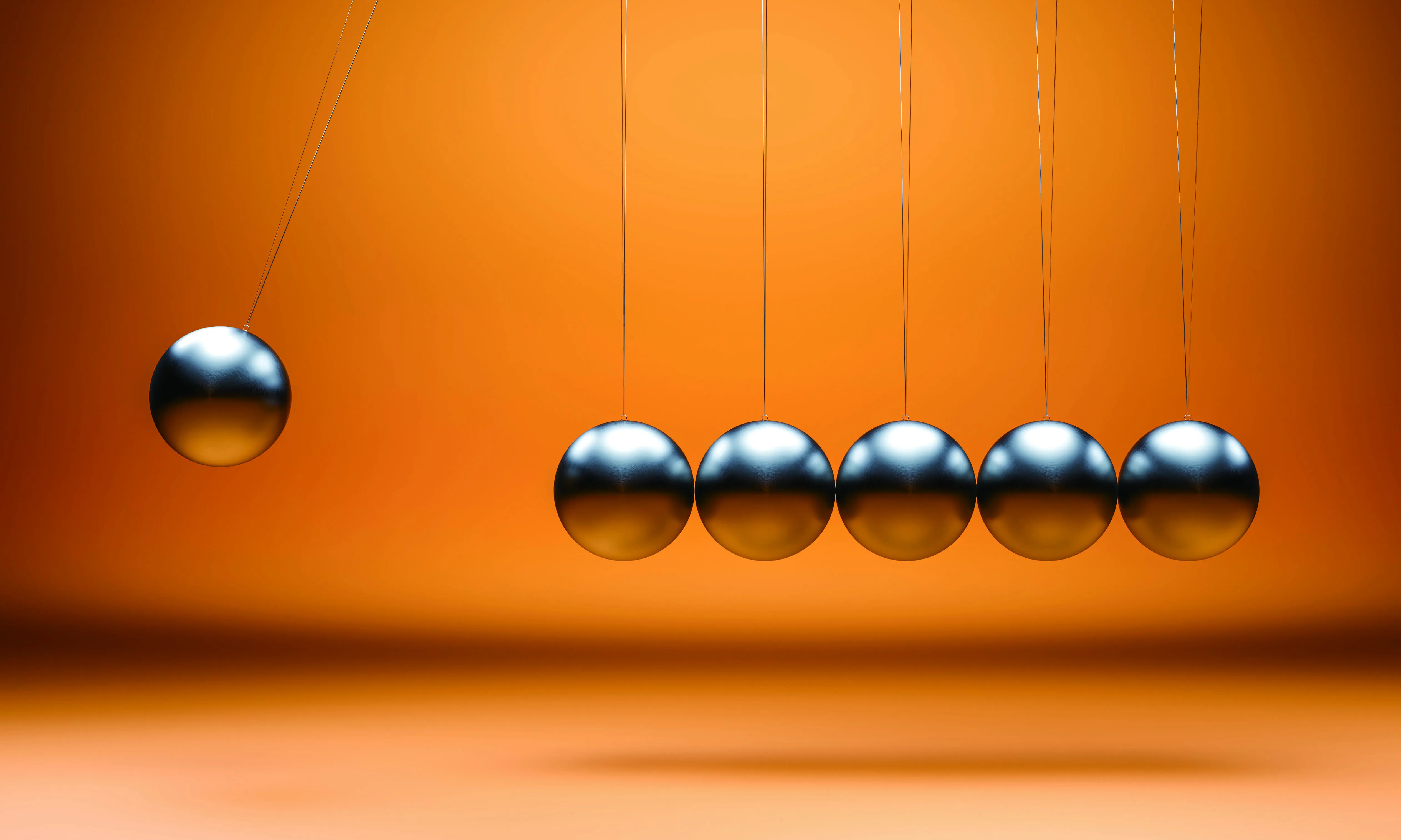「ショート・ショート」(掌小説)こころざしの譜(10)
大学受験に失敗したあの日からだった、明澄が部屋から出なくなり灰色の世界に籠ったのは。太陽が昇るちょっと前、家から抜け出す。近くのパン屋が焼けたばかりの温かいコッペパンを売り始めるからだ。若い店員が手慣れた感じでコッペパンにジャムとバターをさっと塗ってくれる。ある時、その男の左手の指が4本欠けているのに気づいた。ジャムの赤が浮き出て見えた。
部屋に戻りパンを食べると急に眠くなる。起きるのは昼過ぎ。後は朝まで机に向かう。受験勉強を続けるふりをしていたが、気ままに好きな本を読んでいた。
1年たった年末のことだった。早朝の東京は前の晩に降った雪がまだ残っていた。見落とすところだったが、道路の片隅に白い子犬がうずくまっている。抱き上げると右の前足がつぶれていた。部屋でジャムバタを食べさせていると、母がドアを開けて「どうして犬なんか連れてきたの」。
県の保健所の窓口の女性は子犬を抱き寄せた。「捨て犬かしら。きっとそうよね」。整形独特の歪んだ表情で犬の耳を撫でている。母にせかされたとはいえ、ここまで足を運ぶのには勇気が要った。なにしろ明澄は正真正銘の引きこもりなのだ。保健所に近づくと子犬は急に震えだした。二酸化炭素で殺処分される犬猫が全国で16万頭もいるらしい。こんな子犬まで殺されてしまうのだろうか。クーン、クーンと鳴き声をあげながら身体を押しつけてくる犬に何か熱いものを感じた。新しい飼い主を見つけてもらうんだよ、そう言い置いて保健所から一目散に逃げ帰った。
3日たって、子犬に会いに行った。自分が捨てられたような気がして、夜もよく眠れなかったからだ。「あのワンちゃんもう、いないわよ。別の飼い主に引き取られたから」。保健所の整形おねえさんは書類から目をあげずに言った。よほど明澄がしょげてみえたのか、おねえさんは、外へ飛び出した明澄を追いかけてきた。
「本当は教えてはいけない決まりなんですけどね、あの子犬、市役所の横にできた学校にもらわれていったの。会いに行ったら」
「学校?」
「そう、耳の聞こえない人を助ける聴導犬を養成する学校」
「あした葉学校」という新しい看板が見えた。ジャージ姿とぼさぼさの髪が気になったが、ドアを押す。
「いらっしゃいませ。寄宿希望の方ですか」
明澄はひるんだが、「あの、子犬のことで来たんですけど」と思い切って切り出した。
あら、そうなの。ごめんなさいね、と親切そうな女性は少し照れくさそうに、子犬を連れてきてくれた。子犬はぐったりとして元気がなかった。
「そうなのよ。他の犬といっしょにガス室にいれられそうになっていたの。いよいよ、自分の番と言う直前にたまたま私たちが訪問して助かったの。聴導犬用に5頭ばかり、もらいに行ったの。死の渕からはいあがったというわけね。修羅場を経験したせいで、トラウマっていうの? 心が傷ついちゃったみたいなの」
真澄が抱こうとすると、ウーと歯をむいてうなった。思わす手をひっこめた。
「ねっ、反抗的でしょ。幸福になってねという期待を込めて、フクという名前にしたんだけど」
フク、これ以上はない皮肉。そう思い、明澄は保健所に連れていったことを後悔した。
「あのう、さっき、寄宿とか言ってましたけど」。真澄は何気なく聞いてみた。保健所から譲渡してもらった犬は虐待された経験があったり、ペットショップの売れ残りだったりして、ケアが大変なのだという。そこで寄宿生といっしょの部屋で暮らしながら、心の健康を取り戻すのだという。
私には資格もないし・・・と言いかけた明澄に、その女性は、実は校長先生だと後で知るのだが、「資格なんて、何もいらないのよ。元気な体さえあれば」。先週の日曜、公園の壁を相手にキャッチボールを繰り返すジャムバタの店員を見かけた。右手でボールを投げると、左脇の下にはさんだグラブをさっと右手にはめ、それでボールをキャッチする。グラブを左脇の下にはさむと右手でボールを投げる。それを何度も繰り返していた。
自分にできるかどうか自信はなかったが、明澄はあした葉学校の寄宿舎に入ることになった。母はおろおろするばかりだった。不機嫌な父の「大学は諦めろ。明澄、お前はまず今の生活を変えることが必要だ」という一喝で、入寮を決意した。
犬との共同生活は大変だった。朝のフクの散歩から始まり、部屋の掃除、洗濯、食事やトイレの世話、訓練、スケジュールは一杯だ。寄宿している若者が十人ほどいるが、引きこもりや知的障害などいろんな問題を抱えていた。明澄は睡眠障害に悩まされていたが、それもなくなり、心身の健康を徐徐に取り戻していった。不思議なもので、初めは部屋の隅に縮こまっていたフクも明澄になつき元気にグランドを走り回るようになった。
問題は聴導犬になるための訓練だった。教えなくてはならないのは、訪問客があった時に、それを知らせる方法である。玄関のドアフォンがなる。耳の不自由な人は聞こえないので、フクが、部屋の中で座っている障害者に近づき、前足でタッチする。すると障害者が右手人差し指を横にふって、「なあに?」と聞く動作をする。そこでフクが、障害者をドアまで案内するというのが一連の動きだ。これがなかなか難しい。
「駄目だよ、それじゃあ、フク」
「明澄さん、もう一回やってみようか」
プロの訓練士の指導を受けながら、訓練を進める。
「フク、何回言ったらわかるの。もういやになっちゃう」
障害者役の明澄は来る日も来る日も、タッチと人差し指の横振りである。何日、訓練しただろうか。成果はなかなか現れなかった。悔しくて大泣きした時、フクが前足で慰めてくれた。心が通ったような気がした。次の日、突然、フクが、ドアフォンのあったことを前足で教えてくれた。明澄はうれしさのあまり、フクを抱きしめた。フクも飛び跳ねて喜んでいる。うれしかった。ようやく、フクも聴導犬になれそうだ。
それから間もなくしてフクが旅立つ日がやってきた。聴導犬として障害者にもらわれていくのだ。セレモニーでフクはいくらか誇らしそうだった。
別れるのはつらかった。あの愚図だった子犬がここまで成長したかと思うと、明澄も感無量だった。贈る言葉を催促された明澄は「フクの成長はうれしい。実は私もペットシッターになる決意をした。フクに負けないように頑張ります」と挨拶した。
その時、校長が後ろを指さした。意外な姿がそこにあった。父と母だった。目にいっぱい涙をため笑っている。明澄はやっとわかった。この学校は犬の養成をうたっているが、実はもうひとつ、若者の自立促進を使命としていることを。そう、誰もがあしたという未来にかける夢を持っているのだから。
(完)