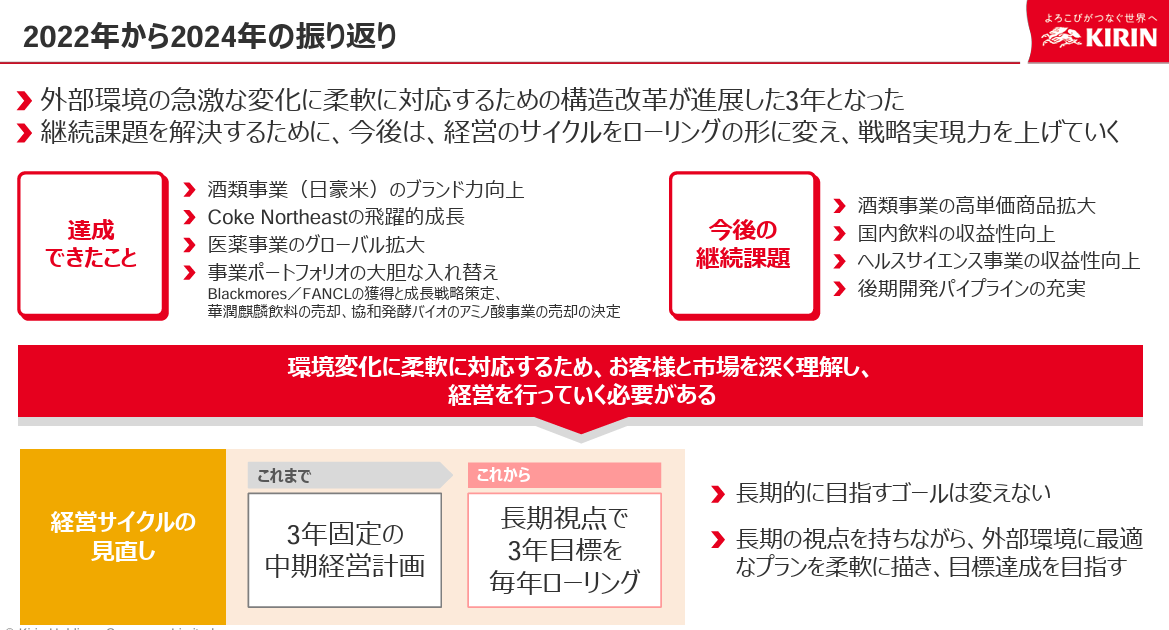■「無私」の自分に気付く
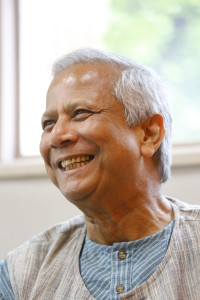
――社会的インパクトを高めるために、どのように人を巻き込んでいけば良いでしょうか。
人には「セルフィッシュネス(私)」の部分と「セルフレスネス(無私)」の部分があります。
椅子でたとえてみましょう。会社の椅子に座っていると、自動的に会社の利益を考えてしまいます。利益を上げることばかりを考えるのに良い環境なのです。それ以外に意識がいきません。
家に帰り、家族と話をするとどうでしょう。そこでは会社の利益ではなく、貧困問題、戦争、誰もが考える社会問題について考えられるようになります。
では、ソーシャル・ビジネスの椅子はどうでしょう。会社の椅子では生かせなかった「無私」の部分を生かせます。
人を巻き込むとは、そういう椅子に座らせること。リラックスしてもらい、「無私」の自分に気付いてもらうのです。
誰しも、一人の自分のなかに、良い部分と悪い部分があります。そのどちらを生かすかは自分次第なのです。
良い部分を使えば、人を助けたり、社会をより良く変えたりすることもできる。悪い部分を使うと軍隊に入って戦争をして人を殺してしまったりする。どちらを使うか。責任をどこに置くかによって、その人がどうあるかが変わってくるのです。
ソーシャル・ビジネスは自己の良い部分を生かすよう力付けるものなのです。
――一般的にいわれるソーシャル・ビジネスとユヌス・ソーシャル・ビジネスの違いは何でしょうか。
私たちは「ソーシャル」という言葉をあらゆる意味合いで使っています。
世の中には社会的企業、社会的起業家などがあり、ソーシャル・ビジネスもそれらの一部だと混同しがちです。
そこで、明確にするために「ユヌス・ソーシャル・ビジネス」という言葉を使っています。「ソーシャル」の概念がはっきりしていれば「ユヌス」の部分を省いてもいいのです。
日本では「ソーシャル・ビジネス」というと、寄付やボランティアなど社会活動に関連する全てのことを意味します。しかし、私の意味するソーシャル・ビジネスではありません。
7原則に基づく「ビジネスの仕組み」で社会的課題を解決していくこと、そしてパートナーシップを組むことなのです。
<ソーシャル・ビジネスの7原則>
1.人々や社会を脅かす 貧困、教育、健康、技術、環境といった何らかの社会問題を解決する
2.財務的、経済的に自立し、持続する
3.投資家は、投資額以上の利益を得ることはできない
4.当該会社の利益は、グラミン・ソーシャル・ビジネスの普及とより良い実施のために使われる
5.環境に配慮する
6.社員に対し、良い労働条件ておよび給料を提供する
7.楽しみながら
◆ムハマド・ユヌス(グラミン銀行創設者)
1940年、バングラデシュ チッタゴン生まれ。チッタゴン・カレッジで講師を務めたのち、大学で経済学博士号を取得。1972年にバングラデシュに帰国後、1974年の大飢饉による貧しい人々の窮状を目の当たりにして以来、同国の貧困撲滅のための活動を開始。1983年に無担保小口融資(マイクロクレジット)を行うグラミン銀行を創設した。2006年にグラミン銀行とともにノーベル平和賞を受賞。教育、医療、エネルギー、情報通信などの様々な社会課題を解決する50社以上のグラミン関連企業(グラミン・ファミリー)を経営。
◆福井崇人(ソーシャルデザイナー)
カンヌ、ニューヨークADC、ADC賞など、国内外の広告賞の受賞歴多数。数多くのソーシャルアクトを起こす。2003年、環境省「環の国くらし会議」分科会メンバー。2005年、NPO2025PROJECT発起。現在電通ソーシャル・デザイン・エンジンの代表であると同時に、プロボノで2025PROJECTを活動中。金沢美術工芸大学、熊本大学大学院、上智大学大学院、宮城大学の非常勤講師。書籍のプロデュースに、宮﨑あおい、将兄妹のチャリティーブック『たりないピース』、『Love,Peace & Greenたりないピース2』、川嶋あいのチャリティーブック『大丈夫だよ』、『エコトバ』、『この子を救えるのは、わたしかもしれない』、『ミスキャンパスpresents世界を変える仕事44』、『希望をつくる仕事ソーシャルデザイン』、藤岡みなみのチャリティーブック『シャプラニール流人生を変える働き方』ほか。
電通 ソーシャル・デザイン・エンジン 2025PROJECT
※この記事はオルタナ38号(2014年9月発売)「ソーシャルコミュニケーション最前線」から転載しました