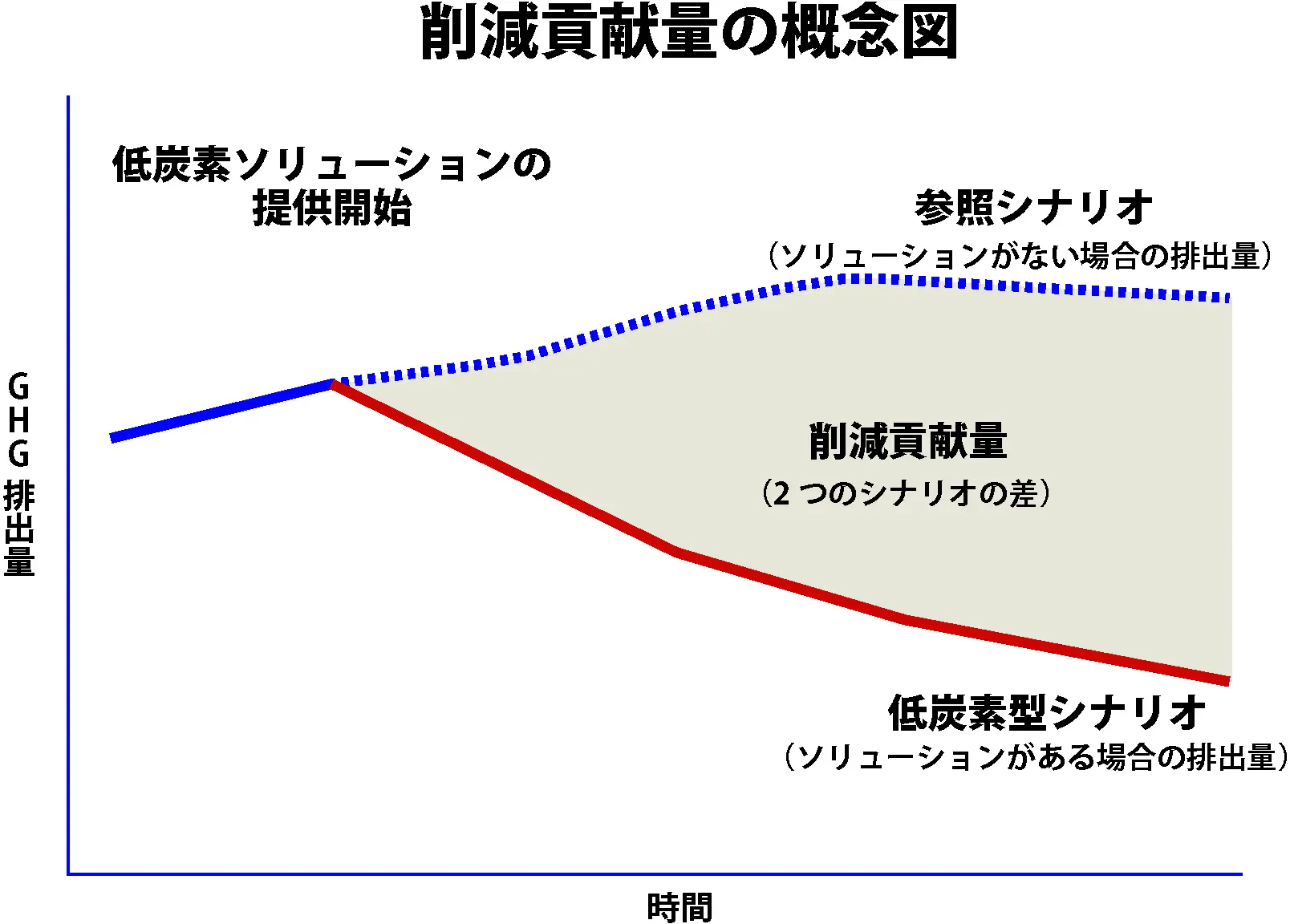記事のポイント
- ミャンマーの大地震発生から2ヵ月以上、これから本格的な支援が必要に
- 6月は雨季に入り、特に衛生面のサポートが求められる
- MFCGは、物資の支援や住民の移動手段となる船の修理に力を入れる
「ミャンマー ファミリー・クリニックと菜園の会(MFCG)」の代表理事の名知仁子(なち・さとこ)です。3月28日にミャンマー中部を震源とする大地震が発生してから、2ヵ月以上が経過しました。今も多くの人が路上での生活を余儀なくされ、約430万人が支援を必要としているとも伝えられています。6月は雨季に入り、特に衛生面のサポートが必要です。MFCGは物資の支援や、住民の移動手段となる船の修理に取り組みます。(ミャンマー在住医師・気功師・名知仁子)

■人々が最も望むのは家の再建
MFCGはミャンマーの人々自立(自律)を最終目的に、医療と農業の支援を続けてきました。この方針は今回の震災支援でも変わりませんが、まずは生命と健康を守る生活用品の提供が急務です。その第一歩として、北東部シャン州の3つの村に以下の物資を届けました。
・毛布 約500世帯分
・蚊帳 約500世帯分
・石けん 約500世帯分
・歯ブラシ 約2,500人分
・脱水予防用ORS(経口補水塩)粉末 約1,000個分
・マット 約200世帯分
(購入費合計 (約200万円)
次に、現地の人々が本当に必要としている支援は何か。アセスメントシートを使用し聞き取りを行いました。その結果、村によって多少の差はあるものの、3つの村で被災した全451世帯が住める家を建てることを希望していました。
外観からは大部分の家は大した被害を受けていないように見えますが、内部はとても住める状態ではありません。家の再建には1軒あたり360万チャット(約25万円)以上かかり、残念ながら全世帯のサポートは難しいと判断しました。
■住民の移動手段・船の修理が急務に
そこで3つのうち1つの村に焦点をあて、住民が病院に行ったり魚を採ったり、少しでも自活できるよう移動手段である船の修理を行う予定です。この船の修理に関して、内部のファイバーなど必要な物品のアセスメントが可能な方や会社、団体をご存じの方がおられればぜひ、ご連絡をいただければ大変嬉しいです。
一方で、MFCGの主要な活動地域である南部のミャウンミャについては、従来通り巡回診療などを続けています。
今回の被災地への物資支援には在ミャンマー日本国大使館の吉武将吾臨時代理大使をはじめ、皆さまに多大なるご協力を頂きました。大変感謝いたします。東日本大震災をはじめ多くの震災支援を経験した目で見ても、ミャンマーの震災は明らかに長期の支援が必須です。
引き続き、皆さまのお力添えをどうぞよろしくお願いいたします。
MFCGへの地震災害への義援金の受け付けはこちらから。