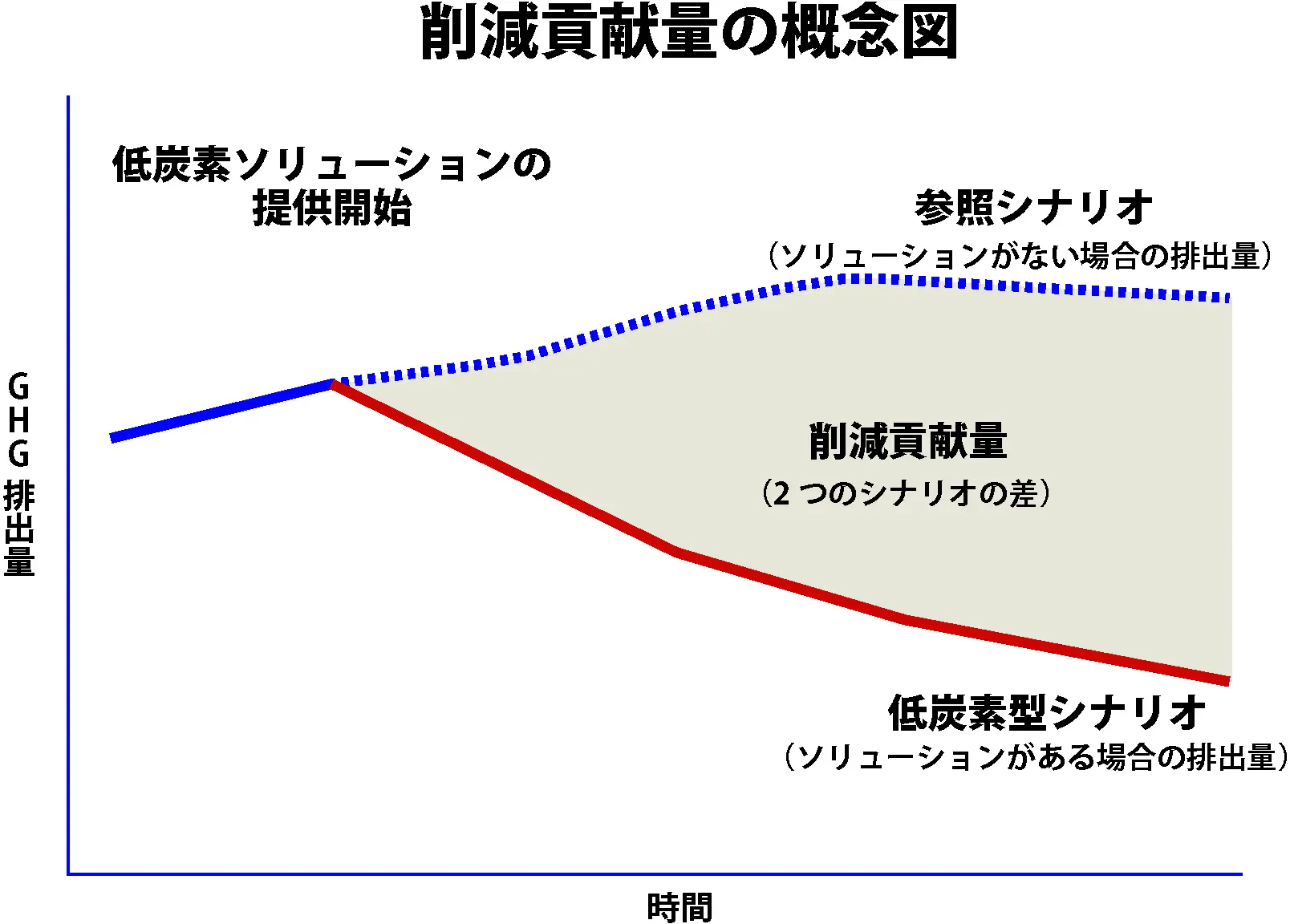記事のポイント
- 10年以上の長期視点で経営に取り組む企業の利益成長率は相対的に高い
- 日立と味の素は社会課題の解決を中核に据えた長期視点の価値創造経営へ
- サステナ経営は不確実性の時代を生き抜く最も実践的な経営のあり方だ
かつての企業経営では、「良いモノを安く、効率的に大量に売る」ことが成長の王道とされてきました。しかし、気候危機や社会の分断、地政学リスクの高まりといった不確実性に満ちた時代において、企業に求められているのは、単なる経済効率ではなく、社会課題の解決を経営の中核に据えた長期視点の価値創造経営、すなわちサステナビリティ経営です。その経営には段階的かつ構造的なアプローチが不可欠であり、本稿ではその実践に向けた8つの要件を提示します。(オルタナ編集委員/サステナビリティ経営研究家=遠藤 直見)
■短期目標に縛られない企業が利益を伸ばしている
7月6日付の日本経済新聞は、「10年先見据える企業ほど利益増 味の素は中期経営計画廃止」と題した記事を一面に掲載しました。
この記事では、中期経営計画(以下、中計)を導入する企業が増加する一方で、中計に縛られず、長期視点に立って経営に取り組む企業ほど、利益成長率が相対的に高いという調査結果が紹介されています。
あずさ監査法人が2024年、国内の主要上場企業404社の最高財務責任者(CFO)を対象に実施した調査によると、短中期(1~6年)スパンで経営を行う企業の直近年度の営業利益成長率(過去5年平均との比較)は18%にとどまりました。一方、10年以上の長期視点で経営する企業の成長率は52%に達しています。
この違いの背景には、既存の中計が持つ「計画ありき」の弊害があるとの指摘もあります。短期の目標達成に縛られるあまり、将来に向けて必要な先行投資を後回しにしてしまうのです。
これに対し、長期的な視点を持つ企業は、自社の価値観(パーパスや企業理念)に基づき、将来の社会像と自社のあるべき姿を見据えつつ、ビジネスモデルの変革、研究開発や人材育成、新規事業への投資などを積極的に進めています。こうした姿勢が、持続的な競争優位を確立し、市場からも高い評価を得ています。
■中計を改革し、長期視点の経営へ転換する味の素と日立
■社会課題を起点に、持続的な成長を生み出す経営へ
■サステナ経営の実践へ8つの構造的アプローチ
■統合報告書では「未来への意志」を伝えよう
■経営者こそが未来に責任を持つ存在に