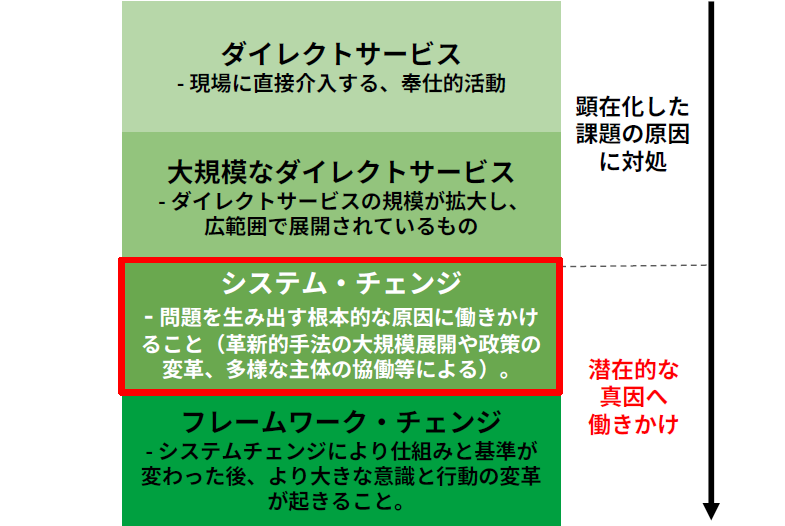記事のポイント
- IASBは気候変動の影響を財務諸表にどう反映させるか例を示した
- サステナ情報開示でも気候変動が財務に与える影響の開示が求められている
- 経営者はIASB設例をサステナ経営の基盤として活用することが重要に
国内でもサステナビリティ情報の有価証券報告書での段階的な開示義務化が始まり、企業は気候関連のリスクと機会が与える「現在および将来の財務的影響」の開示が求められます。そんな中、国際会計基準(IFRS)を開発する国際会計基準審議会(IASB)は7月下旬、気候変動の影響を財務諸表にどう反映させるかを例示した「設例」(イラストレイティブ・エクサンプルス)を公表しました。経営者は、IASB設例を単なる会計処理の手引きとみなすのではなく、サステナビリティ経営の基盤として活用することが重要です。(オルタナ編集委員/サステナビリティ経営研究家=遠藤 直見)
■排出量が多い資産に関する減損の判断根拠など示す
9月8日の日経新聞は「気候変動対策と財務の整合性を IASBが最も暑い夏に投じた一石」と題する記事を掲載しました。
記事では「気候変動対策の重要性が増しており、企業の財務諸表への適切な反映は不可欠」として、IASBが、気候変動対策の取組と財務報告をどのように整合させるべきかを示した「設例」を7月下旬に公表したことを伝えています。
この背景には、企業が投資家に示す気候変動対策の説明と実際の財務諸表との間に齟齬(そご)があるのではないかとの懸念があります。例えば温室効果ガス(GHG)の排出量が多い企業が、「高効率な設備に更新し、将来的に排出量をゼロにする」と有価証券報告書で説明したとします。
投資家は、サステナビリティの観点からはその方針を評価しつつも、財務の観点からは「既存設備に減損処理は必要ないのか」と疑問を抱きます。
IASBはこうした疑問に答えるため、設例を通じて「排出量が多い資産に関する減損の判断根拠」や「将来の排出枠価格の前提をどのように置くか」といった具体的な開示例を提示しました。これは企業に説明責任を促し、投資家との情報ギャップを埋める狙いがあります。
■「気候変動は非財務情報ではなく、財務情報である」
IASBは従来から、気候変動のような外部要因であっても、資産の減損、引当金、耐用年数、将来キャッシュフローなどに影響を与える場合には、既存のIFRSの適用範囲に含まれると説明してきました。
設例はこの考えを具体化したものであり、気候変動は非財務情報ではなく、企業の財務諸表や企業価値に直結する財務情報であることを明確に示しています。
今回公表された設例は「ほぼ確定版のスタッフ草案」であり、確定版は2025年10月に公表される予定です。設例に法的拘束力はありませんが、IFRSを適用する企業にとって、気候変動対策と財務を結びつける上での有力な実務上の手引きとなり得ます。
日本企業でも既に同様の取組が見られます。
- 三菱商事:気温上昇を1.5度以内に抑えるシナリオに基づき気候変動リスクを分析し、原料炭について減損の兆候はないと判断。
- ENEOSホールディングス:脱炭素移行シナリオに基づいて資産価値の毀損兆候が示されても、直ちに財務諸表に反映すべきとは限らないと説明。
これらはIASB設例が意図する「気候変動と財務の整合性」を実務で先取りした例といえます。
■金融庁はプライム企業にサステナ情報開示を義務化へ
■気候関連リスクと機会の財務的影響の開示を
■「現在の会計」と「未来のストーリー」の統合が信頼に