記事のポイント
- JR上野駅に設置された一台の装置「エキマトペ」が、利用者の注目を集めた
- アナウンスや発着音など、駅構内の音をオノマトペなどで可視化する装置だ
- 技術革新と当事者の力を融合させたJR東日本の取り組みの舞台裏を探った
2025年3月、JR上野駅の1・2番線ホームに設置された一台の装置が、多くの利用者の注目を集めた。それが「エキマトペ」だ。この音の視覚化装置は、駅のアナウンスや電車の発着音を文字や手話、オノマトペで表現し、聴覚障害のある利用者に情報を届けた。
しかし、この装置が他の技術と決定的に異なるのは、手話動画にJR東日本の聴覚に障害がある社員が出演していることだ。外部の手話通訳者ではなく、自社の社員が当事者として主体的に参画するーー。これは企業における障害者活躍の新しい形として注目されている。
2025年11月に開催される東京2025デフリンピックを控え、聴覚障害への関心が高まる中、技術革新と当事者の力を融合させたJR東日本の取り組みの舞台裏を探った。(聞き手=NPO法人インフォメーションギャップバスター理事長・伊藤芳浩)

■4年間の信頼が築いた「運命の出会い」
このプロジェクトは一朝一夕に生まれたわけではない。その始まりは、2021年7月に川崎市立聾学校で開催された「未来の通学」をテーマとしたワークショップにさかのぼる。ここで富士通、JR東日本、大日本印刷(DNP)の3社が出会い、「誰もが使いやすく、毎日の鉄道利用が楽しくなるような体験」を目指すという共通の想いを確認した。
JR東日本 グループ経営戦略本部 経営企画部門サステナビリティマネジメントユニットの山下恵さんは、プロジェクトの原点をこう語る。

「駅をご利用の多様なお客さまに対して、安全安心な鉄道利用を実現していきたい。そして、ダイバーシティ・エクイエティ&インクルージョン(DE&I)への相互理解を促進する機会を創出していきたい。そういった想いを同じくする会社として富士通さんと出会えたことが、このプロジェクトの出発点でした」
こうした理念を共有した3社は、2021年9月のJR巣鴨駅での第1弾実証実験に踏み切った。わずか3日間という短期間ながら、SNSを通じて大きな反響を呼んだこの取り組みは、関係者に手応えを感じさせた。
続く第2弾では、2022年6月から12月までの6カ月間、上野駅の1・2番線ホームでより本格的な実証実験を実施。参画企業に駅での自動販売機を展開するJR東日本クロスステーションが加わり、社会実装を見据えた省スペース化・コスト削減を意識した筐体改善を実現。さらに、台東区と連携して地域のDE&Iに関する情報も表示するなど、駅を地域との接点として機能拡張を図った。
2025年3月の第3弾では、社会実装に向けて更なる筐体改良を図りつつ、より長期的なデータ収集と効果検証を行った。
富士通との4年間にわたる協働について、山下さんは信頼関係の深化を強調する。
「富士通さんは本当に脈々と技術と知見を積み重ねてくださっている。一方で当社のメンバーは入れ替わりもありますが、変わらない部分は安全安心な鉄道利用の実現と相互理解によるDE&Iを共に推進していこうという想い」。この一貫した理念こそが、長期にわたる協働を支える基盤となっている。
■「ピンチをチャンス」に変えた技術革新
しかし、この4年間の道のりは平坦ではなかった。特に第3弾で最も大きな技術的挑戦となったのが、JRのダイヤ改正による発車ベルから発車メロディーへの変更だった。
これまでのエキマトペでは、発車ベルの単調な電子音を「ルルルルルルルル」といった文字表現やシンプルなアニメーションで視覚化していた。
第3弾においても、富士通は発車ベルを前提として準備を進めていたが、3月中旬のダイヤ改正で音程のついた発車メロディーに変更される事態に直面したのである。音程やメロディーを文字でどう表現するかという、これまでに例のない課題が突如として立ちはだかった。
「急遽の案件でしたが、富士通さんにかなりご尽力いただきました。音程をどうやって文字で表現するかという、これまでにない課題への取り組みでした」と山下さんは当時を振り返る。
この予期せぬ困難に対し、富士通は「ピンチをチャンス」に変える発想で対応した。富士通コンバージングテクノロジー研究所の今村亮太さんは、この課題解決プロセスを詳しく説明する。
「準備していた中で急遽システムを変更しなければならない状況でした。期間は限られていましたが、早めにJR東日本さんからお伝えいただいたおかげで、デザイナー、特にろう者のデザイナーと一緒に、どういう表現なら自分がホームに立ったときに伝わるかをディスカッションできました」
このディスカッションから生まれたのが、音楽の感情やリズムを視覚的に表現する革新的な手法だった。軽快なリズムにはカタカナを使用し、柔らかな雰囲気には柔らかいフォントを採用。音の高低は文字の抑揚で表現するなど、単なる情報伝達を超えた「感情豊かな表現」を実現した。
「僕らもやったことのなかったメロディーの視覚化に挑戦できたのは大きな成果でした」と今村さんは語る。この経験は、音の視覚化技術の可能性を大きく広げる成果となった。
技術的な精度向上の鍵は、AI技術と人間の知見を組み合わせたアプローチにあった。エキマトペの音識別システムには、富士通のスーパーコンピュータ「PRIMEHPC FX1000」で構築したAI学習モデルが活用されているが、それだけでは駅という複雑な音環境での正確な識別は困難だった。
「駅では本当にいろんな音が鳴っています。その中から『オノマトペ』で表現する音を予め決めて、録音した膨大な音の中から漏れなく拾うという作業を、人的作業と技術を使って行いました」
雨の日、風の強い日、人が混雑する時間帯—駅の環境は常に変化し、録音される音も大きく異なる。その中で電車が進入してくる「ガタンゴトン」という音と、「発車メロディーの音」を正確に識別するため、AIに徹底的に学習させる作業を人間が支援した。
「AIと人の力、特にエンジニアのメンバーの力が合わさってできたこと」と今村さんは技術開発の本質を語る。
■「社員一人一人が主役」から生まれた発想転換
技術的な革新と並んで、このプロジェクトのもう一つの特徴が、JR東日本の聴覚障害のある社員の主体的な参画だった。しかし、意外なことに、この発想は当初JR東日本からは生まれなかった。
山下さんは率直にこう認める。
「会社としては『社員一人一人が主役だ』という話はしているものの、実際に当社の社員がエキマトペの動画に出演するという発想を持っていませんでした。ちょっとお恥ずかしい部分もありつつ、富士通さんから『JR東日本さんにも(聴覚障害のある社員は)いらっしゃいますよね』とお話をいただいて気づきを頂戴し、実現しました」

この提案を受けて、JR東日本は社内の聴覚障害のある社員に打診した。「興味があれば、やってみてくれないか」という声かけから、2名の社員が手を挙げた。山下さんはこの取り組みの意義をこう説明する。
「当事者が主体的に社会課題の解決に関与していくことが社員のやりがいの向上にも繋がっていくと考えました。社員一人一人が主役で誇りを持って自分の業務に取り組んでいこうという方針とも合致します」
エキマトペに出演した八王子支社の田原佳奈さんは、出演依頼を受けた時の心境を詳しく語ってくれた。

「エキマトペは以前から知っていましたが、ニュースやSNSで見るだけで自分にはあまり関わりがないと思っていました。しかしエキマトペは電車の音等を視覚的に表現する装置であるため、お客さまが利用する駅に設置されることは、聴者や聴覚障害者にとって相互理解が深められるという意味でも大きな役割を果たすと感じました」
田原さんは、職場での聴覚障害への理解促進について、以前から課題を感じていたという。
「聴覚障害者である自分が聴者に囲まれて仕事をする中で、周りの理解を得るためにはどういう動きをしていけばいいかを考えていました。しかし、なかなか理想とする動きができなかったり、聴覚障害に対しての理解を求める説明をすることの負担もあったりしました」
そんな中での出演依頼は、田原さんにとって大きな転機となった。
「嬉しさと同時に、本当に自分でいいのかという迷いもありました。でも、この機会は共生社会の実現に向けた大切な一歩になるのではないかと感じ、その発信に自分が関わることができるということがすごく嬉しかった。これは自分一人の力ではなく、富士通さんやJR東日本の関係者の皆さんの協力があったからこそ実現できたことです」
もう一人の出演者、東京統括センター(東京駅)のの田中彰彦さんは、より率直な心境を語ってくれた。
「はじめは私への直接の依頼ではなく、横浜支社の方からお話をいただきました。まだ実際に実施されるかどうか不明の段階でしたが、本当に実施されるのかなという半信半疑な気持ちと、実施できたらいいなという思いがありました。自分を含め、様々な方の生活が豊かになりそうだという期待もありました」
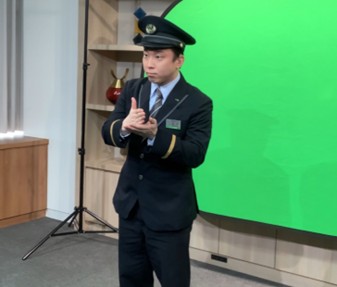
田原さんにとって、エキマトペへの出演は新しい経験への挑戦となった。
「初めての経験でしたが、動画撮影は興味深く、大変には感じませんでした。中高や大学時代にたくさんの人がいる前に立って、手話で話す機会を経験していることや手話で周りの人とコミュニケーションを取っているからなのか、そのおかげで楽しむことができました」
■公共の場での「手話表現」という新たな挑戦
2人の出演への意欲は高かったものの、実際の撮影では新たな課題が浮かび上がった。手話動画の制作では、上野駅という公共性の高い場所での情報提供という特殊性を考慮した表現が求められたのである。
田中さんは撮影時の手話表現の工夫について詳しく説明する。「上野駅にはどんな人が来るのか、どういう表現でどういう年齢層の方に伝えたらよいかを考えながら表現するのが一番大変でした。手話ができる人もできない人もいらっしゃるので、手話だけでなく視覚的にもわかりやすい表現を心がけました」
この工夫は、ろうの映画プロデューサーで、映像制作時の手話監修を手掛ける、今井ミカ氏との綿密な連携のうえに実現した。
「今井さんと相談をしながら進めていきました」と田中さんは制作プロセスを振り返る。
田原さん自身は、撮影時の特殊な環境を意識したという。
「普通に真面目な表現をするだけではなく、周りの目があるということを意識しました。撮影時には実際には人はいませんが、映像が流れる駅のホームでは様々なお客さまがいることを想像して、見られているという感覚で手話表現をしました」
これは手話表現における重要な側面を示している。田中さんもこう付け加える。
「普通におしゃべりする手話と、人に見られているときの手話の表現は変わってきます。それはニュースキャスターがニュースをお茶の間に届けるときと普段の会話が異なるのと似ています」
この公的な手話表現への意識的な取り組みは、エキマトペの情報提供品質向上に直接寄与することにつながった。
■「初めて手話を見た」人たちの心に響いた瞬間
AIを活用した技術革新と、当事者の参画により完成した第3弾のエキマトペは、実際の利用者にどのような反応をもたらしたのだろうか。今回は公開期間が1カ月と短かったため、富士通では利用者の行動をモニタリングした。その結果、予想を上回る反応が確認された。
「かなり多くのお客さまが足を止めて、エキマトペを見ているということがわかりました。ろう者の方が手話で友達と話しながら見ている様子も確認できましたし、小さい子から大人の方まで、足を止めて見ている姿が見えました」
今村さんは、この結果を次のように分析する。「聴覚障害者のための情報提供ではなく、駅を利用されるすべてのお客さまに届けるという観点から、しっかりとエキマトペを見ていただけて、関心を持っていただけたことが調査で確認できました」
さらに今回特に注目されたのは、SNSを通じた影響力の広がりだった。山下さんは新たな広がりを実感している。「政治家やデフアスリート、上野駅を訪れていない方にもSNSに投稿していただき、その場にいない方へのインパクトもあることを実感しました。みんながSNSを使うようになったからこそ、その場にいない方の反応も見ることができる。これは今までのエキマトペとの大きな違いです」
「皆さんに好意的に捉えていただいている反応が多かったので、影響力のある設備だと我々も実感しました」
JR東日本という公共交通機関が手話表現を積極的に取り入れることの社会的意義は計り知れない。上野駅という多くの人が集まる公共の場で手話が日常的に見られることで、手話に触れる機会の少ない人々にとっても貴重な体験となったはずだ。
■個人の変化から見えた「可能性の芽」
エキマトペ出演後の変化について、出演した田原さんはこう語る。「正直、すごく大きな変化はまだ起きていない、まだ見えていないという状況だと思います。エキマトペを設置して実証実験をしたという段階なので、それ一つで何かが大きく変わるということはまだ難しい」
しかし、長期的な視点では大きな期待を抱いている。「エキマトペで初めて手話を見たという体験をした人がいるかもしれないし、そういう人たちが、私たちと関わってくださる距離はきっと近くなったと思います。これをきっかけの一つとして、聴覚障害の理解・啓発に繋がっていくんじゃないかと願っています」
田中さんは、職場での変化をより具体的に感じている。「普段の仕事は企画業務が中心なのですが、今回の動画出演というなかなか経験できない仕事に携われたことで、『こういうこともやってるんだね』と、周囲に別の自分を知ってもらえるきっかけになったと思います」
この「別の自分を知ってもらう」という表現は重要だ。障害のある社員が単に「配慮の対象」ではなく、多面的な能力を持つ「同僚」として認識される契機となることを意味しているからだ。
こうした成果を支えているのが、4年間にわたって築かれた富士通との協働関係だ。富士通コンバージングテクノロジー研究所の今村さんは、JR東日本との関係性の深化をこう語る。
「担当者は変わっても本当に長くお付き合いいただいたのも、共生社会の実現に向けて軸となる会社としてやっていかなければいけないという意識、すべてのお客さまに安心して利用してもらいたいという想いから、様々な可能性・やり方を探っているところに、エキマトペという一つの可能性を感じていただけたのかなと思います」
「そういった方々と一緒にやれたのは本当に誇りです。JR東日本さんだからこそ、その取り組みの発信力や意義が本当に日本中に広がる可能性を感じています」
今村さんは、デフリンピック以降の、継続的な取り組みの重要性も強調する。「デフリンピックはありますが、それが終わった後の取り組みがもっと大事だと思っています。エキマトペや、エキマトペにかかわる取り組みの何が良かったか、何が課題だったかというところを一緒に伝えていけたらと思います」
このエキマトペプロジェクトは、単なる技術導入を超えた意味を持つ取り組みとなった。技術革新、当事者の主体的参画、そして長期的なパートナーシップ—これらの要素が組み合わさることで、真の共生社会実現への道筋が見えてきた。この取り組みが組織内部にどのような変化をもたらし、今後どのような展開を見せるのか。その答えは明確である。プロジェクトが触媒となって生まれた組織文化の変革と、東京2025デフリンピックを契機とした新たな取り組みに現れている。
後編では、エキマトペプロジェクトが組織内部に与えた波及効果と、そこから生まれた新たな技術展開、そして共生社会実現に向けた長期的な展望について詳しく紹介しています。






























.jpg)



