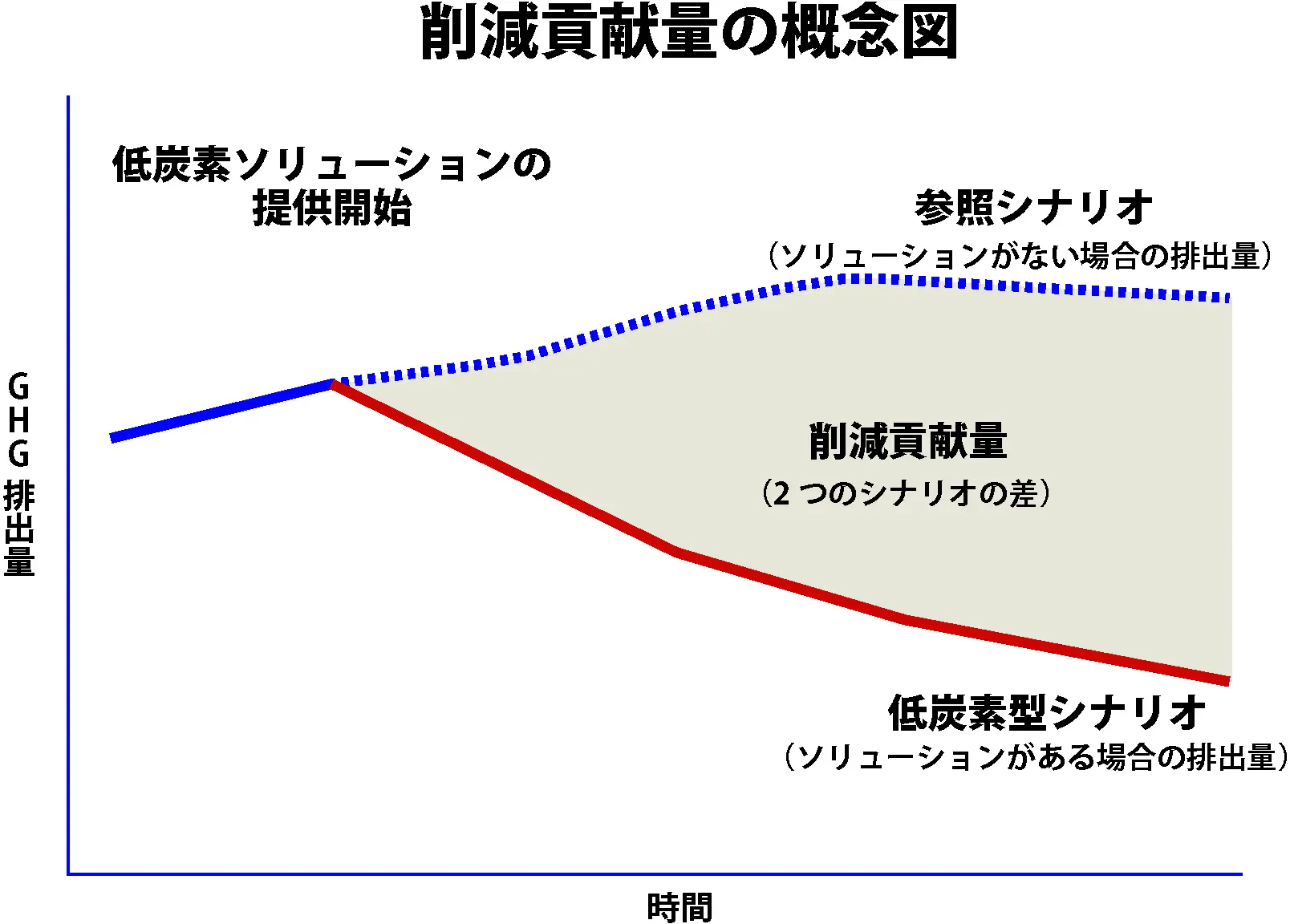■トップインタビュー
記事のポイント
- 雪印メグミルクは創業100周年を迎え、パーパスを「健土健民」と定めた
- 「健土健民」は、1925年の創業当初に提唱した考えだ
- なぜ今になって創業当時に提唱した言葉をパーパスに選んだのか
雪印メグミルクは今年5月に創業100周年を迎え、自社のパーパス(存在意義・志)を「健土健民」と定めた。健土健民は、1925年の創業当初に提唱した考えではあるが、なぜ今掲げたのか。同社の堀成輝・常務執行役員が語った。(聞き手・オルタナ輪番編集長=池田真隆)

雪印メグミルク株式会社常務執行役員(総合企画室・人事担当)
1989年4月雪印乳業株式会社入社、2014年10月雪印メグミルク株式会社関西販売本部担当部長、2016年6月同社財務部担当部長、2017年4月同社財務部副部長、2017年6月同社財務部長、2021年4月同社常務執行役員
――創業100周年を機に、創業者の一人である黒澤酉蔵氏が提唱した「健土健民」をパーパスとして定めました。なぜ「健土健民」を掲げたのか、創業当初の意味との違いを教えてください。
創業100周年を迎えるにあたり、改めて「会社の存在意義や志」を明確にする必要があると考えました。これからどの方向に進むのか、社員全体でベクトルを合わせたいという思いがありました。「健土健民」は、当社の前身である北海道製酪販売組合の創業者の一人・黒澤酉蔵が提唱した理念です。
「豊かな土が健やかな人を育む」という意味であり、当時、栄養が十分に取れなかった時代に、酪農や乳製品を通じて社会課題の解決を目指すという志が込められていました。当時、北海道の土地は穀物の生産に適していなかったため、酪農が地域発展の手段だったという背景もあります。
この「健土健民」は、創業当時から会社の根底に流れている精神です。今回改めて存在意義・志を見つめ直したときに、この言葉が再び浮かび上がってきました。
私たちは今、実際に土を耕しているわけではありませんが、社会課題を解決しようとする「挑戦の精神」としてこの理念を受け継いでいます。社会課題は時代によって変化しますが、それに立ち向かう精神こそ「健土健民」なのです。
創業100周年を迎えるにあたり、「食の持続性」にどう向き合うかを明確にし、「私たちは社会課題に挑む精神で、人と自然が健やかにめぐる食の未来を育んでいきます。」という存在意義・志のステートメントを掲げました。これからも、食の持続性の実現に向けて取組みを進めていきます。
企業経営の中では、これまでにもさまざまな理念やスローガンが生まれてきましたが、複雑化して伝わりにくくなっていました。どれが最も根幹なのかを明確にし、再び「健土健民」を企業理念にあたる存在意義・志として定義し直したのです。
利益を上げるだけではなく、「どういう会社でありたいか」「どういう社会的価値を生み出すか」が重要です。社員にとっても会社はお金を稼ぐだけの場所ではなく、自己実現の場であるべきだと思います。
志を共有することで、同じ思いを持つ人が集まり、自分ごととして会社に関われるようになります。その浸透のために、役員によるキャラバンを実施しています。
中期経営計画の説明とあわせて全国の事業所を訪問し、全社員にパーパスやバリューを直接伝えています。また、自分の思いと会社のパーパスを重ね合わせる取り組みも進めています。
どこが会社の理念とつながるのかを考えることで、社員一人ひとりの気づきや意識の変化が生まれています。
■パーパス策定の背景に「食中毒事件」からの学びも
■エンゲージメントの向上も評価項目に
■日本では乳製品の約4割を輸入に頼っている