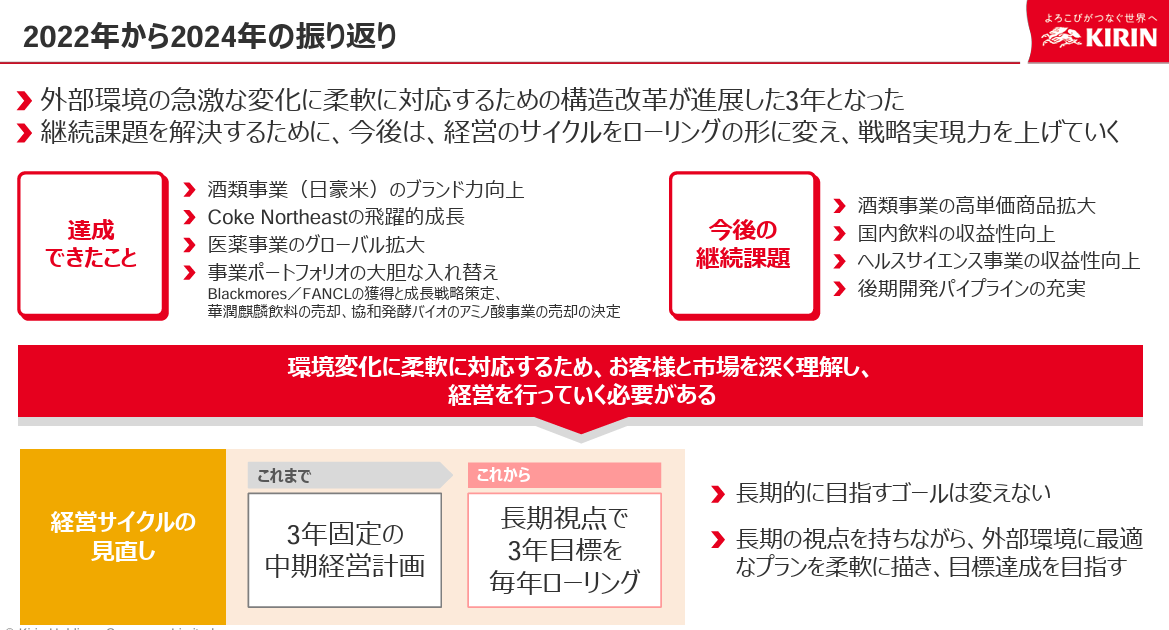記事のポイント
- 11月10日から開催のCOP30は、「目標」から「実施」に踏み出す節目だ
- 気候システムは臨界点に達しつつあるが、自然再生などでフェーズシフトも可能だ
- 政治の動きが鈍い中、先進企業は自ら未来を変えるために行動を始めている
11月10日からブラジル・ベレンで開催されるCOP30(国連気候変動枠組条約第30回締約国会議)は、「目標」から「実施」へと踏み出す節目となる。気候変動の進行は止まらず、気候システムは「負の臨界点」に達しつつあるが、再エネや自然再生などによる「正の臨界点」の指摘もある。政治の動きが鈍い中、先進企業は政治の合意を待つことなく自ら未来を変えるために動き始めている。(サステナブル経営アドバイザー・足立直樹)

■1.5℃を超えつつある現実の中、行動が問われる
まもなく11月10日からブラジルのベレンでCOP30が開催されます。パリ協定に合意した2015年のCOP21から10年を経た今、「目標」から「実施」へと踏み出す節目となります。
2024年の世界平均気温は+1.55℃となりました。まだ1年だけのオーバーシュートですが、今年も昨年以上に暑いとされており、気候システムの一部はすでに臨界点(ティッピングポイント)を越え始めているのかもしれません。
160人の科学者が執筆し、2025年10月に公表された『グローバル・ティッピング・ポインツ・レポート2025(Global Tipping Points Report 2025)』は、氷床、永久凍土、熱帯雨林、サンゴ礁、海洋循環など、少なくとも5つの臨界点に達しつつあると警告しています。
同時に、この報告書は「正の臨界点」も指摘しています。再生可能エネルギーや食料システム、自然再生など、人為的な意思と投資によって望ましいフェーズシフトを起こすことは、まだ可能だといいます。つまり、いま私たちは、「悪い臨界点」と「良い臨界点」の分かれ道に立っているのです。
■政治は遅れても企業の「脱炭素経済」は軌道に
こうした危機的状況に対し、政治の動きは鈍いままです。主要国の利害や政権の不安定さが、国際的な合意形成を難しくしています。一方で、危機感を最も強く抱いているのは企業かもしれません。
世界経済フォーラム(WEF)の「CEO気候リーダーズ同盟」は10月9日、COP30を前に「低炭素でレジリエントな経済への移行を加速せよ」と求める公開書簡を発表しました。
総売上4兆ドル(約616兆円)、従業員1200万人超の130社が連名で、「気候対応はもはやコストではなく、成長の条件である」と明言しています。
実際、2019~2022年の間に、これらの企業は温室効果ガス(GHG)排出を10%削減しながら売上を18%伸ばしました。デカップリングは可能であり、「脱炭素経済」が企業の新しい成長軌道となっているのです。
■COP30の焦点:「行動」の臨界点を越えられるか
今回のCOP30で 特に注目すべきは、次の4つの論点です。
1. 2035年国別削減目標(NDC)の初回見直しと引き上げ
パリ協定後に各国が決めたNDCの積み上げでは、世界全体でGHG排出量の削減は45%減に届かず、1.5℃目標との間に大きなギャップがありました。今回ははじめてそれを本格的に見直すタイミングであり、各国がどこまで野心的に目標を引き上げられるかが焦点となります。
各国は今年2月までに2035年のNDCの提出を求められていましたが、締め切りを9月まで延長しても、提出は64カ国(2025年11月5日現在)にとどまっています。もちろん今後駆け込みが増えるとは思いますが、予断は許さない状況です。
2. 途上国支援と資金メカニズムの制度化
COP29で合意された「バクー・ベレン・ロードマップ」では、2035年までに年間1.3兆ドル(約200兆円)規模の気候資金を動員することが掲げられました。今回は、この資金動員の制度化と民間資金の呼び込みが鍵を握ります。
これは企業にとっては、グリーンファイナンスやトランジション・ファイナンスへのアクセス拡大で、新たなビジネス機会となります。資金の透明性と安定的な制度設計は、世界全体のレジリエンスを支える基盤です。
3. 適応の世界目標(GGA)の具体化
気候変動の影響を「防ぐ」だけでなく、「耐える力」を可視化するため、適応に関する世界共通の指標づくりも進められています。
GGA(適応に関する世界全体の目標、Global Goal on Adaptation)では、100指標以内に絞り込んで各国の適応状況を測定する枠組みの策定が議論されており、企業もサプライチェーンの脆弱性や物理的リスクを評価・開示することが求められるようになるでしょう。適応は守りではなく、価値創造の前提です。
4. 森林保全と自然資本への投資
開催地のベレンは、アマゾンの玄関口に位置します。ブラジルのルラ政権は、前政権で後退した環境政策を立て直し、森林保護を最優先課題として掲げています。実際に森林破壊のペースは減少に転じており、ルラ政権は熱帯雨林保護基金(Tropical Forest Forever Facility)の創設を提案しています。
ベレンは私自身も数年前に訪れたことがあるのですが、決してアクセスしやすい場所ではなく、インフラも十分ではありません。それでもあえてこの地を選んだのは、気候と森林を切り離さずに考えるというブラジルの強い意志の表れです。
「地球の肺」と呼ばれるアマゾンの入口で開催されるCOP30は、まさに「ネイチャーCOP」と呼ぶにふさわしい会議です。
■先進企業は動き出している
これらの論点にどこまで実質的な合意ができるかが、各国の「本気度」を測る指標です。しかし、仮に十分な合意に至らなくても、気候変動の進行は止まりません。企業にとって重要なのは、気候変動を経営環境の前提条件として扱い、制度や市場の整備を待つのではなく、自ら動くことです。
臨界点を越えた地球で次のフェーズへ進むためには、気候・自然・社会の三つを同時に見据える統合的な視点が欠かせません。
やるべきことは既に明白です。企業は、結果を見守る傍観者ではなく、次の経済の秩序を形づくる当事者として、自らの行動で未来を変えていく存在です。政治の合意に合わせるだけでは、もはや間に合いません。すでに先進的な企業は動き始めています。いま求められているのは、「次の臨界点」を自らつくり出す覚悟です。
※この記事は、株式会社レスポンスアビリティのメールマガジン「サステナブル経営通信」(サス経)527(2025年11月5日発行)をオルタナ編集部にて一部編集したものです。過去の「サス経」はこちらから、執筆者の思いをまとめたnote「最初のひとしずく」はこちらからお読みいただけます。