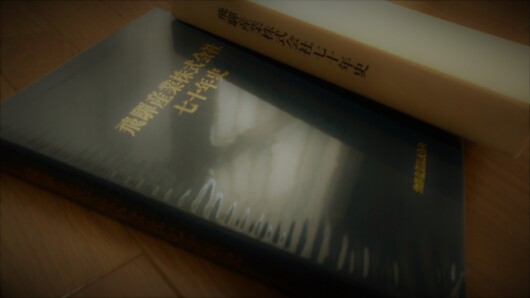その始まりは、「関西で曲木で椅子をつくる技術を身につけた」という森前房二と名乗る男が高山に現れた、100年前の1920年にさかのぼります。飛騨の匠たちは彼らからその技術を学び、豊富なブナ材を活かし、さらには塗装技術が未熟な時代だったため、今では伝統文化財となっている同じく匠の技術ともいえる春慶塗りを採用するなど、地域に根差す文化と自然を最大限に活用し製品化に成功します。
しかし、そこから関西や浜松の木工メーカーに勝てる品質・値段にするのには時間がかかりました。経営に行き詰まるなか、皮肉にも関東大震災という大惨事による復興需要で窮地を脱します。その後、早くからアメリカへも輸出を開始し、世界恐慌も乗り越えていった飛騨産業は、戦時中にはなんと日本初の木製の戦闘機の開発も手掛けました。高山に空襲予告のビラが巻かれた3日後広島に、さらにその3日後に長崎に核爆弾が落とされ戦争が終結、高山は辛うじて空爆を逃れましたが、戦闘機も実用化前に河原で焼かれたといいます。
戦後も海外輸出を主力として成長を続けた飛騨産業は、一時海外売上高が8割を超えるまでになりましたが、材料高騰による採算悪化から海外から国内に市場を転換していく決断をします。しかし、その後の高度経済成長で成長に取り残され、国産のブナ材も不足し、安い海外の木材を輸入していくようになり、いつしか地域資源としての森に見向きもしなくなっていき、業績も伸び悩んでいきます。