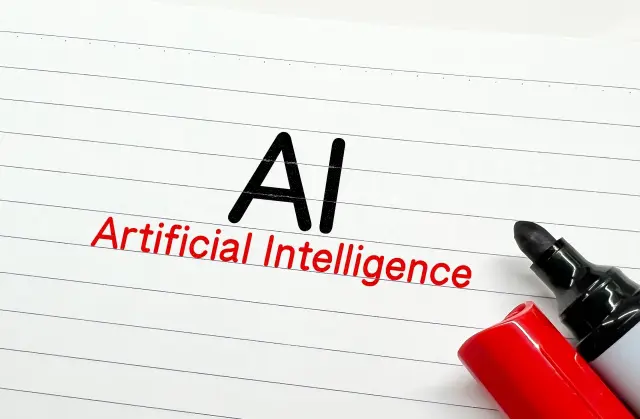記事のポイント
- ろう者たちが手話で「音楽」を奏でるドキュメンタリー映画「LISTEN リッスン」
- ろう者当事者の視点から「映画」を問い直した同作は大きな反響を呼んだ
- 共同監督を務めた牧原依里さんに、制作の背景にある思いを聞いた
-1-1-354x530.jpg)
ろう者たちが手話で「音楽」を奏でるアート・ドキュメンタリー映画「LISTEN リッスン」(2016年公開)。既存の映画が、聴者による「聴文化」を前提としていることに問題意識を持ち、ろう者当事者の視点から問い直した同作は大きな反響を呼びました。 公開から7年経った今、書籍「『LISTEN リッスン』の彼方に」(論創社)が出版されました。監督の牧原依里さん、雫境(だけい)さんが考えたことや、さまざまな分野で活動する表現者・研究者たちとのトークや論考などが一冊にまとまっています。
筆者が映画「LISTEN リッスン」の共同監督を務めた牧原依里さんと出会ったのは2016年。ドキュメンタリー映画「LISTEN リッスン」の公開に先立ち、横浜市のアートフォーラムあざみ野で開かれたトークショーにさかのぼります。
▼聾者が奏でる無音の音楽映画『LISTEN リッスン』聾者の共同監督が語る制作背景
牧原依里さんは、ろうの両親を持ち、ご自身のアイデンティティもろう者です。「博報堂DYアイ・オー」に勤務するかたわら、映画制作学校「ニューシネマワークショップ」で半年間学び、2016年には「ろう者の音楽」をテーマとした映画「LISTEN リッスン」の共同監督を務めます。
現在もこうした視点から表現を模索している牧原さんの活動の背景にあるものを掘り下げていきます。(聞き手=NPO法人インフォメーションギャップバスター理事長・伊藤芳浩 )
■ろう者の両親のもとに生まれて
――はじめに牧原さんの生い立ちを教えていただけますか。
私の両親はろう者で、難聴の姉がいます。私は小学校2年まではろう学校へ通い、3年生から地域の学校へインテグレーションしました。地域の学校へ通う姉を見て、聴者の世界に興味を持ったこと、そして、ろう学校の学習進度が遅くて私の意欲に見合わなかったことが理由です。自分から母に地域の学校へ行きたいと言ったのを今も覚えています。
――周りの同級生たちとのコミュニケーション方法はどのようにされましたか。
私の場合は口話から始まりました。ろう学校でも口話を使っていたので、自然な流れで、そうなりました。
その頃、テレビドラマ「星の金貨」がブームになり周りの友達が手話を覚えてくれました。でも高学年以降は筆談や指文字が中心になって、中学校からは完全に声は使わなくなりました。日本語については、図書館で本を読んだり映画の字幕を見たりして自然と身につきました。むしろ聴者の学校に転校して、聴者と筆談や指文字でのやりとりが増えてから自然と上達したように思います。
――現在はどのような活動をされていますか。
株式会社博報堂DYホールディングスの特例子会社「博報堂DYアイ・オー」と「フェロー」という契約を結びながら個人としての活動をしています。会社の顔としての広報的な活動を業務としており、個人の活動とともに会社を広く知っていただくことが現在の主な任務です。
現在は映画制作だけでなく、ろう者難聴者の俳優や制作者を育成する活動も行っています。映像だけでなく舞台や現代アートなど幅広く視野に入れ、ろう芸術全般にかかわる仕事をしています。
■ローマのろう国際映画祭で映画づくりに出合う
――映画にかかわるきっかけは何だったのでしょうか。
私が子どものころは字幕がついているテレビ番組は少なく、横浜にある聴覚障害者情報提供施設(横浜ラポール)で字幕付きビデオを借りて視聴していました。
ほかにも、きっかけにもなった理由にもうひとつ、日常生活の中でそういう、ろう家族の文化的な取り込みが当たり前のように育ったのもあります。というのも、テレビに字幕がないので、字幕がついている外国の映画を自然と見るようになるろう家族が多いんです。
例外なく、私の家族も、近所の「TSUTAYA」に毎週、家族で行ってDVDをレンタルして観るのが習慣になっていました。なので「観る」ということには慣れ親しんで育ったのかなと思います。
映画を作りたいという思いに目覚めたのは、2012年に旅行に行ったイタリアで、ローマ国際ろう映画祭に参加したことです。そこでろう者でも映画が作れることを初めて知り、ろう者が作った映画をもっと見たい、自分でも作りたいと思って帰国後、社会人が映画制作を学べるスクールに通いはじめました。
それまで映画は聴者が作るものだと思っていたんです。中学校の文化祭でクラスで映画を作ろうということになったときも、本当は監督に立候補したかったけれど、周りに迷惑をかけてしまうのではないかと撮影を担当しました。でも、ほかの撮影担当の子とコミュニケーションがうまくいかず、がっかりしたことがあったのです。
それに検索してみると映画の世界は厳しいことが分かりました。下積みから経験を積まなければいけなくて、いきなり監督ができるわけではない。ADから始めなくてはいけなくて、そのためには言語が壁になる。手話通訳を常に連れていくことも難しいし、ろう者には難しいところがある。どう考えても仕事にはできないだろうと思っていました。
――映画制作に必要な知識はどうやって身につけたのでしょうか。
「ニューシネマワークショップ」というスクールに半年間通って身につけました。本来は1年のコースなのですが、半年間となりました。というのも、残りの半年間は、講習ではなく脚本が選ばれた監督について一緒に制作する形で進める内容でした。自分が監督に選ばれたら良いのですが、そうではない場合、その監督につく必要があります、そうなると打ち合わせなどがイレギュラーになり、情報保障の面で難しいと判断したためです。
また、当時、私の地域の手話通訳派遣の仕組みは利用にいろいろな制限があり、派遣の条件も難しかったからです。最終的には半年間はすべて手話通訳付きの受講をし、残りの半年間は断念しました。手話通訳派遣の窓口やスクールとの交渉に半年もかかり、すぐに学び始められなかったのも悔しかったです。
現在はその制限は緩和されているそうですが、私以外にも趣味や資格取得のために手話通訳を使いたいというケースが続いて変わったようです。こうした積み重ねは大事だとは思いますが、当時はすぐに手話通訳が必要なのに利用が制限され歯がゆい思いをしました。
スクールでは脚本の書き方、照明や撮影の方法を座学と実践で学びました。短編映画の制作の授業では、役割を指示したり、また指示されたりする経験もしました。初めて監督を務めることができたのは貴重な経験でした。
■映画「LISTEN リッスン」ができるまで
――そこから「LISTEN リッスン」はどのように生まれたのですか。
スクールを修了したら作ろうと温めていたテーマではなく、偶然によるところが大きいんです。私は「ろう者にとっての音楽とは何か?」ということに以前から関心があり、いろいろな人にインタビューをしていたんです。
2014年頃、ろう舞踏家の雫境さんに出会い、彼に共同制作を持ち込んで、一緒に撮り始めました。また、同時期に配給会社のアップリンクが主催する配給宣伝ワークショップにも通っていて、ある日、撮影帰りに機材を抱えたまま行ったんです。その時、アップリンク方に「それは何?」と聞かれて、撮影している内容を話したんです。「実はこういうのがある」と。そうしたら「面白そう!どんなのか見せて」と言われて。見せたらほかの方からも励まされて「劇場上映をしたらいいんじゃないか、アップリンクでやろう」という話になったんです。
上映までアップリンクと私たちのチームがともに助け合い、協力しながら進めました。私は制作・監督だけでなく宣伝にも携わりました。資金繰りや宣伝、ポスターの作り方などをアップリンクの方々に教わり、貴重な経験をしました。ろう者が映画にまつわるプロの仕事を経験できるのは稀なことで、私は運よくいい機会をいただいたと思っています。
――配給宣伝ワークショップでは、どんなところが印象に残りましたか。
買い付けた作品を上映する前に、ポスター案を何点か並べて選んだり、邦題を検討したりしたのが印象に残っています。アップリンクの方が「みんなはどう思う?」と意見を求めるので、みんなそれぞれ自分の考えを言うんですね。ポスターにしても邦題にしても、一人ひとりが持つイメージや意見が違うことも勉強になりました。
それから、海外作品を買い付けて日本で販売、上映するマーケティングについても学べました。カンヌ、ベネチア、ベルリンといった国際映画祭は、作品を上映するだけでなく買い付ける場でもあるんです。買い付けたい作品について「みんなはどう?」と意見を求めてくるんです。配給宣伝ワークショップに参加している人たちの意見を聞くのは面白かったです。映画好きの学生や主婦、またコンテンツ配信会社の関係者や映画配給会社の方までさまざまな立場の人が集まって議論するのが楽しかったですね。
ワークショップの後は交流の場があり、人脈が広がりました。「どこから来たの?」「今度一緒にやってみましょうか」といった付き合いができました。「LISTEN」の宣伝グループもその人脈でできたんです。聴者から情報源を得て、交流の中でパイプを作っていくことも含め、映画は作る以外にさまざまなことをする必要があると知りました。
■配給宣伝ワークショップで鍛えられた対話力
――ろう者がその機会やきっかけを作るってなかなか難しいですよね。
はい。手話通訳の問題が大きいと思います。アップリンクのワークショップに行くときは、住んでいる地域の手話通訳派遣窓口へ依頼して来てもらっていました。自己負担はありませんでしたが、夜7時から2、3時間のワークショップの通訳に来てくれる手話通訳者が見つかるかの不安は常にありましたね。
さらに、突然質問をされてもすぐに答えられるように講義中でも答えられる準備をするようになりました。ワークショップで向こうから「どう思う?」と唐突に尋ねてくるんです。初めて問われたとき、私はどう答えていいか分からなかったんです。
すごく勿体ないことをしてしまったなと思って、そのチャンスを無駄にしないよう、もし聞かれたら「こう答えたらいいかな」と頭をフル回転させていました。そういうときに要点をその場ですぐ伝えられるかはとても重要で、配給宣伝ワークショップに鍛えられました。
ワークショップでは自分の経験や思考をどう言語化するか、その話にどういう形で活かせられるか、他者の話も聞きながら一緒に考える必要があります。こういうところで、ろう者は「自分の頭で考えたことを言語化する」経験が足りないと思っています。
というのも、日本の教育では自分で考えて答える、議論する場がかなり少ない。特にろう教育においては聴者の先生が考える「正解」に答えなければいけないと考えるろう児童・生徒や学生が多いように思います。聴者がろう者に質問していいのかどうか遠慮してしまうのも要因の一つですが。
言語化するためには、まず他の人の話をよく聞く、本を読む。なるほど、うまいと思ったら参考にする。そうやってインプットを繰り返していくことで、自分の頭の中にある考え方が自ずと整理されて言語化できるようになりました。
配給宣伝ワークショップでは個性が強い人たちが集まるのもあいまってか、正解も不正解もない。誰でも対等に自由に発言できる雰囲気があったなと今でも良い思い出になっています。
また、手話が日本語より劣ったものだという誤解もよくあります。「日本語の難しい語彙は分からないだろう」と。しかし、私がワークショップに参加し続けることにより、手話が独自の体系を持つ言語であり、日本語と対等なのだと理解してもらえました。
聴者はこうした手話に関する知識がないだけなので「ああ、手話は言語だと知らないのだな」と、割り切って説明する力も私たちには必要だと思います。
■教育の本質をおさえて教えることの大切さ
――手話は「言語」だと説明するのもなかなか難しいですよね。
手話が見下されたときにちゃんと説明できるかどうか――。分かっていても難しいですよね。でも、機転を利かせて答えられたら、手話を言語として公平に見てくれる聴者もいると思います。ろう者の中には自分から積極的に話さない人が多いように思います。
抑圧に慣れているのか、方法が分からないのか、できるのに行動に移さないのか、いずれにしろ言語が異なるので、マイノリティがマジョリティの中に飛び込むのはとても勇気がいることだし、積極的になれないのもわかります。
まず情報が入らないですし。そしてその環境を生み出してきたのは社会です。ろう者が聴者のあいだに飛び込むのは、日本人の聴者が外国に出ることと同じだとよく比較されるのですが、私は全く異なると思っています。なぜならその聴者の日本人は頑張ればその外国の言語を習得できるようになるからです。
ろう者はその国の言語を覚えても、音声言語のみで会話がなされるなら、聴者と同じ場にいることが難しい。だからこそ、何の準備も整っていないろう者にいきなりマジョリティの中に飛び込めというのは酷だと思っています。
その結果、ろう者が聴者に遠慮がちになるというのはそういうところからきているのかもしれないと思うことがあります。でも実はろう者たちはきちんと疑問を持っている。ただ、それを聴者たちに共有する方法がわからない。なぜならその方法を教わってこなかったから。疑問を出しても否定され続けてきた人たちが多いように思います。
■ろうの映画人を育てるために
――今、振り返って「LISTEN リッスン」の上映についてどう思いますか。
正直に言うと、ここまで規模が大きくなるとは思っていなかったです。私自身の生活環境や立場も大きく変わりました。仕事内容もろう芸術に関わる内容にシフトチェンジしましたし、人前で話すさまざまな機会をたくさんいただいています。以前は自分の発言について大して気にも留めていませんでしたが、今は影響力があることを自覚し、注意を払って発言するようになりました。
何より、自分のためではなくて「周りのために」という意識が強くなったのが大きな変化です。以前なら自分がやりたいことが優先でしたが、今はみんなと一緒に高め合うことが必要だと感じています。前と変わったのはそれかなと思います。
その「周りのため」の一つがろう芸術に携わる人たちの育成です。もし私が新しい映画を制作するなら、俳優からカメラマンまでろう者中心でやれると良いなと思っています。聴者と一緒に作ろうと思えばできますが、自分が意図する内容にするために恐らくかなりの労力を要するでしょう。
ただし、ろう者にしても素人ではなく、それなりの技術がある人と仕事をしたい。そのためには育成のための環境整備が必要です。周りを高めることが結果的に自分の作品の質にもつながる。それがスムーズな映画制作への近道だと分かったのです。
※後半は近日公開予定です









-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)