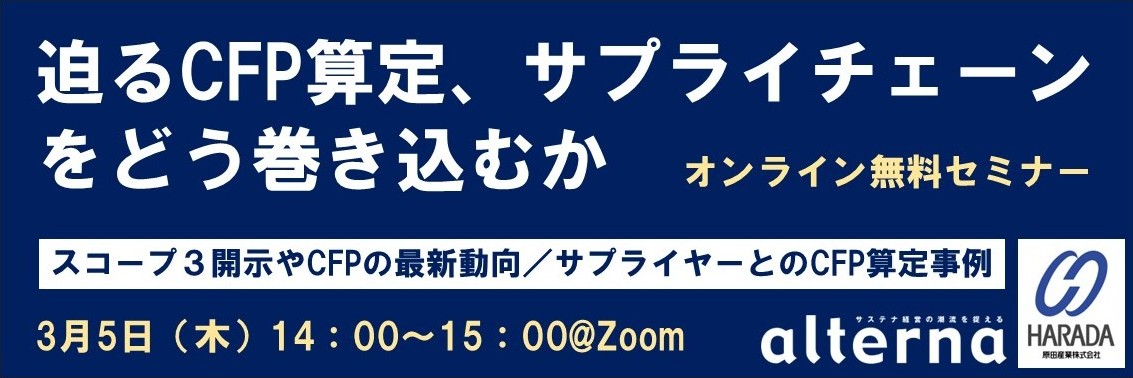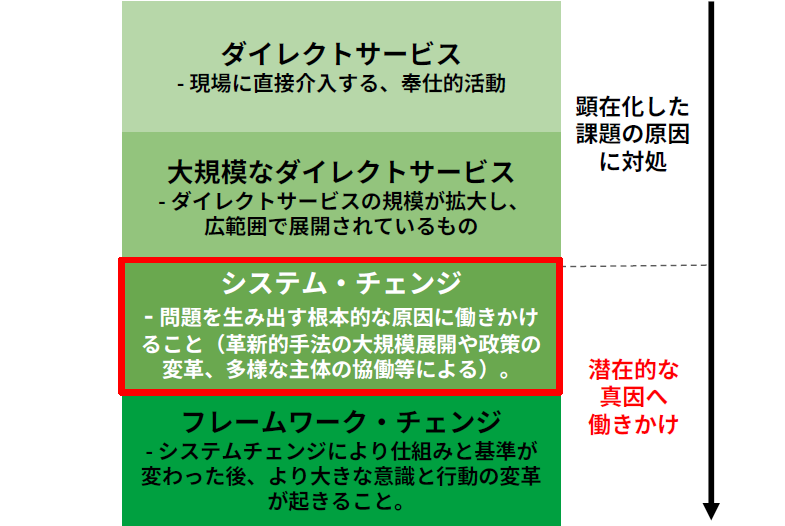記事のポイント
- ベンチャー企業が大学や研究機関とともに農作物の育つ「土の価値」を可視化した
- 土が本来持つ生態系や、地球環境への影響、作物と微生物の住環境を評価する
- 全国の農家や流通、企業と連携し、土にこだわった野菜ブランドを展開する
ベンチャー企業が、大学や研究機関とともに、農作物を育てる土壌の価値を日本で初めて可視化した。土が本来持つ多様な生態系や、地球環境への影響、野菜と微生物の住環境を評価する。全国の農家や流通・企業と連携を広げ、土にこだわった野菜ブランドとして、消費者に身近な小売店へ配荷を進める。(オルタナ輪番編集長=北村佳代子)

■作物の育つ「土」を評価する
次世代農業ベンチャー・BG(東京・目黒区)は、国立研究開発法人 産業技術総合研究所(産総研)とともに、農業活動による地球環境への影響を評価する「環境影響評価スキーム」を開発した。同スキームを活用し、農作物の育つ土壌の価値を可視化する日本初の農業評価指標「アグリLCA+」を開発した。
この指標では、土をつくる多様な生態系の働きを高める取り組みや、微生物や作物にとって健全で住みよい土壌環境づくりへの取り組みに加え、地球環境への影響も評価する。具体的に、堆肥、肥料、農薬の製造・使用や、種苗の製造、農業用水の使用、農業機械の利用といった農業の営み全体の環境への影響を評価する。
これまで消費者に見えづらかった農業の営みや作物が育つ土壌の価値を可視化することで、消費者が、野菜を選ぶ際に「おいしさ」や「健康」の根拠として活用することをねらう。
■土の本来持つ生命力を取り戻す
半世紀前、収穫量を飛躍的に増やし、食糧難に苦しむ国や地域を救うなど、世界の農業に大きな恩恵をもたらした科学技術の進歩は「緑の革命」と呼ばれた。しかしその後、収量の確保を優先するあまり、化学肥料や農薬に過度に依存した農地では、土壌の劣化も進んだ。
国連食糧農業機関(FAO)の推計では、世界の陸地面積の10%超(16.6億ヘクタール)が人間活動の影響で劣化し、その6割超は農地(耕作地と牧草地)だという。FAOは、土地の劣化と干ばつは密接に関連し、生態系や農業の生産性、食料安全保障や、生計基盤の損失などの悪循環を生み出していると指摘する。
劣化した土壌とは、生物多様性が低く、微生物のえさとなる有機物が不足した状態だ。そのような土の中では、栄養や水を保持できず、また水も浸透しにくいために土が乾きやすくなる。土も固くなるため、植物が根を張りづらくなる。
BGは、こうした劣化した土壌の再生に向けて、土の中で微生物が活性化しやすくなる独自の有機発酵資材「Soil Next(ソイルネクスト)」も開発した。農業生産者に販売し、畑の土を自然界本来の多様な土壌生態系へと近づけていく。
■消費者の力で「土の革命」広げる
土づくりで生産者にアプローチすると同時に、土にこだわった野菜を消費者に訴求する。
評価指標「アグリLCA+」の基準を満たした野菜を、野菜ブランド「Next Green Vegetables(ネクスト・グリーン・ベジタブル)」として小売店に並べる。
BGの久保田龍星COO(最高執行責任者)は、オルタナの取材に対し、「消費者が、土にこだわった野菜を『おいしいから』という理由で選ぶ行為が、『土の革命』の原動力となる」と力をこめる。
7月には都内の百貨店でポップアップ販売をしたが、今回、9月29日からの1週間、東急ストアフードステーション・大倉山店(神奈川県横浜市)で試験販売を行う。順次、消費者により身近なスーパーでの試験販売を進め、来春に正式なブランドリリースを目指す。