記事のポイント
- 学校を軍事利用目的で使わせない「学校保護宣言」には、世界121カ国が賛同する
- 法的拘束力のない誓約だが、日本はG7の中で唯一、賛同していない
- 宣言の成果も見られる中、日本政府に賛同を求める声は若者からも
世界で紛争や戦争が多発・長期化する中で、学校が基地や武器の保管庫、訓練所や捕虜の拘束施設などとして軍事利用されることで、軍事目標とみなされて攻撃されるケースも発生している。学校を軍事利用目的で使わないことを誓約する「学校保護宣言」には世界121カ国が賛同するが、日本はG7の中で唯一の未賛同国だ。「学校保護宣言」の成果も見られる中、日本政府に賛同を求める声は、若者からも上がる。11月20日の世界こどもの日に、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの堀江由美子アドボカシー部部長が寄稿した。(オルタナ編集部)

空襲警報が鳴る中、地下のシェルターで勉強する子どもたち
©OLEKSANDR KHOMENKO/ Save the Children
終戦から80年を迎え、今年は非戦への誓いが各地で力強く訴えられた。しかし、世界の状況を見ると、紛争や戦争が世界中で多発し、長期化している。パレスチナ・ガザ地区では、10月の停戦発効後も攻撃による死傷者が後を絶たない。
こうした中、紛争下の学校・大学を攻撃・軍事利用から守るための国際指針、「学校保護宣言」をご存じだろうか。法的拘束力のない政治的な誓約だが、実は主要7ヶ国(G7)の中で唯一日本だけが賛同していない。
■世界の子どもの5人に1人が紛争地で暮らす
最近発表された報告書によると、2024 年には世界36ヶ国で61もの国家間の紛争が起きており、これは1946 年以降最多となる。世界では子どもの約5人に1人、5億2,000万人の子どもたちが紛争地に暮らしている状況だ。多発する紛争に伴って、「教育への攻撃」も多発し、増加している。
「教育への攻撃」には、学校や大学への武力攻撃のみならず、生徒・教員の殺害や拘束、学校・大学の軍事利用、学校や通学路での兵士への勧誘や誘拐、学校や通学路での性暴力といった行為も含まれる。
国際調査によると、2022-2023年の2年間に28の国々で、約6,000件もの「教育への攻撃」が確認されている。この数字は、その前の2年間と比べると20%も増加しており、1万人を超える学生や教員が死傷したり、誘拐・拘束されるなどの被害を受けている。
■紛争下で教育はなぜ重要なのか
「教育は希望」であると言われる。ストレス度の非常に高い紛争下の状況で、教育は子どもたちにとって日常を取り戻せる数少ない場となる。暴力の連鎖を断ち、子どもたちの今と未来にとって、また紛争後の復興のためにも、教育の継続は極めて重要だ。
一方、その重要性にもかかわらず、人道支援において教育は後回しにされやすい。緊急事態が起きると、まず食料など生命の維持にかかわる支援が優先される。人道支援の総額を増やし、教育への支援を拡充すること、また紛争・災害の影響を受けている国のみならず、難民を受け入れている途上国への支援も欠かせない。
■「学校保護宣言」とは
教育への攻撃の多発を受けて策定されたのが「学校保護宣言」である。2015年にノルウェーとアルゼンチン政府の主導で策定されて以降、世界でこれまでに 121ヶ国が賛同しており、アメリカが今年1月、トランプ政権への移行前に121番目の賛同国となった。賛同国には宣言の内容を国内政策などに反映・実施する自主的な取り組みが求められる。
「学校保護宣言」には、紛争下で学校・大学を守るためのガイドラインが含まれており、その内容は以下のとおり:
- 軍事利用の目的で開校中の学校を使わない
- 民間人がいなくなった学校でも、どうしても必要な場合以外は使わない
- 紛争中であっても、意図的に学校を破壊しない
- 敵が学校を軍事利用している場合も、攻撃前に警告をするなど、まずはほかの手段を考える
- 戦闘中の兵士が、学校を警備しない
- 国内政策、関連マニュアルに反映するなどガイドラインに書かれていることを実行する
国際人道法において、学校は民間の所有物として攻撃してはならない対象とされているが、これが守られていない現状がある。学校が基地や武器の保管庫、訓練所や捕虜の拘束施設などとして軍事利用されることで、軍事目標と見なされてしまうことが理由の一つだ。
国際人道法のもとで、攻撃を行う側は学校を攻撃しないよう、可能な限りの予防・代替措置を取る責任があるが、子どもや教員を守るためには、学校の軍事利用をなくすことが不可欠だ。
残念ながら日本政府は未だに「学校保護宣言」に賛同しておらず、主要7ヶ国(G7)の中で唯一の未賛同国となっている。
日本政府の公式な見解は、「宣言の目的自体は、基本的に評価している」が、「ガイドラインの中に、国際人道法の義務を超える内容が含まれ、自衛隊の部隊運用への影響を踏まえると、日本の実態にそぐわない内容も含まれる」というものだ。
しかし、「学校保護宣言」は国際人道法に基づき、教育の保護を促進、強化するものというのが私たちの認識である。日本政府も世界の国々と連帯し、紛争下の教育や子どもを守る取り組みの輪に加わってほしい。
■「学校保護宣言」策定後、成果は出ている
「学校保護宣言」の策定から10年、これまで賛同国による様々な取り組みが続けられており、多くの国で前向きな変化が見られている。
例えばマリでは、紛争が続く中でも、2018年の「学校保護宣言」への賛同後、2019年に教育省が国防省の代表も含む国家専門委員会を設置し、宣言の実施に取り組んでいる。
2020年には教育省が国防省に対し、パンデミックにより学校が閉鎖されている期間中もガイドラインの精神を尊重し、学校を軍事利用しないよう求める書簡を送付し、関係者への能力強化と研修の実施により、防衛・治安部隊の行動に変化が見られるようになった。
これらの部隊は学校の占拠をやめ、代わりに仮設の軍事施設を使用するようになった。2020年には学校の軍事利用が4件報告されているが、2022年には2件、2023年には0件と減少している。現在、武力紛争下の学校保護に関する立法の取り組みも進んでいる。
マリ以外でも、カメルーンや中央アフリカ共和国、エチオピアといった国々では、2020~2021年と2022~2023年を比較すると、学校・大学の軍事利用の報告件数が半分に減った。
また、デンマーク、エクアドル、ニュージーランド、スイスなどでは、軍事マニュアルを改訂し、学校の軍事利用を明確に禁止する規定を新たに含めている。
戦火にあるウクライナでも、2021年に「学校保護宣言行動計画」を策定し、教育施設への攻撃に関するデータを収集・公開している。その他、賛同国間で法律の整備、軍関係者の研修、情報共有などが進められ、国内外での協力関係が広がっている。
今年11月25・26日にはケニアで「第5回学校保護宣言国際会議」が開催される予定で、私たちは日本が参加するよう求めている。
■国際平和と日本への期待
世界では多くの紛争が発生し、地政学的な緊張がかつてなく高まっている。価値観や意見が違う者同士が暴力によらない対話で解決していくこと、多国間で共通ルールを作り、協調してルールを守っていくことの重要性はますます増している。
これは紛争当事国のみならず、日本を含む国際社会の責任である。
署名した若者たちからも「平和主義を掲げる日本政府としてリードしてほしい」との声が多く寄せられている。
国際協調と平和を推進する取り組みは、日本にいる私たち、子どもたちを守ることにもつながるだろう。私たち市民には、対話の力を信じ、あらゆるレベルでの対話と働きかけを続けていくことが求められている。
2015年の策定から10年、私たちは日本政府の賛同を求め、この4月より署名キャンペーンを展開してきた。この宣言がなぜ重要で、日本政府の賛同が求められるのか。企業をはじめとする読者の方々に、紛争下の子どもや教育の現状、それを改善するための「学校保護宣言」の取り組みにつき知って頂き、ぜひ署名にご協力頂きたい。




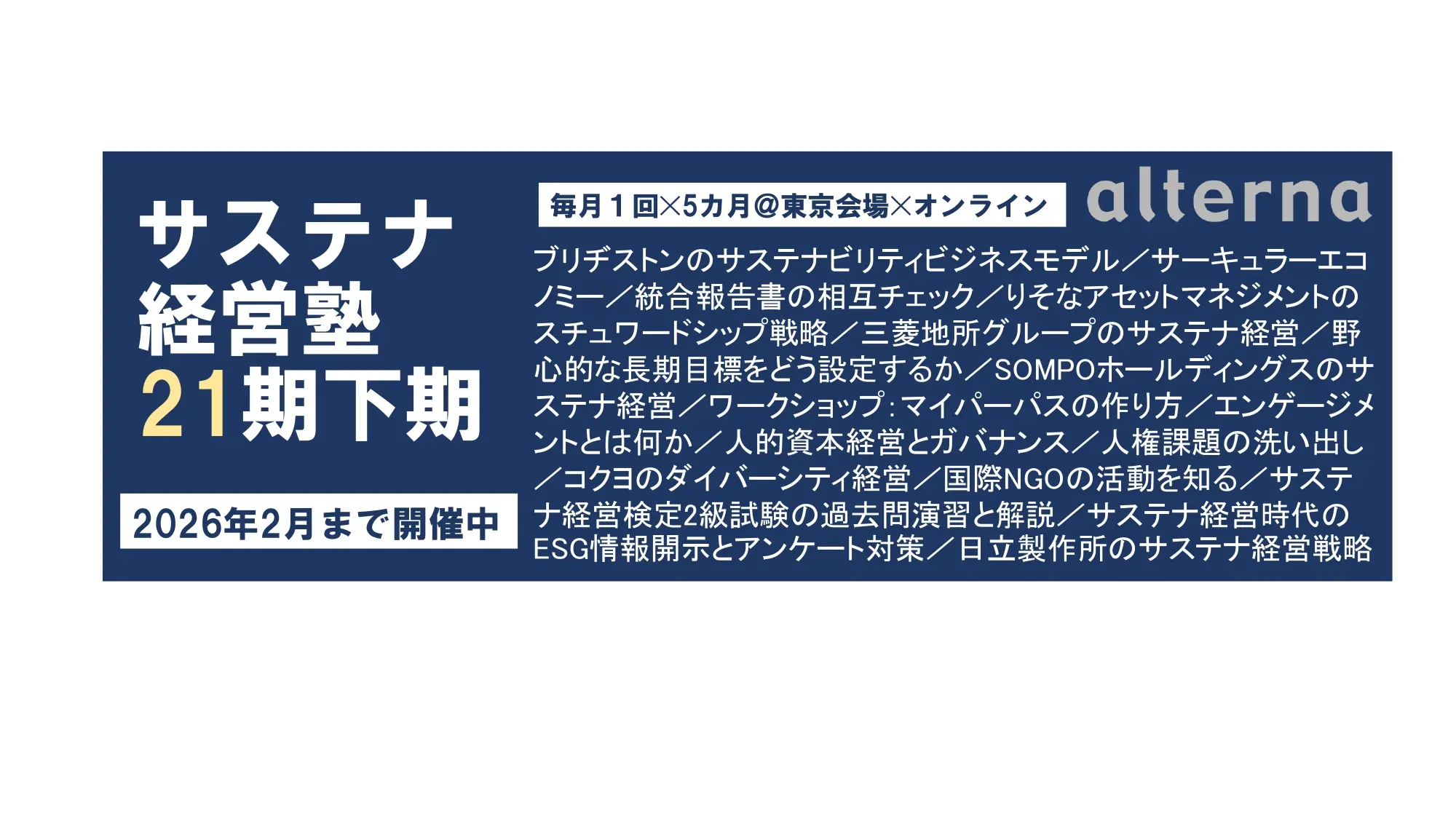








-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)



















