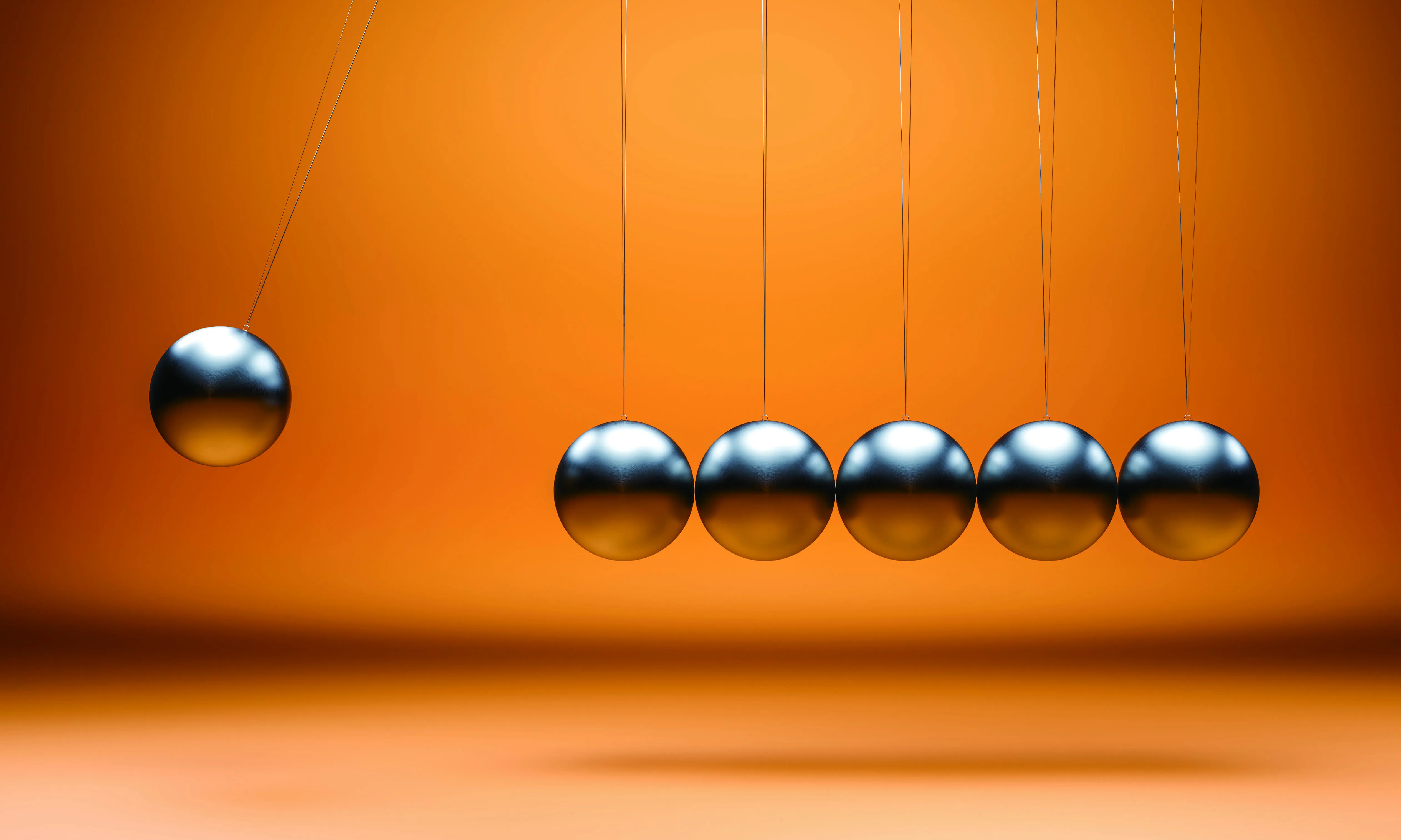「ショート・ショート」(掌小説)こころざしの譜(5)
原発事故で新しい街に引っ越した。私がその一風変わった男を見かけたのは、ハローワーク通いが休みで、自宅近くの商店街をぶらぶら歩いていた冬のある日のことだった。何やら人だかりがしているのでのぞいてみると、ひょろりと背の高い老人がよく通る声で演説している。
「皆さん、昔の話ですが、日中戦争が始まった時、私は中国にわたり現地で中国人難民の医療支援にあたったんですよ。戦争で焼け出され、けがやコレラなんかで苦しんでいる人たちが大勢いたのです」
薄くなった白髪が寒風に揺れている。
「京都の大学の医学生がいっしょに行ってくれましてね。薬品問屋が並ぶ大阪の道修町で期限切れの薬や中古の医療機器を集めたんです」
「よう、じいさんよ」と突然鋭い声があがった。前列にいた労務者風の男である。「日本が中国と戦っている最中に、あんた、敵の中国人を助けたって言うの」。
「そうよ、非国民じゃないの、あなた。尖閣列島を乗っ取ろうなんていう悪い国を助ける必要なんてないわよ」
買い物袋をさげたおばちゃんが加勢する。老人は思わぬ反撃をくらって黙り込んだ。
「あら、またやっているわ」
「特別養護老人ホームの例の認知症の方ね――」
通りすがりの主婦たちが老人を一瞥して通りすぎる。次第に人だかりがばらけ、ひとり残された老人は唐突に歩き出した。気がつくと、私は後を追っていた。高齢だが、かなりのスピードである。思い詰めた目標があるかのように、一刻も早くそこにたどり着きたいという執念を感じさせる歩き方だった。
あっ危ない。思わず声が出た。カン、カン、カン、カンと威勢よく警報機が鳴っている踏切の遮断機を老人がくぐろうとしていたからだ。あわてて駆けよった。腰のあたりを後ろから抱きかかえた途端、バランスを崩して後ろへひっくり返った。列車の轟音。間一髪だった。
特養を探して歩き始めた時、黄色のワンピースの女の子が飛び出してきた。
「まあ、おじいちゃん。どこへ行っていたの、風邪引くじゃない。ずいぶん探したのよ。どうもすみません。ご迷惑をおかけしてしまって」
特養の部屋で横になっていびきをかき始めた老人を心配そうに見下ろしているのは妻の芳子。傍らのやせた男は甥で、たまたま見舞いに来たのだという。その娘が先ほど、私に丁重にお礼を言い、この部屋まで案内してくれた大学生の友紀だ。
「おじいちゃんたら電車にはねられるところだったのよ」という友紀に、芳子は「耳があまり聞こえないし視力も弱っているので」と恐縮しっぱなしである。
老人の名前は吉村寿太郎。とうに九十歳を超えている。布教と奉仕に生涯をささげた牧師だと聞かされた。若いころ、難民医療班を結成し、上海近くで中国人を支援し感謝されたという。
「医学部の学生と私の母ら看護師で医療班を組んだと聞いている。日本は中国を侵略したわけだが、ああいう時代に中国人難民を助けた吉村伯父のような人が存在したことは、日本人にとっては救いだね」と甥。
「中国」「難民」「医療班」といった言葉が刺激したのか、老人は目を覚ましむっくりと起き上った。
「薬の問屋街のみなさん、日本軍閥の罪悪を謝罪し、その償いのため私たちはこれから壊滅、後輩の中国へ難民を助けに行きます、どうか薬を寄付してください、期限切れのもので結構です。よろしくお願いします」
当時の思いに浸っているのだ。声に張りがあるのは牧師時代に説教で鍛えた賜物に違いない。検温で入室した看護師が「吉村さんの説教がまた始まったのね。皆でまた聞きたいわ」と明るく笑った。
老人は再びまどろみ、眠りに落ちた。それを待っていたかのように、甥が「伯父の吉村はここでは聖人扱いでね。意外に思うかもしれないが、それが時に腹立たしいこともあるんだよ」と吐き捨てるように言った。
「牧師として多くの貧しい人、苦しんでいる人に手を差し伸べてきたし、中国難民も支援した。それは確かだ。でも、そのために実家の財産を食いつぶしてしまった。吉村伯父と一緒に中国難民医療団に参加した私の母も奉仕に一生をささげた人だけど、ずっと貧しい暮らしだった。吉村伯父は実は一度離婚している。前の妻は、信仰一点張りで家庭を顧みない伯父に愛想尽かしたんじゃないかな。吉村は立派な人かもしれない。皆、そう言う。だけど、きれいごとはやめてほしいね。家族は大変なんだ。家族をここまで犠牲にして、それで本当に立派だといえるのだろうか。娘の友紀にも、いつもこの話を聞かせているんですよ」
私は甥の話を黙って聞いていた。答えようがなかったからである。やはり一言も発せず静かに耳を傾けるだけだった芳子が私を玄関まで見送ってくれた。
「あの甥御さんはたまに見舞いに来るといつも、あんなお話なのですよ。失礼しました」
「牧師の妻というのは確かに大変でしょう。よく再婚の決意をされましたね」
そう私が尋ねると、「大変?そんなこと思ったこと一度もございません」と芳子は静かな笑みを見せながらきっぱりと言った。
「ただ、お金が本当になくてね。電車賃もないので、よく吉村の自転車の荷台に乗せてもらってあちこち出かけましたわ。でも、それが今一番の思い出なの。おかしいかしら」
ちょうど大きな夕陽が窓を染めながら落ちていくところだった。つるを巻いた中庭の蔦がその陽を受けて輝いている。それは冬枯れの風景のなかで確かな生命力を感じさせた。
しばらくして芳子から手紙が来た。
「先日はありがとうございました。早く故郷に戻れるといいですね。吉村ですが、乏しくなった光で最期まで周りを明るく照らしてくれました。生前に用意していた葬儀目録に従い、指定された聖書が読まれ、賛美歌に送られて天国に召されました」
終わりに「友紀ちゃんが、お父様の反対を押し切ってNGOに就職することにしたそうです」と書き添えてあった。
(完)



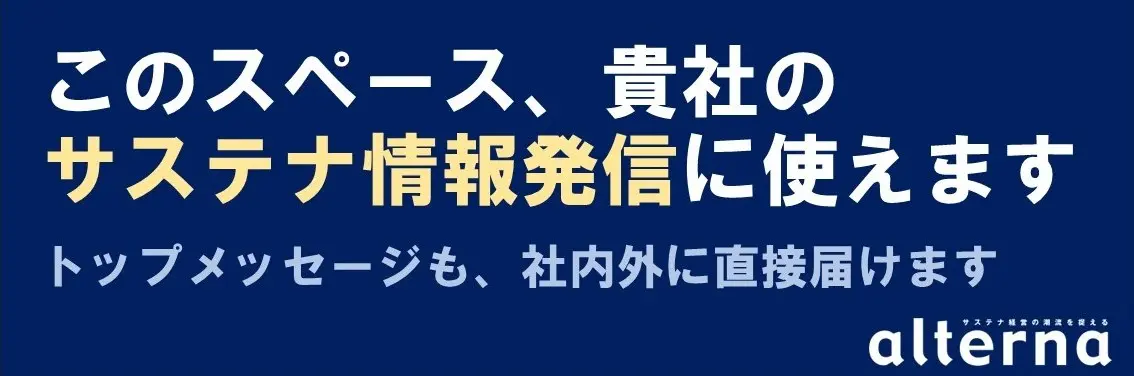
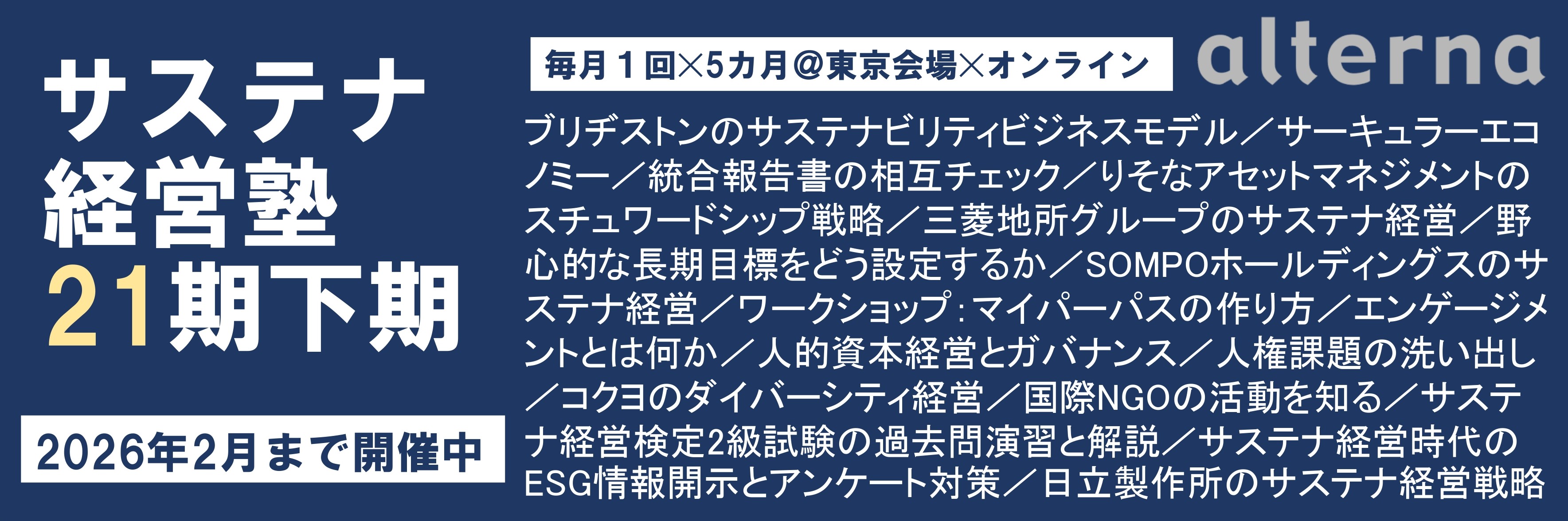
























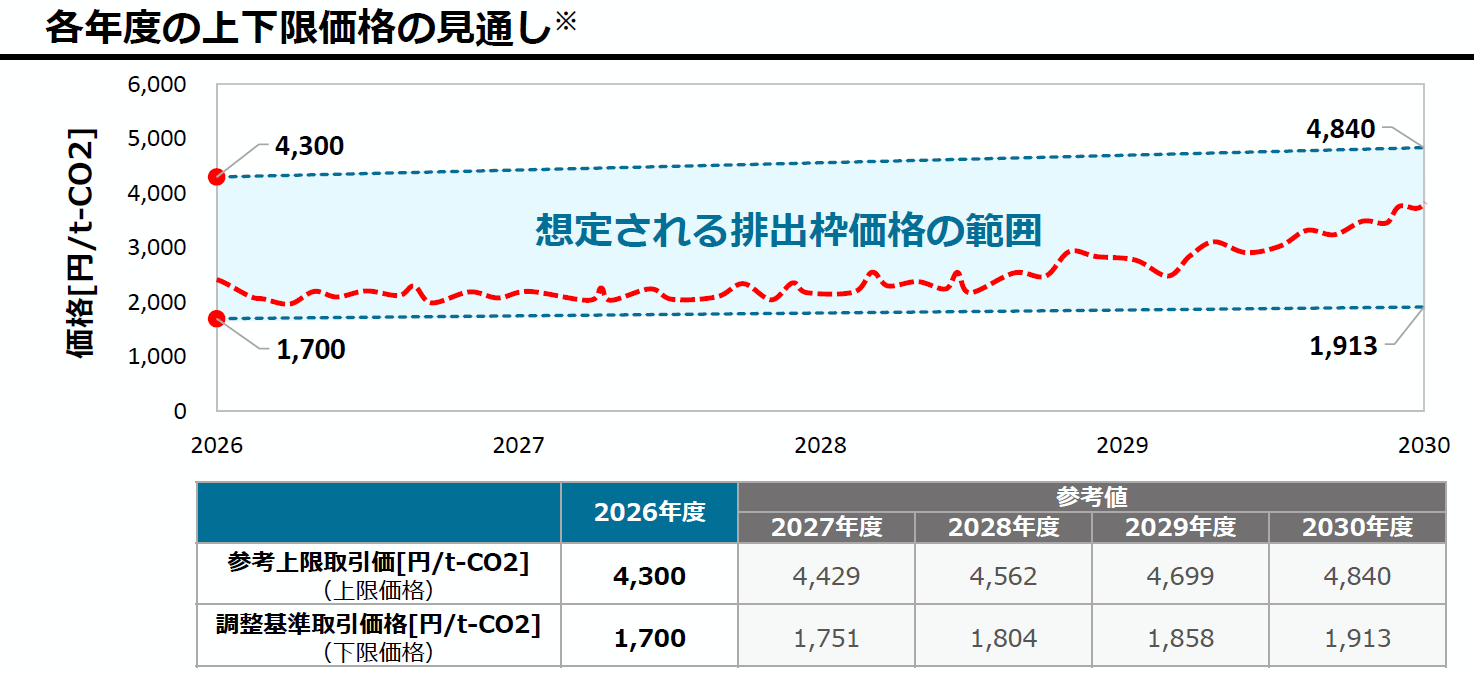
.jpg)