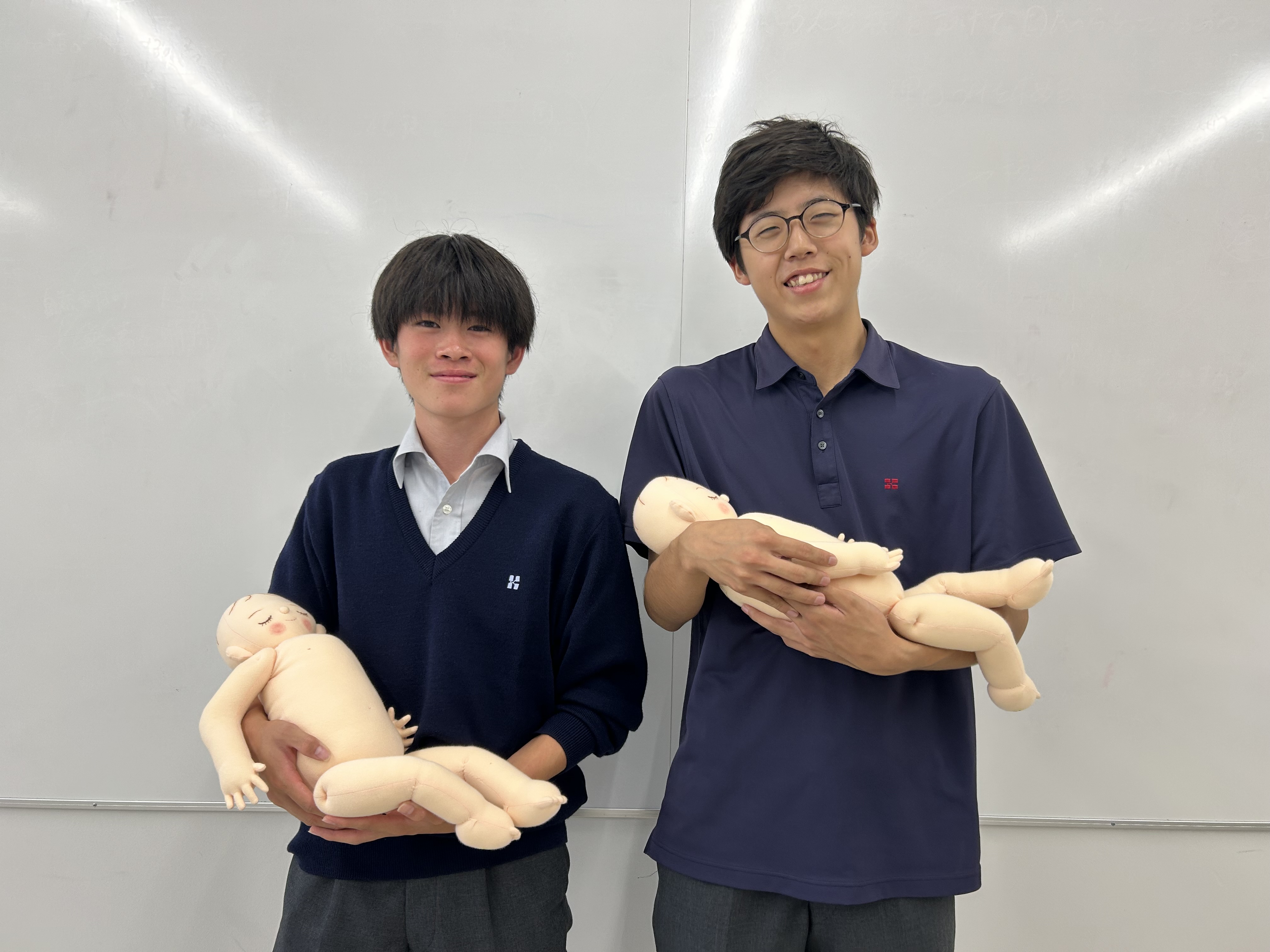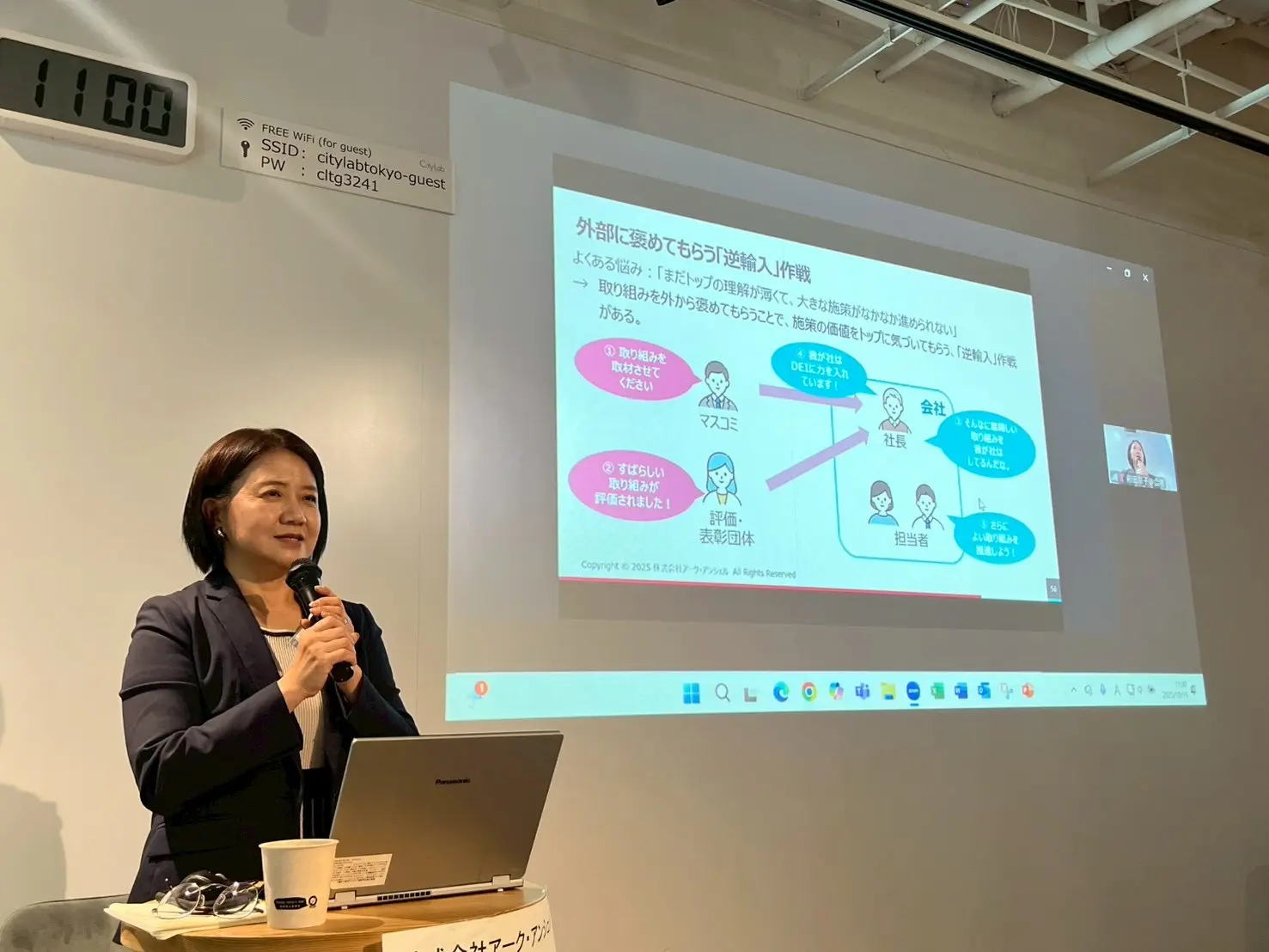「ショート・ショート」(掌小説)こころざしの譜(6)
日が落ち、闇がさびれた工場に溶け始めた郊外の街は静まり返っていた。時折、パトカーが通り過ぎ遠くで犬の吠える声がするくらいで人通りはない。古いビルの角を曲がり三階まで階段を駆け上がる。ドアには確かに聞いた通りの会社名が張ってある。軽く5回ノックする。
中から「ポトゥー」と呼びかけてきたので、合言葉「チュパカブラ」を唱える。ドアが開き、顔中にタトゥーを入れた男が片手を出した。預かってきた包みを渡すと、タトゥー男は、もういい、行け、という風にあごをしゃくった。
走って酒場へ戻ると、右手首から先がないティオ・ぺぺが「アレックスよくやった。ブツを確かに受け取ったと組織から電話があったばかりだ。俺の頼みを断って港に浮かんだ奴もいた。お前は幸せだよ。ほら、約束の手間賃だ」
店を出て確かめると、手垢で汚れた百ボリバル札が5枚あった。思わず口笛を吹いた。
アレックスの家は45階建ての超高層のスラムビルにある。中南米を襲った金融危機で建設が途中でストップしたタワーマンションだ。水道や電気はなかったが、何千人という不法占拠者が殺到、住むために壁や窓を含め大抵の設備は自前で完成させてしまった。エレベーターがないので、上層階は大変だが、住み心地は悪くない。
「お帰り、アレックス。きょうも小学校に行かなかったんだって? 担任のフェルナンデス先生が家庭訪問に来てくれているわ」
姉のラウラが居間の先生を振り返った。学校に顔を出さないアレックスが悪いのだが、親がおらず、紡績工場で働くラウラの安月給では、学校での給食費や文房具代をねん出するのも苦しい。
「アレックス、君は来年から中学校に行く年齢なんだがね。残念だが、きょうの職員会議で落第が決まった」。先生はつらそうだった。
「先生、学校なんかどうでもいいよ。働くから」
ラウラは心配そうだ。
「だめよ。中学校くらい出ておかないと」
「アレックス、街の悪い連中と付き合っているといううわさも聞いたけど、本当かい?」
先生の言葉に、ラウラの表情が曇った。
「えっ、ウソでしょう? アレックス。ね、ウソよね」
アレックスは顔が上げられなかった。
「母に顔向けできないわ」という姉の言葉にアレックスは言い返した。
「うるさいな。親父は銃の密売にからんでマフィアに殺された。お袋は貧乏が嫌で米国へ若い男と逃げたんじゃないか」
「そんな風に言わないで。お母さんを信じるのよ」。ラウラがにらんだ。
先生がおもむろに口を開いた。「アレックス、音楽は好きかい?」。街の子どもたちを対象に音楽を教えているNPOがあるのだという。
「この前、久しぶりに学校に来た時、両手を使って棒きれで床を叩いていただろう。あのリズム感、すごく、いかしてたぞ」。
アレックスはフェルナンデス先生の熱意に負けて、NPOに顔を出すことにした。大きな邸宅のサロンが開放され、子供たちが楽器の練習をしていた。ひとり顔見知りがいた。ギャング団の少年で、去年までアレックスと同じ麻薬の仕事をしていたはずだ。思わずポケットのナイフに手が伸びたが、少年は明るい表情で指揮棒を持っている精悍な若者を紹介してくれた。
「アレックス、このお兄さんはセニョー・ルペレス。プロの指揮者を目指しているんだ」。どこかで会ったことがある気がした。
「アレックス。僕も昔は悪ガキでね。女の子にいたずらしたり、麻薬取引の手伝いなんかしていた。実は君らのグループと一度、決闘をしたこともあるんだ。河原で」
「あっ、あの時の」。アレックスの記憶が蘇った。死者も出た3年前のギャング団同志のケンカだった。
「アレックス、君はバタフライナイフをすごいスピードで両手同時に開閉することができるんだったよな。あの蝶の舞いは見事だったよ。でもな、いつまでもそんなことしていても仕方がないよ」
ペレスのウインクがまぶしかった。そのペレスが「みんな、聞いてくれ。日本のフクシマで原発事故があったことは知っているね。今度、フクシマで演奏会を開くことになった。その練習で、今から、ちょっと合奏してみようか」と声をかけると、子供たちが椅子を持ってぞろぞろ集まってきた。
音合わせのあと、ペレスが指揮棒をさっと振ると、ヘイ、ヤーという掛け声とともにマンボNo.5が始まった。練習の時は、ピーピー、プープーとうるさいだけだった楽器がいまは見事なハーモニーを奏でている。
何十人という子どもたちが指揮に従って、ひとつの音楽をいっしょに作り上げようと必死に心を通わせている。バイオリンはビオラと響き合いチェロと支え合う。後ろでドラムスが時に激しく、時にやさしくリズムを刻む。ペレスはジェスチャーが大きく楽しい。時々、腰を振り笑顔いっぱいだ。
ソロだけでなく、バイオリンのパート全員が立ち上がった。トロンボーンは楽器を左右に思い切り振っている。なんだ、これ。気付くと、アレックスも身体全体でリズムをとっていた。「マンボ、マンボ」。自然に声が出た。
それから何年かたち、アレックスがドラムスの腕を上げたころ、ペレスから「ニューヨークの音楽学院へ進学する気はないか」と誘われた。「NPOの米国支部が君のために奨学金を出してくれるそうだ」。
ラウラがうれしそうに一枚の手紙を見せた。母からだった。
「アレックス、お前は私の誇りだよ。お父さんの事件のあと、私も殺されそうになったのよ。それで駆け落ちを装って消えたの。米国のサンディエゴに脱出したけど、お前のことを忘れたことはないよ。実はあんたのために仕送りもしていたけど、マフィアに知られたくなくて、ラウラに口止めしてもらったの。ニューヨークに来たら会えるね。その日を楽しみにしているよ」
「お姉ちゃん・・・」。アレックスはそう言ったが、ラウラは黙ってうなずくばかりだった。
(完)












-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)