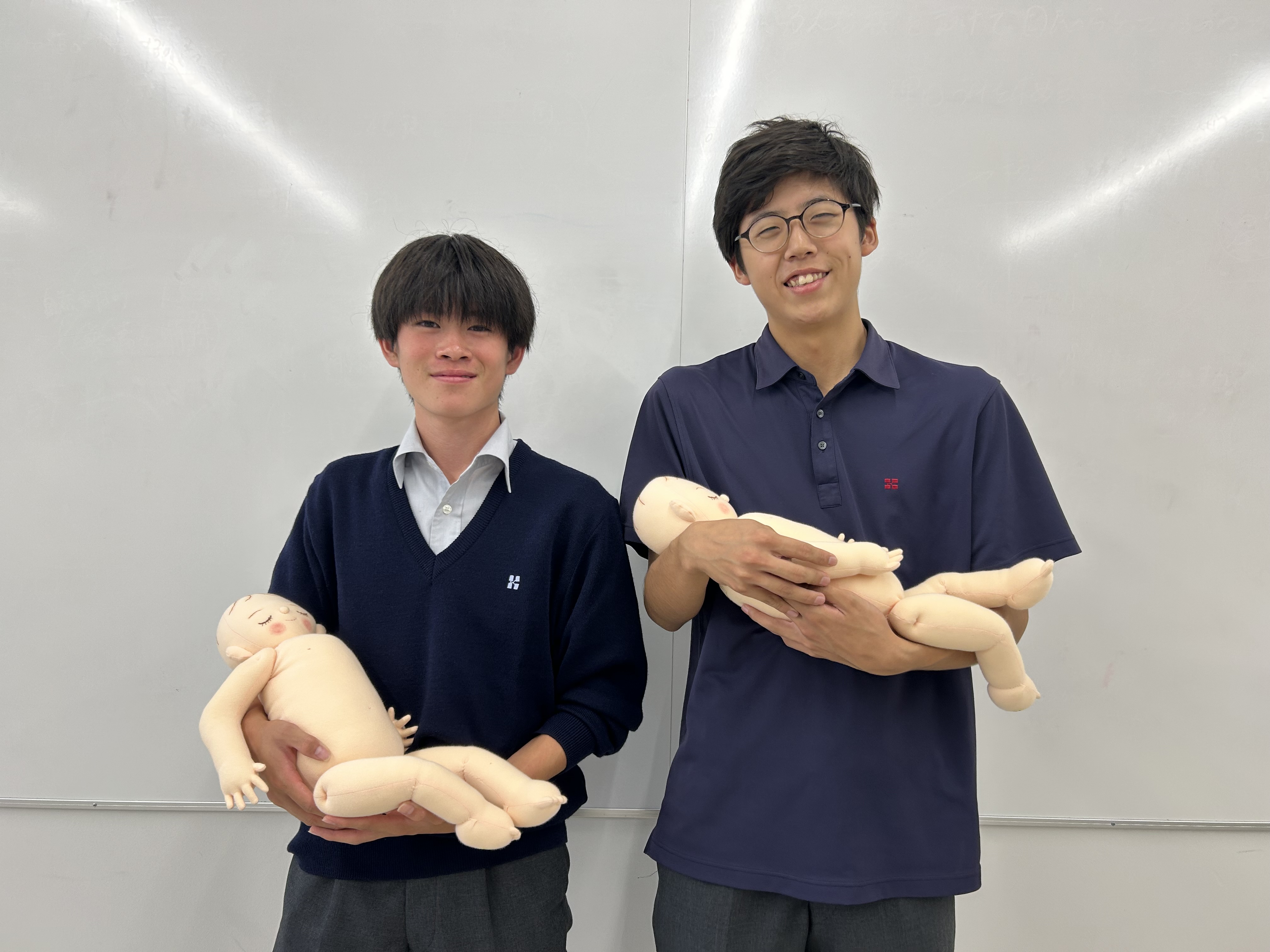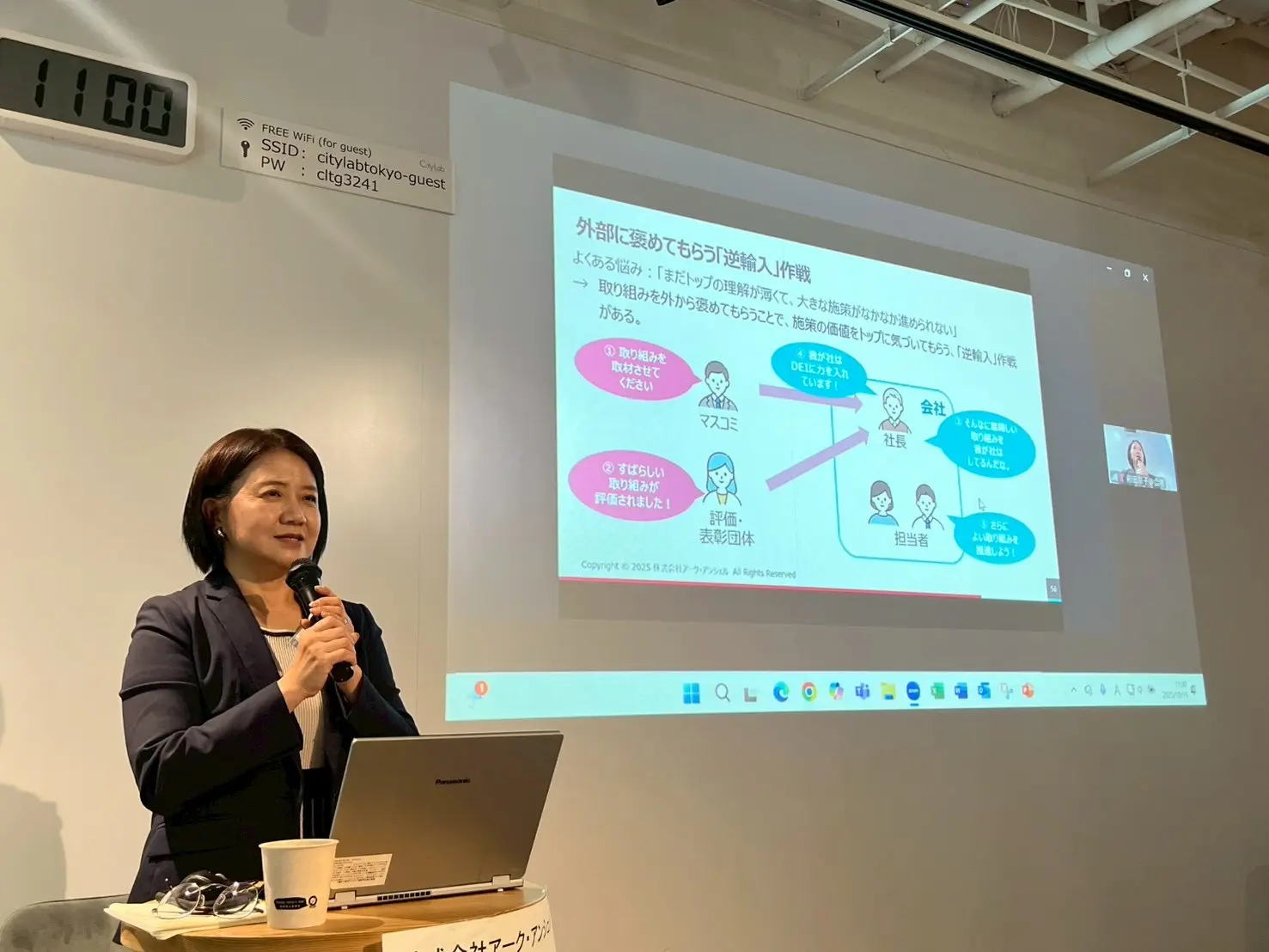「ショート・ショート」(掌小説)こころざしの譜(16)
「あなた、早くして。もう皆さんが飛行場に着くころだわ」
妻の綾子が隆を自宅の居間から追いたてる。
「わかっている。そうあわてるなよ」
役場に顔を出すと、町長が「あれ、山下さん、夫婦おそろいでずいぶん早いですな」と大げさに驚いてみせる。ほら見ろと言わんばかりに、隆が綾子を横目でにらむ。この日は、東京から若年認知症の患者とその家族でつくるNPO「月の影倶楽部」の会員が北海道にやってくるというので、隆と綾子に町役場から協力の依頼があったのだ。
間もなくバスから降りた一行、十人ほどは春とはいえ寒さが身にしみるようで、コートの襟をたて腕をさすっている。だが、どの顔も表情は穏やかだ。この町には自分を理解し助けてくれる人たちがいるという安心感からだろう。一年前の自分はあんなじゃなかった、と隆は振り返る。
隆は銀行の融資部長だった。融資の審査や焦げ付きの処理で気の休まる時がない毎日だった。ある時、妻の綾子から「あなた、最近、ちょっと忘れっぽくなったんじゃない?」と真面目な顔で聞かれうろたえた。実は、自分でも自覚があったからだ。既に、職場でいろんなトラブルが発生していたのだ。
部長席に稟議書が回ってくるのだが、最近、初めて聞く案件が多かった。担当者を呼びつけて、「この件だけど、私は聞いてないぞ」としかると、困ったような顔をして下を向いている。そんなことが何度か続いたある日、次長から慇懃に「ちょっとお話が」と会議室に呼び出された。言いにくそうに語ったところによれば、指摘された案件はすべて事前に隆に説明し内諾をもらっているものばかりだという。
「部長、私も同席していた案件もありますから間違いありません。本当にご記憶にありませんか」
そう尋ねる次長は探るような目をしている。今から思えば、その顔に同情とか憐憫の色が浮かんでいたかもしれない。
「そうか、そうだったな」。そうごまかそうとしたが冷や汗でびっしょりだった。
次の日、銀行から遠く離れた病院の精神科に駆けこんだ。しばらく脳の写真を見ていた若い医者は「初期のアルツハイマー型認知症です」とあっさり診断をくだした。「54歳ですか。若年性ということになりますね。最近多いんですよ」。
疲れがたまっているか睡眠不足のせいだろう、くらいに安易に考えていただけに、思いがけない病名に心臓がつぶれる思いだった。街を歩き回り、人とぶつかって「馬鹿野郎、どこ見て歩いてんだ」と怒鳴られた。泥酔し、どう家に帰ったか記憶になかった。
妻の綾子は診断結果を黙って聞いていた。翌日、借りてきたビデオをセットすると、「見なさい」と言った。徐々に記憶が薄れ、ついには妻の顔もわからなくなる若い男の映画だった。綾子は静かに泣いていた。隆は大きな不安の底でただ茫然とするだけだった。
セカンドオピニオンを求めた別の病院では「脳血流の低下は確かにありますが、アルツハイマー型認知症といえるか微妙なレベルです。ただ、環境を変えないで今の生活が続くようだとストレスで間違いなく発病します」。
銀行を辞めるなんて、人生の終わりだ。隆はそう思いつめた。橋の上から暗い川底をのぞき込んで通行人にいぶかしがられたり、電車に飛び込みそうでホームの端が怖くて歩けない日が続いた。もうだめだ。死にたい。そう綾子に泣きついた時、黙って「月の影倶楽部」のホームページを開いてくれた。勇気を出して訪問した「月の影倶楽部」の事務所では会員らしい男が5人、のんびり茶飲み話をしていた。
「あんた、そりゃ、仕事は無理だ。銀行を辞めるしかないよ」
「ストレスのないゆったりした生活が生き残る道だ」と次々に話しかけてくる。
ゆっくりした話し方だが、同じ病気だけに親身に相談に乗ってくれた。最後にひとりがこう言った。「北海道のある町は町長が若年性認知症でね。しかも、その病気を公表したんだ。そしたら、思いがけなく町民が応援してくれてね。病気への理解も進んでいて、東京からもその街へどんどん移住しているんだよ」。
半年後、銀行を辞め、マンションを売った隆と綾子は北の大地へ飛び立った。街にはひまわりがあふれていた。
隆は驚くほど病状が回復した。大きな空、平原に沈んでいく真っ赤な夕陽。おいしい野菜や魚。人々のやさしさ。周りのすべてが薬となった。
「月の影倶楽部の会のみなさん、東京からようこそ」。町長が大きな声をはりあげている。「庁舎の1階に昼食を用意してあります。どうぞ、こちらへ」。
「町長、私が案内しますよ」そう隆が声をかけると
「そうか、頼むわ。で、あんただれだっけ?」
「あなたからふるさと振興隊に任命していただいた山下隆ですよ、町長」
「ああ、そうそう、そうだった。覚えてるよ。山本隆さん。奥さん、確か・・・」
「綾子です」
「綾子さんね、うちの死んだかみさんと同じ名前だなあ」
「町長の奥様はたしか、百合子さんでは」
「そうだったかな、まあ、似たようなもんだ。さあ、早く皆さんを案内して」
昼食会では、首都圏からこの町に移住した十人が紹介された。隆もそのうちの一人だった。ふるさと振興隊の仕事として、町内を取材し記事を町のホームぺージに掲載している。それを見せながら町の様子を紹介した。
その時だった。後ろにいた女性が突然、立ちあがった。
「あんた、若年性アルツハイマーだと言っていたけど、うそでしょ。ウチの人も同じ病気と診断されたけど、こんなんですよ」と言って傍らのぼんやりした表情の夫を振り返る。
「反応も鈍いし、今言ったことをすぐ忘れる。まともな話ができないんです。あんたが、同じ病気だなんて信じられない。町の宣伝のためにオーバーに言ってるだけじゃないの」
「いや、隆さんは本当に初期のアルツハイマーと診断された人です。北海道の自然の中で癒されて」と町長が説明しようとするが、女性は「うそ、うそ」と譲らない。
隆の傍らに控えていた綾子がすっくと立ち上がった。
「夫が若年性アルツハイマーだというのは本当よ。私たち夫婦も一時は死を考えました。私の顔さえわからなくなる病いと聞いて思いつめたの。でも、この町で生き返ったんです。ここには、同じ病気を抱えお互いに助け合おうとしている人たちがいる。その周りに、病気を理解し支えてくれる人たちも大勢います。だから病気でも働き、町のために役立つ活動を行うことができるんです」
女性は黙った。そして「ウチの人にもできるかしら」
「もちろん、できるわ。そのために、わざわざ北海道まで来たんでしょ?」
綾子は近づくと女性の手を握った。夫が隣でニコニコしている。目に涙がにじんでいる。
町長がパチパチと拍手をし、それがだんだん広がっていく。隆も笑顔で女性に近づいた。
「ヒマワリ、見に行きませんか。元気が出ますよ」
(完)




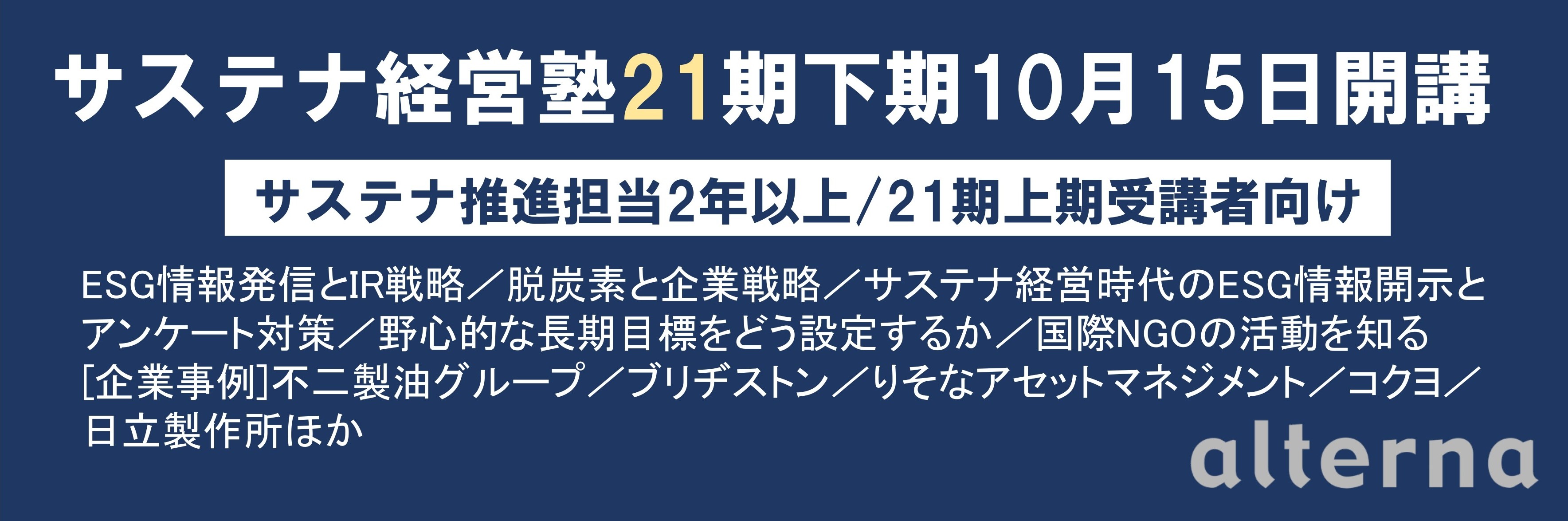








-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)