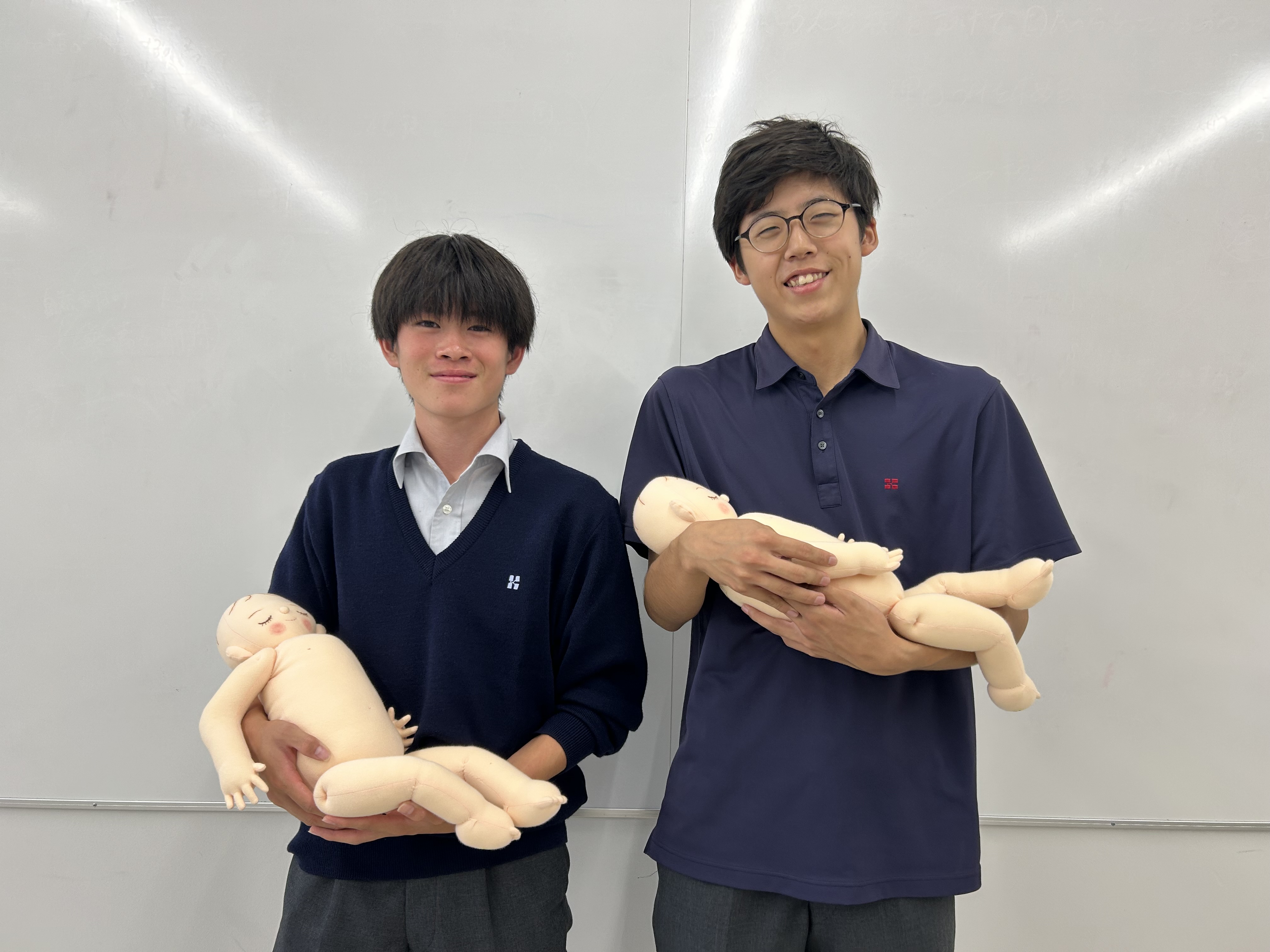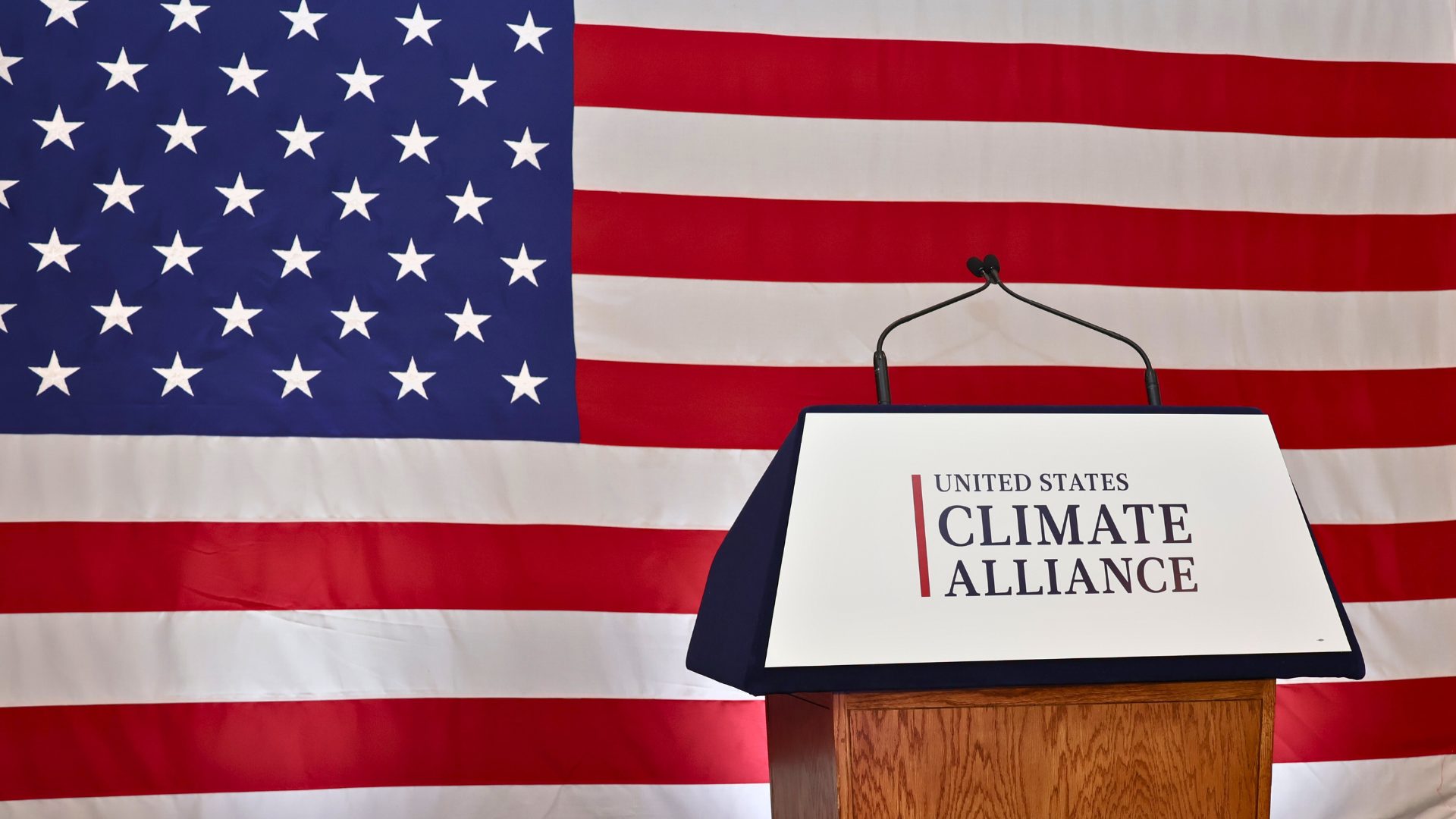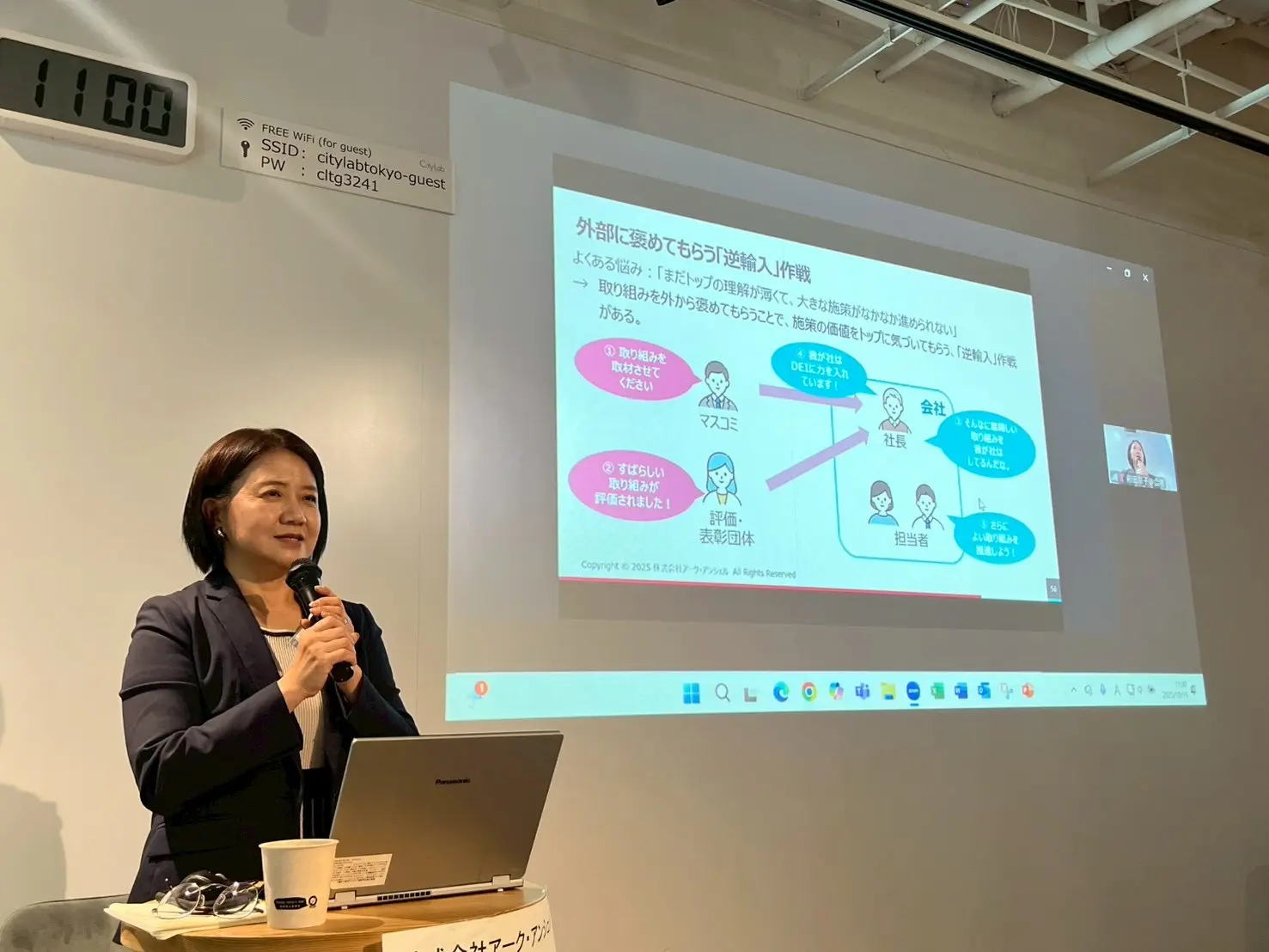アフリカ南部に位置するザンビア。1975年から2002年まで続いたアンゴラ内戦の影響で、大量の難民が同国に身を寄せた。内戦が終わると、多くのアンゴラ難民は帰還したものの、1万人近くが同国に残り、生活を続けている。国際NGO・AAR Japan(難民を助ける会)の直江篤志さんは、国内最大の難民居住区の1つメヘバで、「元難民」が生活を建て直し、地元住民とともに暮らす地域づくりに奔走した。(オルタナ副編集長=吉田広子)

ザンビアで元難民の生活支援を続けてきた直江さんが7月26日(トルコ時間)、マラリアで亡くなった。44歳だった。生前の取材内容をもとに直江さんの軌跡を紹介する。
直江さんは企業に6年間勤務した後、米大学に留学。その後、青年海外協力隊に参加し、理数科教師として2年間ザンビアに赴任。2011年9月にAARに入職した。
「東日本大震災が起きて、復興支援に携わりたいという思いがあった。ちょうどAARが担当者を募集しており、入職することになった」(直江さん)
その後、東京事務局でザンビア・チパパ地域におけるエイズ対策事業を担当。2017年3月からザンビア・メヘバ事務所駐在になった。
「何もないところで、図面を作るところからスタートした。事務所が完成したときは、我ながら『よく頑張った』という思いだった」(直江さん)
■支援が行き届かない「元難民」
ザンビア北西部州のメヘバには国内最大の難民居住地区がある。アンゴラ内戦が終結し、多くのアンゴラ難民が母国に帰国した後も、残った難民のほか、ルワンダ難民や近年急増したコンゴ難民などが居住している。
そこに隣接する形で、直江さんが支援を続けてきた「現地統合エリア」がある。ザンビア政府と国連は2014年、「現地統合(local integration)」プロジェクトを立ち上げ、在留を希望する難民に対し、現地統合地区に土地を用意する移住政策を開始した。
パスポートと永住許可が与えられる代わりに、難民のステータスを失い「元難民」になる。統合エリアには、ザンビア人も住むことができ、元難民とザンビア人がともに暮らす地域づくりが始まった。
だが、直江さんは「統合エリアは、幹線道路から1時間ほど離れたインフラもない未開発エリア。やぶも多く、自分たちで切り拓いていかなければならない。生活していくには非常に厳しい環境だ」と指摘する。さらに、難民支援の対象から外れるため、生活は厳しいものになる。
こうした危惧もあり、難民居住地区からの移住はあまり進んでいないのが実情だ。
■自助グループを毎日訪問

AARはまず、生活基盤となる水衛生事業に取り組んだ。直江さんによると、「井戸はあるものの、全く管理がされておらず、使えない状況」だという。
「女性や子どもたちが、1時間かけて水を汲みに行く。1人あたり1日20リットルの水を使うので、重いバケツを頭に載せながら何度も何度も往復する。当然、女性が働いたり、子どもたちが学校に通ったりする時間はなくなってしまう」(直江さん)
そこで、AARは約230世帯が暮らす統合エリアに約30の自助グループを組織した。そこから水管理委員を選出し、工具の使い方、井戸のメンテナンス方法などを教えた。
「パーツを交換するなど、壊れた井戸を修理するにもお金がかかる。貧しい人たちから集金するのは大変なこと。だが、持続的な仕組みにするには、住民に納得してもらい、少しずつでもお金を工面してもらう必要がある」(直江さん)
支援が行き届かず、未開発エリアで暮らす元難民の生活は厳しい。直江さんは「電話は通じない。ドアをノックするしかない」と毎日、自助グループの訪問を続けた。
「こうした移住政策には賛否両論ある。だが、すでに移住した人たちがここにいる。何かできることをやらないと」。そう静かに、力強く語る直江さんの姿が印象的だった。













-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)