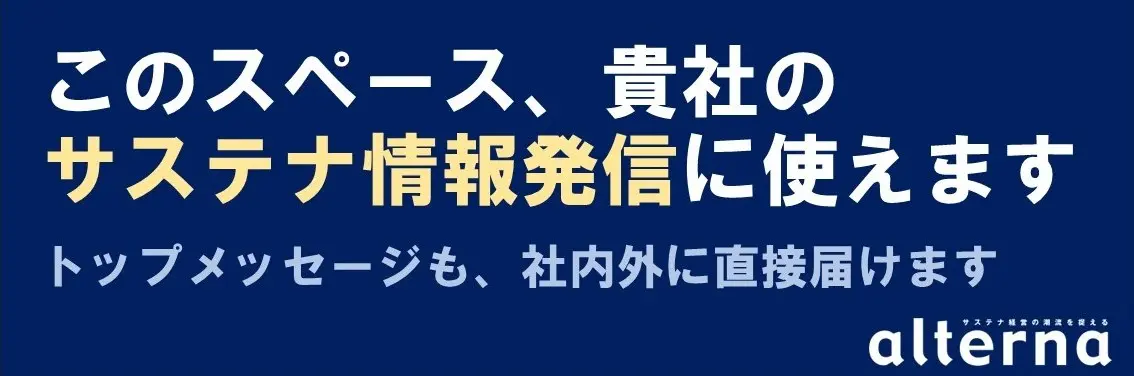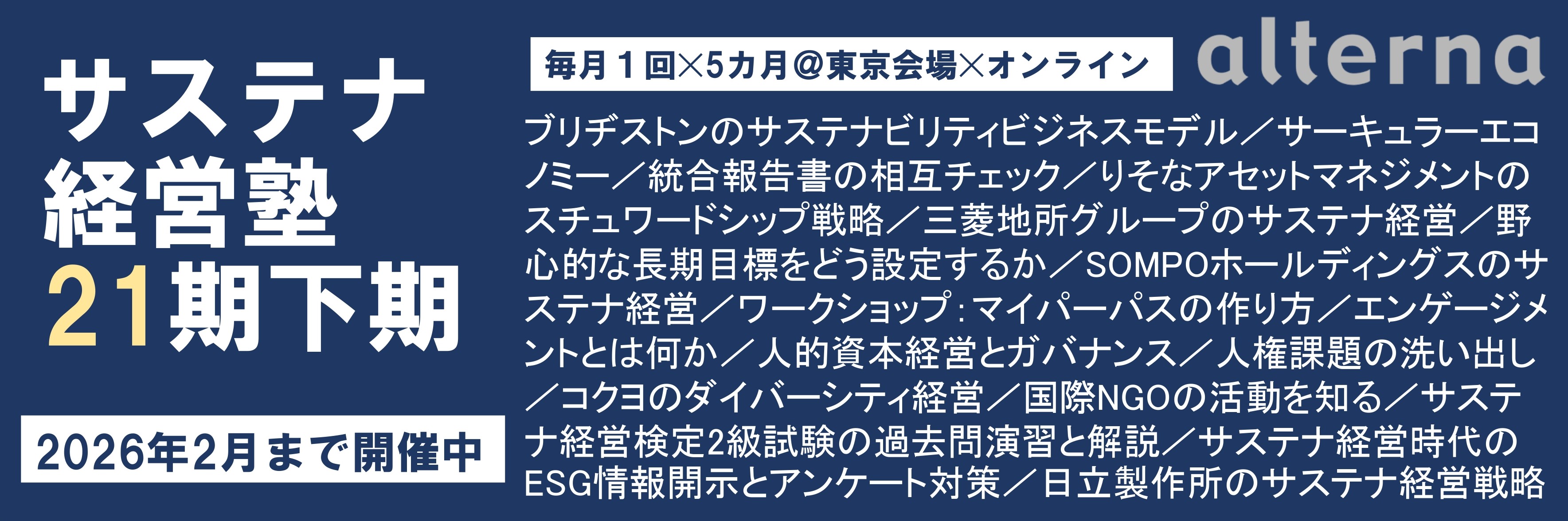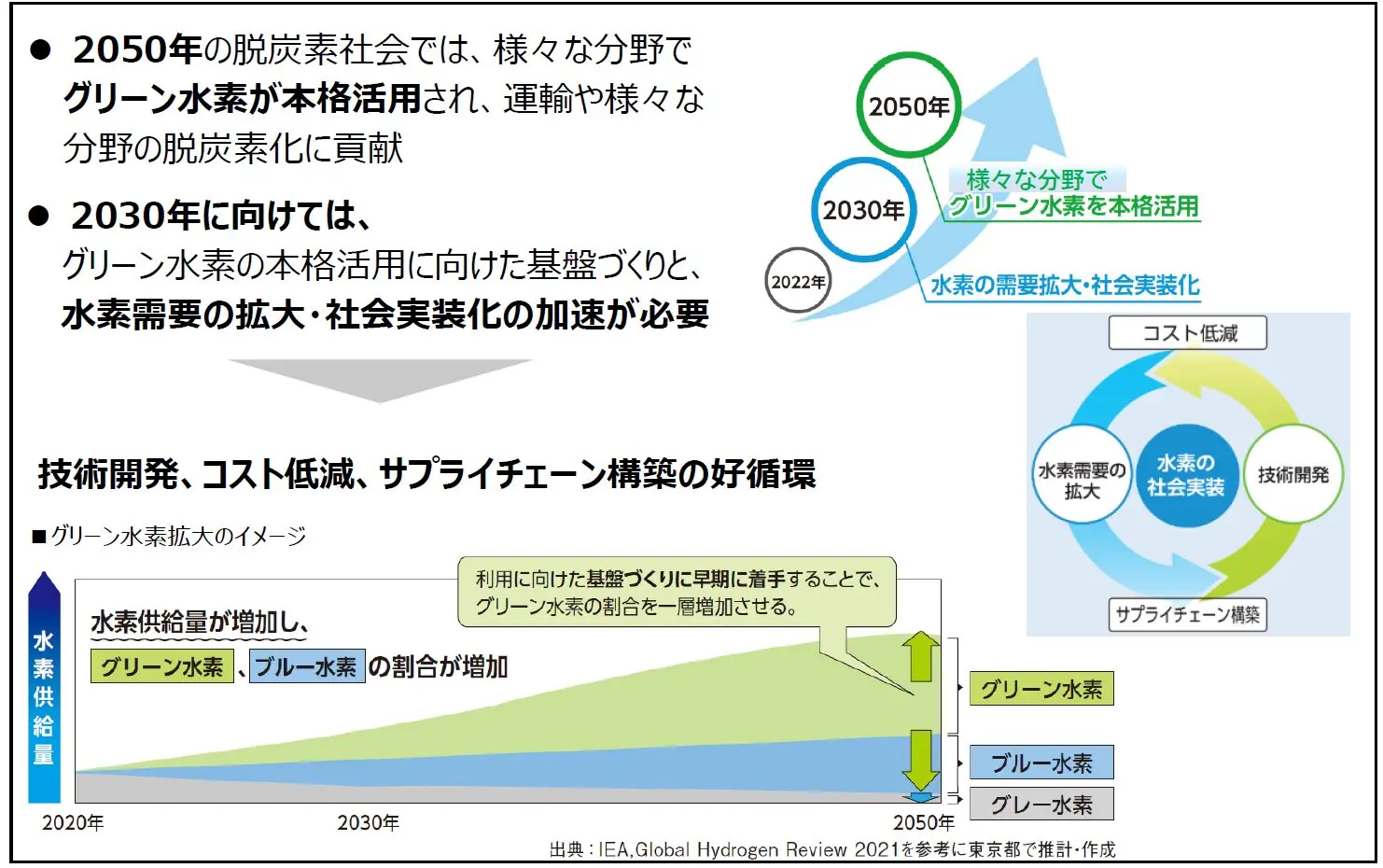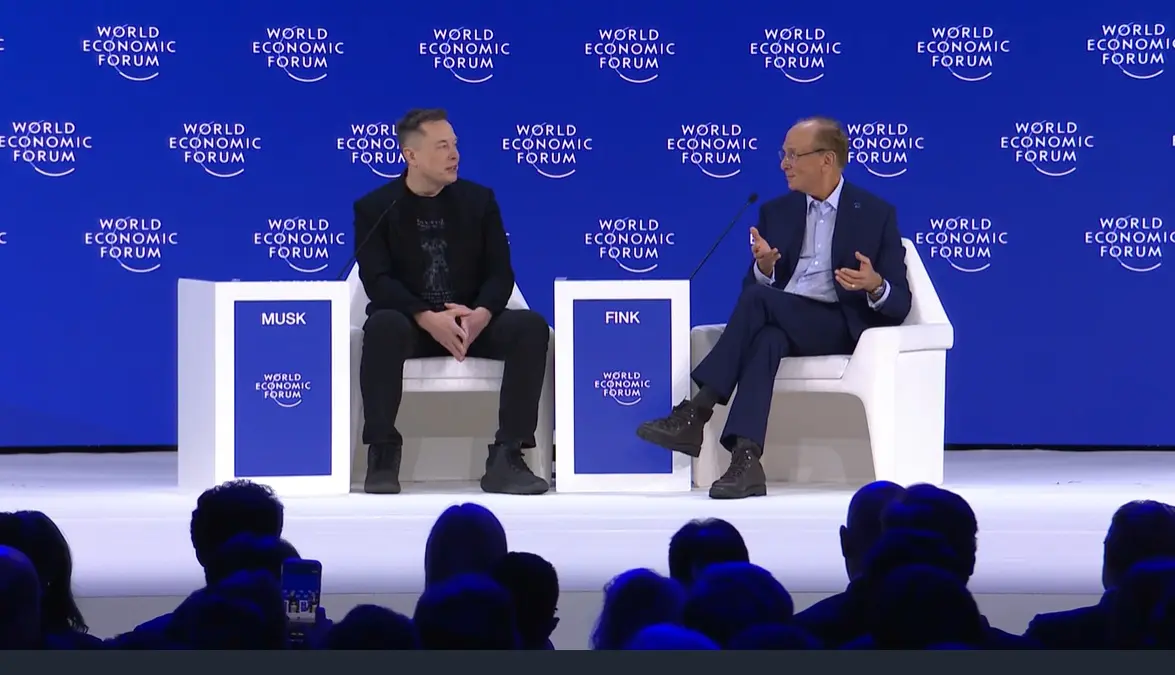「ショート・ショート」(掌小説)こころざしの譜(25)
結婚式の夜、光希子からベトナムへの新婚旅行に車イスを持って行きたいと切り出された時には慎一も困惑を隠せなかった。ニャチャンは海がきれい、歴史を感じたいならフエ、フォーは絶対に食べたいね、などと盛り上がった直後だっただけに、マジで?と思わず光希子の目をのぞき込んでしまった。
「勘違いしないで。もちろん私が使うんじゃないわよ」。希子は白い歯をのぞかせた。「ほら、妹の由貴子よ。小児まひで小さいころからずっと車イスのお世話になっているじゃない。古いのが奥の部屋に何台も眠っているの。あれをベトナムの障害者施設に運べないかと思って」。
慎一は渋々承知したものの、頭に浮かんだのは「慈善」、正直に言えば「偽善」という言葉だった。鉄工所で汗にまみれて働く慎一にとって一番縁がないと感じる世界だった。
春とは名ばかり、街のあちこちに根雪が残っている。おお寒い。慎一はジャンパーの襟を立てながら、マイカーの荷台から車イスをおろした。光希子から運ぶよう頼まれたのだ。運送会社の倉庫には集められた古い車イスが山と積まれ大勢の人が工具片手に修理に動きまわっている。こっちへ、NPOの年配の男性から声がかかった。
「義妹さんが使っていた車イスか。右手が悪いんじゃ、日々の生活も大変だな」
由貴子の不自由な手どちらだったか慎一の記憶はあいまいだった。結婚の申し込みに光希子の家を訪ねた時、応接間で目を伏せていた由貴子の印象は薄かった。
NPOの男性は、本職は運送会社の社員で毎週末ボランティアで車イスの修理をしていると自己紹介した。慎一が早く引き揚げたがっているのを見破ったのだろう。こう声をかけてきた。
「義妹さんの車イスを一緒に磨かないか。大きさから見て彼女が小学生のころ使っていたものだと思うけど、自由が利く左手ばかりで車輪を回すから、ほら、接触が多いここにさびがいっぱい出てる」
旅行の当日、自宅から新千歳空港に到着すると、運送会社のトラックが修理済みの由貴子の車イスを運んできた。運転手は、倉庫で会ったボランティアのおじさんだった。
「いやあ、配達のついでだからさ。面倒はないんだよ」
自分の車イスをどうしても見送りたい、と車イス姿で駆け付けた大学生の由貴子も珍しく明るい笑顔で手を振って見送ってくれた。
チェックインの時、手荷物として預けた車イスを見た航空会社の人が怪訝な顔をした。
「失礼ですけどどなたか身体が不自由なんですか」
事情を話すと、他の荷物と合わせるといくらか重量オーバーになるがウインクして見逃してくれた。車イスをコンテナ船で送るとまとまった数が必要だし何百万円とかかる。飛行機の手荷物で運ぶというのは学生が思いついたらしいが、タダだからなかなかのアイデアである。
ホーチミンのタンソンニャット国際空港の税関でも、何度も「ありがとう」とこちらが恐縮するくらい感謝された。出張のサラリーマンや友達グループで旅行する主婦、卒業旅行の学生らが、こうして車イスを運ぶと聞いた。話を聞いた当初は気乗りしなかった慎一も、不思議な高揚感に包まれている自分の変化を感じた。空港には障害者施設の職員が車イスを受け取りに来ていた。このまま引渡して終わりでもよかったのだが、急ぐ旅でもない。慎一と光希子は施設を訪問することにした。
施設には手足の不自由な子が沢山いた。病気や交通事故の子もいたが、驚いたのは、ベトナム戦争の後遺症に悩む子が多かったことだ。戦争は1975年に終わっているのだが、当時、ジャングルでのゲリラ戦を得意とするベトコン(南ベトナム民族解放戦線)掃討のため、米軍は空から大量の枯葉剤を散布した。これが環境を汚染し人間にも様々な障害をもたらした。床に横たわる子どもたちは苦しそうにうめくだけで人間としての尊厳を奪われていた。
その時、きれいなアオザイに身を包んだ女性が現れた。施設の所長だと自己紹介した。
「国産の車イスは新品でもすぐに壊れてしまいますが、日本の車イスは中古でも高品質で使いやすいんですよ。本当にありがたいです。しかも、わざわざここまで運んできていただいて」
慎一は、床で横になったまま、こちらを見ている子たちの視線が痛かった。
「あなたの車イスはゴー・マイ・チャンという女の子が使うことになっています。ミニーはどこかしら。ミニーというのはチャンのニックネームなの。あら、あそこにいるわ」
所長が指さした庭の方に目をやると木々の間に何か動くものが見えた。地面を這っている。一瞬、大きなネズミかと思ったが、よく見るとそれは小さな女の子だった。髪はボサボザで着ている服も擦り切れている。右手と右足を少し引きずっている。
「まあ、ミニー。どこへ行っていたの。あなたの車イスが届いたのよ」と所長が駆け寄った。
ミニーははじめ車イスの扱いに戸惑ったようだが、すぐに慣れ左手一本で器用に動かし始めた。光希子が駆け寄った。
「あなた、ミッキーの妹なのね。私の名前もミッキーなのよ」と声をかけると、ミニーが小さな声で「じゃあ、お姉さんね」とはにかんだ。
この車イスで何をしたい? 慎一は、言わずもがなのことを尋ねた。散歩とか買い物とかいういう返事を期待していた。しかし、答は思いもかけないものだった。
「家がすごく貧乏だから母をちょっとでも助けたい。この車イスに乗って宝くじをたくさん売り、家計の足しにしたいわ。だから、ずっと車イスが来るのを待っていたの。今までできなかった分を取り戻したい」
この色の浅黒い小さな女の子ははっきりとそう言ったのだ。慎一は、ガーンと頭を殴られたような気がして光希子を振り返った。
「車イスって体の一部なのよ。これがあったから由貴子は生きてこれた。ミニーも同じだと思う。彼女はかわいそうな女の子じゃないの。お母さん思いの強い女なのよ、この子は」
(完)