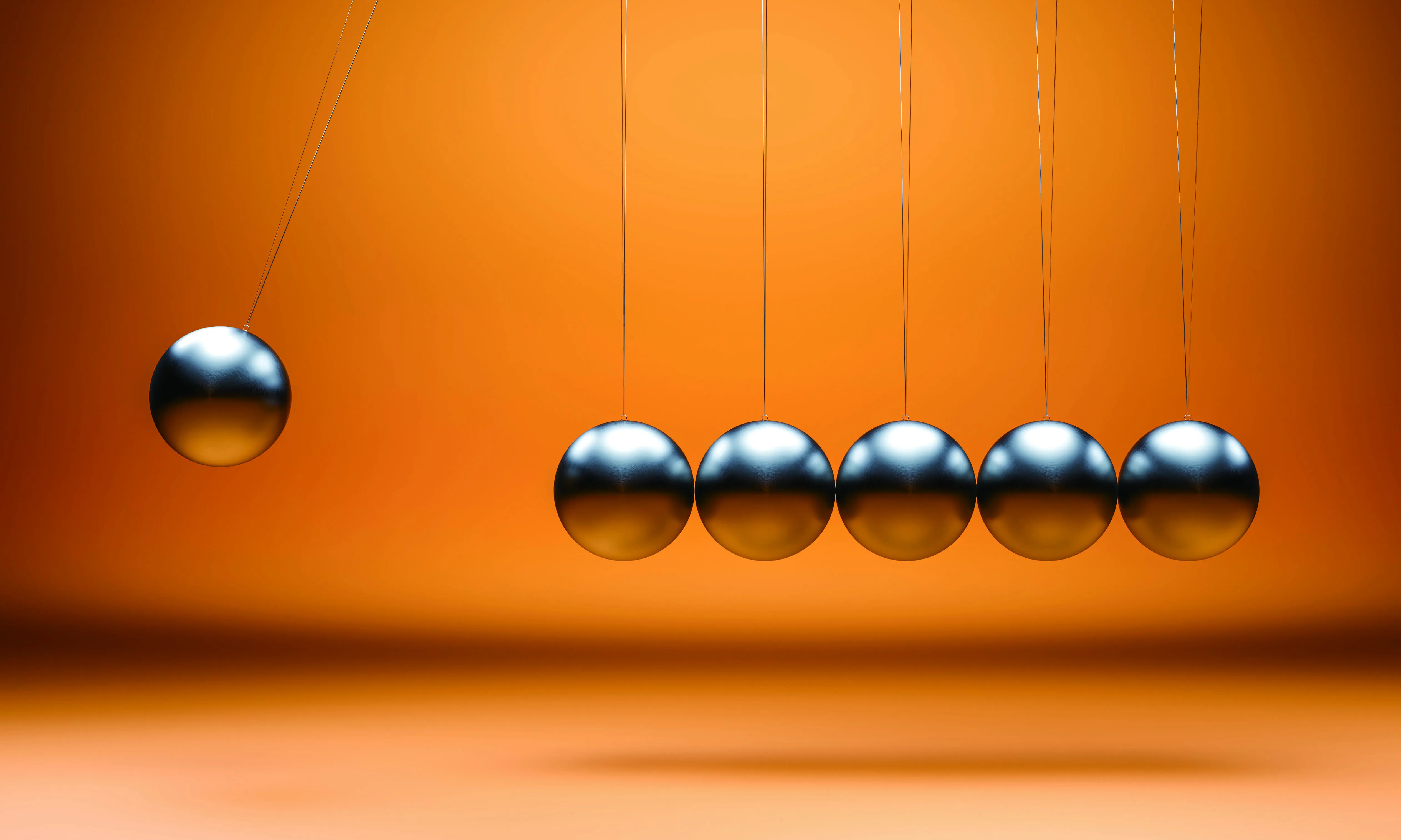◆「ショート・ショート」(掌小説)こころざしの譜(38)
時計の針は午前零時を回っている。三畳一間の古ぼけたアパートの窓から外をうかがうと街灯の下で冷たい雨が風にあおられ湿った曲線を描いている。向こうに見える隣りの公園の紅葉もこの小嵐で散ってしまうに違いない。昨日まではあんなにいい天気だったのにと瑤子の鬱屈した思いはどんより垂れこめた雲の下をさまよっていた。
もう3日も何も食べていない。小さなふとんで寝息を立てている赤ん坊を見下ろす。ミルクをあげていないのでグッタリしている。かわいそうに、もうすぐ、この子も私と一緒に死ぬのかしら。殺すのは気が進まないが、残しても私と同じように乳児院に預けられるだけだ。その方が何倍か、かわいそうだ。
瑤子は生まれて3か月で乳児院に預けられ、児童養護施設で育った。親のネグレクトでまともな世話を受けられないと判断されたらしい。親の顔も知らないし親戚もいない天涯孤独の身である。それでも施設にいる時は楽しかった。子どもが5-6人しかいない小さな施設で、職員もやさしくみな兄弟姉妹のように育った。18歳で専門学校に入りシェアハウスに移った時も同い年で仲のいい幸恵と夕子と一緒だったから寂しさは感じなかった。つらいこともなくはなかったが、3人で笑い話にした。
「きのうパスポートの申請に行ったらさあ、親の印鑑が要るって言われたの。親はいませんと答えたら係りの人びっくりしちゃって、児童養護施設の人でもいいって。ダメなら学校の人でもって。もう、しつこいのよ」
「ハハハ、日本じゃ、なんでも親のハンコなのよ。中学生の時のこと覚えてる? インフルエンザの注射をするのに親の承認よ。私しなかったわ。それで試験の時、運悪くインフルになっちゃて、もう大変」
「シェアハウスに入る時もアルバイトをする時も親のこと聞かれたじゃない。これからもアパート、就職、結婚、ことあるごとに言われるのかな。バカみたい」
しかし、専門学校を出て就職してしまうとバラバラになった。瑤子は孤独が身にしみた。知り合いがおらず、頼れる人がいないのだ。高志という薬剤師と仲良くなったが、気弱で妊娠すると逃げ腰になった。相手の家まで押しかけ結婚を迫ったが、「施設育ちの子じゃね。幼少期に親の愛情を受けられないと人格形成に支障をきたすって言うから」。そう言い放つ母親の陰で高志は縮こまっていた。施設出身ということがそんなに特別なのか。生まれてくるべきじゃなかったというのか。生きている価値がないのかも。瑤子はそう思った。
睡眠薬をウイスキーで流し込んで死のう、その前に赤ん坊を。
そう考えた時、突然、携帯が鳴った。
「瑤子、元気にしてる?」
3人仲間のひとり、幸恵からだった。きれいな顔立ちで施設出身を感じさせない明るい子だった。この夜も声が弾んでいた。
幸恵が施設に来たのは継父の虐待が原因だった。近隣の人から児童相談所に何度も通報されたが、その都度しつけの範囲と言うことで放置された。小学生の時、絶望して自殺しようとして、直前に信頼している先生に連絡したおかげで助かったのだ。施設に来た時は体中アザだらけだったのを瑤子も覚えている。
「瑤子、赤ちゃん生まれたんだってね。おめでとう。大阪にいる夕子から、あなたが悩んでるって連絡もらったんだ。もっと早く電話すべきだったんだけど、忙しくて」
「幸恵、心配かけてゴメンね」涙声になったのを幸恵は見逃さなかった。
「瑤子、あなた、まさか、死のうとなんて思ってないよね」
「・・・・」
「私もひとりになってつらい時があって、そんな気持ちになったことがあるの。でも専門学校の先輩から言われたんだ」
「えっ、何て?」
「うん、生まれてきてくれて、ありがとうって。うれしかった。その一言で立ち直れたの」。
「私は親に捨てられたのよ」
「そうね。それは私も同じ。でも瑤子は私の友達。生まれてきてくれてありがとう。今まで言えなかったけど、それだけはあなたに伝えておかなくっちゃ、と思ったの」
瑤子は泣いた。どれくらい泣いただろうか。しばらくして幸恵のやさしい声が再び電話口に蘇った。
「それでね、その先輩がお金を出してくれて成人式に行ってきたの、振袖来て。瑤子、あの時のこと、覚えているよね」
高校生のある日、大雪が降った。施設前を除雪。そこを振袖姿の成人が通り過ぎた。道がぬかるんで大変そうだった。しかし、瑤子も幸恵も羨ましかった。当たり前の光景だったが、自分たちが絶対に経験できないことを知っていたからだ。あの日の暗い空を幸恵も覚えていたのだ。
「そう、それはよかったわね」と瑤子は冷たく言った。たぶん、幸恵が羨ましかったのだろう。
「本当にうれしかった。普通の子はみなやっているもの。それでいいことを思いついたのよ。皆に、私の様に振袖を着てもらって写真を撮ったらどうかって。瑤子もどう。赤ちゃんと一緒に」
「そんな。お金ないし」
「バカね、ただよ。私、NPOを立ち上げたの。晴れ着は寄付してもらうの。これからヘアメイクやカメラマンはボランティアを募集するつもり」
「そんなにうまく行くかしら」
「大丈夫。振袖来たらちょっと大人になれた気分になれるわよ。じゃあ、来年の成人式の日、瑤子のアパートの隣の公園でね」
冷たい空気が肌を指すようだが、風はなく明るい日差しが針金のような木々を照らしている。
「ここがいいわね」はしゃいだ幸恵が瑤子を池の近くへ招く。
「瑤子、その着物、よく似合うよ」
「ありがとう。紫の晴れ着も気に入ったんだけど、やっぱり赤が入った方が映えるよね」
「はい、こちらへ顔をください」年配のカメラマンから注文がとぶ。「赤ちゃんも、こっち向いてくれないかな。お母さん、表情が硬いですよ。笑ってください。そう、そんな感じで」
「あら、瑤子、赤ちゃんも笑ってるよ」
「本当だ。楽しいのかな、ウフフ」
私には親の代わりに仲間とやさしい施設のお母さんがいる。それを忘れてかけていた。瑤子は改めてそう思った。
1年遅れの成人式だったが、近隣の人が何事かと足を止めて見物している。何人かの顔が並ぶなかに、瑤子は思いがけない顔を見つけた。いつの間に駆け付けたのか、照れ笑いしている高志だった。高志はおどおどと瑤子に近づくと、「アパートへ行ったら留守だったんで。これ・・・」と言いながら一枚の紙を差し出した。
「なによ、今更」瑤子の顔が泣き笑いになった。
「ありゃあ、化粧が台無しだ。困ったなあ。でもいい写真が撮れたわ。遅ればせの婚姻届けか。ああ、旦那さんも一緒に写真に入ったら」カメラマンの笑顔がはじけた。
(完)



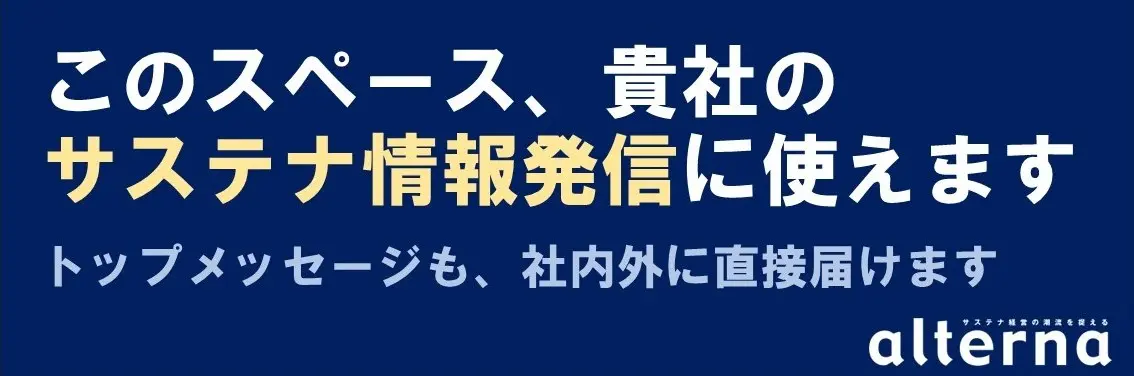























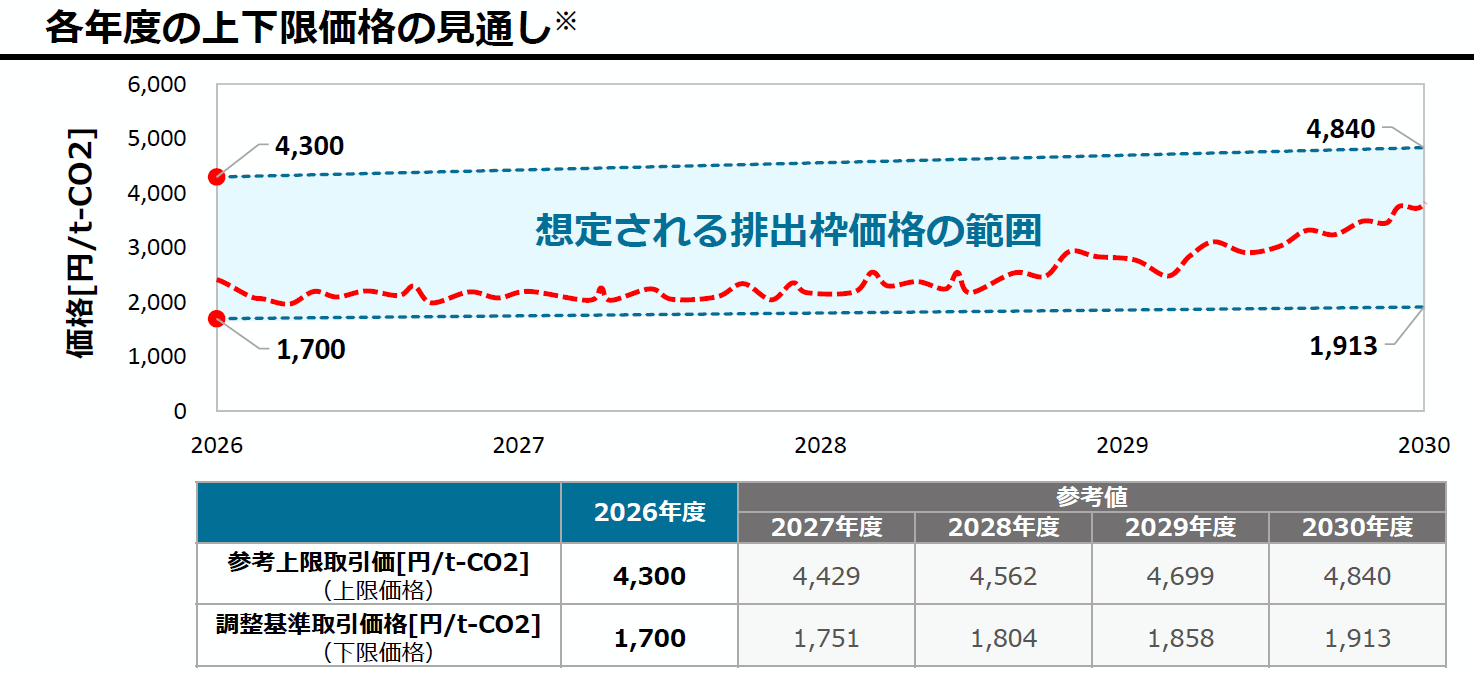
.jpg)